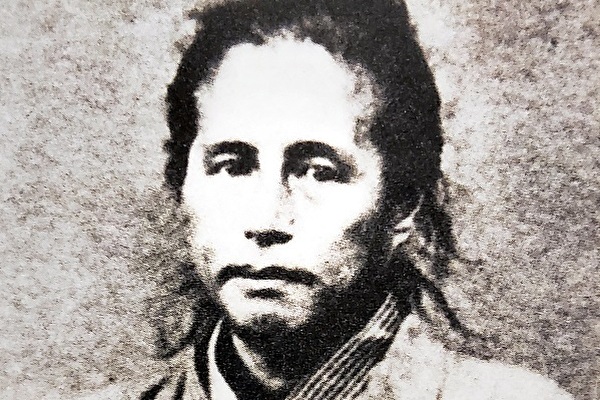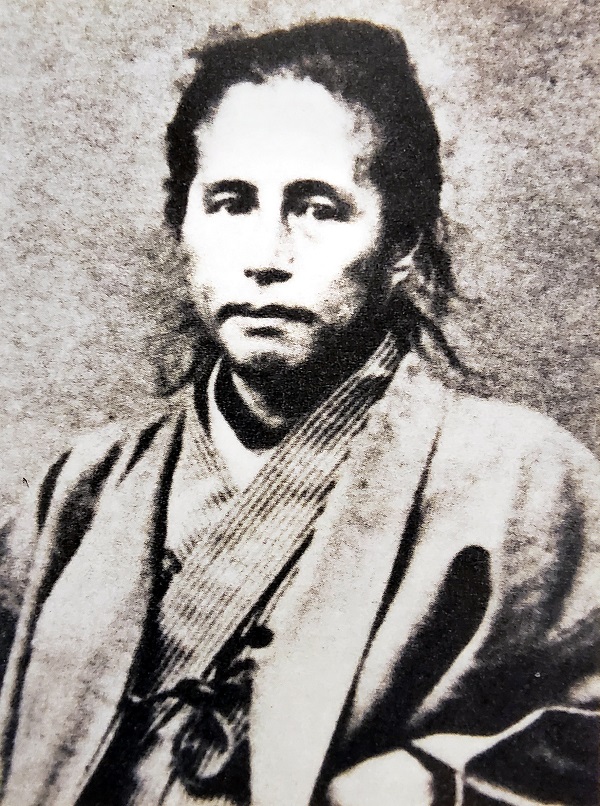偶然か必然か――東京・港区に外国の「大使館」が多い理由
都内屈指のセレブエリア セレブが多く住んでいることで知られる東京都港区。街を歩けば明らかにお金を持っていそうな人が多く歩いています。最近では「港区女子」という言葉もあるそうで、時代そうは変わらないものだと感じます。 筆者の港区の思い出といえば、大学生時代です。両親がリッチで港区にいくつもの超高級マンションを持っている先輩がいたのですが、彼にある日、賃貸に出していた部屋の掃除をバイトで頼まれたことがあります。 当日、先輩と一緒に鍵を開けて中に入ると部屋には家財道具などが一切なく、郵便物のみが散乱していました。それもすべて督促状。あのときこそ「諸行無常」という言葉を強く感じたことはありません。 先輩はその後、明らかに験(げん)の悪そうなこの部屋を事務所にして起業したこともあり、筆者はしばらく出入りしていたのですが、当時はまだ港区に大江戸線の通っていない時代です。 広尾から麻布、麻布十番にかけてのエリアは、東京人でもめったに足を踏み入れたことのない、ある意味で「秘境」でした。 とりわけ、麻布十番の最寄り駅は六本木駅。主な交通手段はバスです。五反田駅や新宿駅から混雑したバスで移動している人が意外に多かったのにとても驚きました。 かつては周遊スタンプラリーも実施 そんな港区ですが、世界各国の大使館が集中していることでも知られています。 残念ながらコロナ禍で中止になりましたが、2020年の1月から港区で開催された「港区ワールドフェスティバル」では「港区大使館等周遊スタンプラリー」という催しも開催されました。 国によって温度差はありますが、一般的に大使館は警備が厳しく、容易に入れません。米国大使館(港区赤坂)は建物に近づいただけで、近くの警察官が「なにか御用ですか?」と声をかけてきます。 米国大使館(画像:(C)Google) もっとも警備が厳しいのは千代田区のイスラエル大使館(千代田区二番町)で、入館する際には小銭入れの中まですべて見せないといけません。 なお日本に大使館を設置している国は156で(2020年2月末時点。欧州連合代表部を含む)、そのうち港区には約半数が存在しています。このともからも港区はセレブエリアでありながら、同時に大使館エリアでもあるのです。 当初、寺に置かれた外国公使館当初、寺に置かれた外国公使館 そもそも、港区にはなぜ大使館が多いのでしょうか。その理由は、幕末の開国に由来していました。 開国した日本では当時、国交を結んだ国の公館を置くことに。最初に置かれた外国公使館は四つで、いずれも港区内の寺に設置されました。 ・アメリカ(善福寺。元麻布) ・イギリス(東禅寺。高輪) ・フランス(済海寺。三田) ・オランダ(西応寺。芝) 寺に設置されたのは、接遇するにふさわしい、格のある施設だったからです。 外国公使館が最初に置かれた港区内の寺(画像:(C)Google) もともと寺は多くの人員を収容でき、加えて使節や位の高い客の接遇に使われていたこともあり、その前例に倣ったのです。 明治時代になると、これらの公使館は明治政府から新たに土地を得て移転することに。その際に得たのが元大名屋敷だった土地です。 外国公使館は固まっていたほうが警備がしやすいという明治政府の都合もあり、積極的に旧大名屋敷を提供されました。 しかしつい数年前までは尊皇攘夷(じょうい)が主張され、各国の公使館が焼き打ちにされたり、外国人が襲撃されたりしていた時代。そうした背景からも、最も重要視されたのが「警備しやすい」という点でした。 また外国人にとっても、港区は政府機関の集まる東京と船の出る横浜港のどちらにも近いということで便利だと考えられていました。 時代を経て、テナント型の大使館も こうした都合により、最初に多くの公使館が現在の港区に集まったことから、遅れて日本と国交を結んだ国も近くに建てていったというわけです。 もともと港区は大名の下屋敷(別邸)があった江戸の郊外だったことから、早い者勝ちで公使館を設置した国ほど土地は広大になりました。 第2次世界大戦後に独立国は一気に増えましたが、この頃になると港区の地価が上がっていたこともあり、多くの国は独自に建物を持つことができずに、ビルのテナントとして入居しているようになったのです。 フランス大使館(画像:(C)Google) ちなみにフランス大使館(南麻布)は2009(平成21)年に新築された、ガラス貼りのおしゃれな建物ですが、敷地内には徳川時代の庭園が維持されています。 社長が多く、下町エリアもちらほら社長が多く、下町エリアもちらほら このような大使館の存在は、前述の「港区女子」が生まれるような独特の文化を後押ししている面もあります。 東京商工リサーチ(千代田区大手町)が2017年にまとめた「東京都23区 社長の住む区調査」によると、港区在住の社長は2万5124人で、当時の人口は約25万人。23区中最多の9.94%となっています。 ほかの区をみると、千代田区が同率の8.62%、中央区6.51%とどちらも高いのですが、港区はいわば10人にひとりが社長なわけで、そのセレブぶりに改めて驚きます。 社長たちが集まる理由には、もちろん港区のブランド力がありますが、そのひとつが大使館の多さ。大使館が多いからといってビジネスに直接関係するわけではありませんが、なぜかブランド力になるそうです。 ロシア連邦大使館(画像:(C)Google) そんな港区でも、庶民的な下町エリアは少なくありません。ロシア連邦大使館(麻布台)はまさにそう。そんなギャップを見物しながら行う散歩も楽しいものです。
- 未分類