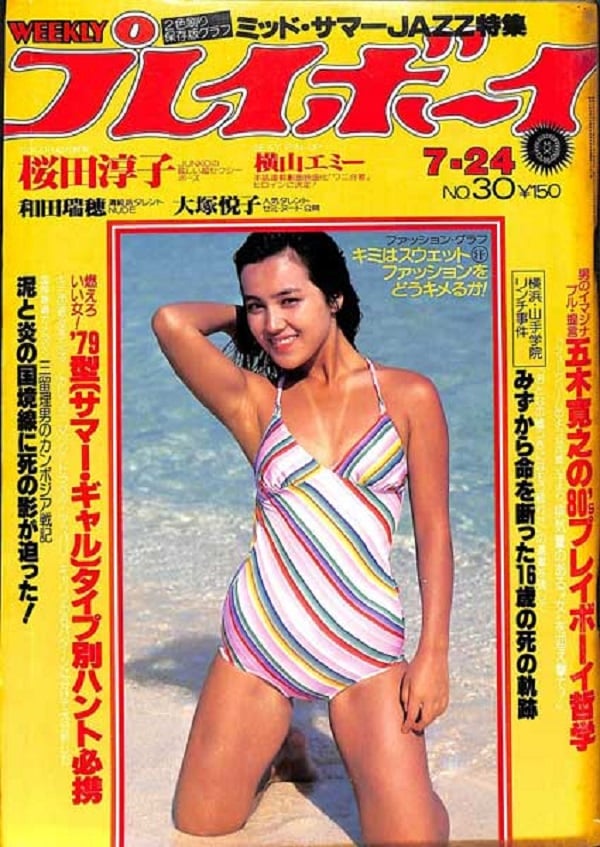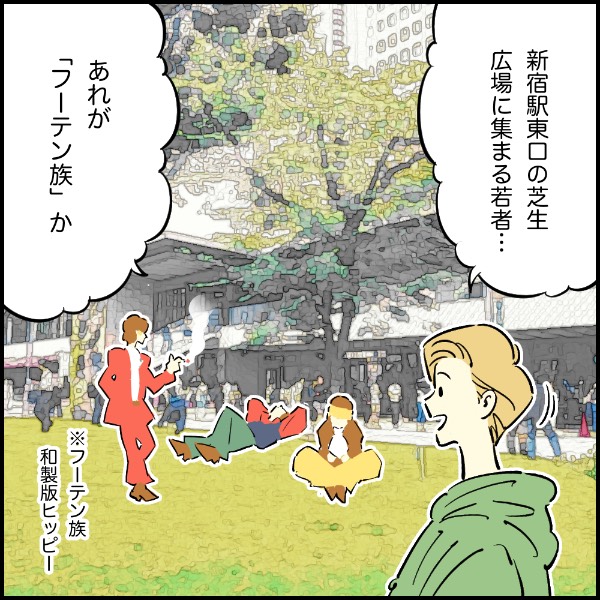都内最古の陸橋が、なぜか多摩「ニュー」タウンにある理由
200余りの橋がある「橋だらけの街」 東京西部の丘陵地帯に広がる多摩ニュータウン。この街はさまざまな特色を持っていますが、そのひとつに「橋がとても多い」ということが挙げられます。 なにしろ丘陵地帯に開発された街のため、高低差は避けられません。移動の際の上り下りを少しでも減らすために多くの橋が不可欠だったのです。 また都市計画にあたって、車道と歩道を分離して人が安全に歩けるようにしたこともあり、車道と歩道が交差する場所では、横断歩道ではなく歩道橋が設けられました。 そうした都市計画の結果、多摩ニュータウンは川にかかるものを含めて200余りの橋がある、ほかでは例をみない「橋だらけの街」になったのです。 ニュータウンに「都内最古」の橋 そんな多摩ニュータウンですが、街としては比較的新しいにもかかわらず、都内最古の陸橋があります。京王線の京王堀之内駅、南大沢駅の南にある長池公園(八王子市別所)にある長池見附橋がそれです。 長池見附橋(画像:写真AC) 長池公園は2000(平成12)年に開園した、多摩ニュータウン西部では最大の公園です。 湊川の戦いで戦死した南朝の武将・小山田高家(生年不詳~1336年)の妻である浄瑠璃姫が高家の後を追い、薬師如来像を背負って入水(じゅすい)。その後、引き上げられた像が祭られている薬師堂が建てられたという土地にあります。最近は、テレビドラマのロケ地としても、よく知られています。 長池公園の歴史は20年程度ですが、長池見附橋はなぜか都内最古というのは理由があります。 この長池見附橋は、もともとJR中央線四谷駅のところにあった四谷見附橋を移築したものなのです。 長らく四谷のシンボルだった四谷見附橋長らく四谷のシンボルだった四谷見附橋 現在の長池見附橋である、初代の四谷見附橋が東京市によって建設されたのは1913(大正2)年のことです。 建設当時、国内でも2番目だったといわれる橋は鋼製アーチ道路橋。日本橋も手がけた東京市の技師・樺島正義(かばしま まさよし)が設計したネオバロック様式の橋でした。 迎賓館の主庭(画像:写真AC) この橋がとてもしゃれたデザインになったのは、近くにあった迎賓館(旧赤坂離宮)との関係です。こちらもネオバロック様式のデザインだったこともあり、調和するよう設計されていたのです。かつては、橋の上から赤坂離宮を見ることができたと言われています。 アーチ形の橋脚や、花模様など凝った装飾の欄干、橋灯をしつらえ、文明開化の雰囲気を残したモダンな橋は、長らく四谷のシンボルとして親しまれてきました。 なお最も古い橋は大阪市の木町橋で、四谷見附橋よりも4か月前に完成ということが調査時に判明しています。 突如、橋を襲った存続の危機 しかし、危機がやってきます。 橋の上を通る国道20号線を拡幅するために、どうしても橋を新しく架け直さなくてはならなくなったのです。 この計画が具体化したのは1978(昭和53)年。高度成長期ならば構わず取り壊されていたでしょうが、この頃になると文化財の保存熱も高まっていました。 なにしろ解体の話が出る前の1972年には、新宿区の彫刻工芸部門の文化財にもなっていたのです。時代に合わないからと壊してしまうわけにはいきません。 四谷見附橋(画像:(C)Google) 東京都は結果として、赤坂離宮と調和する設計がなされている橋の欄干部分は、新しい橋に再利用。下部のアーチになった部分は移設して建設することに決定。このとき、多摩ニュータウンに移設して街のシンボルにしようということになったのです。 橋の設置費用は住宅都市公団が負担、完成後は八王子市が管理するということで計画は進みました。 橋の完成は1993年橋の完成は1993年 明治・大正期の建築物を文化財と考える人が今ほど多くなかった時代、この移設保存は画期的なことでした。 アーチ部分はすべて解体されて、多摩ニュータウンに運ばれて再現作業が始まります。単に組み立てなおすだけではありません。建設当時の図面なども調査され、既に失われていた橋灯などを復元する作業も進められます。 1963(昭和38)年頃、現在の多摩ニュータウン付近の様子(画像:国土地理院) 部品の一部を受け取り、それをもとに建設された当時の橋を再現するわけですから、費用は通常の橋を造る数倍がかかります。 加えて、もとの四谷見附橋は古く、鉄筋が入っていない無筋コンクリートの外側にれんがを施していたことから、現在の基準ではそっくりそのまま再現するわけにもいきません。 現在の基準に沿うように設計しつつ、新規の部品を使うことはなるべく避けるわけですから、なかなかの難題です。 とはいえ、無機質なデザインばかりになりがちな多摩ニュータウンにモダンなシンボルを設置したいという関係者の意欲は強かったのか、工事は着々と進み、1993(平成5)年に完成。橋は結局、もとの四谷見附橋の部品が全体の84%を占めました。 それぞれが「地域のシンボル」に さて、新築された2代目四谷見附橋も上部には旧橋の部品を使ってモダンなデザインで建設することに。欄干などに旧橋の部品を使うだけでなく、下の部分も旧橋のアーチをイメージした設計が行われることになりました。 今、四谷駅を降りて橋を見るとレトロな雰囲気を感じるのは、実際にそうしたデザインと部品が使われているからなのです。 四谷見附橋からの風景(画像:写真AC) もともとの橋がふたつに分かれて、それぞれが「地域のシンボル」になっている――このような例は、東京でもこれしかないと思います。
- 未分類