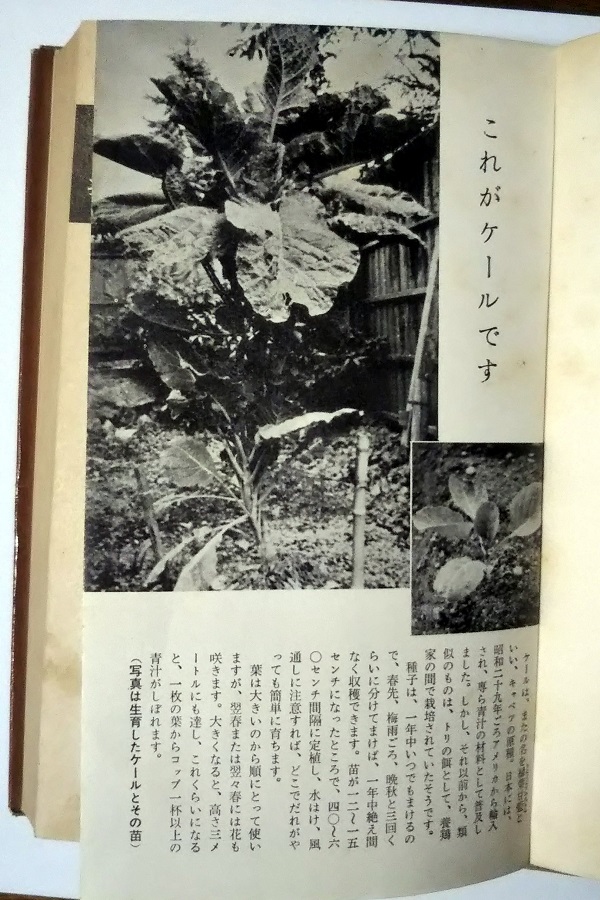東京都全体のわずか3% 山手線内側エリアこそ真の「都心」と呼ぶべき存在か
レジャー情報や不動産情報などでよく使われる「都心」という言葉。東京の意外に知られていない都心の“核心”について、住宅評論家の櫻井幸雄さんが解説します。近年広がり続ける「都心」 近年、「都心」が広まっています。 大阪でも中心部は都心と呼ばれ、福岡、札幌、広島、仙台、金沢でも中心地を都心と呼ぶことがあり……。「えっ、都心は東京だけのものではないの?」と言いたくなりますが、本来の意味で言えば、都心は「都会の中心エリア」を示す言葉。だから、東京以外の大都市の中心地を都心と呼んでも間違いではありません。 それでも大阪市より人口が多い横浜市では、横浜駅から関内駅周辺を都心と呼ぶことはないので、「都心は東京のもの」という意識は多くの人の心にあるのでしょう。 そんな東京の「都心」ですが、こちらも近年広まっています。 山手線内側(画像:(C)Google) かつては、都心3区(千代田区、中央区、港区)が都心でしたが、それに新宿と渋谷区が加わって、都心5区に。さらに文京区が加わって都心6区となりました(渋谷区の代わりに台東区を入れることも)。 「それなら目黒区と品川区も入れるべきでしょう」と2区を加えて都心8区……さらに、都心10区という区分けも生じて「都心」が広がっているわけです。 畑が残る場所でも「都心」?畑が残る場所でも「都心」?「憧れの都心」「いつかは都心のマイホーム」と言われながら、「東京・都心」の定義は、あやふやです。 はっきりした定義がないので、不動産の世界では「都心マンション」と印象づけたいがために東京23区をすべて都心としてしまう傾向もあります。練馬区や板橋区で畑が残る場所にマンションを建設し、「割安な都心マンション誕生」としたいのでしょう。 いまだに多くの畑が残る練馬区(画像:(C)Google) しかし世田谷や杉並を含め、23区内でも閑静な住宅エリアを都心と呼ぶのは少々無理があります。「分譲価格が高くても住宅が売れる場所」こそが都心と考えれば、「JR山手線内側を中心に、一部外側を含んだエリア」が、現実的な「東京・都心」でしょう。 「山手線内側」を都心の目安とすると、喜ぶ人たちがいます。それは、外国人や地方に住む人たち。東京のことはよく分からないが投資物件としてマンションを買いたい、と思っている人たちです。 「都心マンションは値下がりしにくく、投資物件として最高」などと言われるので、都心のマンションを買ってみたい――。しかし、具体的にどの場所のマンションを買ってよいのか、東京のことを知らない人には分かりにくいものです。 一般的には、山手線内側が「都心」 そこで、役立つのが「山手線内側」という線引き。これは、地図上ではっきり分かるため、「この物件は買い」「これは、買わない」という判定がしやすい。判定の目安として、使いやすいのです。 東京「都心」のイメージ(画像:写真AC) その線引きのためか、目黒駅や五反田駅、駒込駅などでは、山手線外側であるだけで、マンション価格がガクンと落ちることがあります。 近年、山手線内側だけで異常に不動産価格が上昇しているのですが、その背景には、この「分かりやすい線引き」の影響があるのでは、と考えられます。 その山手線内側には、意外と知られていない事実があります。その中で、興味深いふたつを紹介しましょう。 想像以上に狭い「山手線内側」想像以上に狭い「山手線内側」 山手線内側の広さは、63~65平方キロメートル。東京23区の総面積が619平方キロメートルなので、その10分の1程度の広さしかありません。東京市部も含めた都全体面積を基準にすると、山手線内側はわずか3%。希少価値が高いのです。 その希少価値をさらに高めているのが、東京湾の存在。東京湾があるため、都心の広がりは制限されている、という事実もあります。 そのことが分かるのは、普段見ている地図を逆さまにしてみること。地図は北を上にするので、いつも見る東京23区内の地図では、東京湾が下になります。この地図を上下逆にし、東京湾が上にしてみましょう。 逆さにした東京23区内の地図(画像:国土交通省) それだけのことで、妙に東京湾が広く見えるから不思議です。海が主役になり、大手町や銀座は港町のような存在に思えてしまう。地図を逆さまにすることで、東京23区は4分の1程度を海で削られていることが実感できるはずです。 その海の一部を盛んに埋め立てて、湾岸エリアが形成されているのですが、埋め立てできるのは、東京湾のほんの一部。都心からの広がりは、東京湾によって、25%ほど削られているのです。 周囲への広がりが4分の1制限されているので、都心への依存度が高くなってしまう……それも山手線内側が便利な場所として偏重される理由でしょう。山手線内側の面積は広がることがなく、その希少価値は、この先も変わりません。 便利さ、楽しさが集約された場所でもある便利さ、楽しさが集約された場所でもある 限られた面積の都心(山手線内側)は、一方で魅力が多い場所でもあります。 政治とビジネスの拠点が集まり、買い物やグルメ、遊びのスポットも集約されています。仕事をこなしやすく、楽しみも多い場所であるわけです。 さらに、坂が少ないのも、山手線内側の利点になります。山手線内側で最も標高が高いのは、新宿区戸山にある箱根山の標高約44.6mとされます。 山手線内側の地形図(画像:国土地理院) しかし箱根山は人工の山なので、自然の地形でそれほど高い場所は山手線内側には存在しません。新宿駅が山手線の最高地点で、標高約36m。山手線内側では、高いところでも標高は30数mとされているのです。 これは、標高が150mを超す場所もあり、坂の多い横浜市内と比べると、平らで暮らしやすい場所が多いことを示す数字です。 虎ノ門ヒルズ(港区虎ノ門)など、再開発が途切れることなく続いているのも、山手線内側の魅力。山手線内側を都心と考えれば、その不動産価値は落ちそうもなく、マンション価格の下落も期待しにくいことになります。
- ライフ
- 東京