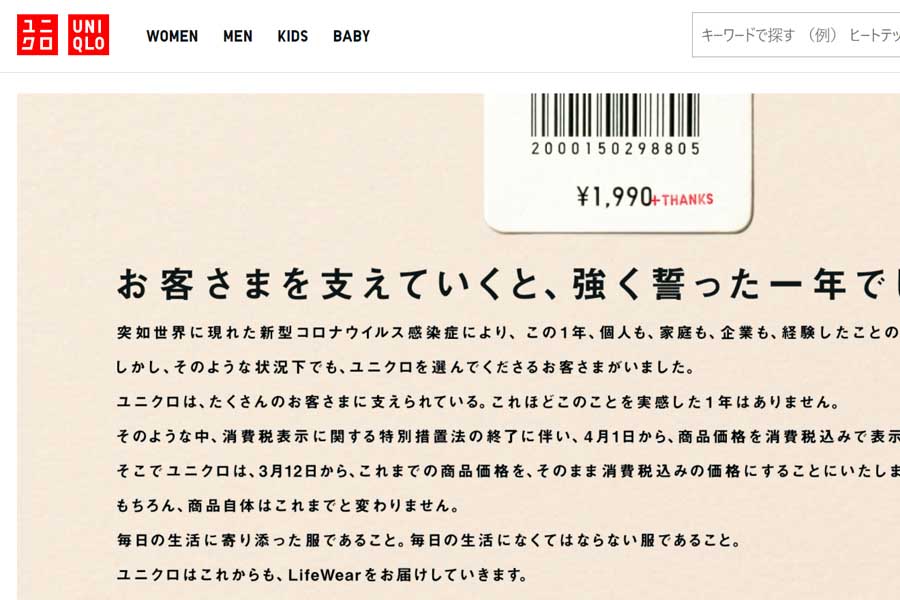新型コロナ収束で、日本の教育現場はいったいどのように変化するのか
教育現場の在り方さえ変える新型コロナ 新型コロナウイルスのさらなる感染拡大を防ぐため、政府の専門家会議から新しい生活様式が提案されています。 スーパーマーケットのレジ待ちでも推奨されている、ソーシャルディスタンス(人と人との距離を保つこと)のように生活に少しずつ浸透し始めているものもあれば、買い物は少人数で短時間のうちに済ませる、といったものまでさまざまです。 このような提案により、コロナ後の教育現場を取り巻く環境も劇的に変化していくのは避けられません。では、コロナ後の教育現場は具体的にどのように変わっていくのでしょうか。 保護者参加の行事も変わるか 現在風邪をひいていなくても、外出時にはマスク着用が、会話時には相手の真正面で話をしないことが推奨されています。 学校で先生や生徒たちが会話をするのはごく当たり前のことであるため、季節に関係なく先生はマスクを着用し、子どもたちは低学年からマスク着用が義務化され、習慣となっていくでしょう。 マスクを付けた子どものイメージ(画像:写真AC) 政府が提案した生活様式を見ても、教室内の机間で距離を作るため、以前のように席替えで盛り上がることはなくなり、給食時の班ごとの対面スタイルもなくなり、全員が黙々と食べるようになります。 学校でのマスク着用はもちろんですが、「3密」を防ぐために大勢の保護者が集まる運動会や授業参観、発表会といった行事も異なった形で行われます。学年ごとに実施されたとしても、保護者が密集しないよう、入れ替え制や人数制限が導入され、感染防止策が徹底されます。 場合によっては、「運動会の場所取りが行われていたのもコロナ以前だったね」――と言う日が来るかもしれません。 体育や調理実習の内容も見直される体育や調理実習の内容も見直される さらに教室以外の授業を行うことが多い学校は、体育や家庭科で大幅な見直しがされます。 文部科学省が3月26日(木)から断続的に公表している「教育活動再開等に関するQ&A」には、体育館を使用する場合は換気を実施し、児童生徒が集合・整列するのを避けることが明記されています。 また、人と人が接しやすい球技の実施は感染状況を踏まえて、年間計画内で順番を変更するよう、現場に工夫を求めています。 文科省の意向を受け、ふたり一組で行う運動や子ども同士が接触することの多いドッジボール、バスケットボールといったグループ競技の回数も例年より減る、または見送られます。 運動会のイメージ(画像:写真AC) 体育は内容を変えることで実施できますが、小学校高学年以上で行われる調理実習はマスクを着用しても、授業目的である実食は普段通りとはいきません。 前述の文部科学省の文書では、家庭科は順序変更のほかに、衛生面の一層の強化を指示していますが、グループごとに対面で料理を食べることを念頭にした机の配置や教室構造を考えると、人数制限を設けて少人数で、合計2~3回に分けて調理実習を行うしかありません。 しかし休校によりカリキュラムの消化が懸念されているなか、家庭科に時間を割くことは現実的に難しくなっているのが実情です。 オンライン化が加速する 学校現場は新型コロナウイルスによって激変しますが、学習塾のような教育産業も急激な変化への対応が避けられません。大手だけでなく家庭教師や個人塾においても、生徒や保護者のニーズに合わせる必要が出てきています。 オンライン授業を受ける子どものイメージ(画像:写真AC) 学校同様に先生たちはマスクをつけ、生徒たちもマスク姿で授業を受けることになります。 しかし公共交通機関での移動や教室での感染に不安を感じ、可能な限り在宅で授業を受けることを望む家庭も出てくるでしょう。 そういった要望に応えるべく、塾側はライブ配信などで対応し、不安を払拭(ふっしょく)させるしかありません。 生徒獲得イベントもオンライン化へ生徒獲得イベントもオンライン化へ コロナ禍により、教室や会場を使った大規模なテストや保護者に向けた説明会の中止が相次いでいます。 オンライン授業を受ける子どものイメージ(画像:写真AC) これまで当たり前のように行ってきたイベントの数々も、インターネットを介して生徒や保護者に届けられるよう、塾側も模索していくでしょう。 授業だけではなく、生徒獲得につながるイベントの数々もオンライン化が進んでいく可能性が、この1~2か月の間で現実味を帯びています。 緊急事態による一過性の対応ではなく、今後は「常識」として定着していくのは自然な流れと言えます。 明治維新や戦後並みの大きな転換期となるか 近代日本が歩んできた教育の歴史を見ると、大きな転換期となったのは ・明治維新による学制公布 ・戦後教育 のふたつです。 教育の在り方が問われている(画像:写真AC) 今回のコロナ禍は、それに匹敵するほどのインパクトを持っています。 官民問わず、既存の教育システムを根本的に見直す機会になっており、コロナ禍が落ち着いても、学校生活や塾はこれまで通りに戻ることは考えにくい状況です。 また、こうした感染症はいつ起きるか分かりません。 この20年を見ても、SARSや新型インフルエンザ、MERSが猛威をふるってきました。感染の芽をつぶすため、不安を取り除くため、あらゆることが変化を求められているなかで、学校教育も教育産業も大きな岐路に立たされています。
- ライフ