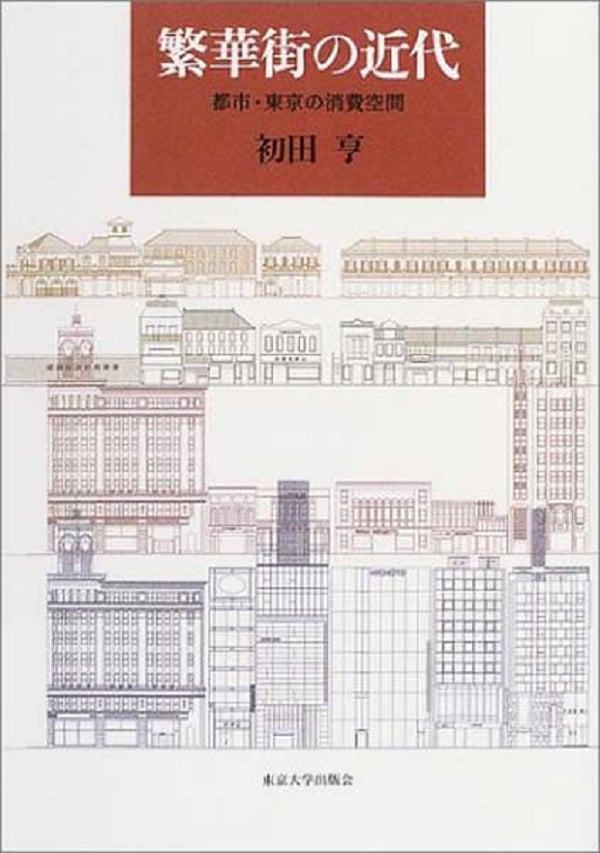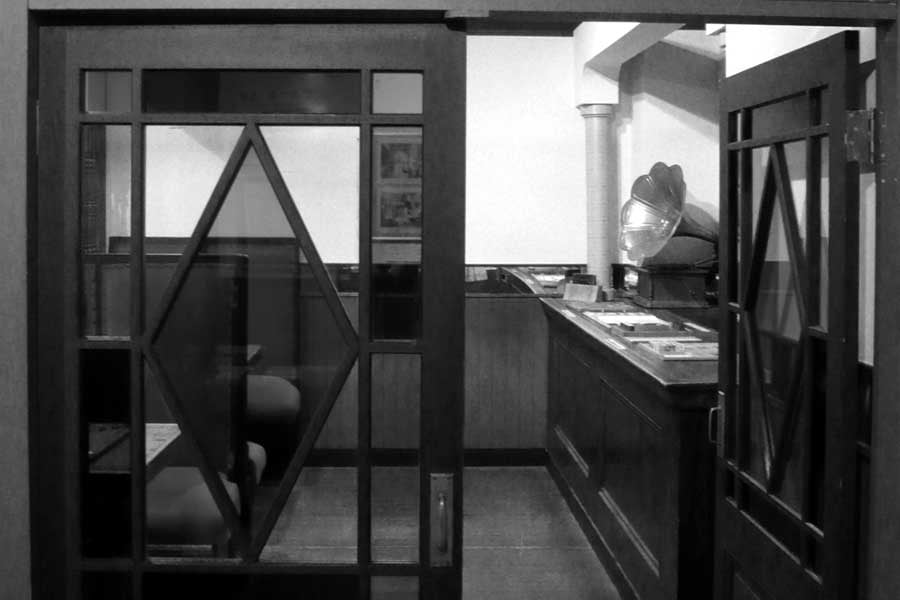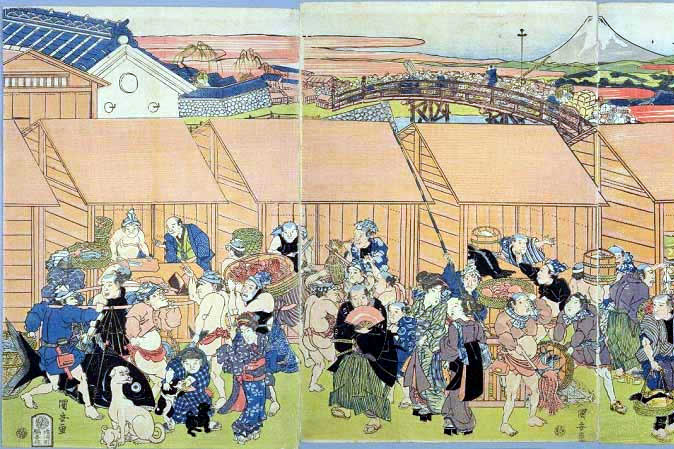都電ファン歓喜? 御茶ノ水駅前の工事で突如現れた「歴史的遺構」の正体
荒川線だけが残ったワケ 東京をかつて網の目のように走っていた都電は、早稲田~三ノ輪橋間の荒川線を残すのみとなっています。他路線が次々と廃止されたのにも関わらず、都電荒川線だけが残ったのにはいくつか理由があります。 JR御茶ノ水駅(画像:写真AC) その理由のひとつに、自動車と電車が混在して走らない、いわゆる「専用軌道区間」が多かったからというものがあります。 廃止された都電の多くは、道路の上を走っていました。路面電車が自動車と一緒に道路の上を走る区間は、「併用軌道区間」と呼ばれます。 併用軌道区間を走ることが多かった都電は、自動車が増えてきた昭和30~40年代にかけて邪魔者とみなされるようになり、次々と廃止に追い込まれました。都電荒川線は専用軌道区間が大半を占めていたこともあり、生き残ったのです。 廃止が相次いだことで、あちこちに都電が走る光景は過去のものになりました。そして歳月は流れ、都電全盛期が遠くなっていた今は都電を懐かしむ人も少なくなっています。 アスファルトの下から線路が露出 しかし、ふとしたことがきっかけで、都電がフィーチャーされる事態が起きています。 このほどJR御茶ノ水駅に隣接するお茶の水橋と聖(ひじり)橋で長寿命化と拡幅を兼ねたリニューアル工事が実施されました。 一連の工事ではいったん、お茶の水橋の道路のアスファルト舗装を剥がしました。その際に、アスファルトの下から線路が露出。その世紀の発見が話題になっているのです。 路面電車の線路が露出したお茶の水橋(画像:(C)Google) 道路の上の架線から電力の供給を受けて路面を走るトロリーバスに転換され、1952(昭和27)年に姿を消した26系統を含め、都電には41系統がありました。都電が都民の足としてフル活用されていた昭和30年代、御茶ノ水駅前には新宿駅前と水天宮前を結ぶ13系統が走っていました。 新宿駅前を出発した13系統は若松町から飯田橋に至り、そこから神田川に沿うように外堀通りを走り、お茶の水橋を渡らずに秋葉原駅から日本橋方面へと向かうルートを取っていました。お茶の水橋の上を走っていた都電は戦後には存在しません。 76年前に廃止された錦町線という区間76年前に廃止された錦町線という区間 都電が走っていなかった区間にもかかわらず、なぜ今回の工事で道路から線路が露出したのでしょうか? 橋の工事でアスファルトが剥がされたために、出現した都電の線路(画像:小川裕夫) それは、今回露出したのは1944(昭和19)年に廃止された区間の線路だったからです。同区間は、お茶の水と錦町河岸(がし)とを結ぶ錦町線と呼ばれる区間でした。 太平洋戦争が激化していた当時、政府は銃や弾丸といった兵器製造に必要な金属類を全国から回収していました。 政府の金属回収でターゲットにされたのは、全国の学校や公園などに建立されている銅像、そして鉄道の線路などでした。線路は軍事輸送にも欠かせないため、政府は不要不急な路線を選び、それらを回収したのです。 廃線をまぬがれた御殿場線・嵐山線 不要不急とみなされた路線は全国に及びました。そして、線路を失った路線の多くはそのまま廃線に追い込まれています。 JRの国府津~沼津間を結ぶ現在の御殿場線や阪急電鉄の桂~嵐山間を結ぶ嵐山線は金属供出により廃線に追い込まれることはありませんでしたが、複線だった区間が単線化されました。 桂~嵐山間を結ぶ阪急電鉄嵐山線(画像:写真AC) しかし、そうした苦境を乗り越えて、現在も単線のままで運行されています。 不要不急とみなされて廃止された路線の線路は、通常なら金属供出の目的通りに回収されます。本来なら、お茶の水橋の道路上にあった線路も回収されるはずでしたが、なぜか免れることができました。70年以上もの歳月を経て、それが姿を現したのです。 歴史的遺構に出会えるチャンス歴史的遺構に出会えるチャンス 線路が露出した現地は、工事の真っ最中です。背の高いフェンスで覆われているわけではないため、ニュースを聞きつけた人たちが多く訪れています。 歴史的な遺構を見るために現地には、多くの人たちが足を運んでいる(画像:小川裕夫) 70年以上前に廃止された区間なので、当時を知る人は多くありません。現地を訪れている人たちも昔を懐かしむというより、歴史的な発見を一目でいいから見てみたいという思いが強いようです。 アスファルトの下から露出した線路は、戦時を知る貴重な歴史的遺構といえます。永い眠りから覚めた線路を目にできる機会はわずかな工事期間だけとなる可能性が高く、それだけに千載一遇のチャンスといえるかもしれません。
- 未分類