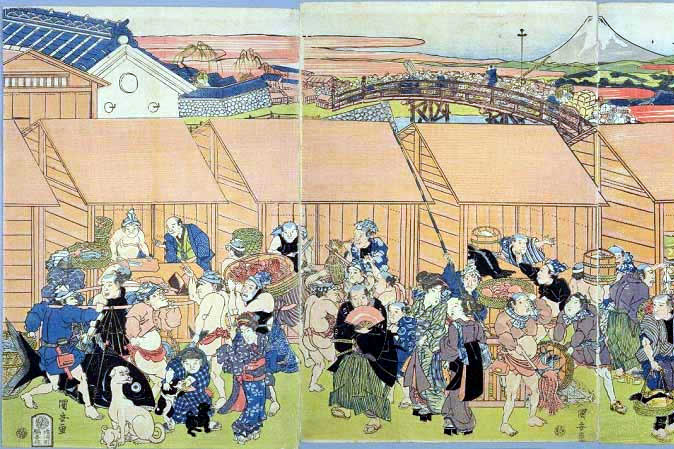昭和レトロな街並みが高架化事業でパワーアップ 大田区・雑色エリアを知っていますか
10年間で大きくイメチェンした大田区 東京23区の中でも、近年著しく変化しているのが大田区です。 区内を走るJR京浜東北線と京急線を使えば、都心に一直線。それなのに、昭和の風景が広がっている――そのような大田区のイメージは、この10年間で大きく変わりました。 銀座や有楽町という一大繁華街へ乗り換えなしで行ける点が注目され、急速にベッドタウンとして変貌を遂げています。 さまざまな店舗が並ぶ雑色商店街通りの様子(画像:(C)Google) 中でもおどろくほど変化したのは、京急蒲田駅(大田区蒲田)と雑色駅(同区仲六郷)の周辺です。 かつて京急蒲田駅からは羽田空港と横浜方面へ向かう線路は幹線道路の第一京浜を横切っており、巨大な踏切が街のシンボルになっていました。 駅の周辺には昭和からそのまま変わらない風景が広がり、せわしない都会に疲れたときにブラブラと歩いて心を癒やすことができました。 それも今では過去の話。京急蒲田駅の高架化とともに、駅前にはマンションが誕生。ロータリーも完成し、新たなベッドタウンの玄関として、変貌を遂げました。 「雑色」という地名の由来 京急蒲田駅よりもさらに変化が著しいのが、横浜方面にひと駅行った雑色駅です。雑色(ぞうしき)という少し変わった駅名は、この辺りがもともと雑色村と呼ばれていたことに由来するものです。 現在の地名は仲六郷2丁目であるため、雑色の地名は駅名だけに残っていることになります。雑色とは、平安~鎌倉時代に宮中の雑役の役目を担っていた下級役人のことを指す言葉です。 平安~鎌倉時代、この地域は宮中のある京都からは遠く離れた、ほぼ別の国のような地域。それにもかかわらず、なぜこのような地名がついたのでしょうか。 調べてみると、地域にある雑色八幡神社に奉公していた人たちが住んでいたことに由来するようです。 雑色八幡神社(画像:(C)Google) 雑色八幡神社は、江戸時代後期に編さんされた『新編武蔵風土記稿』にも記されている神社ですが、そのときすでに「勧請(かんじょう。神仏の分霊をほかの場所に移し祭ること)の年代詳ならず」すなわち、神社の創建された年代や由緒がわからないものになっていました。 ただ、神社とともに古くから人が住んでいた土地であることは間違いないようで、環境のよい土地であったことは間違いないようです。 高架化で商店街の雰囲気も変化高架化で商店街の雰囲気も変化 雑色駅周辺は2017年に高架化工事が完了するまで、完全に昭和な雰囲気があふれる街でした。 駅は平屋建て。改札を一歩抜けるとロータリーもなく、いきなり商店街のアーケードに出くわします。それもアーケードの入り口が駅に面しているのではなく、アーケードと直角方向に結ばれる形です。それが独特の雰囲気を生み出していたのです。 そのような雰囲気も高架化の工事によってガラリと変わりました。 リニューアルした雑色駅前の様子(画像:(C)Google) 駅そのものが川崎方面へ移動。工事を終えた駅の前には広場ができ、コンビニもオープン。一気に、郊外のベッドタウンの駅へと生まれ変わったのです。 こうなると商店街の雰囲気も変わります。独特の雰囲気は、古い店と新しい店とが共存する活気のあるものへと変わりました。 かつてあったオーケー本社 雑色駅周辺は、もともとポテンシャルの高い地域です。というのも、地域には商店街だけでなく、巨大スーパーマーケットのオーケーストアがあるからです。 オーケーストア サガン店(画像:(C)Google) 今はみなとみらいへ移転してしまいましたが、雑色は2016年まで、オーケーストアを運営するオーケー(横浜市)が長らく本社を置いていた地です。たとえ本社が変わっても重要な土地であることには違いありません。 なにせ、駅の南には仲六郷店、北にはサガン店と二店舗も構えているのですから。 郊外のベッドタウンとはまるで違う雰囲気郊外のベッドタウンとはまるで違う雰囲気 そのような商店街とスーパーの充実した雑色駅周辺は、高架化によって京急蒲田駅周辺よりも恩恵を受けているといえるでしょう。 高架化以前は独特の雰囲気が濃かったように、雑色駅は各駅停車しか止まらず、決して便利とは言えません。しかし駅のリニューアルによって、そのような雰囲気はむしろプラスに変化しているといえます。 さまざまな店舗が並ぶ雑色商店街通りの様子(画像:(C)Google) 郊外のベッドタウンにありがちな、チェーン店は一通りそろっているが、まったく面白みがない駅前とはひと味違うからです。 雑色駅一帯を強く推す理由 さらに筆者(昼間たかし。ルポライター)が雑色駅一帯を強く推す理由は、近くを走る第一京浜にあります。 雑色駅近くを走る第一京浜(画像:(C)Google) この一帯は住宅地のため、夜19時を過ぎると人通りは少なくなります。それでいて、幹線道路はひっきりなしに車が行き交っています。空は広く、遠くには都心の明かりも見ることができます。そこをトボトボと歩いているだけで、都会に疲れた心を癒やすことができるのです。 ちなみに周辺散歩で特にオススメしたいのは、日が暮れてから一度川崎まで行き、徒歩で多摩川を渡って都内に戻ってくるルートです。
- 未分類