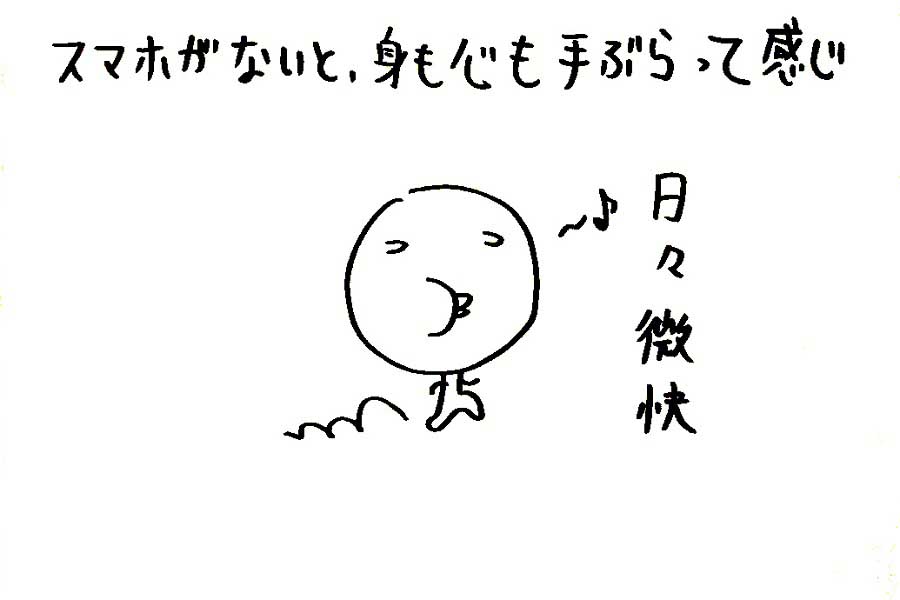金髪ショートの平成「あゆギャル」が、当時「量産型女子」と認定されなかったワケ
「皆が同じ格好」という共通点「量産型女子」という、ややネガティブなニュアンスを持った言葉が現代にはあります。 ファッションやメイク、ヘアスタイル、持ち物や趣味などが均一的で「どこにでもいそうな」若い女性を指す表現ですが、今から20年ほど前も世間の女性たちは皆、同じような格好をして東京の街を闊歩(かっぽ)していました。 当時、誰もがまねしたくなるような「カリスマ」が存在していたからです。 あゆの特集ページが組まれた、筆者所蔵の角川春樹事務所「Popteen」2001年5月号(画像:Tajimax、角川春樹事務所)「皆同じ格好をしている」という点で共通する両者は、本質的には似て非なるもの。今回は、このふたつの時代を「ファッションの流行」という観点から考えてみたいと思います。 なぜ「今」浜崎あゆみなのか 世間が新型コロナウイルス報道一色だった2020年の上半期。テレビドラマもほとんどが収録スケジュールの遅れにより通常放送できていないなか、ひときわ注目を集めているドラマがあります。 平成の歌姫・浜崎あゆみの半生をベースにした「M ~愛すべき人がいて~」(テレビ朝日系)です。 大げさなストーリー展開やクサいせりふ回しは賛否が分かれるところですが、いずれにせよ話題を集めていることは確か。興味深いのは、「M」の視聴を楽しんでいるのが、あゆ全盛期をリアルタイムで見てきた30代の筆者や同世代だけではない点です。彼女のデビュー(1998年)前後に生まれた20代の若者たちも今、このドラマに夢中になっているというのです。 注目を集めているテレビ朝日系ドラマ「M ~愛すべき人がいて~」(画像:AWA) デビュー当時からあゆを知る筆者や同世代以上にとっては「いまさら感」や「懐かしさ」がない交ぜになった感覚を覚える同作ですが、20代にとっては90年代や00年代、さらには浜崎あゆみが非常に新鮮に映るらしく、SNS上などでは「90年代バブル」という言葉が生まれたほど。 なぜ今、令和の若者に浜崎あゆみが受けるのか。まずは平成の時代にあゆが残した流行をひも解いてみましょう。 流行を生み出し続けた歌姫の軌跡流行を生み出し続けた歌姫の軌跡 令和の現代に流行を先導するとされているのは、比較的少数ながら強固な支持者を抱えるインフルエンサーと呼ばれる複数の人物たち。一方、あゆ全盛期だった90年代後半~00年代前半は、時代に選ばれし象徴のような「カリスマ」が、ファッションから振る舞いまであらゆる価値観を生み出していました。 当時のツートップといえば、おそらく多くの人が安室奈美恵と浜崎あゆみの名を挙げるでしょう。 「流行に疲れる」という言い回しをしばしば耳にしますが、筆者が青春時代を過ごした時期に全く退屈することが無かったのは、次から次へと見たこともない新しい流行が、常に目まぐるしく生まれ続けていたからだと思います。 今ではすっかり定番となったアイテムも、当時は新鮮さと輝きを放っていました。 茶髪から金髪へ、ロングからショートへ 筆者の手元にある女性ファッション誌のバックナンバー、安室奈美恵が表紙を飾った1996年10月号「ViVi」をめくると、1994(平成6)年から1996年頃まで、メッシュや茶髪のロングヘアが東京の女の子たちの定番スタイル。 しかし、2000(平成12)年と2001年の「Popteen」を見ると、今度は金髪の威風堂々としたあゆが登場します。 安室奈美恵が表紙の講談社「ViVi」1996年10月号と、浜崎あゆみが表紙の角川春樹事務所「Popteen」2001年5月号(画像:Tajimax、講談社) それまで「悪目立ち」の代表格のようだった金髪を一般に流行させ、また「女の子はセミロング以上がかわいい」という漠然としたイメージを大きく覆したのは、この時期のあゆが披露したヘアスタイルによるところが大きくあります。 何年かに1度はやって来るショートヘアブームですが、ティーン世代に最もはやらせた人物はほかでもないあゆだろうと、筆者は見ています。 また、今ではすっかり知られた言葉となりましたが「ネイルアート」という分野を世間に知らしめたひとりも、やはり彼女。 マニキュア単体では以前から親しまれていましたが、ただ爪に色を塗るだけでなくスカルプチュアネイルや3Dアートといった新ジャンルを提案。2000(平成12)年から2002年、あゆは日本ネイリスト協会が表彰する「ネイルクィーン」に3年連続で選ばれ、同賞初の殿堂入りを果たしています。 見たこともない新アイテムと柄ブーム見たこともない新アイテムと柄ブーム「流行は繰り返す」とは言いますが、前例のないファッションアイテムも彼女によって生み出されました。 象徴的なのが、2001(平成13)年のCDシングル「evolution」のミュージックビデオ(MV)で身につけていたファー素材の「しっぽ」です。 ファーのしっぽを身につけたあゆが登場した角川春樹事務所「Popteen」2001年5月号(画像:Tajimax、角川春樹事務所) 筆者と同世代なら「あゆといえばあのMV!」というくらい有名な映像なのですが、一般女性たちはファーしっぽを腰に付けるのは難易度が高くても携帯電話のストラップにキーホルダーにと、さまざまな形で取り入れていきました。 そして、何と言っても「柄」ブームです。 近年では、特に主だった柄の流行は見られませんが、当時は毎年毎年、目まぐるしく流行が起こりました。 当時は決して多くなかった柄ものが、一般的なファッションアイテムの定番として多産されるようになったのも、あゆの影響なくしては語れないでしょう。 迷彩、ヒョウ柄、ネオンカラー、千鳥格子……。今思えば、よくあれほど多種多様な柄がはやったものだと、驚きを隠せません。ギャル系ブランドからOLブランドまで、とにかくこの時代は柄が流行し、東京の街角には柄ものを着た女子があふれ、その震源地には常にあゆが立っていました。 カリスマなき時代の流行とは あれから20年余り。「カリスマ不在の現代」などとも称される現代ですが、音楽シーンやポップカルチャーが衰退したわけでは決してなく、若者に対して影響力を持つメディアがSNSに移行したことによって幾人ものインフルエンサーが登場し、個々人の興味関心が細かく分散された結果だというふうに筆者は考えています。 そんな現代と照らし合わせると、流行の全てがたったひとりのカリスマにのしかかっていた当時の方が、むしろ特殊だったようにさえ思えてきます。 あゆメイクの仕方を紹介する講談社「ViVi」1999年12月号(画像:Tajimax、講談社) 情報化社会になったことで流行のスピード感は早まりましたが、SNSという手軽で便利なツールによって「正解」を求めるあまり、近年のファッションは「同質化」の傾向を帯びているようにも感じられます。 真っすぐなエネルギーがあふれていた頃真っすぐなエネルギーがあふれていた頃 冒頭でも触れた「量産型女子」という有りようは、悪目立ちしない無難さと常に「正解」をまとう安心感が保障され、確かに居心地のよいものかもしれません。 ただ、その繰り返しの果てに流行が“ルーティン化”されていってしまえば、日常を「退屈」なものにする危うさをはらんでいるようにも、あゆ時代を知る筆者は思うのです。 いつの時代にも「なりたい顔」や憧れの人物というものは存在します。ただ、ありとあらゆる情報があふれる現代は、さまざまなところから引用してきた要素から成るあいまいなモンタージュのようでもあり、ともすれば自分自身の理想すら平均化してしまう印象があります。 もちろん現代には現代の良さがあるのですが、あゆ全盛期に青春を過ごした筆者は今、「ただただ浜崎あゆみになりたい」と渇望したあの時代の、あいまいさのない真っすぐなエネルギーについてあらためて思い出しています。 今見ても、やっぱり「かわいい」と感じる2000年代初頭のあゆ掲載の講談社「ViVi」2002年2月号(画像:Tajimax、講談社) 若者の間に生まれた「90年代バブル」という言葉を紹介しましたが、「流行なき現代」を生きる若者の目に、かつての浜崎あゆみや90~00年代のパワフルさがあらためて新鮮に、個性的に、そして輝きを放って映るというのは、確かにうなずけることのように思えるのです。
- ライフ