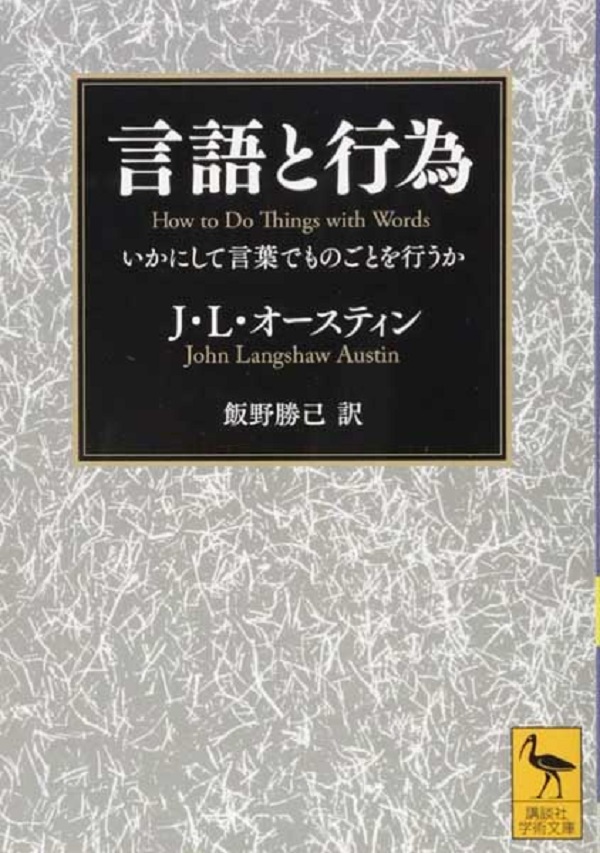「そもそも言葉とは何なのか」
「3密」がユーキャンの新語・流行語大賞に選ばれ、さらには「密」が「今年の漢字」に選出されるなど、2020年は小池百合子都知事の「言葉の力」が目立った1年でした。
新型コロナウイルスの感染状況が拡大し、世間の不安が高まるなかで、会見でフリップを掲げながら明瞭な言葉を発していく小池知事の姿が印象に残っている人も多いのではないでしょうか。
 2020年10月1日に開催された日本最大級イノベーションセンター「CIC Tokyo」のオープニングイベントでの小池百合子都知事(画像:CIC Japan合同会社)
2020年10月1日に開催された日本最大級イノベーションセンター「CIC Tokyo」のオープニングイベントでの小池百合子都知事(画像:CIC Japan合同会社)
しかしなぜ、小池知事の言葉はこれほどまでに影響力を持つのでしょうか。ここでは「そもそも言葉とは何なのか」という少し哲学的な観点から、小池知事の言葉が強力な理由を考察していきます。
言葉には「現実をつくる」機能がある
言霊(ことだま)という言葉があるように、言葉が現実化する働きに対して日本人は古くから畏敬の念を抱いてきました。また世界に目を向けてみても、例えば聖書の「はじめに言葉ありき」というフレーズに見られるように、言葉に対する信仰や特別視は時代や地域を問わず浸透しているものと考えられます。
上記は言葉が現実をつくるという視点が見られますが、「現実」と「言葉」の関係は、実際のところどうなっているのでしょう。「現実と言葉、どちらが先にあるか」と聞かれたら、多くの人は「現実」と答えるのではないでしょうか。仮に言葉が存在しなくても、現実の世界というものは実体として存在しているはずですから、そう考えるのが当然かもしれません。
現実と言葉の関係は、哲学における主要テーマのひとつとして長らく考察の対象となってきましたが、やはりその前提には「言葉は現実の事柄を言い表すためのものだ」という見方がありました。聖書になぞらえるなら「はじめに現実ありき」であって、言葉はそれを映す鏡のようなものだ、というわけです。
ところが時代が進むにつれて、この「常識」は転換されていくことになります。すなわち、「言葉があって初めて、現実というものが構成される」という考え方が登場してくるのです。
 フェルディナン・ド・ソシュールの主著『一般言語学講義』(画像:岩波書店)
フェルディナン・ド・ソシュールの主著『一般言語学講義』(画像:岩波書店)
この考え方の転換点は複数挙げることができますが、もっとも決定的だったのはスイスの言語学者で、「近代言語学の父」と呼ばれるフェルディナン・ド・ソシュールの思想です。
言葉によって現実の見え方は変わる
例えば、目の前に1本の木があると想像してみましょう。
 丘の上にある木(画像:写真AC)
丘の上にある木(画像:写真AC)
木は「根・幹・枝・葉」というさまざまな部分から成り立っています。私たちはそれぞれの部分を指し示す言葉を知っているので、当たり前のように「根・幹・枝・葉」を区別することができます。
しかしこれらの言葉を知らないまま1本の木を目の当たりにしたら、私たちはそれをどう捉えることになるでしょうか。何やらえたいの知れない、茶色と緑の長い物体としてしか認識できないかもしれません。
言葉があることで、私たちは現実の事物や事象をより明確に捉えることができます。「明確に」というのは「区別ができる」ということです。
例えば日本語では、川に生息し硬質なうろこと強力な顎を持った肉食の爬虫(はちゅう)類を「ワニ」という言葉でしか表現できませんが、英語であればどう猛で牙の鋭いcrocodileと、比較的小型で温厚なalligatorといったように区別できます。
言語や文化によって、この区別のあり方は千差万別です。例えば「色彩」は無数のグラデーションから成り立っているものですが、ひとつひとつの色を表す単語の種類によって、「どこまでが同じ色で、どこからが違う色か」という境界線の位置が変わる、ということになります。
ソシュールは「ある言葉が指し示す範囲」というものが言語によってさまざまに異なることを「恣意(しい)性」という言葉で表現しました。
恣意性はここで「必然性」の対概念となっており、「別様でもありうる」ということを意味しています。すなわち、ある言葉と現実との結びつきは必然的なものではなく、言葉が指し示す範囲は流動的に変化しうる、というわけです。
「密」は現実をどのように変えたか
これまで慣れ親しんできた言語のなかに、新しい言葉が侵入してくることによって、世界の見え方は変わっていきます。新しく覚えた言葉をやたらと使ってしまうという経験がある人は多いと思いますが、これは新しい言葉によって「事象の区切り方」が変わるために、新しく切り取られたブロックがことさらに意識に上ってくるためでしょう。
新しい言葉は事象を「分ける」だけではなく、「まとめる」機能も持っています。例えば「密」という言葉は、
・混んでいる
・距離が近い
・閉じている(窓や戸が)
など、それまで別々の状況を示していたはずの言葉を「感染リスクを高める状況」としてひとつのブロックにまとめる働きを持ちました。
 「密」な食事会のイメージ(画像:写真AC)
「密」な食事会のイメージ(画像:写真AC)
「密」という言葉をしきりに耳にするようになって、窓の開いていない満員電車がいっそう恐ろしいものに感じられたり、距離が近い人に対して敬遠する意識が強まったり、ほとんど本能的とも言えるようなレベルで私たちの認知のあり方は変化しました。
ソシュール的な観点に従えば、こうした変化は単純に「危険なウイルスがまん延している」という事実によってのみ引き起こされたものではなく、「密」という言葉によって現実の切り取られ方が変わったことにも起因している、ということになるでしょう。
「言葉」を発するだけでは「行動」にはならない?
ここまでは、言葉が現実に及ぼす影響について述べてきました。ここからは少し切り口を変えて、「言葉」と「行動」という観点から、小池知事の言葉を用いたパフォーマンスについて考えていきたいと思います。
言葉に対して行動が伴わない人のことを、「あいつは口だけだから」とからかうことがあるように、一般的に「言葉」と「行動」は別のものとして考えられています。
コロナの第3波が押し寄せるなか、小池都知事は「5つの小」や「ひきしめよう」といった標語を提示しましたが、これらは「3密」のようには波及せず、「言葉遊びではなく具体的な政策を」といった批判も聞かれます。こうした批判の背景にはやはり、「言葉と行動は別」という前提があるのでしょう。
しかし本当に、言葉と行動を「別物」と考えてしまってよいのでしょうか。
「言葉を発すること自体が行動である」という観点
哲学の長い歴史においても、「言葉」と「行動」は別のベクトルから考えられてきました。言葉は「意味を伝える」ものであり、「現実に作用を及ぼす」行動とは別のカテゴリーとして捉えられていたのです。
そのようななか、「言葉を発すること自体、ひとつの行動ではないか?」という素朴な疑問から出発したのがジョン・ラングショー・オースティンというイギリスの言語学者でした。「言語行為論」とも呼ばれる彼の考え方は、言葉の「意味を伝える」という機能だけではなく、「現実の関係性に対して働きかける」機能に焦点を当てたものです。
例えば、家に招待した友人が「この部屋、寒いね」という言葉を発したとします。言葉の表面的な意味としては「この部屋の気温が低い」ということですが、これに対して「そうだね」と答えるだけでは、冷たい人と思われてしまうでしょう。会話には常に「意味」とは別の「意図」があり、ここでは「暖房をつけてほしい」という友人の意図があると考えられます。
 冬の部屋のイメージ(画像:写真AC)
冬の部屋のイメージ(画像:写真AC)
オースティンが着目したのは、このような「言外の意図」の働きです。
彼は言葉が持つ「意味を言い表す機能」と「意図によって相手に働きかける機能」を区別し、前者を
・事実確認的(コンスタティブ)
後者を
・行為遂行的(パフォーマティブ)
と位置づけました。
ネガティブな例になりますが、例えば上司から「こんなに忙しいのに、君は定時で帰るんだね」と言われれば、部下は職場に縛り付けられるような思いを抱くことでしょう。
事実確認的な言葉の次元においては、上司は「今は忙しい」「君は定時で帰る」という状況を言い表しているに過ぎません。しかし行為遂行的な次元においては、「腕力でもって部下をその場に押さえつけて仕事をさせる」のと同様の効果を生じさせているわけです。
言葉の行為遂行的な側面は、相手に行為を促したり、命じたり、導いたりと、「現実を変える」力を持っています。「言葉に力がある人」というのは、言葉によってある種の行為を成し遂げられる人のことを指すのでしょう。
小池知事の言葉は徹底して「行為遂行的」
小池知事の言葉が力を持つのは、一般に行政機関の発表が事実確認的なニュアンスになりがちなのに対して、極めて行為遂行的な伝え方をしているからだと考えられます。
例えば「密」という言葉は、もともと厚生労働省や首相官邸によって提示された言葉ですが、これを爆発的に普及させたのは小池知事の報道陣に対する「密です!」という発言でした。
3月はじめの段階ですでに、厚生労働省は集団感染の発生源として「換気が悪く」「人が密に集まって過ごすような空間」そして「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」を挙げていましたが、やはりこの発表は事実確認的な側面が強いと言えるでしょう。
集団感染は、このような条件で起こりやすいという事実を報告・伝達するものとして受け止められ、「密を避けろ!」という意図が伝わりにくくなっています。
 ジョン・ラングショー・オースティンの主著『言語と行為』(画像:講談社)
ジョン・ラングショー・オースティンの主著『言語と行為』(画像:講談社)
これに対して、コメントを求め殺到する報道陣に対して「密です!」と連呼する小池知事の姿は、受け取る側に「密を避けろ!」という意図を強く印象づけるものでした。
この場面において、小池知事は当然「この状況は密である」という事実を伝えたいわけではありません。言葉の行為遂行的な次元において、「報道陣に対して離れるように要求している」わけです。
さらに小池知事の真の意図としては、「具体的な場面における実例を示すことで、国民に注意喚起する」という目的があったのでしょう。その場面が切り取られて報道されることまで計算に入れた、極めて自覚的なパフォーマンスであったと考えられます。
「5つの小」「ひきしめよう」に込められた意図は
「5つの小」や「ひきしめよう」は、「3密」に比べると要素が多く、細かい内容を理解するのが難しくなっています。それぞれの「小」が何を指すのか、それぞれのひらがなが何を意味しているのか、しっかり理解しようという人は少ないでしょう。
内容が浸透しないということが、これらの標語に対する批判の要点にあります。オースティンの言葉を使うなら、言葉の事実確認的な次元において、意味を正確に伝えられていない、というわけです。
 東京都行き交う人々(画像:写真AC)
東京都行き交う人々(画像:写真AC)
しかし、わかりやすくキャッチーな言葉に対して抜群の嗅覚を持っている小池知事が、このようなことに気づかないというのもおかしな話です。もしかすると、これらの標語においては事実確認的な次元の意味はあまり重要ではなく、標語を示すことそのものに行為遂行的な意図があったのではないでしょうか。
例えば「5つの小」は、「小人数、小一時間、小声、小皿、小まめ」というそれぞれの意味を覚えてもらおうというのではなく、とにかく「小」という言葉を人々の意識に刻みこむことが目的であるとも考えられます。
「小」という文字に先導される形で、人々が「自分が影響を及ぼす範囲を狭める」ことを無意識に志向する、といった効果を期待しているのではないでしょうか。
あるいは「ひきしめよう」も、それぞれのひらがなからはじまる文はある意味「副次的」なものであり、「ひきしめよう」の文字が物質的に刻みこまれることを意図しているものと思われます。
事実確認的な側面への「割り切り」が強み
そもそも、感染拡大が進むなかで標語を連発していることそのものが、「今は警戒段階ですよ」ということのアピールになっています。「小池知事がフリップを掲げて何か言ってる = 重要な状況にある」という既成のイメージを生かし、会見を行うこと自体をひとつのメッセージとしているわけです。
小池知事の言動において際立っているのは、言葉の持つ事実確認的な機能に対するある種の「割り切り」です。大勢に向かって何かを呼びかける場面において、一語一語にわたって正確な意味を伝えることはまず不可能でしょう。
 2019年12月26日に開催された「年越しそば振る舞いイベント 2019」での小池百合子都知事(画像:東京都麺類協同組合)
2019年12月26日に開催された「年越しそば振る舞いイベント 2019」での小池百合子都知事(画像:東京都麺類協同組合)
おそらく小池知事が重視しているのは、「意味の伝達」よりも「それを見た(聞いた)人たちが、現実にどのような行動を取るか」という部分です。そしてこれを左右するのは、「意味」よりも「意図」を伝える言葉の行為遂行的な側面にほかなりません。
どのような場面で、どのような言葉を発すれば、意図した変化を達成できるかということに対して、小池知事は鋭敏な感覚を持っています。それによって引き起こされる変化を見据えながら言葉を発することは、それ自体で「行動」と呼べるものなのでしょう。