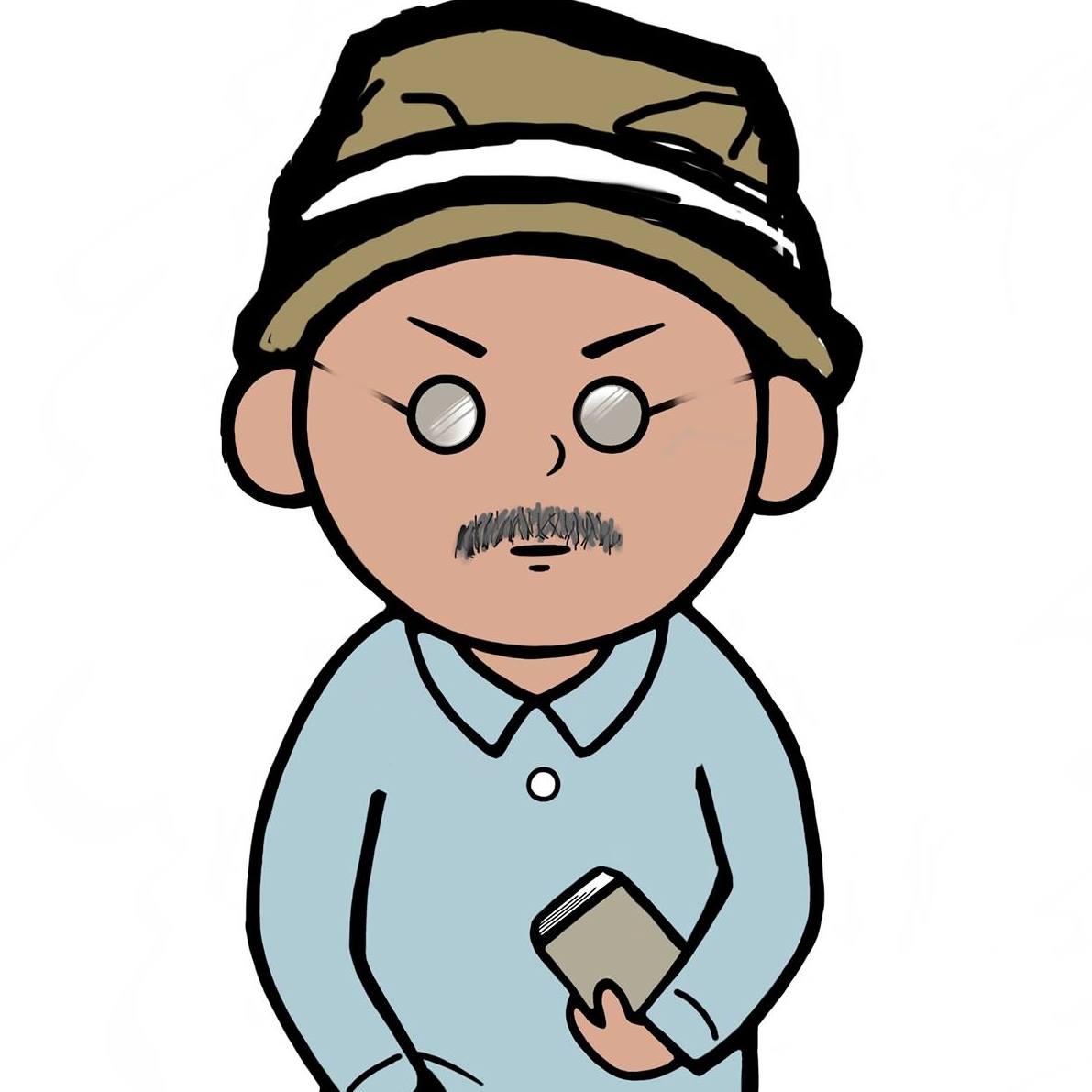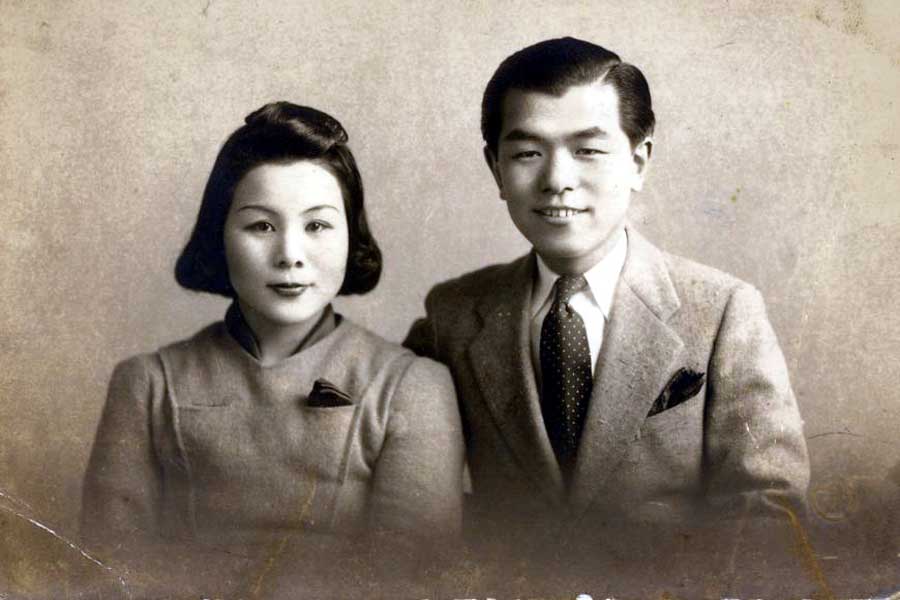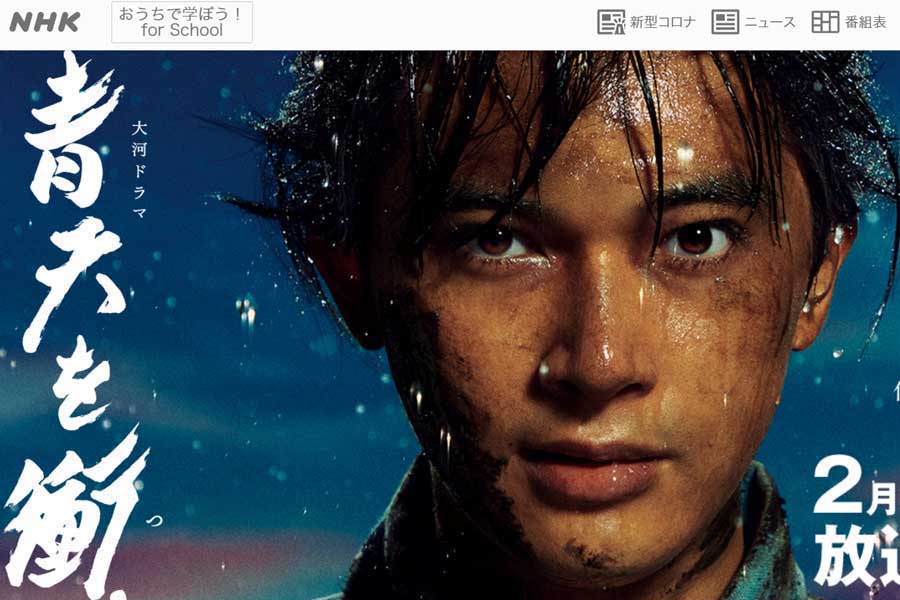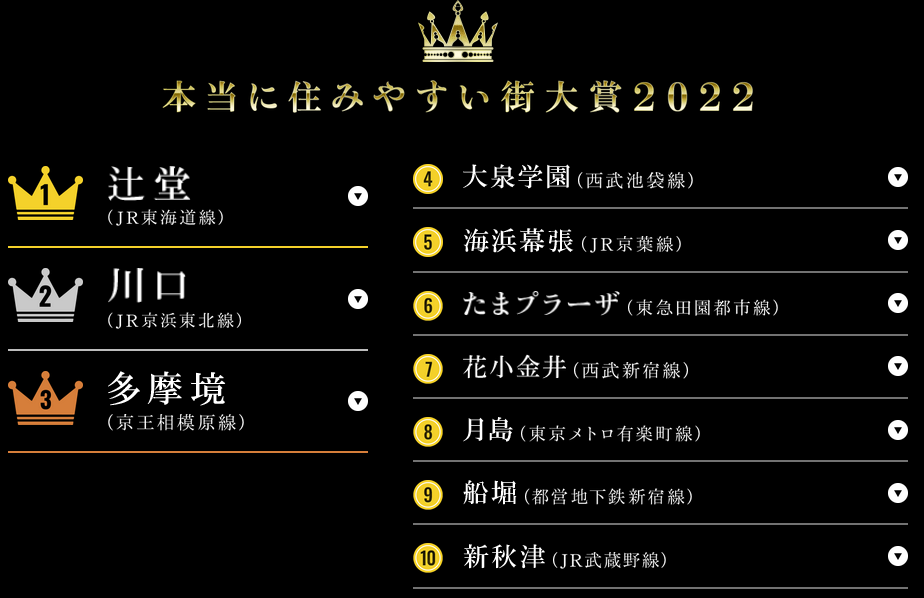覚えてる? 平成の珍事件「矢ガモ騒動」、なんと記念碑が板橋区にあった!
平成に話題をさらった「矢ガモ騒動」からはや28年。テレビなどで連日連夜放送されていた当時について、フリーライターの弘中新一さんが解説します。板橋区にある記念碑 北区の王子駅をスタートして石神井川沿いを歩く風景は、23区でも珍しく絶景です。 石神井川は小平市の小金井公園付近から始まり、西東京市・練馬区・板橋区・北区を経て隅田川へと至る河川です。王子付近では飛鳥山付近の台地の間をくぐり抜けるために、美しい風景が多く残っています。 かつて石神井川が音無川と呼ばれていた時代、音無親水公園(北区王子本町)は春は桜、秋は紅葉の名所として栄えた歴史があります。 そんな石神井川を上流へと歩いていった先、板橋区立東板橋図書館(板橋区加賀)近くにかかる加賀緑橋の近くに「やすらぎの水辺」という名の記念碑があります。この記念碑は、かつて全国を騒がせた「矢ガモ騒動」を後世に伝える記念碑なのです。 騒動発生は1993年1月 矢ガモ騒動の始まりは、1993(平成5)年1月22日のこと。 同日、板橋署には背中に矢が刺さったままのカモがいるという通報が入りました。しかし矢が刺さっているものの、カモは元気に空を飛んで上野の不忍池に移動したり活発に動いたりしていました。 板橋区加賀にある「やすらぎの水辺」(画像:(C)Google) 2月1日になり板橋区役所の職員がカモの捕獲に向かいます。同日、『朝日新聞』『毎日新聞』朝刊は、写真入りで矢の刺さったカモを大きく報じ、 「カモ、無残! 背中から腹を弓矢で射抜く 板橋の石神井川」(朝日新聞) 「オナガガモの背に、非情の矢 寄り添う雄ガモ 東京・板橋の石神井川」(毎日新聞) とインパクトのある見出しを付けました。 さらにNHKニュースでも1月頃から、カモの群れを狙って何者かが矢を射る事件が相次いで発生し、既に死んだ2羽が見つかっていることも報じられました。 報道の反響は極めて大きく、石神井川周辺や不忍池には報道陣のみならず、やじ馬が連日殺到しました。 矢ガモ専門記者まで登場矢ガモ専門記者まで登場 これを受けて、行政も人員を大量投入して捕獲作戦が始まります。 捕獲作戦のイメージ(画像:写真AC) 担当したのはカモが現れた板橋区役所の環境保全課と、北区・台東区の区役所、都庁の鳥獣保護係。板橋区は現場に5人、役所に5人の専任職員をおいての対応でした。 このニュースは海外でも報道され、カモの捕獲作戦を取材しようと現場には常に50人近くの報道陣が張り付きます。加えて、やじ馬もどんどん数が増えました。ちなみに新聞社やテレビ局は交代制でしたが、週刊誌は「お前は矢ガモ番だ!」と命じられ、カモが捕獲されるまで帰社を禁じられた記者もいました。 しかしカモは容易には捕まらず、現場周辺にはテレビカメラが常に並び、やじ馬が記念写真を撮るという光景が何日も続き、ついには立ち入り規制が行われます。ちなみに集まったやじ馬のなかには「不忍池のカモは戦後は貴重なタンパク源だった」と熱く語る人もいたといいます(『週刊現代』1993年2月27日号)。 電話と手紙が行政に殺到 騒動の過熱で特に困ったのは、板橋区役所と上野動物園(台東区上野公園)です。毎日のように電話や手紙が殺到し、なかには自分の考えた捕獲方法を語り続ける人もいたといいます。 結局2月12日になり、ようやく上野動物園の職員がしかけた網でカモの捕獲に成功。矢の摘出手術を受けたカモは回復後、同月23日に自然へと帰されました。 こうして騒動は一段落しましたわけですが、捕獲作戦にかかった費用は約300万円にものぼりました。なにしろ、さまざまな役所の職員がずっと現場に張り付いていたのですから、人件費だけでもばかにならなかったのです。 300万円のイメージ(画像:写真AC) 一方、カモに矢を射るような危険な人物がいることへの恐怖も話題になりましたが、なかなか犯人は捕まりませんでした。警視庁も捜査に乗り出したものの、結局犯人の逮捕には至りませんでした。 8年後に犯人が明らかとなるも……8年後に犯人が明らかとなるも…… それから約8年後、『週刊朝日』2000年12月22日号が実名を伏せる形で犯人を明らかにしましたが、既に過去の事件になっていたこともあり、あまり話題になることはありませんでした。 当時、矢ガモが無事に救出されたことで騒動は鎮静化しましたが、板橋区ではこの騒動を後世に伝える機運が盛り上がります。 そして1993年11月に完成したのが、前述の記念碑「やすらぎの水辺」でした。高さは2m45cm、人造石の台座にアルミ製のオナガガモが水面から飛び上がるデザインで、板橋区は制作に960万円の費用を投じました。これには「動物愛護の啓発」として評価する人もいる一方、あまりに高額になったことへの批判もあったといいます。 緑あふれる「やすらぎの水辺」周辺の様子(画像:(C)Google) 記念碑は今も静かにたたずんでいます。肝心の矢ガモのその後は、誰も知りません。
- ライフ