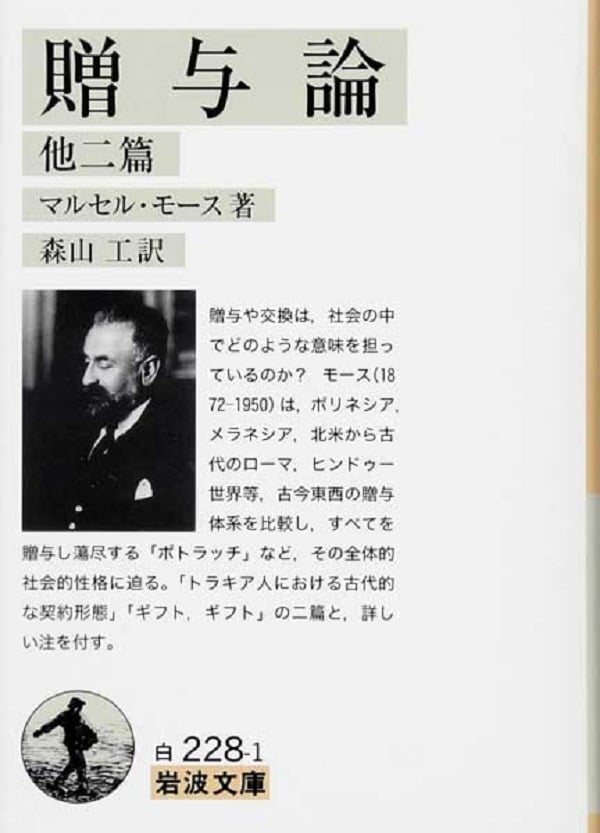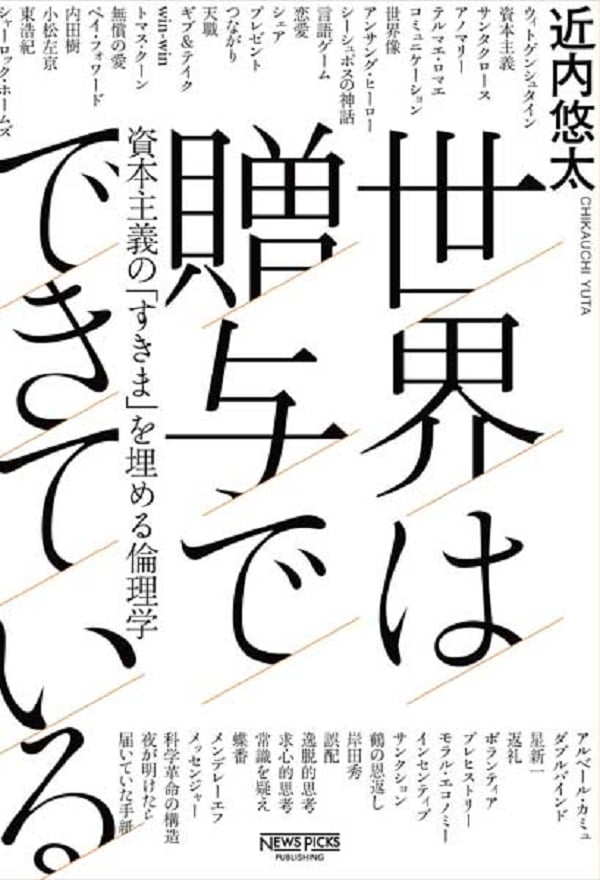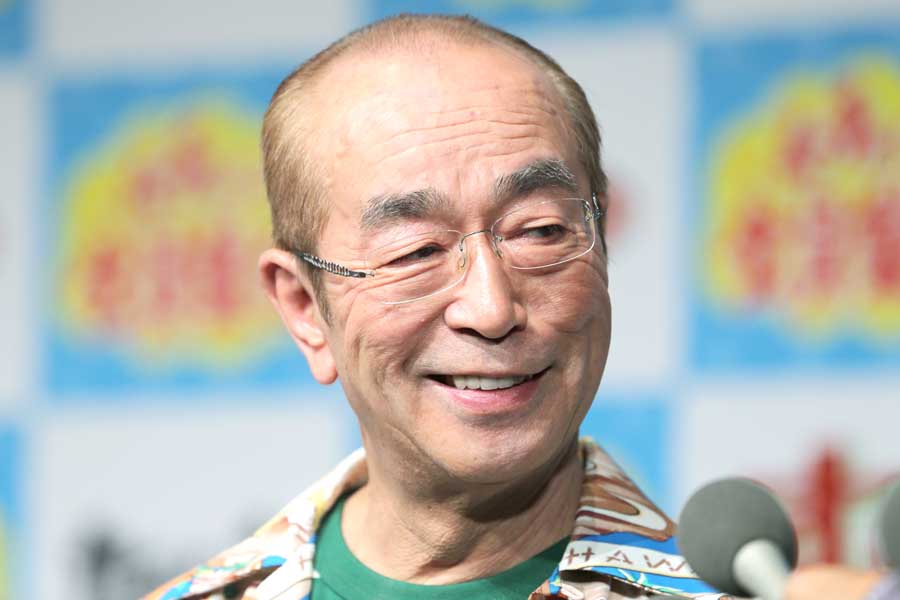ファッション誌ドラマ『ボス恋』好調も、若者は「紙雑誌」を読むのかという根本的疑問
4話まで視聴率ふた桁キープ 2021年1月にスタートした各ドラマは、そろそろ数話目に突入しようとしています。 『遺留捜査6』(テレビ朝日系)といった根強い人気のシリーズものや、綾瀬はるかさん・高橋一生さんが怪演を見せる『天国と地獄~サイコな2人』(TBSテレビ系)などが高視聴率をたたき出す中、ふた桁キープの健闘を見せているのが『オー!マイ・ボス!恋は別冊で』(同、ボス恋)。 ドラマ「ボス恋」ツイッター公式アカウントのスクリーンショット。2021年2月5日現在、フォロワー数8.7万人と人気ぶりがうかがえる(画像:TBSテレビ系ドラマ『オー!マイ・ボス!恋は別冊で』ツイッター公式アカウント) TBSの火曜22時といえば、若い女性視聴者をメインターゲットに仕事や恋愛模様を明るく描くドラマをいくつも生み出している近年注目の放送枠。今作も、主演の上白石萌音さんが地方(熊本)から上京し、東京の出版社で働く奮闘ぶりや恋の行方をコミカルなタッチで表しています。 最新話(2021年2月2日放送の第4話)の視聴率は11.6%。同枠前作の『この恋あたためますか』第4話が8.3%だったのと比べても、好調と言える数字なのではないでしょうか。 出版業界は「お仕事ドラマ」の定番 ところで前述の通り、物語の舞台は東京にある超大手出版社のファッション雑誌編集部。新たに創刊する最先端のファッションモード誌の立ち上げに“雑用係”として加わった主人公がさまざまな困難を乗り越えていく、という展開です。 出版をはじめとするマスコミは、歴代の「お仕事ドラマ」でも医療系や警察などと並んで頻出の業界。とりわけマスコミは長らく華やかなイメージが強くあったため、ハレの世界を描くドラマの題材にはちょうどよいのかもしれません。 しかし、同作の放送開始前、SNSなどではストーリーに対する疑問の声が散見されたのもまた印象的でした。それは「今どきファッション誌の編集部が舞台というのはどうなのか?」といった趣旨のものです。 「今どき雑誌?」という疑問の背景「今どき雑誌?」という疑問の背景 確かに雑誌をめぐる近年の情勢は、かつてのように華々しいばかりではありません。 2020年10月には1975(昭和50)年創刊の20代向けファッション誌『JJ』(光文社)が月刊発行を終了すると発表。同年11月には『ミセス』(文化出版局)も休刊を発表しています。 『AneCan』(小学館)『Zipper』(祥伝社)『Cawaii!』(主婦の友社)『CUTiE』(宝島社)――。女性ファッション誌だけに限っても、実に数多くの媒体がそれぞれの歴史に幕を下ろしてきました。 スマホ全盛の今、女性、特に若い世代は雑誌を読まないのではないかという提起は「ボス恋」放送以前から繰り返し言われてきたもの。果たして実際のところ、今の若者はどのくらい雑誌に接しているのでしょうか。 この疑問に対して、東京都内の大学に通う女子大生ふたりが率直な意見を述べています。 東京の女子大生と「雑誌」の距離感 東京都内の女子大生らでつくる若者トレンドのコンサルティングチーム、ネオレア(渋谷区恵比寿)の朝比奈ひかりさん(22歳、大学4年)と赤峰さえさん(20歳、大学2年)。同社が配信するネットラジオ放送「若者ラジオ」でふたりは、最近の若者と雑誌との“距離感”について語りました。 「読まない派」と話す朝比奈さんは、直近1年間で自発的に買った雑誌は1、2冊程度。「昨年(2020年)1月に好きなアーティストが表紙を飾った雑誌があったから表紙目当てで買ったのだけど。あとは、旅行に行くときに旅行雑誌を少し読んでみるくらいかな」。 電子版読み放題サービスが生んだ弊害電子版読み放題サービスが生んだ弊害 ふたりがファッションやコスメのトレンド情報をチェックするのは、最近ではもっぱらInstagram(インスタ)です。かつて雑誌という媒体が担っていた役割は「今はインスタに替わっている」と感じています。 「好きなブランドのアカウントをフォローしておけば、一番早いタイミングで(新商品の)情報を知れるし」(朝比奈さん)、「ブランドによってはその場で購入までできちゃうから」(赤峰さん)なのだと。 雑誌の場合、たとえ欲しいと思う商品を誌面で見つけても「それを売っているお店まで行くか、ブランドのサイトを検索して開くかをしないといけない。(インスタと比べて)もうワンステップが必要になる」(赤峰さん)のがネックなのだと言います。 雑誌と違ってインスタなら、気になった洋服をそのまま購入できるのが便利という(画像:写真AC) また、月額数百円で数百誌以上の人気雑誌が電子版で読み放題になるサービスを利用したことがある朝比奈さんは、その利用経験によってむしろ「雑誌に対する価値観が下がってしまったように感じる」と話します。 「紙の雑誌を読むときは、最初から最後まで行くのに15分ぐらいは掛かっていました。でも電子版をスマホで見ると、1冊あたり3~4分程度で終わってしまう。『興味ない、興味ない、興味ない、興味ある、興味ない』っていう感じで、電子版ならページをめくるのも一瞬。誌面を拡大表示するのも大変だから、細かい文字は全く読まなくなりました」 「そういうこともあって、雑誌を買おうという気持ちが落ちちゃったというのはあるかもしれません」(朝比奈さん) 読みやすく手軽さが売りの定額サービスが、逆に読者の雑誌に対する体感的な価値を下げてしまっているというのは、非常に示唆に富んだ指摘のように感じられます。 今も毎月購読する雑誌タイトルと理由今も毎月購読する雑誌タイトルと理由 とはいえ、若者の関心が完全に雑誌から離れインスタなどへ移行してしまったと捉えるのも早計のようです。 赤峰さんには、毎月決まって購入する雑誌があるのだそう。タイトルは『ar(アール)』(主婦と生活社)。理由は、「インスタとかでもかわいい服やコスメは見られるけど、雑誌には雑誌の丁寧に作り込まれた世界観があるから、私はそれが好き」だから。 ar以外でときどき買うのは『ViVi』(講談社)と『mini』(宝島社)。「全体的なコンセプトがかわいいから。ただ、自分が着られるかな? と考えたとき着られない服も多く掲載されているから、参考に見るためというより買いたくなったときにときどき買うという感じです」 毎月読んでいる雑誌として名前が挙がった『ar』。毎月12日発売で税込み620円(画像:主婦と生活社) そんな赤峰さんは「買いたい服を探すためとか、新しい何かを見つけるためとか(実用的な目的)で雑誌を読んでいた人にとっては、もう雑誌を読む必要はなくなっているのかも」と、それらはインスタで十分果たせていると指摘。 ただ一方で「買った雑誌は一時的であれ自分の部屋に置く、インテリアの一部になるものだから、表紙のデザインや全体の世界観も大事」とも話し、雑誌の固有性に価値を見出しているとしました。 「ボス恋」が描くべき「第3のテーマ」「ボス恋」が描くべき「第3のテーマ」 ここで冒頭の疑問に戻ると、雑誌が雑誌として若者に評価され続ける地力はインスタなどのネットコンテンツと比較してもなお十分にあると言えそうです。プロたちの手によって編まれ、読者が手元に置いておきたくなるひとつの作品として完成された雑誌は、今後もその価値を維持し続けていく可能性を持っています。 それでは、今すでに雑誌から離れてしまった若者をどう呼び戻すのか。 コト消費やストーリー消費が好まれるとされる昨今。たとえば人気ドラマ「ボス恋」が、1冊の雑誌が作られていく過程やそれに関わる人たちの努力と苦労を丹念に描き出すことができれば、若者の雑誌への思い入れを再び高める好機となり得るかもしれません。 作品の主人公・鈴木奈未ちゃん(上白石さん)の成長ぶりや恋の行方だけでなく、出版業界と雑誌を取り巻く現状や展望は作中でどのように表現されていくのか、その描写を通して“オールドメディア”の一員であるテレビが若い世代に何を伝えようとしているのか。そんなところもまた、今後注目していきたいポイントのひとつだと感じられます。
- ライフ