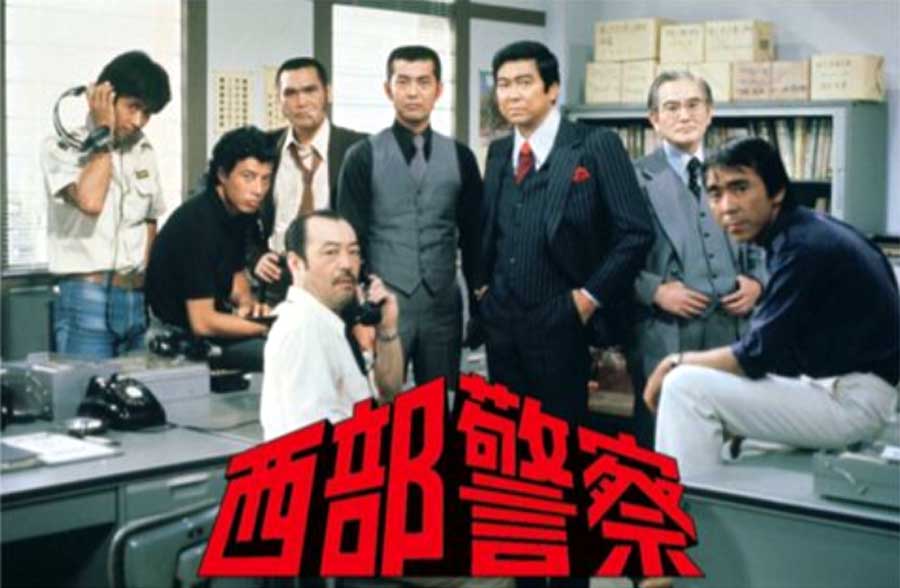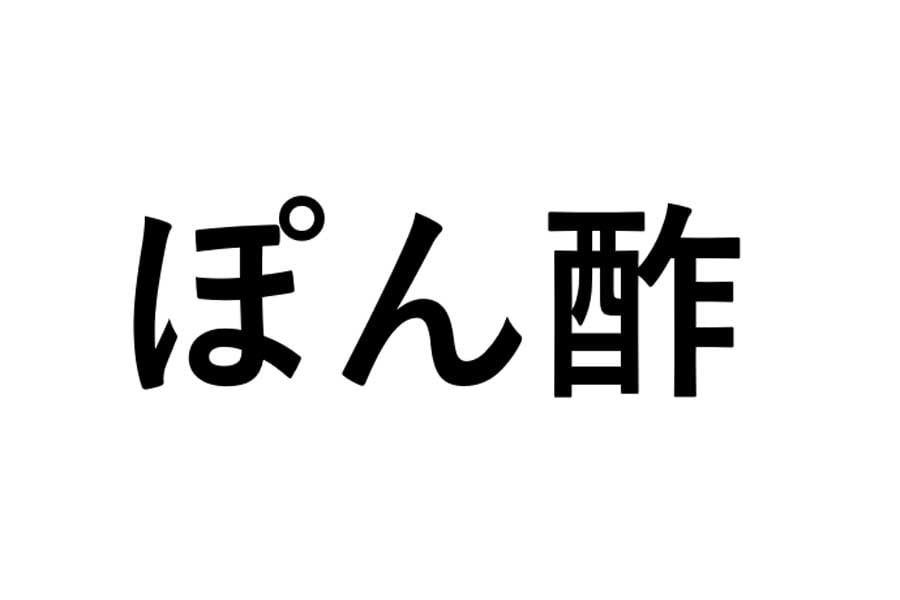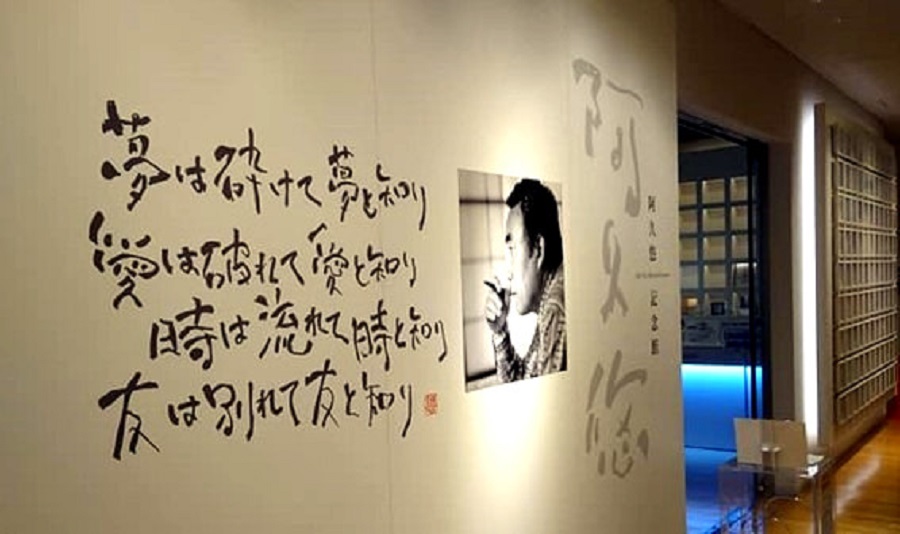「どうして……目も鼻もない」 夜道で見つけた重症のサビ猫は、どうやって「完治」を遂げたのか
壮絶レスキューの一部始終 行き場のない猫の保護やケアや里親を探す活動をする団体(東京キャットガーディアン)が、私の職場です。 これはその団体を始める少し前の、でも今頃の季節のお話。 ※ ※ ※ 台風がいくつか過ぎた後、穏やかな秋の気配は数日足らずで終わって急に寒くなりました。上着なしではとてもいられないほど。 仕事が終了して帰りがけにちょっと外食して、お腹もいっぱいいい気分で自宅近くまで歩いて来て、変わった動きをしているものに気がつきました。 住宅街のさして広くない道。等間隔に並ぶ街灯のちょうど真ん中あたりの地面を、ふわふわゆらゆら黒いものが不規則に移動しています。 「なんだろ?」 目を凝らしてみる。 「あ、ぶつかった」 揺れながら動いているそれは、木の塀に勢いよく衝突しました。大きな音がします。 「ね……こ?」 心配になって駆け寄りました。その途端に黒っぽい影が反対方向へ向かいます。 近寄る、逃げる、一歩進む、下がる。何回か繰り返してるうちに、自分の足音に反応しているような気がして、思い切って靴を脱ぎました。 目も鼻も見つからない顔面目も鼻も見つからない顔面「ひゃっ」 ストッキングごしですが、気温が10度そこそこの夜の道は冷たい。 忍び足で近づいてみる。今度は逃げない。 たぶん、黒の多いサビ猫。 「おいで」 小さい声で呼びかけてたりしながら、あと少しで触れそうなほどの距離になって、見ると顔が無いような気がする。いやそんな……。 夜道をさまよっていた重症の猫。「顔がない……どうして?」(画像:写真AC) あたりに人通りはありません。けっこう怖い。薄暗い中でよくよく見ても、猫の顔があるはずの場所には、やっぱり目や鼻が見つかりません。 とにかく目が無いか、見えてない様子。放っておくわけには行かず、もう保護しようと決めました。 自宅はすぐそこ。猫用のキャリーケージがある。でも一瞬の隙にどこかに行ってしまわないだろうか。 決心して、靴を脱いだまま家に向かってダッシュ。 見失うのが怖くてキャリーを抱えてすぐに猫の所に戻ります。 先ほどとほぼ変わらない場所にゆらゆらとその子は立っていて、街灯の反対側から改めて見た猫は、頭がゴツゴツとした感じになにか覆われていてジャガイモのようでした。 何とか保護して家へ運ぶと何とか保護して家へ運ぶと キャリーと一緒に持ってきた猫おやつのササミを出して、鼻先(と思われる場所)に放ります。 小さいかけらを点々とつないで、キャリーの中まで誘導。たどりながら入ってくれますように。 30分以上かかってやっと前足が入りましたが、それ以上進もうとはしてくれません。迷った末に片手をキャリー、もう一方を猫のお尻に当てて押し込みました。ガタガタと暴れる音がしてヒヤッとしたものの、なんとか無事保護に成功です。 帰宅して温風をつけたお風呂場に直行して、大きめタオル何枚かと猫缶とペットシーツやブラシなども用意しました。 先住猫たちに感染症などをうつさないように、新入りさんはまず場所を分けてお世話します。 用心しながらキャリーを開けて、明るい場所でじっくり見たら、ジャガイモのようだと思ったのはひどくひどく腫(は)れ上がった目や鼻でした。 猫缶を開けたらすぐに完食。ビクビクした感じが消えて、背中をなでると急にすり寄ってきました。 グイグイと頭から押してきたり、何度も体をこすりつけたり。激しい。愛しい。でも猫に見えない。 「ご飯は食べたし、あとはケージに移して。あ、その前に猫トイレ作らなきゃ」 そのとき、猫の乗っていた私のひざが不意にじわぁっと温かくなりました。 膝に突然のかゆみと痛みが膝に突然のかゆみと痛みが「おしっこしたね(笑)」 以前、行き倒れ状態で拾った猫も似たようなことをしてくれたのを思い出し、苦笑まじりに立ち上がろうとしたら、ザワザワッと今までに感じたことのない気持ちの悪さ。 続いて、痛いようなむずがゆいような、そして何か得体の知れないものがうごめいているような異様な感触が始まりました。 急いで猫を仮住まいのケージに入れて、トイレをセットし、追加のご飯も入れたりしている間にも、膝の違和感が止まりません。 かゆい? そして、かくと痛い……。 猫が突然激しく動き出して、あちこちぶつかりながら苦しそうな鳴き声をあげます。前足を顔に当ててこすったり、床を転げ回ったり。 「あっ! これ、疥癬(かいせん)!?」 ダニが大量に猫に寄生して起こる皮膚病のことです。 ものすごいかゆみと聞いていたし、症状が出ている子も何頭か見たことがあったのですが、こんなにひどくなっている猫は初めて。そしてそれがまさかの自分にも! そこから何日も、猫と一緒に苦しい時間を過ごすことになりました。 洗い流したり、ふいたりを繰り返しましたが、耐えようのないかゆみや痛みに一睡もできずに朝を迎えることになり、かかりつけの動物病院に泣きつきます。 膝は赤と紫の派手なまだら模様になりました。2日3日とたつうちに次第にしぶとい痛みやかゆみも薄れていきました。 何とか完治した猫のその後何とか完治した猫のその後 獣医さんの話では「人間も一時的に痛がゆくなるけど、まぁ人では繁殖はしないから大丈夫(笑)」だそうで。 一方サビちゃんの方は、首の後ろに垂らすスポットオンタイプの駆虫薬を使って、こちらも時間がかかりましたが完治しました。 自分自身も大変苦しかったのですが、あんなに顔が腫れて目も鼻も見分けがつかなくなるほどの症状でさまよっていた猫に比べたら、何十分の1くらいの辛さだったのだと思います。 筆者が代表を務める東京キャットガーディアンで保護したサビ猫(画像:山本葉子) 駆虫やワクチンが済んで、やせていた体に栄養がまわって、顔の腫れも引いて、落ち着いて甘えられるようになったサビちゃんは、受け入れを希望するお家にご縁がつながり、もらわれていきました。 しばらくして里親さんから送られてきた写真には、まぁるい大きな目のサビ猫が「お家の子の顔」になってご家族の真ん中に収まっていました。 ※ 猫を引き取った個人のプライバシーなどに配慮し、写真は全てイメージ画像です。
- ライフ