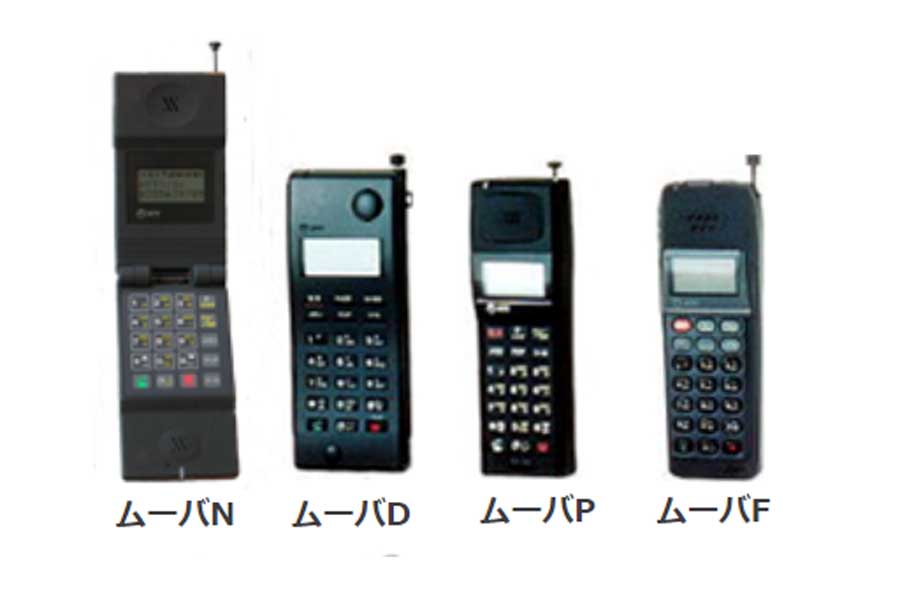売上高はピーク時の半分でも、百貨店が決して「オワコン」じゃない理由
小売企業を揺るがすアマゾン 私たちはコロナ禍でも、暮らしを楽しむために欲しいものは欲しいし、買い物はするものです。 しかし新しい生活様式のなか、その「買い方」「買う場所」は大きく変わりました。あなたも最近の買い物を振り返って、そう実感するのではないでしょうか。 そうした変化を証明するように、この10年間に売上高を約4倍に伸ばし、2020年も25%以上成長した企業があります。コロナ禍で多くの企業が業績を落とす企業が続出するなか、独り勝ちと言っていいでしょう。 いったいどの企業でしょうか? あなたの生活を思い出してみましょう。 巣ごもりの自宅でソファにくつろぎながら、あなたはスマホを手にします。欲しいものがあれば、数クリックで購入手続きは済み、早ければ翌日には宅配便が届けてくれます――そう、コロナ禍で伸びたのはインターネット通販のアマゾンです。 先の数字は日本事業の業績で、直近2020年の売上高は2兆1893億円。この数字、イオン、セブン&アイ、ファーストリテイリングという名だたるメード・イン・ジャパン小売企業に迫る国内4位の規模となっているのです。 小売業進化の裏にある理論 ここで質問です。あなたは「小売りの輪」という言葉を聞いたことはありますか? 百貨店のイメージ(画像:写真AC) これは、アメリカのマルカム・P・マクネアという経営学者が1957年に唱えた、小売業の栄枯盛衰を説明する理論です。「輪」とは次の四つを繰り返すことを意味します。 1.革新的小売企業が低コスト・低サービス・低価格路線で、既存の企業の顧客を奪って市場シェアを拡大。 2.同じ手法を用いた追随者が登場して、競合が激しくなる。 3.差別化を図ろうと、品ぞろえやサービスのレベルを上げて高付加価値ビジネスへ移行していく。 4.すると、新しいイノベーションを用いた革新的小売企業が現れて顧客を奪っていく。 こうした四つの局面をループ状に繰り返しながら、小売業が進化していくというものです。 止まらない百貨店の業績悪化止まらない百貨店の業績悪化 そういえば、ニュースで百貨店の業績悪化と閉店を最近耳にします。かつては「小売業の花形」として就職人気ランキングでも上位で、他の小売業よりも高級なイメージがあったのが百貨店でした。 百貨店と女性のイメージ(画像:写真AC) それが今、存亡の危機にあります。年間売上高のピークはバブル経済真っただ中の1991(平成3)年で、約9兆7130億円。それが直近2020年は4兆2204億円。この30年で半減しています。県庁所在地に百貨店のない県も、山形、徳島、滋賀と増えはじめています。 百貨店と言えば、あらゆる商品を扱っていることが強みでした。だから「百貨」というわけですが、専門店チェーンの成長により、家電、家具などの売り場が消えてきました。 とりわけ縮小しているのが、かつては百貨店の花形売り場だった衣料品です。前年比31.1%減の1兆1409億円にまで落ち込み、商品別売上高で初めて衣料品が食料品に逆転されました。百貨店はもはや「オワコン」となりつつあるのでしょうか。 革新を忘れると時代に忘れられる 小売業の花形と言えば、かつては百貨店でした。 世界最初の百貨店として、パリに「ボンマルシェ」が開店したのは1852年。帽子屋の息子だったアリスティド・ブシコーと、その妻であるマルグリットは「五感が震えるようなまったく新しい店」をつくろうと、これまでの業界常識にとらわれない店づくりに取り組みました。 その特徴は、 ・バーゲンセール ・ショーケース陳列 ・定価販売 といった今では常識ですが、当時としては革新的な販売手法が多くの顧客の心をとらえたのです。 一方、日本では江戸時代から続く三井呉服店が1904(明治37)年に「デパートメント・ストア宣言」と銘打ち、最先端の品ぞろえとサービスがそろった百貨店を目指すことを宣言。日本の百貨店の始まりとなりました。 百貨店が集まっている日本橋エリア(画像:写真AC) 前身となる越後屋は革新的手法で繁盛した店として知られています。それが「現金掛け値なし」です。 当時は相手によって価格を変え、盆暮れに代金を徴収する「掛け売り」が商いのルールでした。それを越後屋は誰に対しても同一価格、さらに現金販売を貫くことで価格破壊をなしとげた江戸時代のディスカウンターだったのです。 しかし、小売りの輪の理論のとおり、百貨店は自らの成功法則にとらわれ、次代に合わせた革新を忘れ、後進のイノベーターにシェアを奪われていきました。革新者が革新をやめたとき、衰退は始まるのです。 百貨店を超える「百八貨店」とは百貨店を超える「百八貨店」とは 2020年12月、百貨店を超える「百八貨店」を名乗る店が現れました。東京湾岸エリア、ゆりかもめ有明テニスの森駅から徒歩3分ほどの立地にオープンした「無印良品 東京有明」(江東区有明)です。 暮らしづくりから街づくりまで、暮らしの全部がそろう店を掲げる「無印良品 東京有明」。関東最大の売り場面積を擁する新しい「百八貨店」だ(画像:笹井清範) 関東最大の売り場面積を誇り、生鮮食品から衣料品、住関連雑貨、部屋のリフォーム、戸建て販売、そして街の活性化まで、暮らしにまつわるすべてを、百貨店を超える“百八貨店”として、ユーザーが求める「感じ良いくらし」のサポートを目指しています。 生産者と直接つながった青果の品ぞろえ、フードロス削減を目的のひとつとする量り売り販売の導入を始め、新しい小売業の在り方を具現化する店となっています。 無印良品は1980(昭和55)年12月、西友ストアー(現・合同会社西友)のプライベートブランドとして40品目から船出。現在では約7000品目、店舗は日本を含む31の国・地域へと広がっています。 小売業の役割とは、時代の変化に寄り添いつつ、その時々の暮らしの豊かさをサポートすること。その形は一定のものではなく、変化することが必然です。 小売業の革新者だった百貨店が危機にあるのも、新しく生まれ変わるための必然です。産みの苦しみに心折れることなく、暮らしを彩る新しい革新者となることを期待しています。 そのために必要なのは「誰のために」「何をもって」「どのように」役立つかを考え直し、これまでのやり方にとらわれず実行すること。こうした心構えは、百貨店だけではなく、私たちひとりひとりにとっても必要なことなのです。
- ライフ