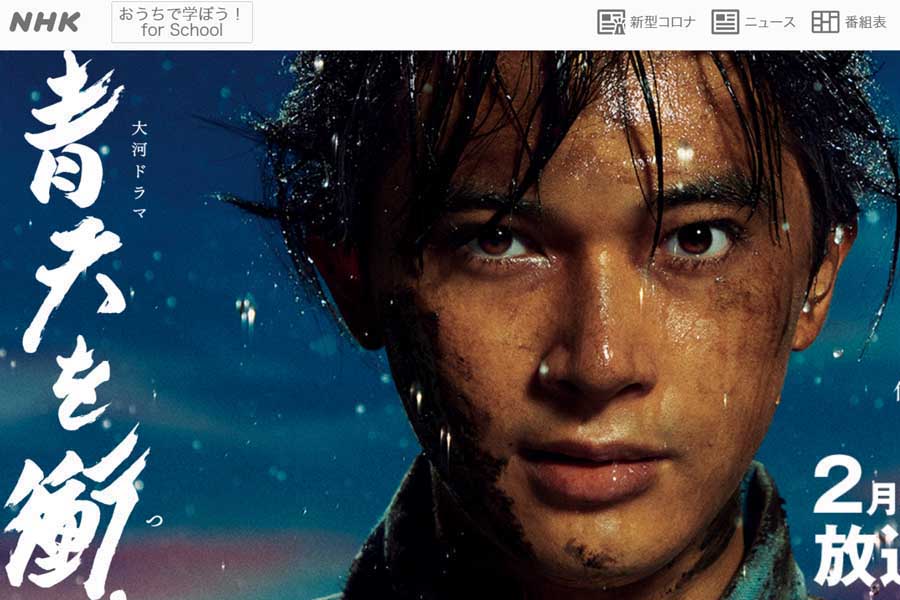震度5強の夜、都心から“自転車”が一斉に消えたワケ SNSで「帰宅困難者 対策だ」と話題に
2011年3月11日の東日本大震災以来、10年ぶりに東京23区で震度5強を観測した2021年10月7日夜の地震。その夜、東京都心からは一斉に「自転車」が姿を消していました。いったいなぜなのでしょうか。鉄道がストップ、帰宅困難に 2021年10月7日(木)夜に発生した地震では、東京23区でも東日本大震災以来10年ぶりに震度5強を観測。首都圏の鉄道各社が一時運転を見合わせたことで、主要駅前のタクシー乗り場には「帰宅困難」となった人たちの長い行列ができました。そうした中、ある交通手段がこの機にあらためて脚光を浴びることとなりました。 ※ ※ ※ 「ドコモの赤チャリ、都心から在庫が消えたと思ったら、勝どきと晴海に大量に集まってる」 ツイッターにそんな投稿をアップしたのは、千代田区内に住むsattobiさん(@sattobi_c)。東京都心のマップ上に「0」や「1」といった数字がズラリと並ぶスクリーンショット画像を併せてアップしました。 東京都心のマップを表示したアプリの画面。「0」や「1」などの数字がズラリ(画像:sattobiさんのツイート、ULM編集部でトリミング加工) sattobiさんの言う「ドコモの赤チャリ」とは、ドコモ・バイクシェア社(港区虎ノ門)が運営する電動自転車シェアリングサービスのこと。車体が真っ赤に乗られていることから、利用者らからはこの愛称で呼ばれています。 ドコモのほかにもソフトバンクグループの「HELLO CYCLING」などのサービスがあり、街なかに設置されている拠点(サイクルポート)で自転車を借りて、目的地周辺まで乗った後で近くのポートに返却。支払いはICカードや専用アプリに登録したクレジットカードで決済するという仕組み。 15分70円など手軽な料金で自転車を利用できるため、都心でのちょっとした移動などを目的に近年利用が増加しています。 10月7日夜には、電車をはじめとする公共交通機関がストップしたことで帰宅の手段を失った通勤者らが、別の“足”を求めてシェアサイクルに殺到したもよう。 sattobiさんが「バイクシェア」アプリのスクリーンショットを撮った8日(金)未明の1時5分時点では、とりわけ都心への通勤者が多く住むタワーマンションが林立する中央区晴海や勝どきエリアに多数の自転車が返却されている様子が見て取れました。 有事にはインフラにもなる?有事にはインフラにもなる? この投稿を見たフォロワーたちからは、 「そうかその手があった!」 「なるほど、帰宅困難者対策でもあるんだ」 「すごい。鉄道が止まった時の代替交通」 「こういう時のインフラにもなるんだなー」 「大手町あたりから自転車で帰った人が多かったんでしょうね」 「登録だけでもしとくか」 と、シェアサイクルの有用性をあらためて感じるリプライ(返信)がいくつも寄せられました。 ドコモ・バイクシェアのシェアサイクル(画像:写真AC) また、なかには 「こういうので人の動き見えるの面白い。状況自体は笑えないけど」 「都心部のベッドタウンがよく分かる」 と、可視化された都内の人流に興味を抱く人も。 画像を投稿したsattobiさんによると、自身も日常的にシェアサイクルを利用しているユーザーのひとり。都心在住ということも相まって 「移動の7~8割はシェアサイクルを使っているかもしれません」 と話します。 今回、発災の直後にシェアサイクルのアプリを起動した理由は「地震の後片付けをした後、24時間営業のドラッグストアへ買い物に出かけようと」したため。 都心のポートが軒並み「0台」と表示されたことに驚き、思わずツイッターに投稿したと言います。 延長料金を無料にする措置も延長料金を無料にする措置も ドコモ・バイクシェアの広報担当、山口恵さんは、 「特に新型コロナ禍では3密回避などの理由から利用件数や登録人数は増えていましたが、ここまで自転車の偏在が見られたのは過去に例がありません」 と話します。 東京都心のマップを表示したアプリの画面。中央区晴海や勝どきに自転車が偏在していることが分かる(画像:sattobiさんのツイート、ULM編集部でトリミング加工) 同社は8日、地震発生の7日22時41分から翌8日早朝5時までに利用を開始した料金のうち延長料金を無料とする対応を発表。SNSでは「すばらしい取り組み」といった称賛の声が相次ぎました。 山口さんによると、こうした利用料金の減免措置は2018年6月に発生した大阪北部地震に続き2回目。 「利用者の方が適宜安全を確認したうえで、便利にご利用いただけたようでよかったです」としています。 災害時は「とどまる」が基本 一方で注意すべき点もあります。 政府は、大都市で地震に遭遇した際の行動について 「まずは、身の安全を確保した後、むやみに移動を開始しないことが基本! 安全な場所にとどまることを考えましょう」 としています。余震により頭上から物が落下してきたり、移動中に火災が発生したりといったさまざまな危険が予想されるからです。 今回の地震では大規模な建物倒壊や火災といった被害は報告されませんでしたが、水道管の破損や道路の冠水などの状況が確認されました。 山口さんは、「シェアサイクルは適宜安全を確認したうえでご利用いただき、大規模な災害時にはその場にとどまっていただく」ようにと呼び掛けています。 見直されるシェアサイクル見直されるシェアサイクル シェアサイクルの主なメリットとして挙げられる点は、 ・低料金で借りられて、修理代の自己負担もないためコストを抑えられる ・出先でも、好きなときに借りることができ、好きな場所で返却できる ・特に都心では、電車や自動車よりスムーズに目的地に到着できることもある ・二酸化炭素を排出しないため、環境にも優しい など。 大規模災害の発生時はさておき、たとえば電車の急な運転見合わせといった場面ではシェアサイクルが非常に便利という認識が、今回あらためて共有されたようです。 投稿者のsattobiさんは、 「シェアサイクルは、個人が移動する『個別交通』と、その場に行けば利用できる『公共交通機関』のふたつの性質を併せ持っていると思います。今回のドコモの割引対応を含め、新しい形の公共交通としての有用性を感じました。行政各区ともさらに連携して、対応エリアや自転車台数を増やすなどより使いやすいサービスになってほしいです」 と、サービス内容の拡大に期待を寄せました。 課題は台数・ポートの拡充 また、シェアサイクル愛好家として業界動向を取材するライターの石坪マナミさんは、 「2011年3月の東日本大震災のときと比べても、シェアサイクルの普及によって都内の帰宅困難者は確実に助けられました」 と指摘。ただ一方、今回の被災経験を通してシェアサイクルのニーズがさらに広まるだろうと見越したうえで、 「現状、すでに需要に対して供給(自転車の台数、バッテリーの交換など)が追いついていない面もあります。今後ユーザーがさらに増えた際、『使いたいときに自転車がない』状況になるのでは」 と懸念します。 また、 「サイクルポート設置のための用地確保は難しく、現状どうしても(設置場所の)偏在が見られるので、その点を改善していければさらなる利用促進につながるのではないでしょうか」 とも話しています。
- ライフ
- 東京