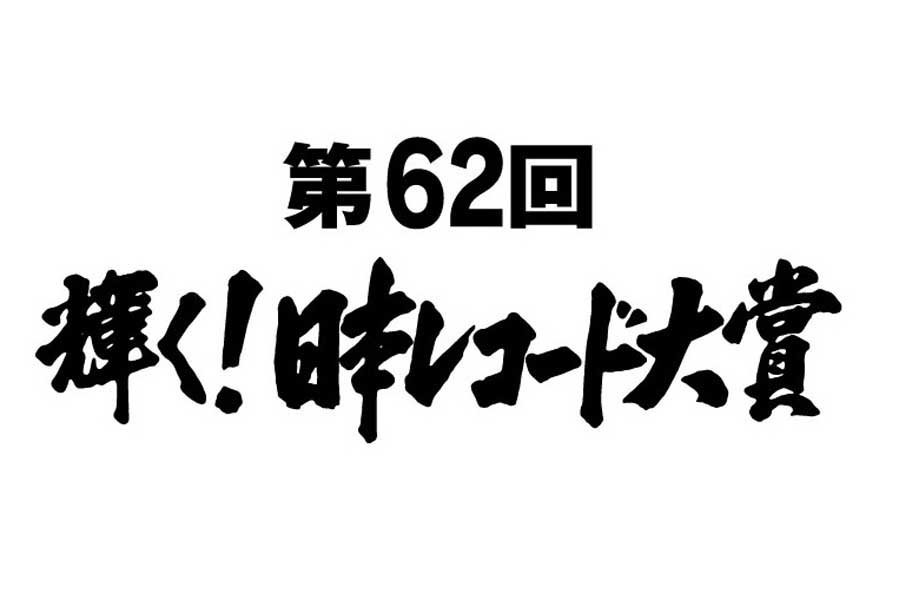コロナに自然災害にどう立ち向かうか
近年、毎年のように世界各地で自然災害が発生しており、先日も九州地方や広島で大雨による洪水で大きな被害を出しました。もちろん東京も例外ではありません。こうした近年の気候変動は地球温暖化が起因しているといわれています。
さらに、地球温暖化が徐々に私たちの生活環境へ影響を及ぼしている間に、新型コロナウイルスの感染拡大は私たちの生活を一瞬で一変させました。現在、私たちは経験のない未曾有の状況下にありますが、それだけを考えるのではなく、前進しなければなりません。
つまり、コロナや気候変動などの地球規模の問題に対応・配慮した社会を創造していくことが求められています。
今こそ求められる「レジリエンス」
「レジリエンス」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。
レジリエンスとは、もともと「回復力」「強靭力」「跳ね返す力」といった意味でしたが、近年では災害や貧困、経済の再生など、都市や地域の課題に柔軟に対処・克服して再生していく力やしなやかな強さという概念で使用されています。
国連が提唱している「持続可能な開発目標(SDGs)」にも、貧困、まちづくり、気候変動などさまざまな社会問題の解決や地域の活性化の重要な要件ともなっています。つまりレジリエンスは、コロナや環境問題という地球規模の問題に直面している現在、私たちに求められているものと言えるのです。
では、レジリエンスはどのようなところで生まれるのか。それは、多種多様な人々が一致団結し、環境問題やコロナの対処や経済再生のチャンスの際に、公共的な利益に即して協力し合い、地域やコミュニティが一体となって迅速に柔軟に対応し克服する社会ではないでしょうか。
地域やコミュニティーを基本としたのは、文化的な基盤に基づいたものとして、ここでは捉えているためです。たとえば、国、都道府県や市町村、コミュニティーといった共同体、組織や団体の単位となります。
小さな単位が、それぞれに見合った災害やコロナなどの対策を足元から実施していくことが重要になってくるでしょう。そうした小さな単位同士が水平的につながり協働することによって、地球規模の対策につながっていくのです。
環境問題に対峙するアーティスト
アートを通じて、グローバルに環境問題への警鐘を鳴らし続けているアーティストがいます。オラファー・エリアソンです。サイト・スペシフィック(特定の場所を生かした)なインスタレーションの作品を多く制作しています。
先述にあるように、小さな単位といいましたが、彼のドイツ・ベルリンのスタジオには約100人程度のスタッフがおり、その半数は建築家などで、研究者や科学者なども中には含まれています。まさに、同じ考えや価値観を共有した人々で構成されている小さなコミュニティーといえるでしょう。
特筆すべきは、彼らはアートを通じて環境問題を表現しているだけではないことです。
 アートを通じて環境問題への警鐘を鳴らし続けるオラファー・エリアソン(画像:いちご、Jacob Jorgensen, JJFilm, Denmark)
アートを通じて環境問題への警鐘を鳴らし続けるオラファー・エリアソン(画像:いちご、Jacob Jorgensen, JJFilm, Denmark)
彼らは日常的に環境に優しい、地域経済の活性化となる、クリエーティブでサステイナブル(持続可能)なライフスタイルを送っています。たとえば、彼のオフィスは4階建ての古いビール工場です。新たな近代的なオフィスビルではなく、古き良き趣のある建物を改築して、アトリエ兼オフィスにしており、1階には、ガラス工房が入居しています。
スクラップ・アンド・ビルドをするのではなく、昔の文化的な趣のある建造物をそのまま残しているのです。都市論者のジェーン・ジェイコブスも古きものと新しいものとが共存した多様性のある社会が発展すると論じています。
また、食生活に関しても徹底しています。オラファーのスタジオでは、週4日毎回100食以上のベジタリアン向けの料理がスタッフに提供されます。この食材は地元で採れたオーガニック野菜で、二酸化炭素排出量などを抑えた循環型農法で生産されているものです。
欧米で広く導入されている、環境に配慮された地域支援型農業(Community Supported Agriculture)で、地産地消を基本とし、消費者は経営のリスクパートナーとして直接農家と契約し、週に1度配送される生産物を受け取ります(宮津2020)。
環境への意識を体現する暮らし方
環境問題に対する意識や精神を体現した食事をスタッフ全員で食することで、そうした意識を彼らと共有しているのです。それが協働で作品づくりをする際に具現化されていくことにつながるのでしょう。このベジタリアン向けのランチはレシピ本としても世界中で販売されています。
加えて、オラファーは社会的事業も行っています。「Little Sun(リトル・サン)」という太陽の形をした携帯用のソーラー発電式電灯を開発し、世界中で販売する事業です。
このプロジェクトは2012年から始まり、エチオピアをはじめとしたアフリカなど、まだインフラが整備されていない地域への支援事業です。電気のある地域には24.90ユーロで販売され、電気インフラのない地域には安い値段で販売されています。
価格差を設けることで電気のない地域に支援をする仕組みです。電気が整備されていない地域では、まだ灯油のランプが使用され、お金がかかる上に長時間使用による健康被害をもたらします。電気のある暮らしをしている私たちも、先述の自然災害や電力源が何らかの問題が起こった際には一転して明りを失います。
オラファーはこうした電力エネルギーに関する環境問題や社会的不均衡の問題にも関心を寄せている訳です。
環境経済学者の宮本憲一氏は、日本の公害の経験から、人間の命や健康などの基本的人権が保障されている生活環境下でないと地域経済は持続的な発展に向かわない、と実証し論じています。
ちなみに、リトル・サンですが、日本ではBeams(ビームス)などでも当初販売されていましたが、現在は、近代美術館(MoMA)のオンラインデザインストアやアマゾンで入手可能です。
こうしたオラファーのアートコミュニティーにおける実際のライフスタイルは、小さな単位の足元から着実にサステイナブルな社会を創造することにつながっているのです。
アートを介して世界に発信する試み
ライフスタイルから環境問題に対峙しているオラファーですが、それをテーマとした作品はグローバルに発信されています。
筆者(清水麻帆。文教大学国際学部准教授)が最もダイナミックと感じた作品は、ニューヨークでの巨大インスタレーション「The New York City Waterfalls」です。イーストリバーに大きな人工の滝を四つ作り出しました。アートに興味がない人でも、見れば「あれは何だ」と思うはずです。
そうした関心から環境問題への関心へと誘います。
 映画『オラファー・エリアソン 視覚と知覚』より、オラファーがニューヨークに出現させた滝(画像:いちご、Jacob Jorgensen, JJFilm, Denmark)
映画『オラファー・エリアソン 視覚と知覚』より、オラファーがニューヨークに出現させた滝(画像:いちご、Jacob Jorgensen, JJFilm, Denmark)
その活動は日本・東京でも注目が集まっていて、2018年に新宿区西新宿のホテルでドキュメンタリー映画の上映会が行われたほか、東京都現代美術館(江東区三好)では2020年6~9月、オラファーの個展が開かれました。ベルリンから日本への作品の輸送にも環境に配慮しており、初めての試みだそうです。
なるべく二酸化炭素の排出量が少ない輸送方法を選び、ベルリンからロシアまではトラックで運び、ロシアから中国までを鉄道、中国から日本までは船で運んでいます。
これも作品展示の一環であると捉えることができますし、上述の環境問題に対峙するライフスタイルがつぶさに反映されているともいえるでしょう。
あらためて考える、コロナ禍のライフスタイル
有機野菜の地産地消などは小さいことかもしれませんが、地域やコミュニティーにおけるライフスタイルのあり方が足元から環境問題を克服する一歩になります。
環境問題だけではなく、昨今のコロナも同様に、私達の日常の生活のあり方や草の根活動のひとつひとつが今後の地域や経済の発展を左右するといっても過言ではありません。
サステイナブルな社会の構築に向けて、さまざまな問題に地域やコミュニティー、ひいては、その中のひとりひとりが向き合うことが大切になるでしょう。
アートを通じて、コロナや環境に配慮するライフスタイルがスタイリッシュでクールという価値観が定着すれば、問題が解決の方向に少なからず向かうのではないでしょうか。社会におけるアートやコミュニティーの役割を再考してみる良い機会なのかもしれません。