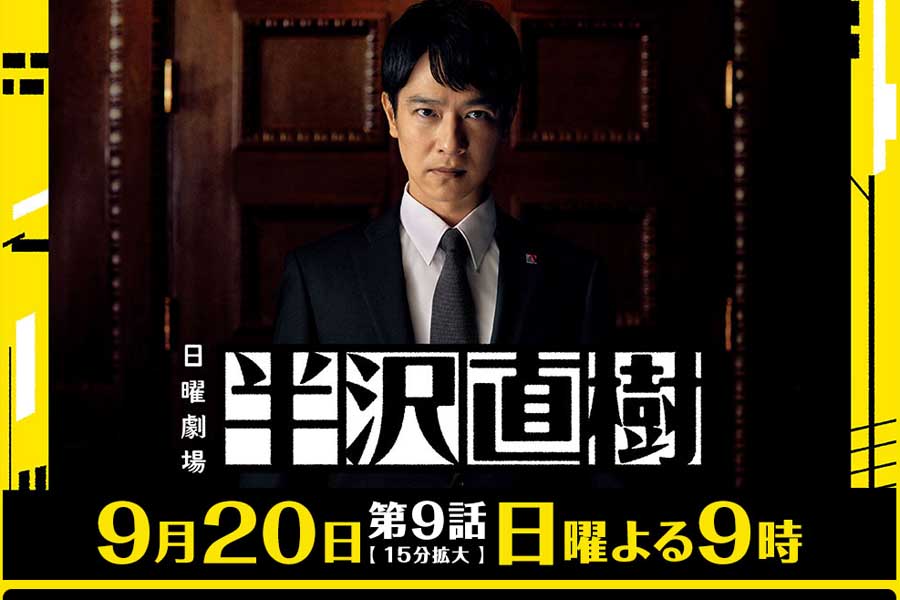背景に映る石材が気になる
人気ドラマ「半沢直樹」(TBS系)を見ていて、「石材」が気になってしまうのは私(西本昌司。名古屋市科学館主任学芸員)だけでしょうか。
 『半沢直樹』のメインビジュアル(画像:TBSテレビ)
『半沢直樹』のメインビジュアル(画像:TBSテレビ)
まさか石材によってドラマのロケ地が決められていたなんてことはないでしょうが、偶然とは思えない石材セレクションに驚いています。
「なんて、マニアックな!」と言われてしまいそうですが、石の研究をしている私としては、石材にスポットライトを当てることが「石への恩返し」。ドラマの脇役として盛り上げている石材を紹介しましょう。
三井本館の美しい「稲田石」
半沢が勤めている東京中央銀行の本社ビルの外観は、どこかで見たことがあるという人も多いのではないでしょうか。
ローマ風の石柱が並んだ重厚感ある低層部は日本橋にある三井本館(中央区日本橋室町)で、高層部はCGを合成しているのだそうです。
三井本館は、関東大震災後の1929(昭和4)年に再建された近代建築で、重要文化財に指定されています。
外装に使われている石材は「稲田石(いなだいし)」と呼ばれる茨城県笠間市産の御影石で、岩石名でいえば「花崗岩(かこうがん)」。実際にそばに行ってみると、その存在感に圧倒されます。
稲田石は東京証券取引所(中央区日本橋兜町)、旧連合国軍総司令部(GHQ)の第一生命館(現DNタワー21。千代田区有楽町)や、最高裁判所(同区隼町)といった有名建築物のほか、駅の階段や銀座中央通りの歩道など、東京では古くから使われてきた石材です。
 「稲田石」で作られている三井本館の外観(画像:西本昌司)
「稲田石」で作られている三井本館の外観(画像:西本昌司)
大和田が半沢に「お・し・ま・い・DEATH!」というシーン(第2話)や、金融庁検査で訪れた黒崎を役員が並んで迎えるシーン(第6話)など、何度も登場する同銀行内の階段は、1938(昭和13)年に開館した東京国立博物館本館の大階段です。
この階段に使われている石材は「茶竜紋(ちゃりゅうもん)」と呼ばれる徳島県阿南市産の大理石(※)で、岩石名で言えば「石灰岩」。遠目にはグレーですが、よく見ると茶色や白色の筋がたくさん入っていることがわかります。
※本稿でいう「大理石」は、石材業界でいう「大理石」のことで、地質学における「結晶質石灰岩」「石灰岩」「トラバーチン」などを含みます。
老舗銀行をイメージさせる貴重な石
かつて、徳島県阿南市からは同様の石材が採掘されていたようで、「茶竜紋」のほか、「時鳥(ホトトギス)」「淡雪」などといった銘柄がありました。
これらは今や入手不能な貴重な石材で、
・国会議事堂(千代田区永田町)
・明治生命館(同区丸の内)
・日本橋高島屋(中央区日本橋)
・日本橋三越本店(同区日本橋室町)
などの歴史的建造物で使われています。
 東京国立博物館の大階段に使われている「茶竜紋」(画像:西本昌司)
東京国立博物館の大階段に使われている「茶竜紋」(画像:西本昌司)
このように、東京中央銀行本店の外装・内装に使われている石材は、そこが老舗銀行であることを暗示させるものとなっているのです。
電脳のビルには赤っぽい木目調の石
半沢の訪問先でも、多くの石材が映し出されていましたので、考察してみましょう。私は特に、電脳雑伎(ざつぎ)集団のビル外壁やロビーが気になってしまいました。
半沢が部下の森山に傘を竹刀替わりに攻めかかるシーン(第1話)で、背景にあったのが、赤っぽい木目調の石材。「レッドトラバーチン」と呼ばれるイラン産トラバーチンです。
 電脳雑伎集団ロビーのロケ地として使われた、住友不動産六本木グランドタワーの外壁の「レッドトラバーチン」(画像:淺野友紀瑛)
電脳雑伎集団ロビーのロケ地として使われた、住友不動産六本木グランドタワーの外壁の「レッドトラバーチン」(画像:淺野友紀瑛)
この石材でできた大きな壁を見て、ロケ地が住友不動産六本木グランドタワー(港区六本木。2016年完成)だとわかったくらいの印象的な石の壁です。
ロビーで伊佐山が半沢に声をかけるシーンでは、この石材に社名が掲げられていましたから、電脳雑伎集団のアイコンとされたのかもしれません。
IT企業としま模様の石との関係?
これに対して、スパイラル社のビル外観がわかるようなシーンを見つけることはできませんでした。
しかし、森山が同社を訪問するシーン(第2話)で、同社オフィスのロビーが少しだけ登場します。その壁に、木材のようなしま模様のある石材が壁にあることを発見しました。
ロケ地が東京ミッドタウン日比谷(千代田区有楽町。2018年完成)だというファンによる情報と合わせると、この石材は、おそらく「ダークセルペ」と呼ばれる中国貴州省産トラバーチンだろうと推測されます。
 スパイラル社のロケ地として使われた、東京ミッドタウン日比谷に使われている「ダークセルぺ」(画像:西本昌司)
スパイラル社のロケ地として使われた、東京ミッドタウン日比谷に使われている「ダークセルぺ」(画像:西本昌司)
つまり、IT系新興企業の2社いずれにもトラバーチンが使われていることになります。これは、果たして偶然なのでしょうか!?
トラバーチンは、温泉に溶け込んでいた炭酸カルシウムが結晶となって沈殿し、積み重なってできた岩石で、地層のようなしま模様が特徴です。
他の石材と比べると、形成速度が速い岩石ですから、もしかすると、急成長を果たした企業の象徴ということでしょうか?……そこまで考えていたとしたら脱帽です。
帝国航空本社ロビーにはイタリア産の石
もうひとつ、気になってしまった石材は、半沢が白井大臣を見かける帝国航空本社ロビー(第5話)です。
なにしろ柱と壁が白っぽい石材で覆われており、明るくゴージャスな雰囲気を醸し出していました。
これは「ビアンコブルイエ」と呼ばれるイタリア産大理石で、岩石名では「結晶質石灰岩」。いわゆる「大理石柄」と言えるようなグレーの網目状の模様が特徴です。
 「ビアンコブルイエ」で飾られた帝国航空本社のロケ地として使われた、キヤノン本社ロビー(画像:キヤノン株式会社)
「ビアンコブルイエ」で飾られた帝国航空本社のロケ地として使われた、キヤノン本社ロビー(画像:キヤノン株式会社)
ロケ地は一体どこなんだろうと調べてみると、キヤノン本社(大田区下丸子。2002年完成)のロビーだそうです。同社の写真をみると、ドラマで巨大スクリーンがある壁面も実際はすべて大理石のようですから、間違いなく圧巻の吹き抜け空間となっていることでしょう。
帝国航空の社員説明会シーンにはドイツ産の石
帝国航空が会社再建案について社員説明会のシーン(第5話)で目についたのは、壁に使われていたまだら模様があるベージュ色の石材です。
これは「ジュライエロー」と呼ばれるドイツ産大理石で、岩石名は「石灰岩」。アンモナイトなどの化石を含むことで有名な石材で、前回の記事(東京は巨大な「石の博物館」有名ビルの外壁もよ~く見てみると……一体何がある?)でも紹介しました。
 「ジュライエロー」という石材。帝国航空説明会会場のロケ地として使われた、リンクフォレストのフォレストホールに使われている(画像:西本昌司)
「ジュライエロー」という石材。帝国航空説明会会場のロケ地として使われた、リンクフォレストのフォレストホールに使われている(画像:西本昌司)
ということは「アンモナイトが見えるかもしれない!」と目を凝らしてみましたが、見つけることはできませんでした。実際に近づいて観察すれば、見つかるかもしれません。
ロケ地は、多摩センターのリンクフォレスト(多摩市鶴牧。2020年完成)内のホールだそうですので、入る機会があれば化石を探してみたいですね。
このように、ドラマ「半沢直樹」にはいろいろな石材が登場するので目が離せません。企業の風格を表現するため、石材だらけの場所がロケ地として選ばれているように思えてしまいます。
一体なぜでしょうか。
石材を含め自然素材というのは、一般に工業製品と比べて高価であり、いわばぜいたく品です。さらに、建築デザインとの相乗効果もあって、石材が醸し出す独特の雰囲気があります。
こうしたことから、必然的に石材が多い場所がロケ地に選ばれたのではないでしょうか。