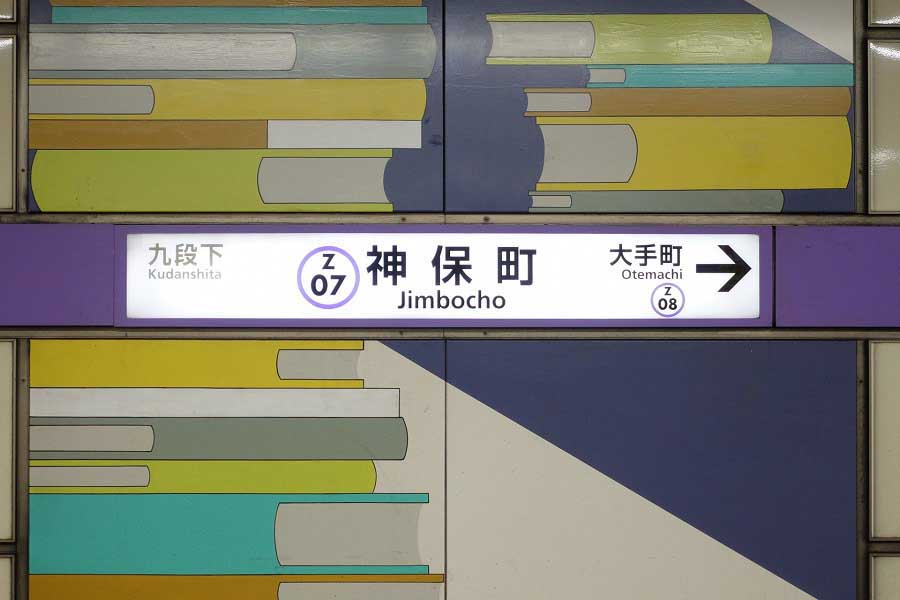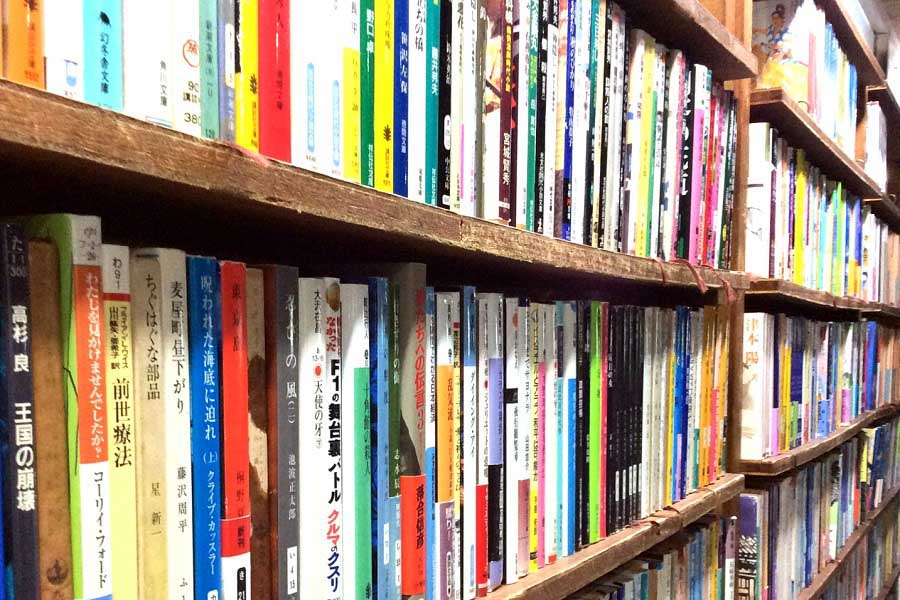外出自粛で散歩を我慢していた全ての人たちに贈りたい、ウィズコロナ時代の散歩方法とは
ひとりで家を出て、ひとりで帰宅する 新型コロナウイルス感染拡大の影響でこれまで外出自粛が叫ばれていましたが、街に人が少しずつ戻ってきています。散歩ライターである筆者(下関マグロ)が、ウィズコロナ時代の散歩について考えてみました。 ひとり散歩のイメージ(画像:下関マグロ) スーパーマーケットがひとりで来店するよう、しきりに店内放送しているように、ウィズコロナ時代の散歩は、ひとりで家を出て歩くソロ散歩がおススメです。 ひとりで家を出て、ひとりで帰宅する――これが基本です。 では、どこをどう歩けばいいのでしょうか。 以前は、いわゆる人気の散歩コースやエリアがありました。しかしこれからは、誰もが行く場所ではなく、自分だけの散歩コースを探すことが大切になっていきます。 「住宅街」散歩がアツい? まずは家を出て、駅や商店街のにぎやかなエリアではなく、その逆方向へ歩いてみましょう。 場所によっては工場があったり、農地があったり、住宅街があったりします、中でも筆者がおすすめの散歩コースは、「住宅街」です。 住宅街のイメージ(画像:写真AC) 住宅街を歩いて本当に楽しいのかどうかと聞かれそうですが、実はとても楽しいのです。 家々の生け垣を見たり、お庭に生えている四季折々の花や木々を楽しんだりすることができます。もちろん他人(ひと)様の敷地に入るわけにはいかないので道から眺めるだけですが、それでも十分に楽しめます。 「音」や「匂い」も楽しさのひとつですね。 古くからの住宅街の細い路地を歩いていると、三味線の音色が聞こえてくることもあります。また、ご飯をつくっている音なども。まな板で何かを切っている音や匂いを感じると、なんとも言えない気持ちにかられます。 住宅街散歩はパーソナルなもの住宅街散歩はパーソナルなもの 筆者の母親も住宅街を歩くのが好きな人で、あるとき何がそんなにいいのか聞いたことがあります。いわく、いろいろな形の家を見るのが好きだとのこと。 また知り合いの編集者も住宅街散歩にハマっていて、その魅力は変わった形の集合住宅を見ることなんだそうです。人によって住宅街散歩の楽しみ方はいろいろあり、奥が深いのです。 住宅街のイメージ(画像:下関マグロ) しかし、筆者はこれまで住宅街の散歩記事を書いたことはありません。というのも、住宅街散歩はとてもパーソナル(個人的)なものだからです。自分の家からぶらぶら歩くわけですから、それは誰にでも共通しているのではないでしょうか。 マスクを少しずらして呼吸も 東京の最高気温が28度を越えた先日、炎天下の中をマスクをして散歩してみました。 正直、少し歩いただけでかなり息苦しく、ちょっと危険な感じがしました。誰もいない場所を歩くなら、マスクを少しずらして、呼吸しやすくしてもいいかもしれません。 またコロナ以前から言われていましたが、しっかり熱中症対策をして散歩に出掛けましょう。飲料水を持って、できれば日傘をさして歩きたいですね。ソーシャルディスタンスも保てます。 筆者は夏の散歩の際は晴雨兼用の傘を持って出掛けます。最近の東京の夏は熱中症だけではなく、ゲリラ雷雨にも対策が必要だからです。 ひとり散歩のイメージ(画像:下関マグロ) またコンビニや自動販売機は、喉が渇いてから探してもなかなか見つからないことが多いので、水分は必ず携帯しておきましょう。夏に限らず、散歩時は喉が渇く前からこまめに水分補給をすることをお勧めします。 誰もいない住宅街を歩くなら、マスクのストックも必ずバッグに入れて出掛けましょう。マスクは、今やマナーやエチケットのひとつです。 散歩の楽しみ方はむしろ広がる散歩の楽しみ方はむしろ広がる また休憩するなら、どこか公園を見つけて、周囲と距離を保ってベンチに座りましょう。食事は、家でお弁当を作って持参するのもいいですね。 サンドイッチ弁当のイメージ(画像:写真AC) 筆者は最近、自作のサンドイッチを持って散歩に出掛けることにハマっています。そうすると、「今日はどんなサンドイッチにしようか」など、いろいろ考えるようになりますし、またそれも楽しいのです。 このように、散歩の楽しみはウィズコロナ時代でさらに広がるような気がします。 もともと散歩はとてもパーソナルなものですが、今後はさらに「その人なりの散歩の時代」になるのではないでしょうか。 さあ、あなたも散歩に出掛けてみませんか?
- おでかけ