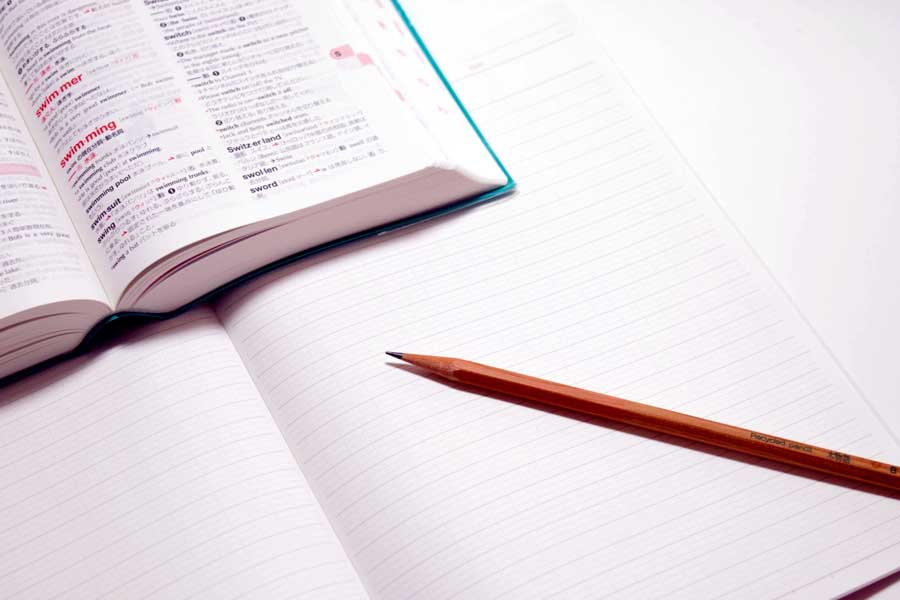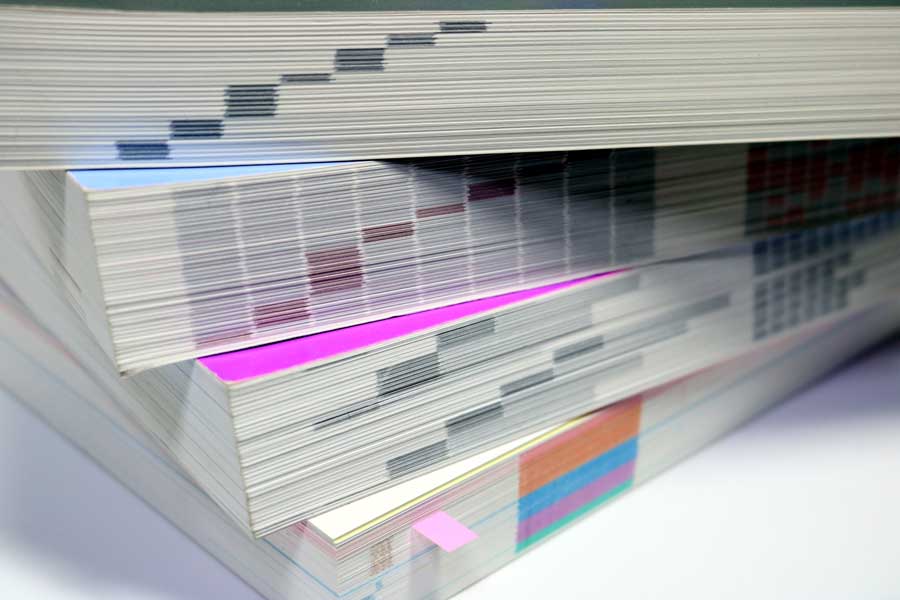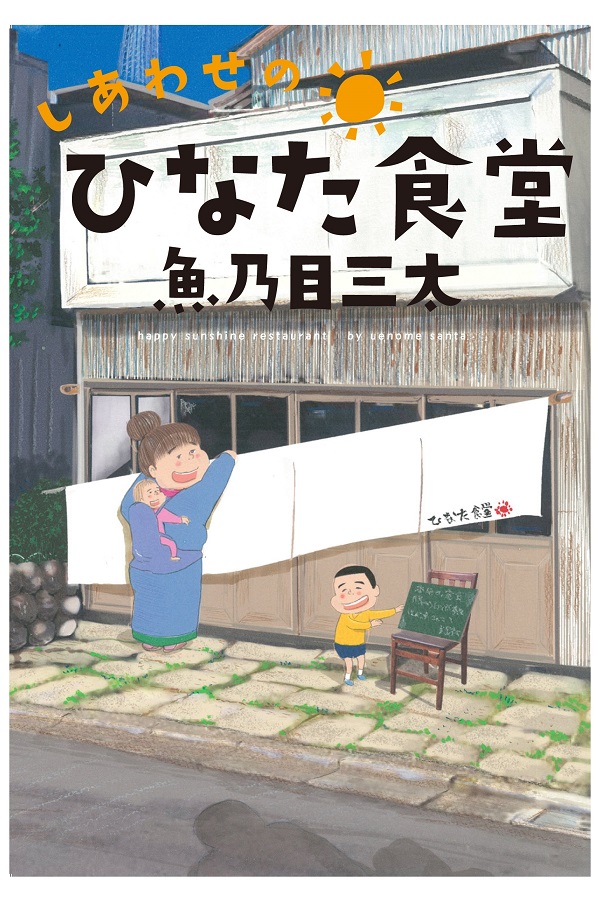突っ張り棒が「再配達問題」を解決? 都内マンションで実験中、いったいどうやって?
物流系ITベンチャー「Yper」が、宅配ボックスのないオートロック付きマンションで発生している再配達問題の解決に取り組んでいます。受取人不在、配送員が建物に入れず 防犯上、一人暮らしの女性にとって頼もしいオートロック付きマンション。そのようなオートロック付きマンションで、現在あることが問題になっています。それは宅配便の再配達です。 深刻な再配達問題(画像:画像AC) 通販サイトやフリマアプリの利用拡大で、EC(電子商取引)の浸透がこれまで以上に進むなか、国土交通省が2018年6月に発表したデータによると、都市部での宅配便の再配達率は約16%に及ぶといいます。 そんななか、近年特に問題になっているのが、宅配ボックスのないオートロック付きマンションの存在です。その理由は、受取人が不在の場合、配送員が建物の内部に入れず、荷物がすべて再配達になってしまうためです。 このような問題を解決すべく、物流系ITベンチャー「Yper(イーパー)」(渋谷区神宮前)が2018年10月から、都内のマンションでユニークな実験を行っています。いったい何を行っているのでしょうか。 アプリとバッグの連携で再配達を解決 Yperが行っているのは、オートロック付きマンション専用の宅配ボックスを使った実験です。実験には、同社が提供する荷物管理アプリ「OKIPPA(オキッパ)」と、同アプリ連動の置き配バッグ「OKIPPAバッグ」を使っています。 OKIPPAバッグを購入すると、バッグのほか、専用ロックや内鍵、専用バンドなど計7点が送られくる(画像:Yper) OKIPPAは、指定のネット通販サイト(Amazonと楽天、ZOZOTOWN、ユニクロ)を使って買い物をして、荷物が届くと配達完了を知らせるアプリで、不在の場合はアプリを使って、簡単に再配達を依頼することができます。 空きスペースに置かれた簡易スタンドの様子(画像:Yper) 置き配とは、配送員が受取人に顔を合わせることなく、建物の指定の位置に配送物を置く配達方法のこと。受取人は、マンションの空きスペースに置かれた、突っ張り棒を改修した簡易スタンドにOKIPPAバッグを取り付け、OKIPPAを自身のスマートフォンにダウンロードします。 宅配ボックス取り付けに立ちはだかる壁宅配ボックス取り付けに立ちはだかる壁 そのようなOKIPPAとOKIPPAバッグを使った、今回の実験の流れは次のとおりです。 OKIPPAとOKIPPAバッグを使った、オートロック付きマンションへの配送の実験の流れ(画像:Yper) 荷物を持った配送員はオートロックの外側に置かれた専用タブレットに、あらかじめ知らされた荷物の配送伝票番号を入力します。その後、OKIPPAのサーバ内で、商品購入時に割り振られた配送伝票番号と照合が行われ、それらが一致すればオートロックが開錠されるという仕組みです。 OKIPPAとOKIPPAバッグを使った、オートロック付きマンションへの配送の実験の流れ(画像:Yper) マンション内に入った配送員は、突っ張り棒に吊るされた受取人のOKIPPAバッグに荷物を入れ、バッグのファスナーを閉じてから、バッグに付属しているダイヤル式の南京錠を使って施錠します。 その後、受取人のスマートフォンに配達完了の連絡が届き、帰宅した受取人が南京錠を開錠し、荷物を取り出します。 なお、OKIPPAバッグは突っ張り棒の柱にリール式の専用ロックで固定されているため、南京錠とあわせて二重の盗難防止機能となっています。 「突っ張れる場所ならどこでもOK」 東京23区内で、オートロック付きで宅配ボックスがあるマンションは、全体の70%程度ですが、「築20年過ぎると10%まで落ち込む」と同社代表の内山智晴さんは指摘します。 「そのような古いマンションに新しく宅配ボックスを設置するという提案は通常出てきません。共有スペースを使うため、住人全員の賛同を得なければなりませんし、共益費もかかる。また高齢者の住人は、若者ほどECを使いません。ですから宅配ボックス取り付けのニーズ自体が少ない。そもそも取り付けるスペースすらない物件も多い。その点、既存の空きスペースを使うのであれば、そのようなことを考える必要がないのです」(内山さん) Yperは今回の実験に際し、大阪市の老舗収納用品メーカー「平安伸銅工業」とタッグを組み、同社のヒット商品だった突っ張り棒を採用しました。ここで疑問が。なぜ突っ張り棒という「アナログ」なものを今回使おうと思ったのでしょうか。 「突っ張り棒であれば、突っ張れる場所があればどこにでも置けます。管理人室の空きスペースや階段下のスペースなど、これまで宅配ボックスが設置不可だった場所へ、手軽に宅配ボックス機能をつけることが可能になります。避難経路以外でしたら柔軟に対応ができます。OKIPPAバッグの購入については、管理組合やマンションオーナーがまとめて購入して利用者に配布するケースを想定しています」(同) 同社では、2019年までにOKIPPAバッグを50万個まで拡大していく構えです。
- ライフ