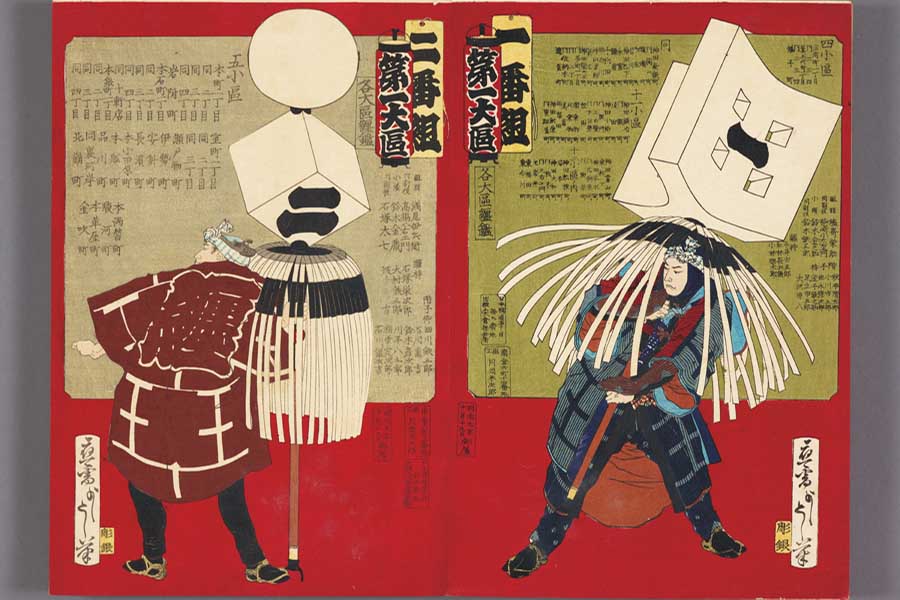豊洲で温泉も!――場外市場「豊洲 千客万来」は多彩なグルメに囲まれた「泊まれる市場」だった
いよいよ明日2月1日、豊洲市場から徒歩3分の場所に「豊洲 千客万来」が開業します。気になる施設や店舗の詳細とこれまでの経緯について、都市商業研究所の若杉優貴さんが解説します。豊洲市場の横に「場外市場」が誕生! 今年(2024年)2月1日、江東区の豊洲市場前に新スポットが誕生します。その名も「豊洲 千客万来」。豊洲の「場外市場」として、館内には温浴施設や多くの飲食店などが出店するといいます。一体どういった内容となるのでしょうか。 (イメージ画像:万葉倶楽部リリース)【その他の画像】>> 豊洲の場外、運営は温浴施設でおなじみ「万葉倶楽部」 「豊洲 千客万来」は、「(仮称)千客万来施設」として東京都が豊洲市場の場外に誘致した複合施設。築地市場に隣接する商店街「築地場外市場」のような施設とすることを目標としており、ゆりかもめ市場前駅からも直接アクセスすることができる陸橋が設けられます。 当初「(仮称)千客万来施設」は喜代村(「すしざんまい」運営企業)と大和ハウス工業により運営される予定でしたが、周辺施設との競合などを懸念して2015年に撤退。再公募の末、2016年3月に全国各地で温浴施設や宿泊施設を運営する「万葉倶楽部」(本社:神奈川県小田原市)の運営となることが決まったものの、市場の開場延期などにより条件が折り合わないとして再び開業が危ぶまれた時期もありました。 豊洲市場完成から8年、開場から6年。開場延期、そしてコロナ禍を経て、ようやくの「場外開業」となる訳です。 豊洲市場からは徒歩約3分。市場内の飲食店は月~土曜の午後2時頃までに閉まってしまうので、これからはそれ以降の時間もゆっくり楽しめる場所が増える。これから市場を訪れた際には「場外」も楽しもう!(写真:若杉優貴)温浴施設は年中無休・24時間営業――無料の展望足湯も! 「豊洲 千客万来」の敷地面積は約17,000平方メートルで、大きく分けて「温浴」と「グルメ」の2つのエリアに分かれます。 「豊洲 千客万来」の構成。都心寄り(画像右)に温浴施設が、市場前駅寄り(画像左)にグルメ系施設が設けられます。(イメージ画像:万葉倶楽部リリース) そのうち、温浴棟「東京豊洲 万葉俱楽部」は地上8階建ての大型施設。温泉は豊洲で湧いたもの…という訳ではなく、神奈川県の箱根や湯河原から運んでくるそう。目玉は東京湾を望むことのできる露天風呂で、そのほか館内には癒処(マッサージコーナー)やエステコーナー、ドライサウナ、塩サウナ、岩盤浴なども併設。 露天風呂と客室(イメージ画像:万葉倶楽部リリース)「東京豊洲 万葉俱楽部」館内にはサウナや岩盤浴も設けられます。男性風呂にはベイビューを横目にした屋外の整い椅子も(イメージ画像:万葉倶楽部リリース) 他の多くの万葉倶楽部の温浴施設と同じく年中無休・24時間営業なので、お台場での大型イベント前に館内で仮眠を取ることや、露天風呂付の宿泊客室で本格的にお休みすることもできます。料金はマル得セットで大人3,850円から(午前3時~9時は3,000円を加算。詳細は公式ウェブサイト参照)。ちなみに、豊洲市場から東京ビッグサイトまでは約2km、歩いて25分ほどとなります。(ゆりかもめでは9分) このほか8階の無料ゾーンには、眺めのいいカフェやバー「スカイダイニング」などに加えて、誰もが入ることができる「千客万来足湯庭園」が設けられます。 「東京豊洲 万葉俱楽部」屋上。写真左は一列に並んだ無料の展望足湯庭園。写真右は360度パノラマでシーサイドビューが楽しめる入館者用の展望足湯庭園。東京湾が一望できる。(イメージ画像:万葉倶楽部リリース)今のうちに行こう!多彩なグルメに加えて手土産もそろう「江戸前市場」 併設されるグルメゾーンの食楽棟「豊洲場外 江戸前市場」は3階建て。全館が飲食店を中心とした商業施設で、1階は「豊洲 江戸前通り」としてラーメンやコンビニ、カフェなど近隣住民も楽しめる手軽なエリア。万葉倶楽部側にはイベントが開催できる「お祭り広場」も設けられます。 2階「目利き横丁」「豊洲目抜き大通り」は館内に江戸の街並みを再現したエリアで、東京都の観光PRコーナー「いちばの広場」も併設。この2階には、海鮮の飲食店のみならず、ラーメン店や蕎麦店などといった「東京グルメ」も集結しています。 安土桃山時代に起源を持つ小田原の海鮮珍味店「魚商 小田原六左衛門」ではワンハンドおつまみが、江戸時代から続く老舗青果仲卸店「かねす」ではフルーツサンドやスムージーが、創業60年のマグロ仲卸「相馬水産」ではマグロバーガーなども楽しめます。 そのほか産直野菜やおいものソフトクリームなどを販売する青果仲卸「芋松」、神戸のアート和菓子店「Oh!huggy‼︎」などといった「お持ち帰りできるお店」も数多く出店するということで、豊洲ならではの「食べ歩き」や「手土産」スポットとして活躍しそうです。 豊洲場外 江戸前市場2階の「目利き横丁」イメージ。お持ち帰りグルメも楽しめます。(イメージ画像:万葉倶楽部リリース)豊洲場外 江戸前市場2階「豊洲目抜き大通り」イメージ。 「うなぎ・寿司・天ぷら・蕎麦」をそろえるとしています。(イメージ画像:万葉倶楽部リリース) そして3階は寿司のフードコートを中心とした飲食店が集まる「よりどり町屋」。 「銀座 鮨たじま」「築地海鮮虎杖」といった寿司店を中心に、北海道を中心とした産地直送のうに専門店「築地うに虎」や、生本マグロを使った江戸前海鮮丼を提供する「江戸辻屋」などの多彩な丼を楽しむこともでき、「映え」も「おいしさ」も一度に楽しめそう。 このほか、3階には肉寿司の「東京29寿司」、飯田橋の焼肉店「焼肉 塩ホルモン 好ちゃん 豊洲」などといった「肉食派」にオススメの店舗も集まります。 外国人観光客が増えつつある東京都内。この豊洲 千客万来には、大型車向けの駐車場も設けられており、将来的には「観光バスの定番コース」になるでしょう。豊洲場外を思う存分楽しむならば、観光客からの認知度が上がる前の今のうちかも知れません。 豊洲場外 江戸前市場3階「よりどり町屋」で楽しむことができるグルメ。新鮮な海鮮はまるで宝石のよう…フードコート形式の寿司店もあるため、好きなものを気軽に楽しむことができます。(イメージ画像:万葉倶楽部リリース)もう1つの場外「江戸前場下町」は再開発へ さて、豊洲市場場外のグルメスポットといえば、市場横にある「江戸前場下町(えどまえじょうかまち)」を思い出す人もいることでしょう。 江戸前場下町は三井不動産グループによって運営されるグルメスポット。2020年1月に開業し、当初は飲食店を中心に約20店舗が出店していたものの、開業直後のコロナ禍によって残念ながら空き店舗が目立つ状態となっていました。 実はこの江戸前場下町はもともと千客万来施設が完成するまでの「中継ぎ」として設けられたもの。「豊洲 千客万来」の完成を受け、今年1月30日に約4年の歴史に幕を下ろし、近く再開発がおこなわれる予定となっています。こちらの具体的な開発内容については1月時点では発表されておらず、今後が期待されます。 4年間の営業を終えて1月で閉店となる「江戸前場下町」。 こちらの再開発にも期待がかかります。(写真:若杉優貴)■豊洲 千客万来 住所:東京都江東区豊洲6-5-1 TEL:03-3533-1515 営業時間: 【物販・食物販】10:00〜18:00 【飲食店】 1F/10:00〜18:00 2F/9:00〜22:00(目利き横丁9:00〜18:00) 3F/10:00〜20:00 ※一部店舗では営業時間が異なる ■東京豊洲 万葉倶楽部 TEL:03-3532-4126 営業時間:24時間(万葉倶楽部・ローソン)/展望足湯10:00〜20:00 温浴施設料金:マル得セット大人(中学生以上)3,850円/子ども(小学生)2,000円/幼児(3歳~未就学児)1,400円(入館料+タオル+館内着他アメニティ+館内利用料込み) ※深夜(3:00~9:00)滞在は3,000円追加 アクセス: 新交通ゆりかもめ「市場前駅」より徒歩4分 築地より都営バスで約15分「市場前駅前」停留所より徒歩5分 東京駅より都営バスで約25分「新豊洲駅前」停留所より徒歩9分 虎ノ門・新橋方面から東京BRTで約30分、「豊洲市場前」停留所より徒歩3分 参照:豊洲 千客万来 公式サイト https://www.toyosu-senkyakubanrai.jp/
- スポット
- 市場前駅