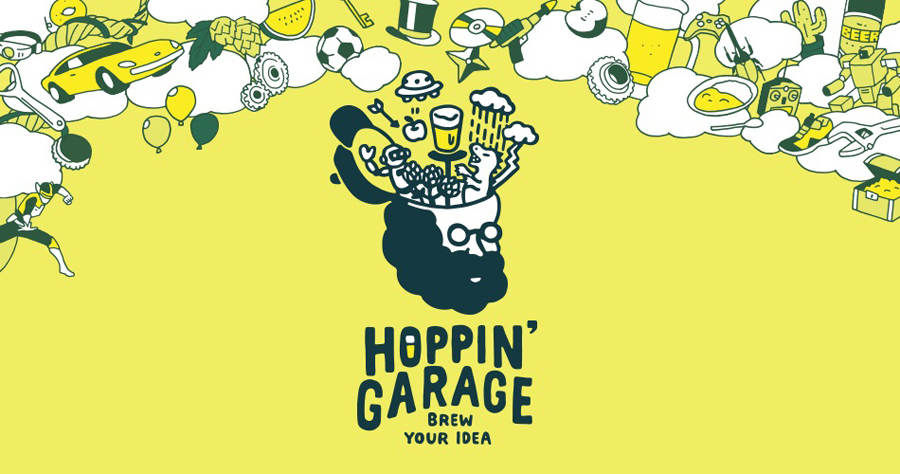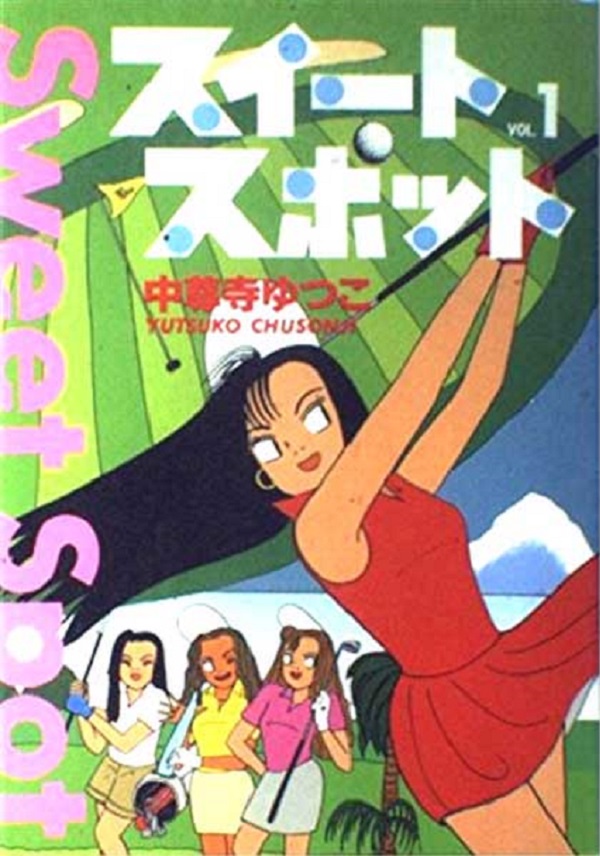子ども用おもちゃ「スクイーズ」が在宅勤務の大人にも人気がある理由
ほかに類を見ない、「癒やし」特化型おもちゃ インターネットで「スクイーズ」と検索すると、以前なら野球の戦術(スクイズ)に関するページがヒットしたかも分かりませんが今は違います。 ぐにゅぐにゅ、もちもちした触感で、本物の食べ物そっくりな色・形をしたポリウレタン製のおもちゃ、スクイーズ。だいたい2017年頃から女子小学生の間で大はやりしているこの商品が、意外にも今20~30代の女性たちにファン層を拡大しているとの話を耳にしました。 スクイーズのお店が多数軒を連ねる“聖地”といえば、やはり竹下通りを中心としたご存じ原宿。「日本スクイーズセンター」や「モッシュ スクイーシー」といった人気店には、休日ともなれば女子児童や女子生徒が大挙して押し寄せるといいます(もちろん2020年4月現在は、外出自粛や営業自粛により各店周辺も閑散としているのですが)。 大人と呼ばれる年齢に達した者にとっては、なかなか近寄りがたい一画に思えるのですが、意外や意外「子ども女子」たちのだけの物にしておくにはもったいないスタイリッシュかつシックな商品も確かにいろいろと取りそろえられているのでした。 食パンの形をしたスクイーズ(画像:虎屋) 例えば、「Picnic原宿店」などを運営する虎屋(同区千駄ヶ谷)の「ELEGAシリーズ」。 ラメ入りマニキュアをかたどった全長約6.5cmと手のひらサイズのスクイーズは、キーホルダーチェーン付きでバッグにぶら下げてもアクセントになりそう。普段はマニキュアもネイルアートも全くしない人でも、「指先のおしゃれにまで気を遣っている」かのような雰囲気を装えそうな予感です。 このように、メーカーが大人の女性もターゲットに商品を展開するのはなぜでしょうか。同社の商品担当、藤原央光(てるみつ)さんにお話を聞いてみることにしました。 知らず知らず気晴らしになる、不思議な触感知らず知らず気晴らしになる、不思議な触感 はじめに、藤原さんが何より強調するスクイーズの魅力とは「これほど『癒やし』に特化したおもちゃというものは、ほかに例が無い」という点。 メロンパンや食パン、イチゴのショートケーキ、チョコレートドーナツ、プリンアラモードなど、本物そっくりに作られた、かわいいかわいいその見た目。そしてもちもちの柔らかな触り心地と、ぐにゅーっと握り込める低反発性。さらに、どの商品にも付いている甘~い香り。それらひとつひとつの要素が、手にする人を魅了しとりこにするのだとか。 また「形も香りも千差万別、数えきれない種類の商品があるというコレクション性の高さが、スクイーズという新たな商品ジャンルを確立していったのでは」とも、藤原さんは付け加えます。 東京ビッグサイトで開かれた「ギフト・ショー」でも人気を集めた、虎屋の大人女性向けスクイーズ。SNS映えもよさそう(2020年2月、遠藤綾乃撮影) それでは、子どもだけでなく大人の女性も興味を引かれる理由は何なのでしょうか。 「先ほど挙げたスクイーズの癒やし要素が、人によって程度はさまざまですが『ストレス解消』にもつながるという効果があるようです」 2020年4月現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響で外出もままならなかったり、東京では在宅勤務(テレワーク)を敢行したりしている人も数多くいる情勢。 「仕事が行き詰まったとき、スクイーズを片手でぐにゃぐにゃ触ってみるだけで、ちょっとした気晴らしになるのかもしれません」(藤原さん) ちなみに2019年頃からは、スクイーズだけでなく同じように触り心地が特徴的な「スライム」の人気も高まっているのだそう。 スライム人気と聞くと1970年代後半から80年代にかけて、鮮やかな色合いで液体みたいな質感のおもちゃが大はやりした記憶がありますが、それが今、再び注目を集めているというのです。こちらの人気は男女を問わず、また年代ももっと幅広いのだとか。 ストレス解消と「手遊び」の密接な関係ストレス解消と「手遊び」の密接な関係 スクイーズとスライム。両者に共通するのは、前述した通りその独特の触り心地。ぐにゅぐにゅと柔らかく包容力ある触感を手のひらに抱いていると、確かに少し気持ちがまぎれたり落ち着いたりする感覚を得られるのかもしれません。 このように手で何かをいじくる「手慰み(てなぐさみ。手遊びのこと)によって気持ちが安定するという効果については、以前からしばしば指摘されていました。 例えば2017年頃に突発的な流行を見せた「ハンドスピナー」は、手のひらサイズの本体を指ではじいてクルクル回すだけの単純なおもちゃですが「気分が落ち着いたり、集中力が維持できたりする気がする」という声が愛好者たちからよく聞かれました。 子ども時代を思い返せば、俗にいう「ライナスの毛布(安心毛布)」もこの手の類いのひとつでしょう。お気に入りのタオルや毛布、ぬいぐるみをいつも手元に置いて触っていることで、安心感を得られるというものです。 お気に入りの毛布に触れながらリラックスするイメージ(画像:写真AC) また、医療・介護の現場で患者や入所者たちが犬・猫の温かく柔らかい体に触れて癒やしを得る「アニマルセラピー」にも、どこか通じるものを感じます。 自分にとって心地よい触り心地のものに触れている、また手元に置いておくことの効果は、ストレスを感じやすい大人にとってもかなり有用であると言えそうです。 大人がうれしい効果……ずばりストレッチ ちなみに、今回スクイーズについていろいろ調べるうちに、もうひとつ、大人にこそ非常にうれしい“効果”があることを知りました。 スクイーズ商品の中でも比較的歴史の古い、バナナの形をした全長20cmほどの商品。これは、両端を握って背中の後ろでぐにゅーっと伸ばすと、気持ちのよいストレッチにもなるのです。 手軽なストレッチ道具にもなる、便利なバナナのスクイーズ(2020年4月24日、遠藤綾乃撮影) すっかり忘れていましたが、筆者の自宅にも1本、以前購入したこの「バナナ」がありました。ネット通販で買う場合は、ひとつ数百円前後で入手できるようです。 在宅勤務でストレスもたまりがち、おまけにデスクに座りっぱなしで体もガチガチ……。そんな大人の皆さん、この機会に流行のスクイーズにちょっと手を出してみるというのはいかがでしょうか。
- ライフ