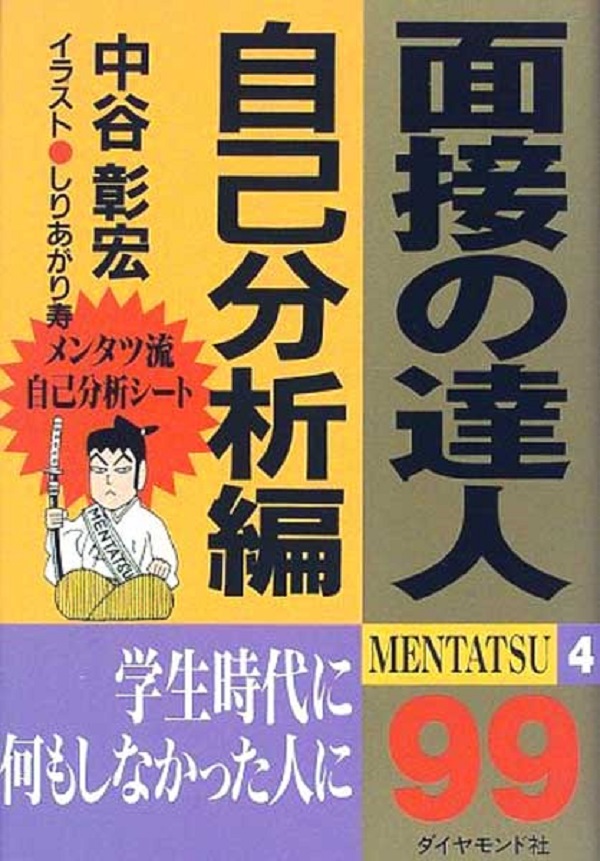コロナで行き詰まる大学授業 早稲田大学が打ち出す「7割対面」は実現できるか
キャンパスライフが激変した2020年 2019年の師走はラグビーワールドカップ2019の大健闘もあり、多くの人が来る2020年東京オリンピック・パラリンピックの盛り上がりを期待していました。あれから1年がたとうとしていますが、オリパラの盛り上がりどころか、前代未聞の事態が次々と起き、混迷した1年となりました。 教育現場も例外ではなく、ほとんどの大学では感染リスクを考慮し、授業をオンライン主体で行っています。 新型コロナウイルスの感染拡大による重苦しい空気が漂い始めた2月、多くの大学は卒業式を見送りました。同月27日(木)には、早稲田大学(新宿区戸塚町)と立命館大学(京都市)が2020年度の入学式中止を発表し、話題を呼びました。 新宿区戸塚町にある早稲田大学(画像:写真AC) さらに早稲田大学は3月24日(火)、2020年度新学期のスタートを5月11日(月)に先延ばしすることも発表。くしくも同日、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催延期の決定が下されました。他大学も早稲田大学に追随するように、授業開始時期を軒並み5月以降にずらしました。 大学構内への立ち入りは禁止され、大学キャンパスはいつものにぎやかさとは程遠い人気のない姿へと変貌したのです。 2021年度に向けて動き始めた早稲田2021年度に向けて動き始めた早稲田 新型コロナウイルスの感染収束はまだ見えませんが、都内の大学では秋から厳格なルールの下で、段階的に対面授業やサークル活動の再開へ動き出しています。しかし小学校から高校までが6月以降再開したことに比べて、大学の規制は依然として厳しい状況です。 大学側はこれから本格化する受験シーズンを控え、大学構内でのクラスター発生は絶対に避けたいところです。そのため軽々しく対面授業再開を公言することが難しく、道の前方にはいくつもの高いハードルが待ち受けています。 各大学の手探りが続くなか早稲田大学の田中愛治総長が12月1日(火)、大学ホームページで「コロナ禍での現在と今後の学校生活について」と題するメッセージを発表。 「2021年春学期には、感染状況が許せば約7割の授業を対面で実施できるように、現在計画をたてています」 と学校再開に向けた決意表明を述べました。 早稲田大学のウェブサイトに掲載された「コロナ禍での現在と今後の学校生活について」(画像:早稲田大学) 同メッセージのなかでは、早稲田大学が図書館や図書室、戸山キャンパスの学生会館を再開し、サークル活動も厳しい制限の下で行っていることが触れられています。 また、初めてのオンライン開催となった「早稲田祭2020」に携わった学生たちが構内を消毒したり飲み会を自粛したりと規律のある行動をとったとも。その結果、クラスターが発生していないことから、上記のメッセージを発表したといいます。 もちろん、リスクを冒してまで対面授業に出席を求めるものではありません。 他大学も追随か他大学も追随か 2021年度もオンライン主体で授業は行われる可能性が高いと考えられますが、一方、他の私立大学が早稲田大学の動きに追随する可能性も否めません。 早稲田大学より学生数が多いのは日本大学(千代田区九段南)くらいのため、早稲田大学が対面授業再開に本腰を入れているとなれば、模倣とは言わなくとも、他大学も何らかのアクションを取らざるを得ないでしょう。 現に明治大学(千代田区神田駿河台)では、大六野(だいろくの)耕作学長が12月17日(木)、2021年度から対面授業を主体とする方針を打ち出しています。 千代田区神田駿河台にある明治大学(画像:(C)Google) 翌18日には東洋大学の矢口悦子学長が2021年度に向けた授業運営を表明。現在行われているオンライン授業を導入しつつ、できるかぎり対面授業を行う方向で準備しているとしました。 私立大学の多くが2021年度の授業に関して公式発表を控えるなか、「感染状況次第」と前置きをしつつも、自らの進む道を示した明治大学と東洋大学にも注目が集まります。 現在の感染状況を踏まえても、コロナ以前に戻ることは不可能です。 そうしたなかで早稲田大学が出した「約7割の授業を対面授業で」という具体的なメッセージは、困難な状況下でも自らのスタンスを発信する教育機関としての、本来のあるべき姿なのかもしれません。
- ライフ