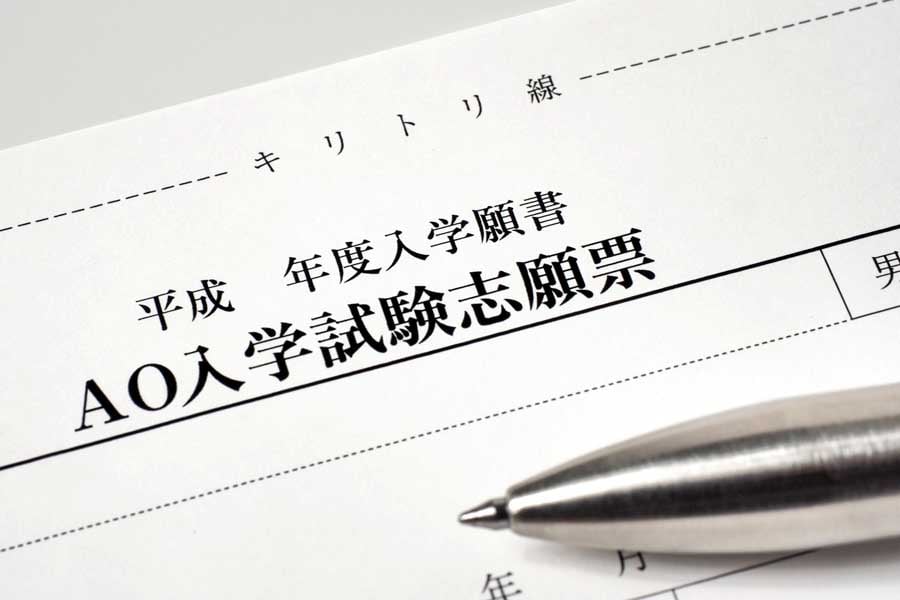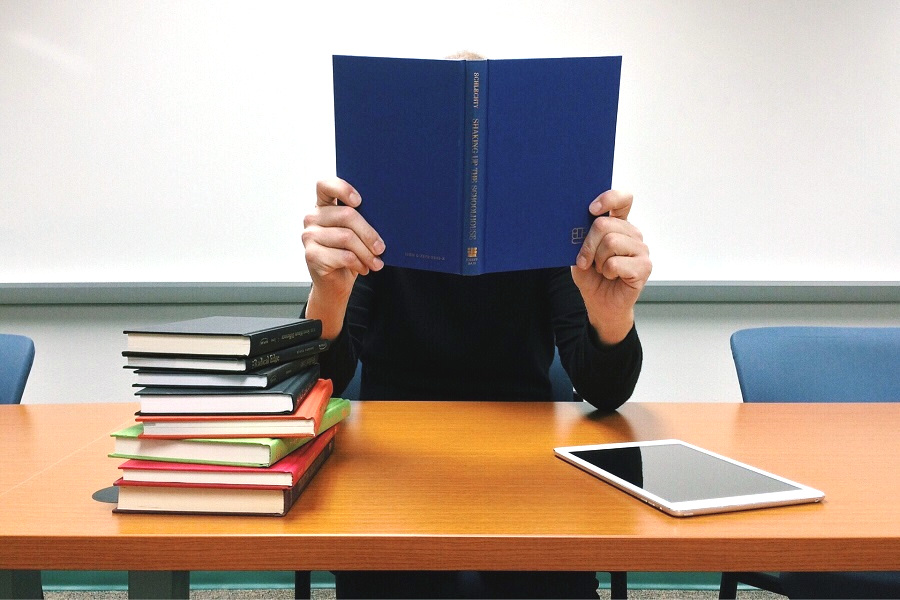マイナー企業も続々参戦 SNSのオリジナル「4コマ漫画」、狙いを聞いたら想像以上に奥が深かった
大手企業が次々と作品を投下している、ツイッター上のPR漫画。でも実は、決して知名度が高くない企業も、「自作の4コマ漫画」をいろいろ投稿していることにお気づきでしたか? 手作り感あふれる「ヘタウマ」な作品の数々、探し始めたら夢中になってしまいそうです。たとえ「いいね!」が少なくても 大手企業や有名企業がツイッターで漫画を使ったPRを展開するようになったのは、いつ頃からのことでしょうか。 東京にある会社に限っても、カネボウ化粧品(中央区日本橋茅場町)や大東建託(港区港南)、メルカリ(同区六本木)、「日ペンの美子ちゃん」でおなじみの通信教育がくぶん(学文社。新宿区早稲田町)、メイトーなめらかプリンの協同乳業(中央区日本橋小網町)などなど、少し検索しただけでも次々にヒットします。 最近は、ツイッターで数万~数十万以上のフォロワーを抱える人気の漫画家やイラストレーターに制作を依頼し、漫画家のアカウント上で「#PR」というタグを付けて発表するスタイルが主流のよう。 有名な企業と人気の作り手がコラボすることで、相乗的に注目を集めているようです。 一方、知名度や事業規模という点では決して「大手」ではない企業や団体も今、次々と漫画(特に4コマ漫画)をツイッター上で配信していることにお気づきでしょうか? 「ヘタウマ」な味わい深い作品が多い、ツイッター漫画の世界(画像:品川区オリンピック・パラリンピック準備課) こちらの場合、漫画制作を担当するのは主に当該企業や団体の社員、職員たちです。 プロによる作り込まれた絵柄やストーリー展開と違って、どこか「ヘタウマ」な味わい深い作品が多いのが特長で、試しに読んでみると独特の魅力が満ち満ちています。 たとえフォロワー数が少なくても、「いいね!」やリツイートが少なくても、こつこつと更新されていく4コマ漫画たち。一体どのような狙いがあるのでしょう? 各担当者に話を聞いてみたら、その奥深さに気づかされました。 健康に携わる企業の萌え系CSR漫画健康に携わる企業の萌え系CSR漫画「社名を名乗ると、『日清食品さんですか?』と聞き返されることもあるんですよ」 そう言って笑うのは、ヘルスケアフードを取り扱う日清医療食品(千代田区丸の内)広報課の神戸修さん。食品大手の日清食品(新宿区新宿)と資本関係はないと言います。 同社が発信しているのは、「萌(も)え」風タッチの女の子たちが、熱中症の症状や対処法などについて学ぶギャグ4コマ漫画連載。 熱中症について考える漫画の1コマ(画像:日清医療食品) ストーリー原案を神戸さんが考え、知人の女性が作画を担当している同作品、「第1話」が投稿されたのは2020年5月11日(月)と比較的最近ですが、実は2014年から同社ウェブサイト上に掲載していて、全60話を読むことができます。 少し天然ボケな女の子が毎回、勘違いしたりアタフタしたりしながら熱中症について学んでいく様子は、脱力系で読んでいるとほのぼのした気持ちに。 医療・福祉・保育施設からの給食業務を受託している同社は「B to B」が事業の中心ですが、「これから熱中症対策に気を配る季節になりますので、少しでも(広く市民の)お役に立てれば」(神戸さん)と、予想気温が高い日を狙って1話ずつ投稿しているそうです。 漫画の制作を始めた2014年当時、まだまだ熱中症の認知が進んでいなかったといい、「難しいマニュアルよりも分かりやすい漫画で伝えてはどうか」と考えたのが、そもそものきっかけ。 健康に関わる企業として「ためになる情報」を届けようと、最近では新型コロナウイルスの感染予防に関する作品も配信しました。 何気ない日常に願う、幸せな世界何気ない日常に願う、幸せな世界 やさしい童話の挿絵のような絵が印象的な「フクイのポチ子ちゃん」は、洋服のタグなどを企画・製造するフクイ(台東区柳橋)の公式アカウント上で2020年4月24日(金)から連載中。 おかっぱの女の子ポチ子ちゃんとラブラドールレトリバーのポチ、それからおばあちゃんの3人(ふたりと1匹)による、派手なオチは付かない、何気ない日常のやり取りが不思議と心に残る作品です。 ポチ子ちゃん、ポチ、おばあちゃんの何気ない日常を描いた漫画(画像:フクイ) 作品制作を全て担当しているのは、同社開発部の黒田まゆみさん。なぜ「ポチ子ちゃん」と「ポチ」なのかというと、工学博士の佐川賢氏と同社が共同で開発した「いろポチ」という洋服用のタグから生まれたキャラクターだから。 いろポチは幅3cm長さ5cmの布テープ。そこに色相環(代表的な色相を環状に並べたもの)を表すポチポチ(突起)と穴が計23個付いていて、視覚障害のある人もこのタグに触れれば、それぞれの洋服の色を把握できるという優れもの。アイロン接着シートなどで服や小物に付けて使うそうです。 ただ漫画ではこの製品に関する言及は一切なく、「気になった人が当社のURLをクリックしていただけたら」(黒田さん)と控えめです。ちなみに2020年7月7日(火)現在のフォロワー数は10人。 ちなみにポチ子ちゃん、作品の主人公なのにいつも後ろ姿です。顔は見せません。ツイッターのプロフィル欄には、「決して後ろを振り向かない前向きなポチ子ちゃん」とあります。 「いろポチを開発した際、最初にパンフレットに描いたイラストが後ろ姿だったので、顔はあえて見せないことにしました。その代わり、おばあちゃんとポチがいろいろな表情を見せています」と黒田さん。 後ろ姿だけのポチ子ちゃんですが、着ている服は毎日カラフル、おしゃれ。「すべての人が色を楽しめる社会を」という、いろポチに込められた思いを体現しているようです。 汗と涙で描くオリンピックへの道汗と涙で描くオリンピックへの道 企業ではなく自治体発で、ひときわ派手な作品を発見しました。2020年6月22日(月)から連載が始まった、品川区オリンピック・パラリンピック準備課(品川区広町)の公式アカウントです。 同課課長の辻亜紀さんによると、職員たちでネタだしをし、オリンピック出場経験のある同課の女性職員が作画を担当しているそう。 同じく同課の若手男性職員をモデルにした主人公シミスくんが、オリンピック関連イベント開催に向けて悪戦苦闘する様子を描いています。 勢いと迫力に圧倒される品川区オリパラ準備課の漫画(画像:品川区オリンピック・パラリンピック準備課) ご覧いただければ分かるように、とにかく勢いがすごい! 太眉が特徴的なシミスくんたちが繰り広げるドタバタの数々に、思わず吹き出してしまう迫力系コメディー作品に仕上がっています。 辻課長いわく、「東京オリンピックが延期になってしまい先が見えにくい状況ではありますが、こんなときだからこそ前向きに、今できることを考えて始めることにしました」。作品に通底する「勢い」は、職員たちのやる気の表れでもあります。 当初は「区役所なのにふざけてる、と捉えられたらどうしよう……?」という不安もあったそうですが、今のところそのような外部からの指摘はなく、区役所の中でも「面白いことやっているな~」と好意的に受け止められているそう。 ちなみにこの作品は、2020年7月23日(木・祝)に開催予定のオリンピック関連のオンラインイベントまでの、1か月間限定連載とのこと。 あらかじめ連載回数を決めた展開の仕方は、2019年12月から2020年3月までツイッターなどで連載されて話題になった「100日後に死ぬワニ」に影響された部分もあるそうです。 ツイッターのユーザーたちが固唾(かたず)を飲んで見守った、ワニくんの100日間。果たして品川区のシミスくんの1か月間は、どのような結末を迎えるのでしょうか。 私だけのお気に入り作品を求めて私だけのお気に入り作品を求めて この「100日後に死ぬワニ」がツイッターの4コマ漫画に及ぼした影響は非常に大きいようで、同連載の終了後には「○日後に××する△△」というパロディー漫画がさまざまな書き手によって誕生しました。 大手企業もこのスタイルに乗っかっているようで、ハンバーガーチェーン「バーガーキング」を運営するビーケージャパンホールディングス(千代田区一番町)は、2020年7月16日(木)までの期間限定バーガーメニュー3種をPRするために、ゆるキャラ3人が登場する漫画で「販売終了まで あと○日」とうたっています。 「100日後に死ぬワニ」のオマージュ? バーガーキングのキャンペーン漫画(画像:バーガーキング・ジャパン) 残り日数をカウントダウンする形式は、やはり読者の関心を集めやすいのかもしれません。 ※ ※ ※ 大手企業から小さな企業、行政まで参戦して、群雄割拠(ぐんゆうかっきょ)のツイッター漫画界。有名な会社や有名な作者の作品を見るのももちろん楽しいですが、まだあまり知られていない作品を自分で発掘したら、思い入れもより強いものになりそう。 毎日のちょっとした息抜きや楽しみに、ツイッター漫画。皆さんもいかがでしょうか。
- ライフ