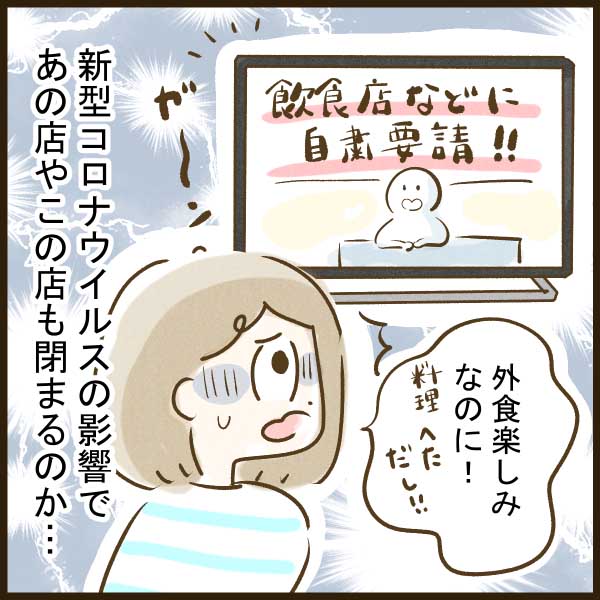僧侶・天海が尽力した上野の「桜の名所化」
春になると、まず思い出すのは上野恩賜公園(台東区上野公園)の桜です。2019年の人出はなんと約400万人。全国に花見の名所は数あれど、2週間あまりの花見期間にこれだけの人が訪れるのはもちろんぶっちぎりの第1位です。
 上野公園の表玄関・袴腰広場のオオカンザクラ(画像:五十嵐泰正)
上野公園の表玄関・袴腰広場のオオカンザクラ(画像:五十嵐泰正)
上野が桜の名所となったのは、江戸時代初期、徳川家に側近として仕えた僧侶・天海が、吉野の桜を植樹したことに始まります。
徳川家の菩提(ぼだい)寺・寛永寺(同区上野桜木)の創建に1622(元和8)年から取り掛かった天海はほかにも、清水寺に倣って清水観音堂を、琵琶湖の竹生島に見立てて不忍池に人工島を作って弁天堂をと、上方(京都およびその付近)の名所に見立てた堂宇(どうう。堂の建物)を次々に建立していきました。
これは、当時の文化先進地だった上方の名所を上野に再現し、しかもそれを一般に開放して、新興都市の江戸の庶民に親しまれるような名所を作る――という、天海による一種の文化政策でした。
江戸庶民に深く浸透した将軍家の威光
その結果、寛永寺は冷たい印象を与える「官」一辺倒の寺と受け止められることがなくなりました。
将軍家の威光は、上野の山という「楽しい行楽地」を提供してくれたことへの感謝の念とともに、江戸の庶民の心に深く浸透していったのです。
明治時代に上野の山が数々の博覧会の舞台となり、この地に日本を代表する文化施設が建設されていったのも、この時代の
「文化先進地 = 西洋の文化的威光」
という考えをもって、将軍家の威光を明治天皇と新政府の威信へと塗り替えようとした、明治政府の思惑があったと考えるべきでしょう。
「悪の巣窟」の汚名返上がきっかけ
そして、現代に連なる上野の桜まつりは、戦後復興期に始まります。
愚連隊(ぐれんたい)が大手を振って歩き、スリ・置引・恐喝が横行した上野駅の地下道が「悪の巣窟」と呼ばれ、上野恩賜公園に400人前後の街娼(がいしょう)が繰り出した終戦直後の上野は、「ノガミ(野上。上野の逆さ読み)」という隠語で恐れられる街になりました。
この「ノガミ」の汚名返上は、戦後の混乱の渦中にあった街の人々の切なる願いでした。
 所狭しと宴席が張られた、過去の「うえの桜まつり」の様子(画像:東京発フリー写真素材集)
所狭しと宴席が張られた、過去の「うえの桜まつり」の様子(画像:東京発フリー写真素材集)
そのために1947(昭和22)年に結成された上野鐘声会(うえのしょうせいかい。上野観光連盟の前身)は、硬軟取り混ぜた施策を矢継ぎ早に打ち出します。
その目玉となったのが、「国土美化と同胞偕楽(かいらく)」のための「公共事業」とうたった、上野の山への1000本の桜の植樹と、「うえの桜まつり」の開催だったのです。
新型ウイルスで「桜まつり」中止も……
しかし残念なことに、2020年は新型コロナウイルス拡大の懸念を踏まえ、3月20日(金)から予定されていたうえの桜まつり・桜フェスタは中止となりました。これは東日本大震災が発生した2011年以来のことです。
それにともない、袴腰(はかまごし。上野恩賜公園の中央通り側の入り口)から上っていく桜並木のメインストリートにも宴会用のスペースは設置されなくなりました。
 例年のうえの桜まつりは街をあげての大イベントに(画像:五十嵐泰正)
例年のうえの桜まつりは街をあげての大イベントに(画像:五十嵐泰正)
ただ、桜並木を彩るちょうちんは例年通りつり下げられ、3月下旬から4月上旬にかけての桜の時期にはゴミ置き場も設置されます。2020年はワイワイ楽しむお花見ではなく、一味違う上野恩賜公園の桜めぐりをしてみるのもよいでしょう。
桜ファン必見の「上野公園桜マップ」
現在の上野恩賜公園に咲く桜の大半はソメイヨシノですが、実は多種多様な品種の桜の木があります。
上野の桜について知りたいときに、必ず見てほしいのが「上野公園桜マップ」です。
上野の桜を守り、伝えることを目的として活動している「上野桜守の会」が作成しているこのマップは、公園内のどの場所に、どの色の品種が植えられており、いつ頃咲くのかが網羅されている優れものです。
同マップ(平成25年版)によると、上野恩賜公園にはなんと52種類ものサクラ属の木があるとのこと。桜の季節と言えば、卒業式~入学式シーズンのソメイヨシノのイメージがあまりにも強いですが、実は1月下旬から5月まで桜の見頃は多種多様。なかには、秋から冬に咲く変わり種もあったりするのです。
公園内で見られる早春を象徴する風景とは
上野で最も有名な「季節外れの桜」は、中央通りへと開けた上野恩賜公園の表玄関・袴腰広場にある2本のオオカンザクラです。
2月の終わりごろに上野をぶらぶら歩いていて、「もう桜が満開?」と驚いたことありませんか? この光景を見れば、「温暖化がここまで来たか」と震えなくても大丈夫です(それでも以前より1週間ぐらい早まっているようですが……)。
しかし、早咲きはこのオオカンザクラだけではありません。公園内メインストリートのソメイヨシノ並木沿い、清水観音堂のはす向かいに2本あるカンザクラは、1月末には咲き始め、見ごろは2月上~中旬です。この記事の写真を撮りに行った2月末には、もう盛りをすっかり過ぎていました。
上野で忘れてはいけない早咲きの桜は、まだまだあります。
 不忍池畔のカワヅザクラの幼木(画像:五十嵐泰正)
不忍池畔のカワヅザクラの幼木(画像:五十嵐泰正)
特に目立つのは、不忍池の東岸、下町風俗資料館前の池畔に何本かあるカワヅザクラです。中でも背が低くてかわいいカワヅザクラの幼木ごしに、不忍池弁天堂と池之端のタワーマンション群を臨むこのアングルは、令和の東京の早春を象徴する風景といっても過言ではありません。
注目したい遅咲きの桜の魅力
そして2020年に注目したいのが、遅咲きの桜です。
4月中・下旬から5月にかけて見頃を迎える遅咲きの桜はシロタエ、イチヨウ、フゲンゾウなど色味もさまざまで、上野恩賜公園には多種多彩なのです。
 両生爬虫(はちゅう)類館から東天紅を経て上野区民館へと至る不忍池西岸には、遅咲きのカンザンの並木が(画像:五十嵐泰正)
両生爬虫(はちゅう)類館から東天紅を経て上野区民館へと至る不忍池西岸には、遅咲きのカンザンの並木が(画像:五十嵐泰正)
特にお勧めしたいのは、不忍池西岸(東天紅前あたり)から南岸(水上音楽堂あたり)にかけてのエリア。ここには、濃い紅色の八重桜・カンザンの並木を中心に、ショウゲツ、カスミザクラ、バイゴジジュズカケザクラといった、個性的な遅咲きの名木がめじろ押しです。
宴席を張れる場所もあるため、新型コロナの脅威も収束していることを祈りつつ、ゴールデンウイーク前の晩春のお花見に期待をかけましょう。
2020年は「一味違う」桜めぐりを
上野恩賜公園には貴重な桜が多々寄贈されていて、あたかも日本各地の希少な桜の展覧会のようです。その代表格は、国立西洋美術館裏の植え込みに植えられたソノサトキザクラでしょう。
 国立西洋美術館裏手のソノサトキザクラ(画像:五十嵐泰正)
国立西洋美術館裏手のソノサトキザクラ(画像:五十嵐泰正)
ソノサトキザクラは2001年、フゲンゾウの古木の枝代わりとして長野県須坂市で発見され、新品種として認定された黄緑色の八重桜です。5月に満開となるソノサトキザクラは見つけやすいところにあるので、ぜひ探してみてください。
満開のソメイヨシノの下で行う大宴会も楽しいですが、それだけではない桜の奥深さを教えてくれるのが上野恩賜公園です。
2020年はぜひ、一味違う個性的な上野の桜めぐりを楽しんでみてください。