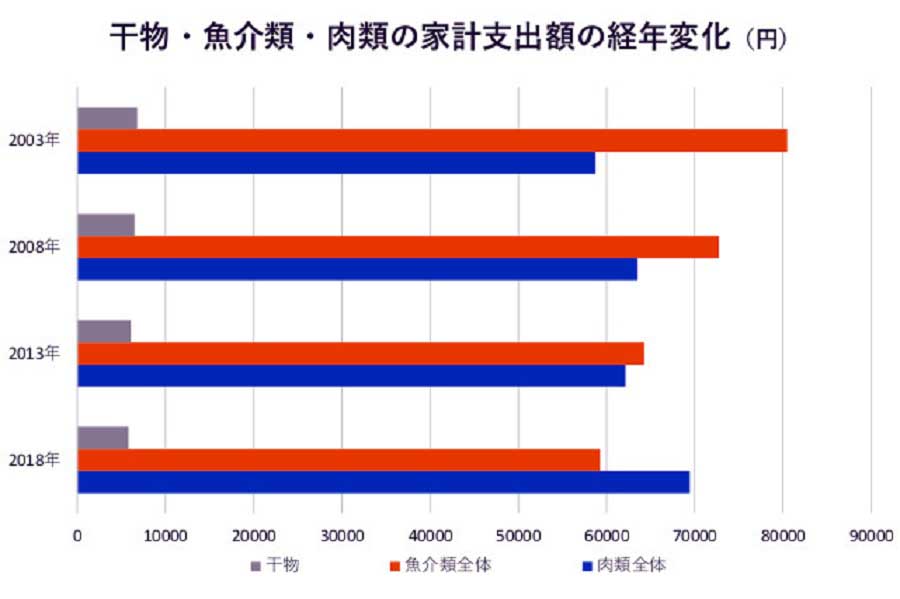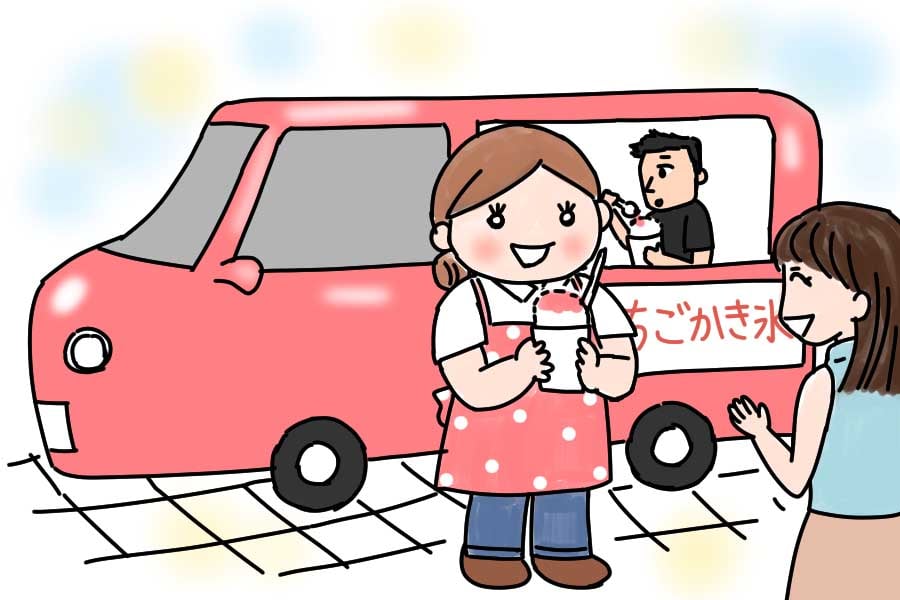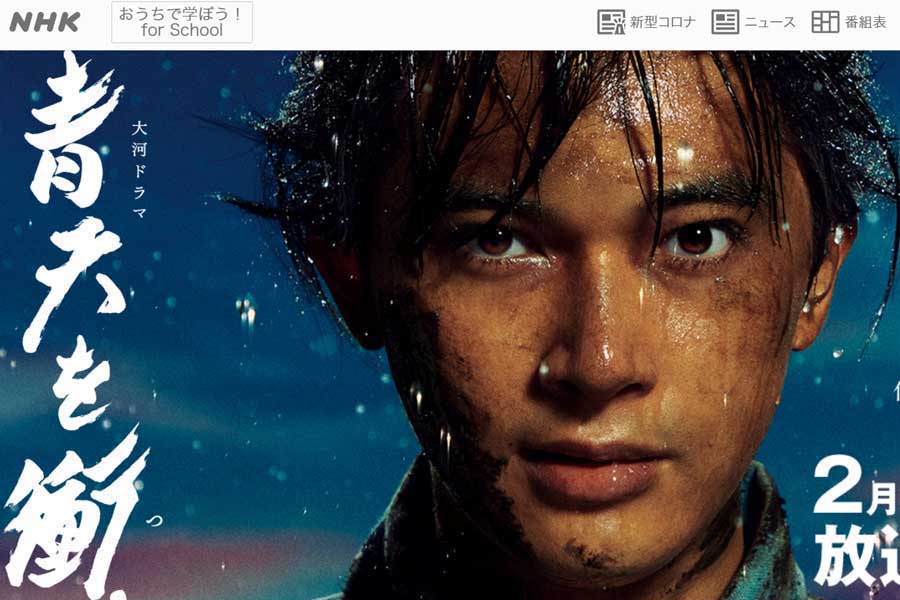家も学校もなじめなかった30代女性が、猛暑の「日雇いバイト」で少しだけ自信を取り戻した話
不思議な縁で「かき氷」売りバイトに 数年前の猛暑日、わたし(いしいまき。漫画家、イラストレーター)はかき氷を売っていました。 「いらしゃいませ~。かき氷はいかがですか? 手作りイチゴシロップがおいしいですよ~」 大きな声で呼び込みと接客。うっすら汗をかきながら、久しぶりに労働の充実感をかみしめていました。 しかしこのかき氷売りのバイト、バイト情報誌を見て応募したわけでも、知り合いの紹介があったわけでもありません。それはひょんなことがきっかけでした。 上京するも、思うようにいかない日々 漫画家として自分の力を試してみたくて鹿児島から東京に出てきたのですが、なかなか思ったように仕事は来ません。 もんもんとした日々。生活費のために週4、5日アルバイトに入ると今度は逆に漫画の仕事が入り、バイトのシフトがうまく組めず辞めざるをえなくなる……。 何をやっているんだろう……。空回りして自分のことを嫌いになりそうな日々でした。 その日は気晴らしに街をひとりで出てぶらぶらしていました。 バイトも辞めたところで漫画の仕事も終わったところ。次の仕事はいつくるのか……新しいバイトを探した方がいいのか……。 ぐるぐると考えながら過ごしていました。 ショッピング施設に止められた赤い車ショッピング施設に止められた赤い車 わたしのうっすら不安な気持ちとは対照的な、晴れやかな空とカンカン照りの猛暑日。おしゃれなショッピングビルの中にはすてきな服や化粧品、インテリア、雑貨が並べてあり、見ているだけでも楽しいです。 それらを見ている間は自分の現状を忘れることができました。 ひと通りウインドーショッピングを楽しむも、お金はないので何も買えません。むなしさにつつまれていると、ショッピングビルの入り口に赤い車が止まっているのが見えました。 赤い車の、かき氷売り屋さん。そこで飛び込みのバイトをすることになった理由とは――?(いしいまきさん制作) 車のボディーには「いちごかき氷」の文字。どうやら催事でイチゴかき氷の専門キッチンカーが来ているようです。 「服を買うお金はないけど、かき氷を買って夏気分を味わうくらいなら許されるんじゃない……?」そう思ったわたしは引き寄せられるように赤い車に近づいていきました。 思わず「わたし手伝いましょうか?」 店主は30代半ばのスポーツマンっぽい気のいい男性で、オーダーすると赤くてとろりとした自家製イチゴシロップのかかったかき氷を渡してくれました。とても暑かったので夢中で食べたのを記憶しています。 食べていると店主がなにやら独り言をつぶやいているのが聞こえました。 「あーあ……明日のバイトの子見つからないな……。あーどうしよう、困ったな……」。なるほどバイトがいなくて困っているようです。 それを聞いて「よければわたしがバイトに入りましょうか?」。瞬間的に言葉が出てきました。 引っ込み思案、だけどときどき積極的引っ込み思案、だけどときどき積極的 普段、自分のことを引っ込み思案だと思っているのですが、たまにこのように積極的になることがあるのです。 わたしの実家はラーメン屋です。「バイトがいなくて困る」という状況がかなり痛いということがよくわかったのでした。加えて店も手伝っていたので、接客業をすること自体に不安はありませんでした。 これらの理由から声をかけたのですが、店長はすごくビックリした様子でした。 しかし「ありがたい、早速3日間来てほしい」と言われて、不思議な縁のかき氷売りバイトが始まったのでした。 呼び込みの声がいいね、と褒められて 仕事内容はイチゴをイメージした赤地に白の水玉模様のエプロンを着て呼び込み、オーダーを聞き、店長に伝え、商品をお客さんに渡すというものでした。 初めは緊張しましたが、もともと接客業に慣れていたので大きな声で呼び込みをするのは楽しく、家の中でくすぶっているより心の健康に良い気がしました。 猛暑日にかき氷をお客さんに渡すと、オアシスに出合って生気がよみがえったかのようないい笑顔になるのです。それを見るのも楽しかったです。店長からも声が大きくてよいと褒められました。 日に5時間くらい3日間働いたと記憶しています。あらためて考えてみても、どこの誰かもわからないわたしを3日間とはいえ使ってくれた店長はすごいですね。でもそれだけ困っていたのかなと思います。 家庭や学校にはなじめなかったけれど家庭や学校にはなじめなかったけれど 先ほどは自分のことを引っ込み思案な性格だと思っていたと書きましたが、振り返って考えてみると今は違うような気がしてきました。子ども時代は、家庭や学校になじめずにいただけなのかもしれません。 家庭や学校になじめなかったという理由で、「自分は引っ込み思案」と決めつけていたかもしれない(いしいまきさん制作)「こうでなければならない」と決められたルールで動くのがすごく苦手でした。それゆえに苦手がばれないよう、おとなしくするしかなかったのかなと思いました。 大人になってからは思い切った行動をとれるようになっているように思います。 抑圧されていたものが少しずつ解放されているような感覚。当時の学校の先生が今の私を見たら驚くかもしれませんね。自分がまさか飛び込みで接客業のバイトを申し出るなんて……。 店長にも感謝され、3日間のバイトはいい心のストレッチになりました。「こんな風に気軽にバイトができたらいいのにな~」と今も思っています。 自分の得意・不得意を知ることの良さ わたしは接客は好きですが、バイト先で発生する人間関係が苦手なのです。 自分のことを引っ込み思案だと思って居場所を作れないでいる人も、コミュニケーションが苦手なだけで決められた接客をするのは苦ではない人もいるのではないでしょうか。 わたしのように短期のバイトをしていくことで小さな自信を積み重ねていくのはひとつのよい方法かもしれません。その中で自分の好き、嫌い、得意、不得意を細かく見ていくと、居心地のいい場所に近づける気がするのです。
- ライフ