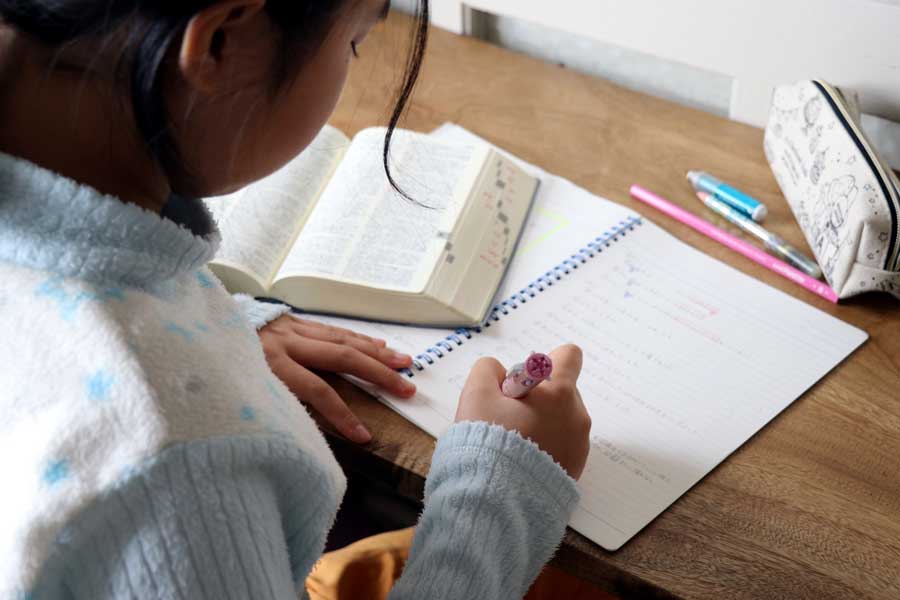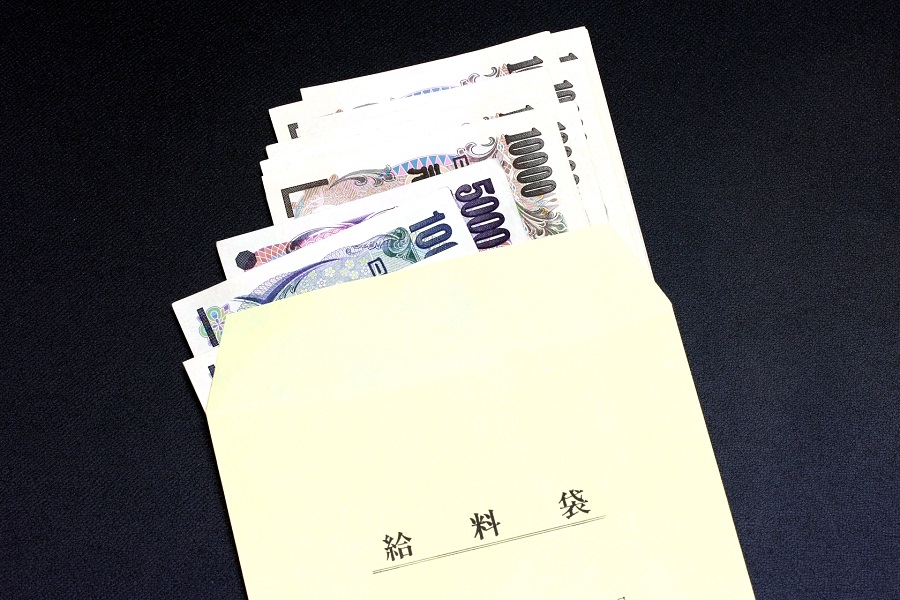4月に全面施行 「東京都受動喫煙防止条例」はノンスモーカーの建前「どうぞお構いなく」を解決できるか
新たなビジネスチャンスも 東京五輪に向けて一段と禁煙化の波が激しくなり、喫煙者は肩身の狭い思いをしているという声がよく聞かれます。一方で、これを新たなビジネスのチャンスとしてポジティブに捉える事業者も多いようです。 2020年4月から全面施行予定の「東京都受動喫煙防止条例」では、受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防止することを目的としています。そのため公共施設はもとより、一般の飲食店でも原則として屋内は禁煙となります。 喫煙のイメージ(画像:写真AC) この規制ルールでは、これまで通りの喫煙ルールを継続できる ・都指定特定飲食提供施設 ・その他飲食店(第2種施設) と、要件を満たしたバーやスナックを対象とした、 ・喫煙目的施設 に分類されます。一時は、バーやスナックまで禁煙になってしまうのではないかと多くの店舗が危惧していましたが、緩和的な措置として小規模店は全席で喫煙が可能となりました。 東京都は約13万軒が対象に 喫煙ルールを明文化した法律としては現在、国の健康増進法があります。ここでは客席の面積や資本金の規模などで規制の対象を決めていました。東京都の条例はこれよりも厳しいもので従業員を雇っている場合には原則禁煙となります。 喫煙室のイメージ(画像:写真AC) 東京都によれば、都内の飲食店のうちおおむね84%が喫煙専用室や加熱式たばこ専用の喫煙室を設けなければならなくなります。84%というのは店舗数にして約13万軒ですから、相当な規模です。 喫煙席か禁煙席かを選ぶ配慮がなくなる喫煙席か禁煙席かを選ぶ配慮がなくなる 喫煙者にとっては、たばこが吸いにくい環境になるという見方が一般的ですが、実際にはそうともいえません。客席を全面禁煙する店舗がある一方、喫煙専用室や加熱式たばこ専用の喫煙室を新たに設ける店舗も増えています。 これまで、友人と会ったり商談などで飲食店を利用したりするときに、たばこを吸う人と吸わない人が混じっていたというシーンに遭遇したことのない人はまずいないでしょう。 たばこの自動販売機が並ぶイメージ(画像:写真AC) そうした場合に困るのは、喫煙席か禁煙席かどちらを選ぶか。お互いに相手の立場に配慮して遠慮し合うこともありますが、そうなるとどちらかは確実に不満です。とりわけ「喫煙席でいいですよ」となっても、吸っている人は「煙いなあ」という顔をしている相手に配慮して、いい気持ちでスパスパとたばこを飲むことはできません。 吸わない方は副流煙を吸わされているわけで、内心でははらわたが煮えくりかえっているかもしれません。その点、喫煙専用室が設置されていれば「ちょっと失礼」と席を外して一服することができるので、どちらにも利点があります。 加熱式たばこの台頭で喫煙環境に変化 また、新たな店舗に設けられた喫煙専用室というのは、たいてい空気清浄器を備えていてきれいです。従来の喫煙室というと、どこでも取って付けたような壁で中はヤニだらけというのが当たり前でしたが、東京都の条例を前に設けられているものは、そうしたネガティブな雰囲気はありません。 また、加熱式たばこ専用の喫煙室を設けている店舗も多いことから、加熱式たばこのCMやプロモーションも増えています。 加熱式たばこのイメージ(画像:写真AC) かつては、たばこを売っている店の近くでたばこの試供品を配ったりしている光景はよく見かけましたが、最近は加熱式たばこばかりです。周辺に匂いをまき散らす量も少ないですし、比較的健康に害がないというイメージの加熱式たばこ。「専用」の喫煙室が増えることによって新たなビジネスのチャンスとなっているようです。 訪日外国人は驚くかもしれない都の分煙施策訪日外国人は驚くかもしれない都の分煙施策 条例により厳密になる分煙ですが、結果として若干の問題も起こっています。受動喫煙を避けるために街角から灰皿が消滅しているのです。 街角の喫煙所のイメージ(画像:写真AC) これまでタバコ屋やコンビニの店頭に置かれていた灰皿もどんどん撤去されています。そうなると、灰皿のある店の前に人が集まります。店側としては、多くの人がたばこを吸うだけで売り上げにも貢献しない。また、近所迷惑になり苦情が来てしまう。そうした負のスパイラルによって、街角の灰皿はどんどん減っているのです。 完全に迷惑施設扱いになった喫煙所。全国で初めて路上喫煙を禁止する条例を決めた千代田区では、禁止とともに喫煙所の整備も進めてきました。 2018年からは車でけん引して移動できるタイヤ付きの「喫煙トレーラー」を導入しました。購入費は1000万円と換気のできる建物タイプの喫煙所を建設するよりも大幅に安いもの。ところが2019年に新たに2台を設置しようとしたところ、近隣住民の反対で置き場が決まらないというトラブルになったことが報じられています。 とにかく「迷惑」な喫煙所は、外部と遮断するタイプにするのが主流。渋谷区のモヤイ像前の喫煙所も2020年に入って、工事が予定されています。 ここまでの分煙施策を、東京五輪を契機に来日する外国人はどう見るでしょう。おそらくたいていの国の人は「日本はなんて進んでいるのだ!」と驚くはずです。 「屋内は禁煙」でも屋外で平気に吸うヨーロッパ「屋内は禁煙」でも屋外で平気に吸うヨーロッパ というのも、ここまでハードな分煙を行っている国のほうが少ないからです。例えば、ヨーロッパでは多くの国が「屋内は禁煙」と法律で定められています。 ところが、それらの国では「屋内でなければいいのだろう」という意識。屋外の建物の前では大勢がたばこを吸っています。おまけに、吸い殻は路上にポイ捨て。それもふりかぶって車道めがけて投げ込むのが多い事例です。 屋外でたばこを吸う外国人のイメージ(画像:写真AC) アジアでも中国・台湾・韓国、どこでも路上喫煙はごくごく当たり前に見かけます。中国の都市部ではゴミ箱に灰皿がついているものも多いのですが、あまり利用はされていません。 分煙の強化による新たなビジネスチャンス、加えて海外からの印象がよいという点で、東京都の厳しい条例もプラスの面はあるのではないでしょうか。ただ、喫煙者としてはもう少し喫煙所が増えると助かります。
- ライフ