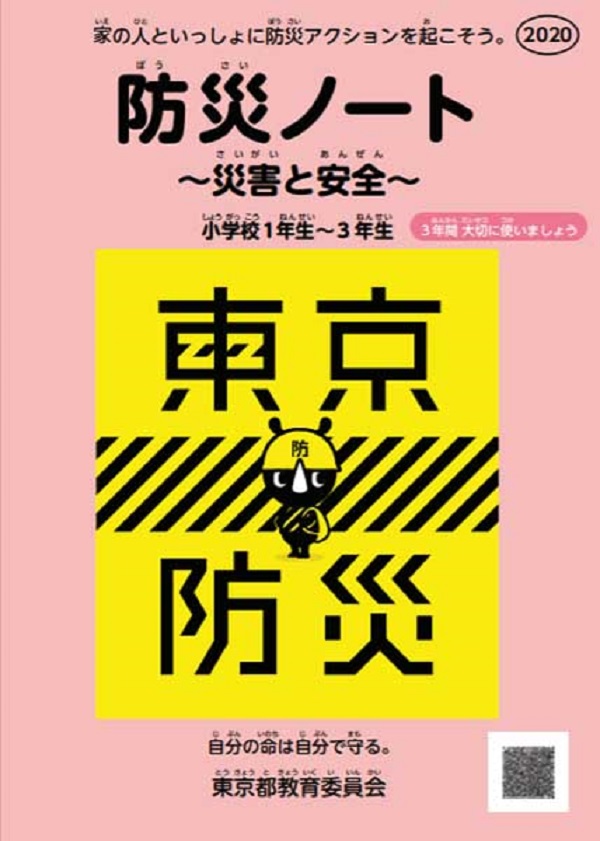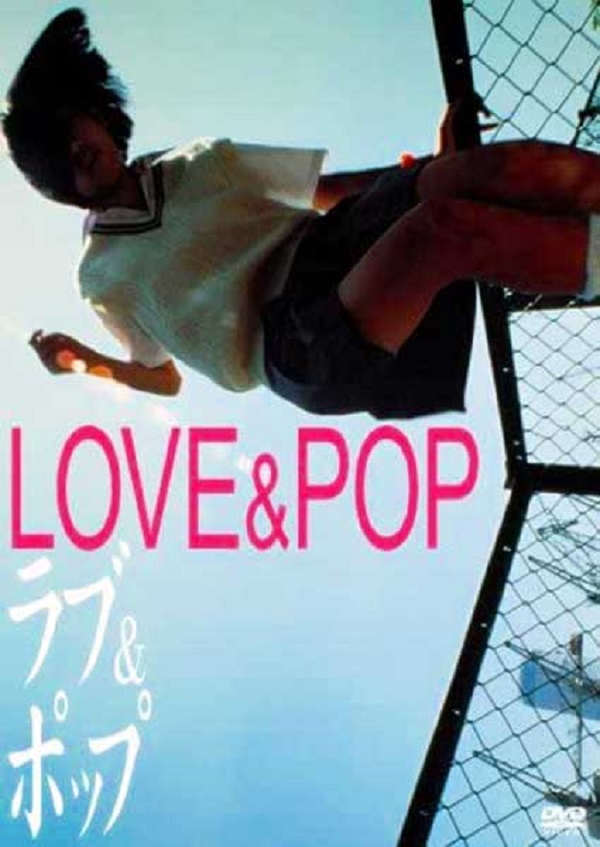私大文系改革の起爆剤となるか? 早稲田の看板「政経学部」、数学必須化の衝撃
私大文系最難関・政経学部のジレンマ 新年度がスタートし、早くも1か月が過ぎようとしています。 2021年度大学入試を振り返ると、大学入学共通テストの記述式と英語民間試験の導入見送り、コロナ禍と混乱の連続でした。 そうしたなか、早稲田大学(新宿区戸塚町)の政治経済学部も入試改革初年度を迎え、注目を集めました。改革のベースとなったのは、2018年5月に発表した「2021年度 政治経済学部 一般入試改革」という文書で、同学部は大学入学共通テストの「数学I・A」を必須科目にしたのです。 早稲田大学(画像:写真AC) 入試科目は、次のとおりです。 ●外国語(以下いずれかひとつを選択) ・英語(リスニングを含む) ・独語 ・仏語 ●国語 ●数学I・数学A ●選択科目(以下いずれかひとつを選択) ・地理歴史(世界史B、日本史B、地理B)から1科目 ・公民(現代社会、倫理、政治・経済、倫理、政治・経済)から1科目 ・数学(数学II・数学B) ・理科(物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎)から2科目、あるいは(物理、化学、生物、地学)から1科目 「2021年度 政治経済学部 一般入試改革」には、大学入学共通テストでの4科目受験を義務とし、大学独自の問題として、日本語と英語による長文読解が出題されると記されています。 2021年1月に実施された政治経済学部の入試問題は、問1がグラフや表を多数掲載した少子高齢化に関連する日本語の長文読解、問2が英語の長文読解、そして問3が問われたことを英語で書く自由英作文が出題されました。 また入試改革では一般入試での募集人員が450人から300人へと、人員削減も決定。合格のハードルがより高くなりました。 これらの改革からは、単に学力レベルの高い学生を求めるだけでなく、政治経済学部の抱える問題点が見え隠れします。 数学を学ぶ国立併願組と早稲田本命組数学を学ぶ国立併願組と早稲田本命組 2020年までの政治経済学部の一般入試は国語と英語の2教科が必須科目で、日本史B・世界史B・数学から1科目を選択する3科目方式でした(2017年度までは政治・経済を含めた4科目からの1科目選択制)。 早稲田大学の所在地(画像:(C)Google) 東京大学(文京区本郷)や一橋大学(国立市中)、京都大学(京都市)といった国立大学と併願する受験生がいる一方、「政治経済学部が本命」という受験生のなかには科目を絞って対策していた人もいます。 早稲田大学が公表しているデータを見ると、2016年度から2018年度入試までの政治経済学部志願者のうち、数学を選択したのは全体の38%から40%まででした。 数学以外の科目を選択したのは残りの約60%。このことからも「国立大学不合格」組と「政治経済学部が本命」組の間には、入学時点で数学力に埋められないほどの差があることがわかります。 その後、入試改革の発表後に行われた2019年度では、数学の志願者数は全体の44.3%、2020年度の入試は46.3%と増加しました。政治経済学部の「数学重視」の影響は改革直後から出ているのです。 私大文系が簡単に追随できないワケ私大文系が簡単に追随できないワケ 私大文系がバランスの良い学力を持つ学生を求めるなら、早稲田大学の政治経済学部のように数学を必須科目にすることは近道かもしれません。しかし、そう簡単に数学必須にかじを切ることはできません。 早稲田大学の一般入試の志願者数は約半世紀ぶりに10万人を切り、メディアでも大きく取り上げられました。入試改革初年度の政治経済学部を志願者する学生は2020年より2000人減り、学部間併願で他学部の志願者数にも影響が及びました。 コロナ禍の東京(画像:写真AC) コロナ禍や浪人生が少なかったことを考慮しても(2020年より約2万人が減少)、数学必須化によって受験生が増えないことがはっきりと証明されました。 少子化の影響で受験生の減少は避けられず、加えて志願者数が受験料収入に直結する私立大学では、思い切った入試改革を決断することは容易ではありません。経営を取るか、学生の質を取るか――のはざまにいるのが現状なのです。 長期的に見れば数学必須は吉となる長期的に見れば数学必須は吉となる その一方、ビッグデータや人工知能(AI)を駆使した商品開発や顧客管理などが企業で当たり前のように行われている昨今、数学で培われる論理的な思考力はこれまで以上に求められています。さらに、数値を正しく読み取る、数値を活用した資料作成技術も必須の社会人スキルとなっています。 ビッグデータ・AIのイメージ(画像:写真AC) また、コロナ禍を起因とする不景気に突入すれば、これまでのように理系学部の人気が高まります。そのためにも、受験での数学必須化は長期的に見れば、受験生にとっても大学側にとってもプラスに働きます。 入試内容の変更は実施年度の2~3年前に告知されるため、コロナ禍の影響で、早稲田大学政治経済学部のように私大文系でも数学必須の動きが出てきても何ら不思議ではありません。
- ライフ