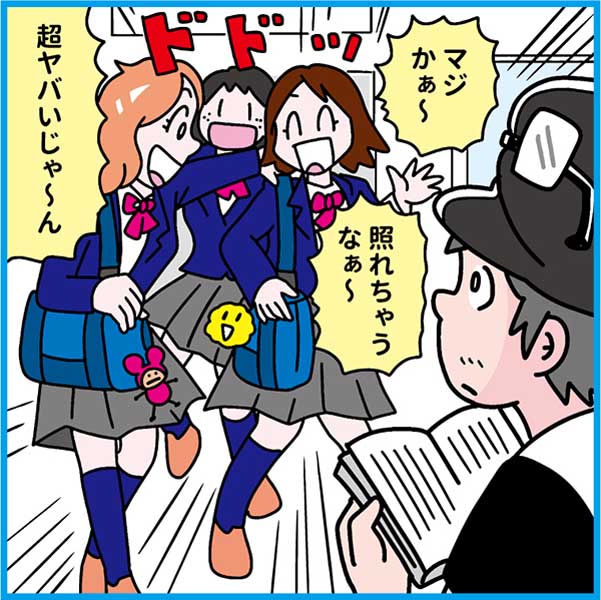金太郎飴の「本店」は東京にある
切っても切っても切っても金太郎の顔が出てくる「金太郎飴」。その「本店」が東京にあるのをご存知でしょうか。その名もずばり「金太郎飴本店」。明治のはじめに飴売りの露天商からはじまり、現在は6代目が営む老舗です。
そんな同店の公式サイトを見ていたところ、衝撃的な写真が目に飛び込んできました。それは巨大な金太郎の「顔」。おおよそ直径35cm。人間の顔よりも大きく、今までに見たことのない類の表情をしています。
 金太郎飴(左)と、わたしたちの手元に届く前の金太郎の「顔」(右)。この写真は、公式サイトに掲載のものではなく、取材当日に制作されていたもの(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
金太郎飴(左)と、わたしたちの手元に届く前の金太郎の「顔」(右)。この写真は、公式サイトに掲載のものではなく、取材当日に制作されていたもの(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
まさかこんなプロセスを経ていたとは……! この顔は、いったいどのようにして私たちが普段見ている姿へと変貌するのでしょうか。そもそも、どうやって組み上げているのでしょうか。作業現場を見せてもらいました。
金太郎飴の作業場は冷房NG
やってきたのは日比谷線三ノ輪駅。ここから歩いて1分ほどの場所に「金太郎飴本店」はあります。
 店先には金太郎飴のほか、さまざまな模様の飴が並ぶ(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
店先には金太郎飴のほか、さまざまな模様の飴が並ぶ(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
飴づくりが行われているのは店舗の2階です。階段をのぼり、まず感じたのは売り場との温度差。取材は夏真っ盛りの7月下旬でしたが、作業場には冷房が入っていないのです。
「金太郎飴は、飴がやわらかい状態でないと成形できません。冷気は飴の固まるスピードを早めてしまうため、冷房が使えないのです」(「金太郎飴本店」6代目渡邊さん)
通常7、8人で行うという金太郎飴の製造。機械も用いるものの、多くの作業は職人の手腕にかかっており、未経験から飴の成形が立派にできるようになるまでには、2~3年ほどかかるといいます。
飴に空気を含ませることで色や食感が変わる
工程は、飴を溶かすところからスタート。溶かした飴は90度前後とかなり高温です。
 水飴と砂糖を釜の中で煮詰める(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
水飴と砂糖を釜の中で煮詰める(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
その飴を冷ましつつ、丸めたあとは「精白機」でぐるぐると練り回し、空気を含ませます。すると飴の色が透明から白に変化。
 空気を含ませることで、透明色だった飴が白くなる(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
空気を含ませることで、透明色だった飴が白くなる(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
空気は色以外にも影響を及ぼします。金太郎飴が、ほかの飴に比べてサクッとしているように感じるのもこの工程によるもの。歯にくっつきにくくなるのも空気の影響といいます。
 白以外は食紅を混ぜたあと、精白機にかけて色をととのえる(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
白以外は食紅を混ぜたあと、精白機にかけて色をととのえる(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
直径35cmの大きな「顔」をゴロンゴロン
色付けのあとは、いよいよ直径約35cmの「顔」の組み立て。4、5人のチームで製作します。各自、担当パーツを組み上げていくのですが、その作業はあまりにも自然に始まりました。迷いなく、止まることなく、全員ほぼ無言でアイコンタクトをとっている様子もほとんどありません。
 職人さんたちは、黙々と作業をすすめている(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
職人さんたちは、黙々と作業をすすめている(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
事前に綿密に打ち合わせをしているのでしょうか。聞いてみたところ「なんとなく、事前打ち合わせのようなものが、あるにはあります。ですが完成予定図を見るだけでも、自分が何をつくればよいのかは、なんとなくわかります」と渡邊さん。
 各々、担当部位の部品をつくっていく(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
各々、担当部位の部品をつくっていく(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
 と、飴が貼り付いてしまった……!(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
と、飴が貼り付いてしまった……!(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
お互いがお互いの動きを常に把握しあっていることも見て取れました。たとえば、飴が貼り付いてしまい剥がそうとしている人いると、一瞬のうちに、ハサミを持って剥がすのを手伝い始める人が現れます。
「飴の成形は時間に限りがあります。固まる前に組み上げなくてはいけません。でも、早ければ早いほどいいというのでもなくて、周囲の状況を見ながら、その進捗に合わせていく必要があります」(渡邊さん)
さて、口、鼻、目、眉毛とパーツが組み上がっていき、金太郎の表情が見えてきました。
 徐々に組み上がっていく金太郎の顔。まつげは、白と茶色の飴が細かく交互に組まれている(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
徐々に組み上がっていく金太郎の顔。まつげは、白と茶色の飴が細かく交互に組まれている(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
 まつげは、つくりはじめの当初は生えていなかったそう。約50年前から生えているとのこと。本数は6本(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
まつげは、つくりはじめの当初は生えていなかったそう。約50年前から生えているとのこと。本数は6本(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
顔が組み上がると、今度はゴロンゴロン。大きな顔を左右に揺さぶります。形をまるく整えるためです。
 ゴロン(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
ゴロン(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
 ゴロン(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
ゴロン(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
飴の外枠部分になる白い飴をくるっと巻き、さらに端をぎゅっと絞ったのちに機械の中へ。飴の塊の重さは約40kg、持ち上げる時は2人がかりです。
 端をぎゅっと絞る(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
端をぎゅっと絞る(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
 飴を細く伸ばす機械の中に入れ込む(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
飴を細く伸ばす機械の中に入れ込む(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
怒涛の勢いで2cmの小顔に変身!
機械にかかった顔は、あっという間に伸ばされていきます。次から次へと出てくる細長の金太郎。機敏な機械の動きに、職人さんがしっかりと呼吸を合わせながら受け止めています。
 慣れた手つきで、細くなった飴を引き出していく(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
慣れた手つきで、細くなった飴を引き出していく(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
飴は作業台の長さに合わせて切断、冷えるまでコロコロと転がします。冷めたあとは一口サイズにカット。ここでようやく、普段わたしたちが見ている金太郎飴が登場します。
 伸ばした飴は、冷えるまでコロコロと台の上で転がす(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
伸ばした飴は、冷えるまでコロコロと台の上で転がす(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
 刻まれていく金太郎飴(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
刻まれていく金太郎飴(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
 出来立ての金太郎飴(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
出来立ての金太郎飴(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
組みあげた飴1体から生まれる金太郎飴はおおよそ7000個。さっきまであんなに大きかった金太郎は、1円玉くらいのサイズへと、あっという間に変貌しました。その手順を肉眼でずっと見ていたはずなのに、良い意味で現実感がなく、まるでトリックを読み解けない手品を見ていたかのような心持ちです。
「1本あたりに使える飴の量は決まっていて、増えることはありません。その中で、どう組み上げたら、最終的に直径2cmの飴の中に絵柄や文字が収まるかを計算し、そこから逆算しながら考えています。
経験を積むと、頭の中で少しずつその量の感覚ができてくるんですが、その感覚がつかめないと、丸くするための飴がなくなって形にならなくなったり、絵がすごく小さくて見にくいということになったりします」(渡邊さん)
 飴を切る機械もある(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
飴を切る機械もある(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
実は商標登録されている「金太郎飴」
「切っても切っても同じ顔が出てくる」とよくいわれる金太郎飴ですが、よく見ると、ひとつひとつに独自の表情があることに気がつきます。眉毛がつりあがり気味の金太郎、ほっぺがふっくらした金太郎――厳密にいえば、まったく同じ顔をした金太郎飴はふたつとありません。
そんな金太郎飴の顔を形成する技術は「組み飴」というもので、同店が組み飴を始めたのは2代目から。「他の店とは違う、特色のあるものを販売したい」と考えていた時に、関西のほうに組み飴の技術があると聞き、学びに向かったのが始まりです。金太郎をモチーフに選んだことには、「子どもが健やかに育つように」という意味が込められているそうです。
 よく見ると表情がちょっとずつ異なる(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
よく見ると表情がちょっとずつ異なる(2018年7月、高橋亜矢子撮影)
誕生から100年以上の時が経ち、現在「金太郎飴」は商標登録されています。言葉が一般名称のように使用されてしまい、登録商標としての認識が広がっていかず、苦労している点も多いとのこと。
「(商標として持っていないと)何かあった時、強く言えないところがあるので。認知を広めるためには、機会があるごとに言っていかないと、と思っています」(渡邊さん)
存在が全国区となったがゆえに新たな悩みも生じているようですが、本店の職人さんたちの手から生まれる「同じ顔でありながらも少しずつ異なる」金太郎たちが、これからも作られ続けていくことを願ってやみません。
●金太郎飴本店
・住所:東京都台東区根岸5-16-12
・交通アクセス:日比谷線「三ノ輪駅」2番出口から徒歩1分
・開館時間:09:00~17:30
・定休日:土曜日(不定休)、日祝日
※記事公開時点の情報です。