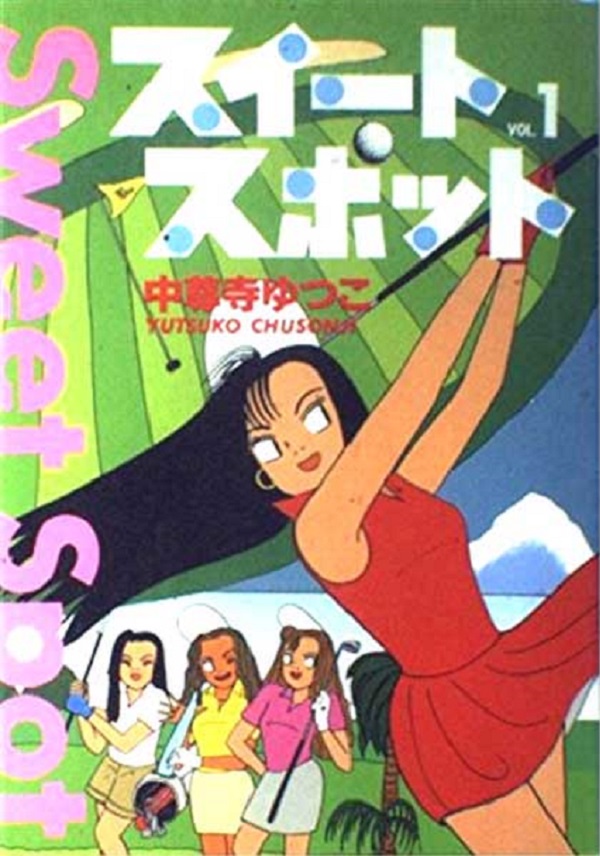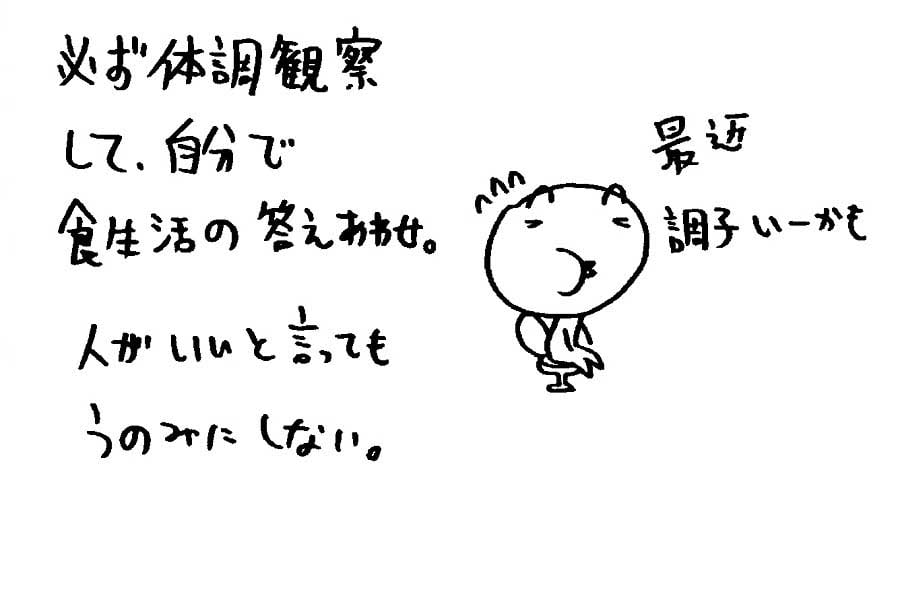『シン・エヴァ』公開記念 綾波とアスカ、彼女にするならどっち? 都内デートコースを含めて考える
3月8日に公開された完結作 映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』がついに完結しました。公開初日(3月8日)に劇場で鑑賞しようと、チケットの販売開始日には深夜の争奪戦がぼっ発し、話題となりました。 初日は月曜日だったものの、観客動員数は50万人を突破。初日の興行収入も8億277万4200円と、エヴァンゲリオンならではのスタートを切っています。緊急事態宣言下にもかかわらず、「熱いファンと一緒に鑑賞したい」「最も熱いファンが集まるのは東京だ」と、わざわざ上京する人もいたほどです。 新宿の劇場で初回上映を見た人からは、こんな話も聞こえてきました。 「今回が最後なんですから、きっと心の炎が治まらずに前日から劇場前に待機している仲間がいるだろうと思って……。近くのホテルを予約して深夜に様子を見に行ったのですが、誰もいませんでしたね。前回まではゼーレのアレとか、にわかコスプレの人がいて、学園祭の前夜祭のような雰囲気がありましたが……。これほど新型コロナが憎いと思ったことはありませんよ」 エヴァンゲリオンについては、世界中のファンがこれまで作品の考察に多くの言葉を費やしてきました。気がつけば四半世紀が経ったというわけで、これからも人生の重要なエピソードとして語り続けられるでしょう。 そんなエヴァンゲリオンですが、作品の完結にあたって、どうしても決着をつけなければならない問題が残されています。それが「綾波か、アスカか」問題です。 「綾波か、アスカか」問題とは何か「綾波か、アスカか」問題とは何か テレビ放送当時、作品の謎が深まるとともに、友人と集まり、その内容を考察し合う機会が増えました。もちろん真面目に考察していたのですが、それより重要だったのが、 「綾波とアスカ、付き合うならどちらか」 という話題でした。これを読んで、「そうそう」「あったあった」と思わず独り言をつぶやいてしまった人は少なくないでしょう。 『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』劇場用ポスター(画像:錦織敦史、カラー、Project Eva.、EVA製作委員会) 現代では、アニメヒロインに対する愛情を「俺の嫁」と表現する人もいますが、当時はそんな言葉はありませんでした。 「萌(も)え」という言葉も、1995年から1997年まで『週刊少年ジャンプ』(集英社)に連載されていた『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』を通じて、徐々に広まりつつありましたが、一般的ではありませんでした。 今思えば、極めて稚拙な方法でしか愛情を表現できていなかったと思います。しかし当時のファンは、まるで一生添い遂げる相手を選ぶかのごとく、「綾波か、アスカか」を語り合っていたのです。 綾波とアスカの間で揺れる理由 今思えば、少し上の世代の人たちが『うる星やつら』のラムちゃんにゾッコンだったことに影響されているのかもしれません。還暦近くなった今でも、ラムちゃんを愛し続ける一途な人を筆者は知っています。 ただ、勢力が比較的小さかった「ミサトさん」派や「マヤ」派を選ぶ人に比べて、綾波かアスカかで悩む者は、心が結構ぶれていたような気がします。 自省を含めて話しますと、包帯に巻かれて登場し、その後も感情表現に乏しくミステリアスな綾波は、混沌(こんとん)とした90年代に青春をおくった筆者にとって魅力的でした。 綾波の存在は、 「怪しげなもの = 格好良くておしゃれ」 と思われていた時代にマッチしていたのではないでしょうか。 ただ「綾波、綾波ぃ~」という感情もアスカの登場によってぶれ出しました。強気で感情豊かなアスカは気弱な若者にとって、かえって守られているような魅力があり、それでいて、後半になるにつれ出てくる闇の部分が深い魅力でした。 暗闇で光る怪しい花(画像:写真AC) この問題は、テレビ放送が伝説的な最終回を迎え、その後の劇場版が完結しても決着がつきませんでいた。そして始まった新劇場版は、 「アスカならば、惣流か式波か」 に始まり、マリ派やサクラ派などの新勢力も生みつつ、おのおのの心の中で混沌を深めていきました。そして「完結するまでには決着をつけよう」と、長らく結論を先送りしてきた人生でもあったわけです。 しかし四半世紀が経ち、今や誰もがアニメヒロインへの愛情、それも「ガチ恋」を隠さない時代になっています。 綾波とのデート、どこへ行くべきか綾波とのデート、どこへ行くべきか さて、「綾波か、アスカか」どちらを選ぶにしても、せっかく付き合うならデートについて考えてみるのも面白いでしょう。ということで、まずは綾波から。 綾波と最初に一緒に行きたいのは、すみだ水族館(墨田区押上)です。くらげの水槽を長い間眺めているうちに、お互いの人生について自然と語り合い、次第に距離は近づいていくことでしょう。 その後、東京スカイツリーの展望台から夜景を――としたいところですが、ここはあえて避けます。それより周辺の下町の路地を散歩するほうがよいでしょう。夕暮れとともに歩く人が少なくなりますからね。 そうするうちに、口数の少ない綾波は少しずつ語り始めてくれるはず。この日は駅で別れて、翌週は東京都写真美術館(目黒区三田)に行くことを約束しましょう。 目黒区三田にある東京都写真美術館(画像:(C)Google) このときは展示作品を見て、写真家の心情を想像しながら語らうことで距離を縮められます。このデートが終われば、ふたりはもうすっかり恋人同士です。 アスカとのデート、どこへ行くべきか 次に、アスカとのデートはどうでしょうか。 まず最初のデートですが、はっきり言って、上野動物園(台東区上野公園)以外あり得ません。待ち合わせは上野公園口改札が動物園に近くて便利ですが、ここは迷わずジャイアントパンダ像を選びましょう。 台東区上野公園にある上野動物園(画像:写真AC) 動物園に入り、目玉のパンダは後回しにして、ゾウやライオン、トラといった定番を順に観察していきましょう。普段から気が張っているアスカですから、自然体で生きる動物たちの姿に肩の力が次第に抜けていくに違いありません。パンダを見る頃にはすっかり素の姿を見せてくれるでしょう。 2回目のデートは、休日のお台場がお勧めです。にぎやかな観光をひと通り見た後、お台場海浜公園(港区台場)の砂浜で人生を語らううちに、ふたりの心はひとつになるのです。 人生経験を積んだ私たちは、恋愛が成就しても、その後の幸せは一辺倒でないことを知っています。今回、人生をエヴァンゲリオンと歩んできた友人たちに、デートについて尋ねましたが 「一緒に田植えでもして、のんびり生きたい」 「恋愛よりも老後だよ」 などという意見が多数でした。 明確に「綾波か、アスカか」を選べた人は皆無です。ああ、終わらない考察の果てに私たちはすっかりと丸くなってしまったのか――それでもヒリヒリと焼け付くような恋愛を求める筆者は、どちらかを選ばずにはいられません。 でも選ぶのが怖くて、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』を見ることはできません。ネタバレ禁止ということで、いまだ会員制交流サイト(SNS)などでは、完結作の評価はあまり出ていません。 あなたはもう見ましたか? どんな感想を持ちましたか? そして「綾波か、アスカか」の結論はでましたか? よかったら教えてください。
- ライフ