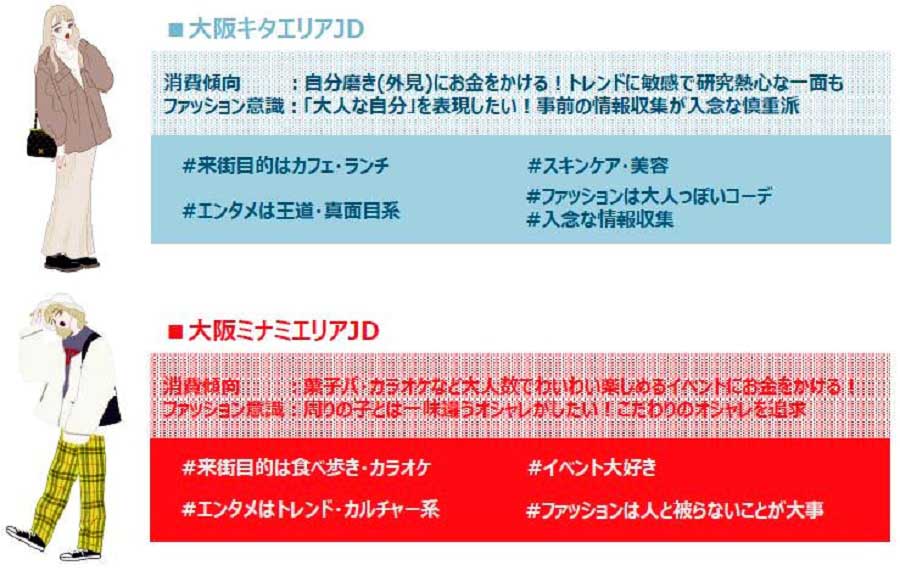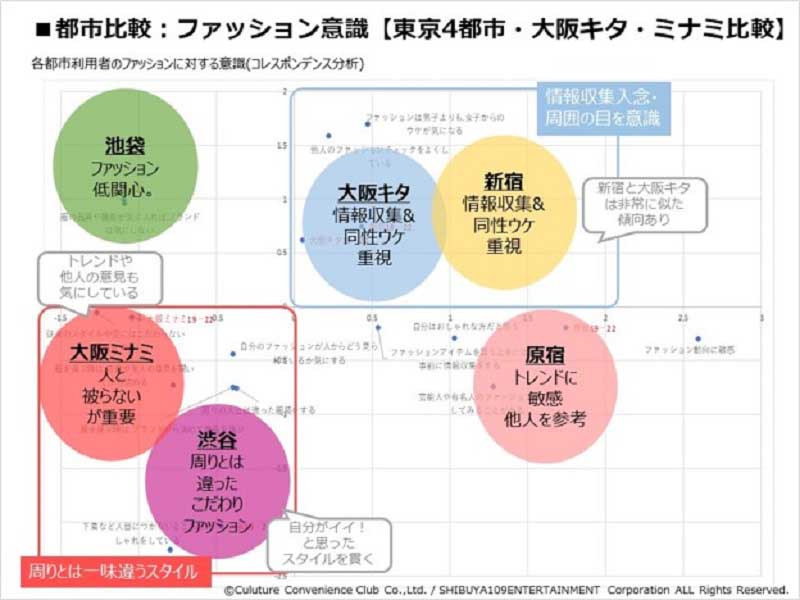子どもの病気「手足口病」に大人がかかってしまった悲劇を描く漫画「熱、発疹……いつ治るんだよ~!」
東京在住15年のイラストレーター・どらミーさんは、日々の生活が生みだす「ちょっとした驚きや喜び」を描いています。今回は、「大人もかかる手足口病」についての話です。「いつ治るんだよ~ 仕事も休めないのに!」 どらミーさん(ペンネーム)は東京在住15年、ビジネス雑誌のマンガなどを手掛けているイラストレーターです。現在は「比較的都心」に住んでいますが、かつては都内のさまざまな街を移り住んでいたといいます。そんなどらミーさんが描くアーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「大人もかかる手足口病(てあしくちびょう)」です。 どらミーさん自身の体験を描いた漫画のカット(どらミーさん制作)――どらミーさん、今回の作品を作った背景を教えてください。 手足口病は6月から8月にかけて、主に子どもの間で流行る病気なのですが、まさに現在が流行期だと思って描きました。 ――手足口病の存在は、以前から知っていたのでしょうか。 以前、私の甥っ子がかかっていたので少し知っていたのですが、手足口病は子どもの病気で、大人の私には関係ないと思っていました。作品は、私が子どもを産む前の話ですので、なおさら馴染みがありませんでした。 ――手足口病と診断されたときの驚きを教えてください。 病院に行く前、高熱にうなされながら、スマートフォンでいろいろと調べていたところ、手足口病の病名を見つけ、「もしや……」と。そうでないことを期待しながら病院に行ったら、手足口病と。やっぱり「ガーン……」という気持ちでしたよ。甥っ子がかかったときに「爪が剥がれた」と聞いていたので、重症化しないことを願うばかりでした。 ――結果、「自宅療養」を勧められました。 「この発疹はいつ治るんだよ~ 仕事も休めないのに」と心の中で泣いていましたよ! ――そして、会社に電話。上司の口調が今でも記憶に残っているそうですね。 「てあし? くち? え? なにそれ?」といった感じで、そんな病気あるのかとびっくりしていました(笑)。 ――発症してから、ご自宅でどのように過ごされていたのでしょうか。 発症翌日には熱が38度台くらいに落ち着いたのですが、2~3日間は発疹のムズムズと全身の倦怠感が辛かったですね。発疹もなかなか消えず、出社もできずで、1週間以上自宅で仕事をしていたんですよ。薬の処方もありませんでしたし。 症状がひどかったとき、家族が出張などで家におらず、自宅にひとりっきりだったので、誰にもうつさずに済んだのは不幸中の幸いでした。帰ってくる家族にうつさないよう、家の中をフラフラになって除菌していました。 ――それは大変な思いをされました。 元気だったのに突然倦怠感に襲われ、熱がグングン上がっていった「あの瞬間」が今でも忘れられません。「ウイルスに感染するってこういうことか」と思いました。 ――この経験で学んだことを教えてください。 子どもの通う園で手足口病が流行りだしたら、私もマスクを着用し、子どもと一緒に手洗いやうがいを念入りに行っています。 ――漫画の読者にひと言お願いします。 私が病院で診察を受けたとき、「疲れて免疫力が低下していると、大人でもかかることがある」と言われました。確かに当時は仕事がとても忙しいく、加えて夏バテで疲れていました。皆さんも「大人もうつる危険性がある」と思って、対策を行うことをお勧めします。
- 未分類