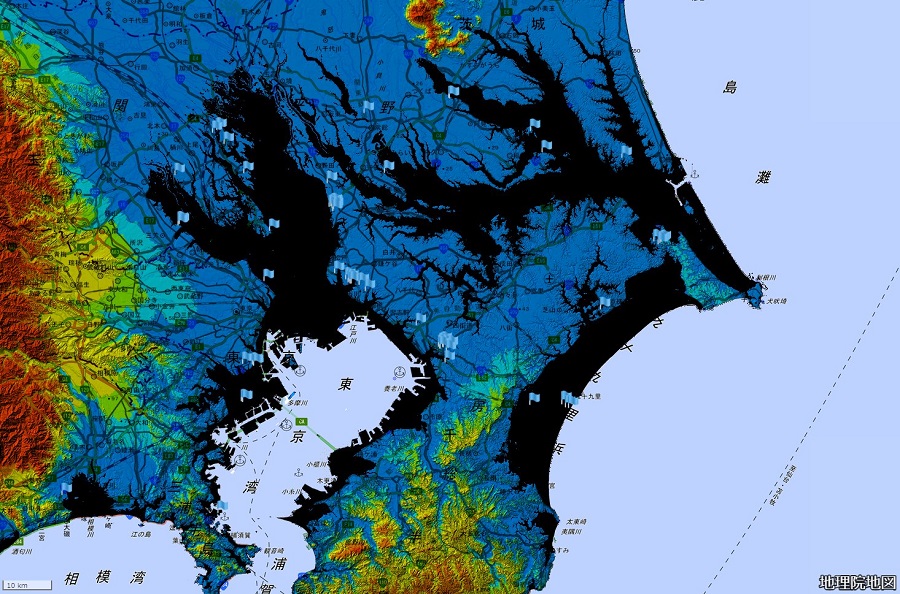90年代の「たまごっち」ブーム 原宿の大行列に並んだ元総理大臣って誰?
日本中の話題をさらったおもちゃ「テトリンよりも売れているらしいぞ」 1996(平成8)年11月に発売された、ひとつのおもちゃが、にわかに注目を集めました。バンダイ(台東区駒形)から発売された「たまごっち」です。 正式な発売は11月23日。その少し前から渋谷など雑貨店やレコード店でのテスト販売が行われていました。そうしたところテスト販売を行った5店舗のうち、4店舗で即日完売という評価を獲得したのです。 そうした盛り上がりを受けての正式発売。その日から、たまごっちはメディアと日本全国の話題をさらうことになります。 まず飛び付いたのは女子高生たち 最初に飛びついたのは、当時「コギャル」という言葉で呼ばれることが多かった女子高生たち。彼女たちの通学グッズの定番として、たまごっちは大人気になったのです。 それまで、同様の携帯ゲームとしてゲームテック(福岡市)から発売されていた「テトリン」が女子高生の間では人気でした。 これは、モノクロ画面でテトリスなどをプレーできる超小型のゲーム機です。これに対して、たまごっちはデジタルなペット飼育。 液晶画面の中の謎の生物・たまごっちに、餌を与えたり、トイレの世話をしたりしながら少しずつ成長させていきます。 芸能人も次々ゲット、徹夜行列も芸能人も次々ゲット、徹夜行列も 餌が欲しかったり、遊んで欲しかったりするときには、ピーピー鳴いて飼い主を呼びつけます。はたまた、トイレの世話をしないと病気になってしまうことも……。 バンダイが狙っていた主なターゲットは当初から女子高生でした。デザインも渋谷や女子高生に街頭アンケートを実施して決めたといます。 覚えていますか? 1996年11月に発売された初代「たまごっち」(画像:バンダイ) 同年12月初頭に「女子高生に大人気」と盛んにメディアに取り上げられると、芸能人の話題も、やっぱりたまごっち関連で持ち切りに。 「ユーミンのラジオ生放送中に生まれちゃったとか、安室チャンがダウンタウンにプレゼントしたとか、ともさかりえチャンやシャ乱Qのつんく、リサ・ステッグマイヤーサンも育てているらしいとか……。こうした話を聞くたびに「『たまごっち』欲しい~っ!」となるわけです」(『FLASH』1997年1月28日号) この「『たまごっち』欲しい~っ!」となった人たちは、とにかくお店に殺到します。 徹夜で行列なんて当たり前。バンダイにはどこで売っているのかと、問い合わせの電話が毎日かかってきます。 入電の数は資料によってまちまちなのですが、発案者である横井昭裕さんの『たまごっち誕生記 超ヒット商品はこうしてつくられた!』(ベストセラーズ。1997年)では1日に5000件。前述の『FLASH』では「冬休み期間中には毎日200本もの電話があり」と記されています。 便乗や詐欺まで現れて社会現象化便乗や詐欺まで現れて社会現象化 とにかく、当時たまごっちは持っているだけでステータス。高額で取引されたり、詐欺を働く人が出たりと社会現象になっていきます。 その結果、発案者の横井さん(彼は元バンダイの社員で当時、新会社ウィズを立ち上げていました。同社はのちに『デジモンアドベンチャー』のヒットで知られています)と開発者の真板亜紀さんは「数百万人分の労働時間を仮想ペットの育成時間に費やさせた」ことに対して1997(平成9)年にイグノーベル賞を受賞しています。 バンダイは増産に励んでいましたが、ブームに対して生産は追いつきませんでした。社員でも手に入らないのですが、社員には家族や親せきから「どうにかならないのか」と電話が殺到する始末です。 発売15周年に開かれたイベントにも大勢のファンが詰めかけた(画像:バンダイ) 中には、バンダイの本社に売ってくれと尋ねて来る人もいます。ニッポン放送がラジオ番組で、たまごっちのプレゼントを告知したところ応募数は15万通にも及びます。 そんな人気に乗じて、新たなビジネスも生まれます。小売店では、入手したたまごっちをネタにして「お買い上げ○○円でたまごっちが当たる『抽選券』を進呈」なんてキャンペーンを実施するところもありました。果たして売り上げに影響があったかは……謎です。 ちなみに地方でのことですが、岐阜県の岐阜信用金庫では給与振込口座をつくった新社会人に抽選で200人に、たまごっちをプレゼントなんて企画を実施したそうです。 91~93年まで総理だったあの人も91~93年まで総理だったあの人も こうして人気がどんどん加熱したたまごっちですが、人気に火がついて間もない1997(平成9)年1月頃に、ひとつのウワサが流れました。宮沢喜一元総理大臣が原宿のキディランドに買いに来たというのです。 この真偽のわからぬウワサをもとに取材をしているのが『週刊宝石』1997年1月30日号です。 1991年から93年までの644日間、第78代内閣総理大臣を務めた故・宮沢喜一氏(画像:内閣官房内閣広報室) 記事によれば取材班は、宮沢元総理の私邸前で帰宅を待ち構えることに。取材意図が意図だけに警備している警察官にも苦笑されるほどです。 ところがバカバカしい取材意図に断られるかと思いきや、宮沢元総理は自ら取材に応じてくれたのです。 なんでも、孫娘からクリスマスプレゼントにたまごっちをねだられた宮沢元総理。孫娘が「朝の8時に行かなきゃだめだ」というのを、そんなバカなと思い10時にいったら大行列で買えなかったそう。その後、なんとか入手できたそうで、うれしかったのかこんなコメントを。 「孫娘2人いるからね、小学生と中学生。いやあ喜んでね。これでおじいちゃんの面目が立ったんだ。ウン、よかったな。」(同誌) 果ては都市伝説までささやかれた果ては都市伝説までささやかれた たまごっちブームの最中には、経済面でも大きな動きがありました。1997(平成9)年1月23日にセガとバンダイが合併することを発表したからです。 プリクラが大ブームのセガとバンダイの合併ですから、経済誌では「プリクラとたまごっちが合体する」と大注目されたのです。 従来とは違うスタイルのゲーム機として人気を集めた、たまごっち。まだ多くの人には「未知」のゲーム機という側面もあったからでしょうか。実は都市伝説の宝庫でもありました。 99歳まで育てると願い事がかなう。飼育の手を抜くとかわいくないキャラになるが、それを葬り去ると便通が良くなる……なんて都市伝説が、次々と生まれました。 中には「たまごっちという生き物は実在する」なんて都市伝説もあったそうです。 こんな生き物がホントにいたら、ちょっと怖いかもしれないですね……
- ライフ