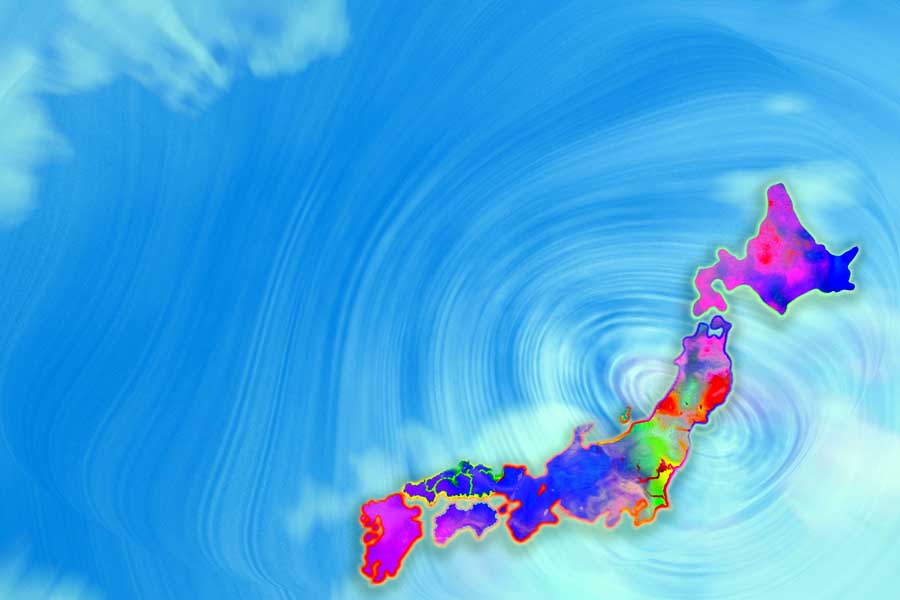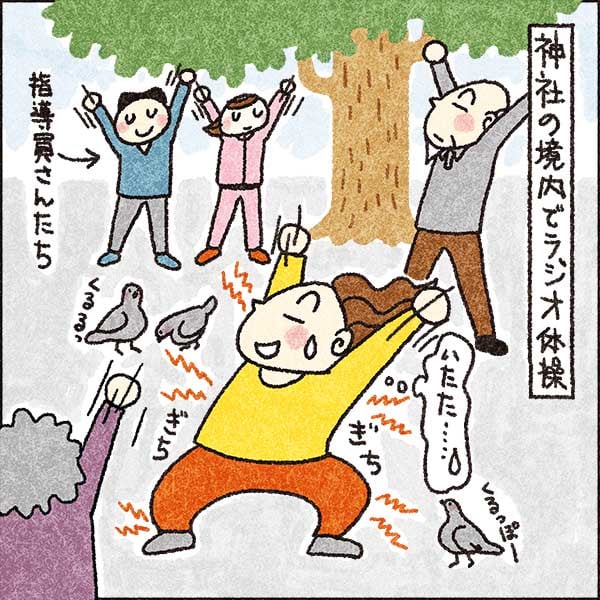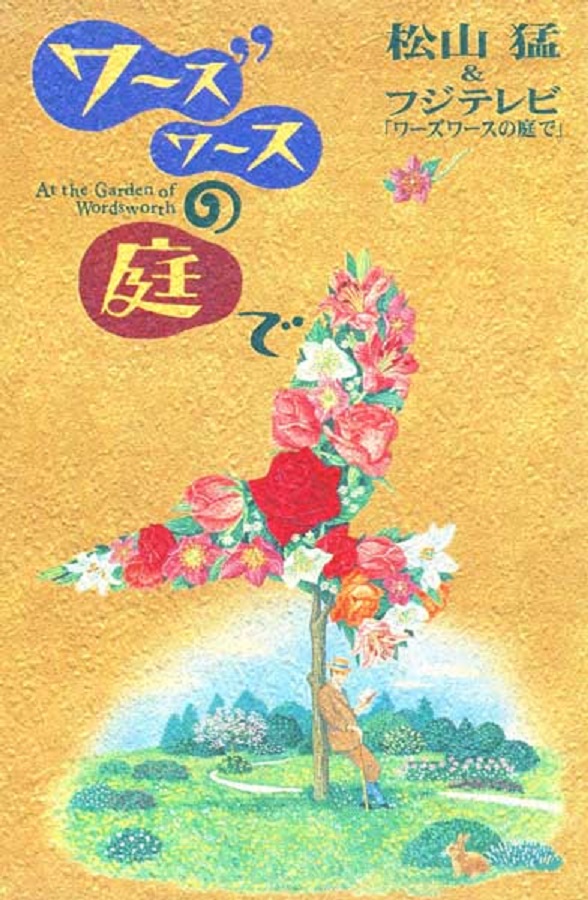キーワードは「おやつ以上、食事未満」 コロナ禍で注目の軽食ジャンル「0.7食」とは何か
コロナ禍で食スタイルに変化が起きています。鍵を握るのが「おやつ以上食事未満」の軽食です。ホットペッパーグルメ外食総研・上席研究員の有木真理さんが解説します。「コロナ太り」は本当に起きたのか 新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るい始めてから、1年半が過ぎようとしています。長引くコロナ禍で「3密」回避、非接触が当たり前になり、人々のライフスタイルは変化を続けています。 外出自粛や外食制限だけではなく、仕事でもリモートワークが中心となったため、通勤も含めた日常的な活動量は変化、消費カロリーは減少しました。その結果ともいえる「コロナ太り」というキーワードも世間をにぎわせました。 コロナ太りについては、2021年3月の記事「在宅勤務の宿命? 話題の「コロナ太り」で何割の人がぽっちゃり化したのか?」で詳しく書きました。 コロナ太りのイメージ(画像:写真AC) その際に出した、筆者(有木真理)が上席研究員を務めるホットペッパーグルメ外食総研の調査データによると、緊急事態宣言が発令された2020年4月以降、体形に変化があった人は ・女性:34.6% ・男性:27.2% となりました。 しかしその中身をひもとくと、コロナ太りといわれるわりには、太った消費者と痩せた人の差があまり大きくないという結果になったのです。 コロナ禍の食生活変化の実態 そこで、ホットペッパーグルメ外食総研では「コロナ禍における食生活の変化」について、さらに調査を進めました。 ・1日の食事回数 ・食事1回当たりの量 の増減を調査したところ、なんらかの変化があった人は50%となりました。 全国20代から50代までの男女1107人を対象に行ったアンケート調査の結果(画像:リクルート) また、変化のパターンで最も大きな割合を占めたのは、食事回数・量ともに「減った」15.9%でした。これは前述したように、ライフスタイルの変化、働き方の変化……つまり在宅勤務やステイホームの影響が大きいといえます。 筆者は昨今のマーケットを見ていて、軽食ニーズが食事トレンドとして高まっており、軽食そのもののバラエティーが増えていると感じていました。そのため、消費者の心理を探るべく一定の仮説を立て、調査を行い、 「朝昼晩の食事量が多いと感じ、3食のうち1回はおやつ以上食事未満の軽食(目安として0.7食程度)にしたいと感じる・そのようにしているか?」 という質問を投げました。 この問いに対して、「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」と答えた人が約16%存在することがわかりました。この結果からも、軽食ブームの兆しが捉えられることがわかります。 トレンドの兆し「0.7食」とはトレンドの兆し「0.7食」とは さてここからは、そんな軽食ブームについて論述していきます。 コンビニなどで気軽に買えるサンドイッチや肉まん、ハンバーガーに代表されるファストフード(軽食)はこれまでも根強い人気がありましたが、コロナ禍においてブームになっています。 これらの定番だけではなく、人気が集まっているのは「おやつ以上食事未満」。ホットペッパーグルメ外食総研では、このカテゴリーを新軽食ジャンル「0.7食」とし、さらに消費者動向を探りました。 ハンバーガーのイメージ(画像:写真AC) そもそも「1日3食」という食習慣はいつから存在するのでしょうか。 諸説ありますが、日本人はもともと1日2食、朝と昼を兼ねた食事をとり、夕食は明るいうちに済ませる習慣がありました。しかし菜種油の普及で、あんどんなどに代表される明かりが普及。夜遅く活動する習慣がついたとされています。 その結果、1日の活動時間が延び、日中におなかが減るため、朝食、昼食、夕食という3食になったとも。また「腹が減っては戦ができぬ」という言葉があるように、人々の活動において「食事をしっかりとればパフォーマンスが上がる」と考えられていたともいえます。 ほかにもさまざまな食文化の歴史はありますが、文明の進化やライフスタイルの変化は「食生活の変化」に大きな影響をもたらしています。 コロナ禍では朝食後、自宅で仕事を開始。通勤などの移動は大幅に減ったため、おなかがあまりすかず、夕食までの間に昼食ではなく「おやつ以上食事未満」、つまり0.7食をとる傾向が増えているのではないでしょうか。 0.7食の人気メニューとは0.7食の人気メニューとは さて、新軽食ジャンルである0.7食では一体どのようなメニューが人気なのでしょうか。 同様に「今後食べてみたいおやつ以上食事未満の軽食」について調査をしたところ、 ・1位:フルーツ大福 ・2位:マリトッツォ ・3位:フルーツサンド と、スイーツのなかでも、少し重めの食感でおなかにたまるものが上位にランキングしました。 断面がほぼフルーツといえっても過言ではない見た目の「フルーツ大福」、ブリオッシュ生地のコロンと丸いフォルムのパンにたっぷりと生クリームの入ったイタリアンスイーツ「マリトッツォ」、季節によってさまざまな種類が登場する「フルーツサンド」は、まさに「おやつ以上食事未満」の軽食といえます。 全国20代から50代までの男女1107人を対象に行ったアンケート調査の結果(画像:リクルート) そのほかにもぷるぷる食感の台湾カステラなど、SNSを中心に話題のスイーツが上位を独占し、トレンドを語る上でも、SNS映えは相変わらず切り離せないことが伺えます。 このようなアイテムは専門店だけでなく、成城石井やカルディコーヒーファームなどでも一部取り扱いがあり、気軽に手に入ることもブームになった要因のひとつでしょう。 都内で「0.7食」を楽しめるお店 東京都内でフルーツ大福を気軽にテイクアウトできる店といえば「覚王山フルーツ大福 弁才天」(中央区銀座など)が挙げられます。同店は市場から直送される旬のフルーツを丸ごと1個使い、甘さ控えめの白あんと一緒に求肥(ぎゅうひ)で包んだ至極のスイーツを堪能できます。 中央区銀座にある「覚王山フルーツ大福 弁才天 銀座店」(画像:(C)Google) また、マリトッツォはイタリアン食材やデリを気軽に楽しめる「イータリー」(渋谷区神宮前など)が有名です。最近では、ピスタチオフレーバーやティラミスフレーバーなど期間限定で多様な展開も。 また調査では「コロナ禍において、コーヒーやお茶を飲む頻度が増えたか?」と聞くと、36.6%の人が増えたと答えています。このことからも、昼食を0.7食に置き換えて、コーヒー・紅茶・お茶とともに楽しむ人が増えていると考えられます。 今回紹介した0.7食のように、人々の食生活はコロナ禍で変化し続けており、そのニーズに応えるべくさまざまなアイテムの開発が進んでいます。外食、中食、内食ともに楽しみ方のバラエティーが増えることは、筆者もいち消費者としてうれしい限りです。それ以上に、おいしい料理とドリンクを囲み、外食を楽しむ人々の笑顔が見られる日を願ってやみません。
- ライフ