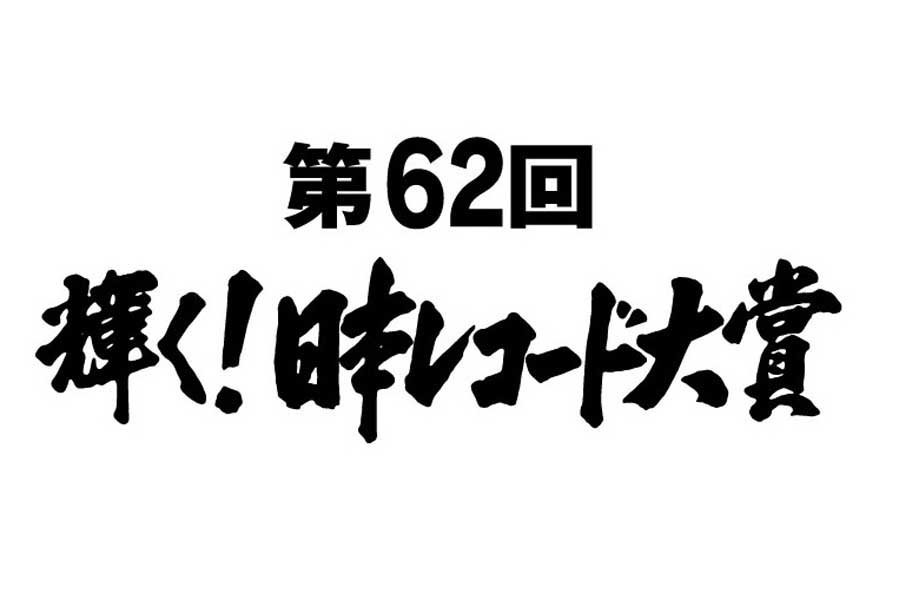全盛期は月2回開催も「レコ大」以外の音楽賞が消えたワケ
「レコ大」は1959年スタート「第62回輝く!日本レコード大賞」が12月30日(水)、TBS系で放送されます。今回は瑛人「香水」、乃木坂46「世界中の隣人よ」、LiSA「炎」など10作品の中から大賞が、Novelbrightや豆柴の大群など4組の中から最優秀新人賞が選ばれることになっています。 「第62回輝く!日本レコード大賞」のロゴマーク(画像:TBSラジオ) この「日本レコード大賞」は日本作曲家協会(港区六本木)が主催する音楽の賞で、第1回の授賞式は文京公会堂(現・文京シビックホール)というホールで1959(昭和34)年に行われています。 ある年代以上の人ならご記憶だと思いますが、日本には過去にこれと似たような音楽賞、歌謡賞の類いが多数存在していました。なかには、新宿音楽祭、銀座音楽祭、メガロポリス歌謡祭……といった、そのタイトルだけでは概要がつかみかねるものがあります。それらは、どんなもので、どのように生まれ、なぜ消えてしまったのでしょう? 「新宿音楽祭」とは何か 歌謡曲、ポピュラー音楽を対象とした音楽賞が増え始めたのは1968年のことです。 先陣を切ったのが、「新宿祭」というイベントの一貫として始まった「新宿音楽祭」です。これは新人歌手のみが対象という独自性があり、開催時期は10月頃。新宿区若葉に局舎があった文化放送が毎回、ラジオ放送を行っていました。 新宿区若葉にある「文化放送発祥の地」の碑(画像:(C)Google) また、年末には有線音楽放送に関連したふたつの賞が同時に始まっています。 ひとつは、大阪有線放送社(現・USEN)系の「全日本有線放送大賞(当初は「夜のレコード大賞」)」。もうひとつは、現在は東京杉並区に本社のある日本音楽放送(現・キャンシステム株式会社)を中心に生まれた「日本有線大賞」です。 このふたつの賞は、有線放送の特性上、演歌系が強いという傾向がありました。 「レコ大」に対抗する賞を創設も……「レコ大」に対抗する賞を創設も…… テレビ・ラジオともTBSが独占放送する「日本レコード大賞」に対抗し、TBS以外のテレビ・ラジオの民放各局が手を組んで1970(昭和45)年に創設したのが「日本歌謡大賞」です。 時期は毎年11月で、当初はホテルで授賞式を行っていましたが、1973年の第4回から日本武道館(千代田区北の丸公園)に進出しています。 千代田区北の丸公園にある日本武道館(画像:写真AC) 日本歌謡大賞は大人気コンテンツでしたが、テレビ放送は年ごとの各局持ち回り制だったため、どの局も“放送のチャンスは4年に1度だけ”というもどかしさを抱えていました。そこで、それぞれの局が日本歌謡大賞とは別途に独自の音楽賞を作る流れが生まれます。 先鞭をつけたフジテレビ まず、フジテレビが1974年に「FNS歌謡祭」を始めます。現在も同名の音楽番組が年末に放送されますが、この番組はもともと、グランプリや最優秀新人賞などを決めるイベントだったのです。 続いて、1975年に日本テレビが「日本テレビ音楽祭」を、NETテレビ(現・テレビ朝日)が「全日本歌謡音楽祭」を始めます。日本テレビ音楽祭は他と差異化を図るために8月に開催。10月放送の全日本歌謡音楽祭は、視聴者の投票によって受賞者を決めるという方式でした。 70年代にはほかに、九州朝日放送の「KBC新人歌謡音楽祭」、朝日放送の「ABC歌謡新人グランプリ」など地方局による新人対象の音楽賞も生まれていきます。 第1回の「日本レコード大賞」が行われた文京公会堂の後継施設・文京シビックホール(画像:(C)Google) さらに、1982年にテレビ東京が「メガロポリス歌謡祭」を立ち上げます。これは「日本テレビ音楽祭」より早い7月の放送が主で、演歌とポップス、それぞれの大賞が設定されました。 また時期は前後しますが、AMラジオキー局にも同じような現象がありました。 有楽町に局舎があったニッポン放送が1973年に「銀座音楽祭」を、横浜をホームとするラジオ関東(現・アール・エフ・ラジオ日本)が1974年に「横浜音楽祭」を始めています。このふたつは、文化放送系の「新宿音楽祭」同様に、新人歌手が対象でした。 平均月1度以上で開催平均月1度以上で開催 このように最盛期には「日本レコード大賞」以外に、新人限定のものが五つ、総合的なものが七つもありました。 つまり、夏から年末まで平均で月に1度以上、新人に至っては月に2度以上のペースで、類似した賞の発表の場があった訳です。そして、受賞者はその都度、驚いたり、喜びを表現したり、涙を流したり……というリアクションが求められました。 「第62回輝く!日本レコード大賞」の大賞にノミネートされたLiSA「炎」(画像:SACRA MUSIC) しかし、80年代の中頃から音楽業界の状況が変わっていきます。 既存の芸能界のシステムとは一線を画すミュージシャン、他との同列扱いを嫌うアイドルなどが現れ、こうした音楽賞の辞退者が増えていくのです。 さらに1987年には、審査や投票ではなく客観的な数字(音楽ソフトの売り上げ)を基準とする「日本ゴールドディスク大賞」(日本レコード協会主催)がスタートしたこともあり、旧来型の音楽賞は形骸化していきます。そんな背景から、1990年頃にまるで示し合わせたように各賞は姿を消していきました。 その後も根強く続いていた「日本有線大賞」も2017年で終了。日本ゴールドディスク大賞を別物とすると、2020年に残っているのは最古の日本レコード大賞のみとなったのです。
- ライフ