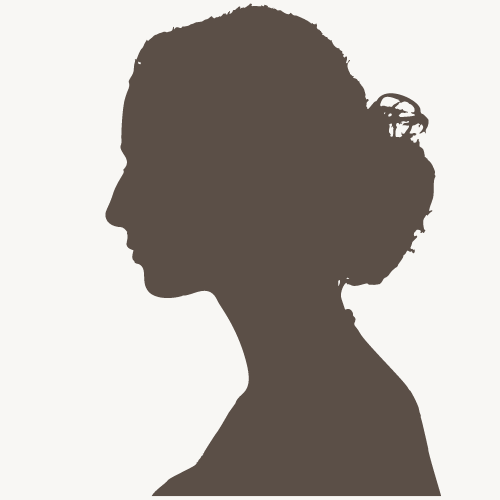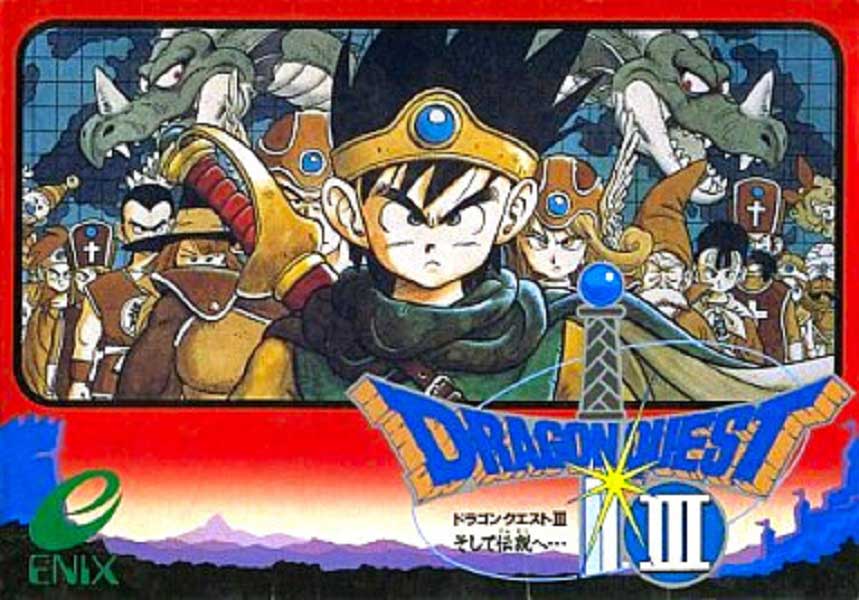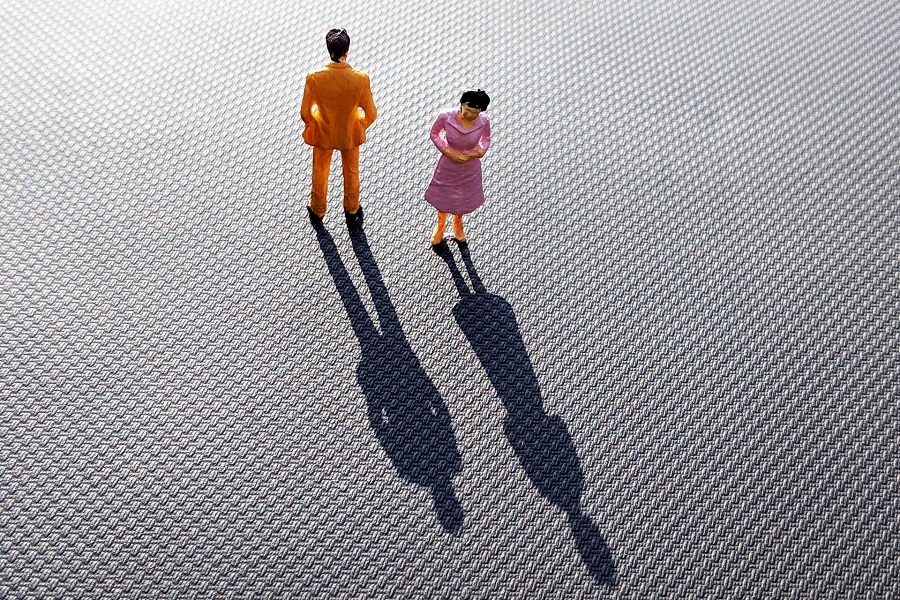節分に続く年中行事「事八日」を知ってる? 6つの具で無病息災を願う「お事汁」とは
風邪を引きがちなこの時期にぴったり! 栄養満点「お事汁」 節分が終わりましたが、年中行事は続きます。「事八日(ことようか)」をご存知でしょうか。古くから伝わる日本の年中行事のひとつで、事を始める節目として、その年の無病息災や五穀豊穣(ごこくほうじょう)を願う日とされてきました。12月8日と2月8日がその日にあたります。 事八日には、針供養も行われる(画像:写真AC) 和文化研究家 三浦康子さんによると、事八日が年に2回あるのは、2つのとらえ方があるためとのこと。 「1つめは、田の神様にまつわる農耕儀礼としてのとらえ方で、『事始め』が2月8日、『事納め』が12月8日になります。2つめは、年神様にまつわる正月儀礼としてのとらえ方で、『事始め』が12月8日、『事納め』が2月8日になります。 一方の始まりの日は、もう一方の終わりの日になっており、両方とも大事なので『事八日』と呼ばれるようになりました」(三浦さん) 事八日には、使えなくなった針の労をねぎらい供養する行事「針供養」を行ったり、無病息災を祈って野菜たっぷりの「お事汁(おことじる)」を飲むなどの風習があります。 「お事汁」とは、基本の食材として「里芋」「大根」「にんじん」「ごぼう」「こんにゃく」「あずき」の6種類の具材で作ったみそ汁のこと。別名「六質汁(むしつじる)」とも呼ばれます。 「基本のお事汁(六質汁)」(画像:味の素) ただ、地域によって入れる具材が異なる場合もあるため、必ずしも具材を先に挙げた6種類にこだわり抜く必要はないとのこと。味の素(中央区京橋)では、「オリジナルの『お事汁』をご家族で作ってみるのもきっと楽しいはずです」と、医師で料理研究家の河埜玲子さんが考案したレシピで、さまざまなお事汁作りを提案しています。 たとえば、赤みそに合うように考案されたレシピでは、豚肉ではなく、牛肉を入れることを提案。「みそ汁に牛肉は意外な組み合わせですが、コクのある赤みそとよく合います」とのこと。 「牛肉入りごちそうお事汁」(画像:味の素)「赤みそは塩分濃度が白みそより高く、香りとコクが強いのが特徴。みそに負けない強い味を持つ食材(肉・魚介類・きのこなど)を合わせると、みそがお肉や魚介類のくさみを抑えつつ、みそと食材のうま味の相乗効果でより美味しく食べられます」(味の素) さらに、カラフルで新食感の「カラフル野菜とチーズのお事汁」では、ブロッコリー、カリフラワー、パプリカ(黄色)、プチトマト、ボイルえび、カマンベールチーズ(!)……と斬新な具材が盛りだくさん。 「カラフル野菜とチーズのお事汁」(画像:味の素) みそとチーズは発酵食品同士で非常に相性が良く、お互いにうま味や味の深みを引き出してくれるのだとか。 「みそ汁は意外にどんな具材にでも合います。定番にとらわれず、冷蔵庫の残りものを入れて試してみると、これまでにない新しい美味しさを発見できるかもしれません!」(味の素) これらのレシピは、「『うちのみそ汁』応援プロジェクト」公式サイト内に掲載されています。 材料/調理時間(4人前/20分) ・里芋:4個(200グラム) ・大根:150グラム ・にんじん:1/2本(80グラム) ・ごぼう:1/2本(100グラム) ・こんにゃく:1/2枚 ・あずき(水煮):大さじ4 ・水:1000cc ・「ほんだし®︎」:小さじ山盛り1 ・みそ:大さじ3 ・青ねぎの小口切り:5本分 調理法 ①里芋は皮をむき、厚さ1センチの輪切りにする。大根は皮をむき、厚さ5ミリのいちょう切り、にんじんは皮をむき、厚さ3ミリの半月切りにする。ごぼうは皮をきれいに洗い、ささがきにする。こんにゃくは半分に切った後、厚さ5ミリの短冊切りにし、熱湯でさっとゆでてざるにあげる。あずき(水煮)は水気を切る。 ②鍋に水と「ほんだし®︎」、里芋、大根、にんじん、ごぼう、こんにゃくを入れて中火にかけ、沸騰したら弱火にしてフタをし約15分煮る。 ③野菜が柔らかくなったら、あずき(水煮)を加えてひと煮し、みそを溶き入れる。器に盛り付け、青ねぎの小口切りを添える。 お事汁だけじゃない。想像以上に具に寛大な、みそ汁の世界「うちのみそ汁」応援プロジェクトは、だしの素「ほんだし®︎」による、みそ汁の良さを、生活者のお悩み解決の観点で伝え、いまの時代ならではの価値を再認識していくための取り組みです。 公式サイトには、「お事汁」以外にも、多種多彩なみそ汁のレシピが盛りだくさん。なかには「焼きいも」「レタスと餃子」「キャベツとソーセージ」「ラタトゥイユ風」など、その組み合わせもアリなのか……と唸らされるレシピも。 レシピを参照しながら、新しい味に挑戦するのも一興ですが、ただ眺めているだけでも、「みそ汁の世界は、私たちが思っているよりもずっと自由なのかもしれない」という気持ちがふつふつと湧き上がってくるかもしれません。 今夜、具沢山のみそ汁をつくって、ほっと一息ついてみるのはいかがでしょうか。 ●味の素「うちのみそ汁」応援プロジェクト URL:https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/corner/products/hondashi/misoshiru
- ライフ