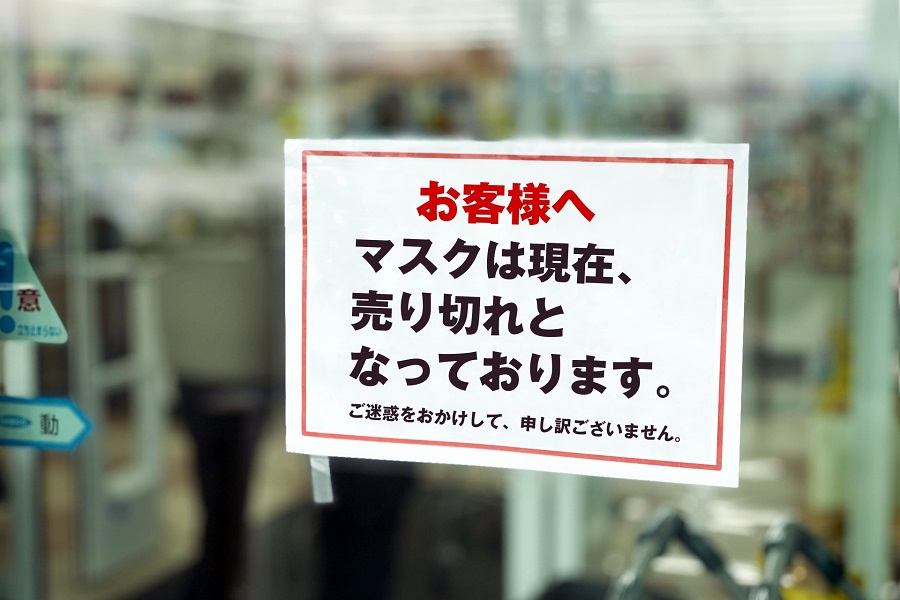昔はスーパーが1軒だけ 病院も本屋もなかった「お台場」が雑多な観光地に変身するまで
東京を代表する観光地となった港区・お台場。そんなお台場ですが、スタートは意外にも順風満帆ではありませんでした。20世紀研究家の星野正子さんが解説します。都市博中止で危ぶまれた未来 新型コロナウイルス感染の「第3波」到来で都内を歩く人が減っています。しかし、お台場海浜公園(港区台場)の周辺は休日になるといまだ多くの人であふれています。 お台場(画像:写真AC) そんなお台場は紆余(うよ)曲折を経て生まれた街で、東京臨海副都心として開発されるようになったのは、バブル絶頂期の1989(平成元)年からです。 しかし街の運命は過酷でした。1993年にレインボーブリッジが開通したものの、盛り上がりのきっかけとして期待されていた1996年の世界都市博覧会が中止になってしまったのです。 しかし既に開発の始まっていたオフィスや商業ビルは計画を止めるわけにいかず、開業が始まります。当時は1年も持たずに撤退してゴーストタウンになるのではないか――という見方が大半でした。 そして1996年になると、3月にホテル日航東京(現・ヒルトン東京お台場)、7月に東京ジョイポリスとデックス東京ビーチが次々とオープン。また、3月からはとバスが東京臨海副都心をめぐるコースを始めています。 世界都市博覧会の中止で見捨てられた埋め立て地に客など来るはずがない――という予測とは裏腹に、観光客は殺到します。 東京ジョイポリスは開業20日で入場者10万人を達成。デックス東京ビーチは開業1か月で120万人。ホテル日航東京の8月の稼働率は83%になっていました(『アクロス』1996年10月号)。 お台場に人が集まった理由お台場に人が集まった理由 お台場に人が集まったのは、都市博中止が生んだ「雑多な雰囲気」があったからです。デックス東京ビーチに代表されるようなオシャレな施設は多少ありましたが、空き地などの周囲の風景が何とも言えない「隙間」をつくり出していました。 周辺の路上には焼きそばやかき氷の屋台が出店し、雰囲気はまるで縁日。さらに、お台場海浜公園には釣りをする人や日焼けをする人が集まり、完全に海水浴場モード。水上バスの呼び込みも盛んでした。 元々はウオーターフロントのおしゃれな新都心ができるはずでしたが、ふたを開けて見たら土着感満載の、ゆるい観光地だったというわけです。 そして1年後の1997年に、お台場の象徴となるフジテレビが河田町から移転してきます。 フジテレビ(画像:写真AC) 当時のフジテレビは、移転そのものを番組ネタにするくらいの遊び心があったテレビ局でした。そんなテレビ局の拠点ができたことで、雑多な雰囲気はさらに加速していきました。 2020年1月時点で5648人が在住 観光地のイメージが強いお台場ですが、意外にも多くの人が住んでいます。 2020年1月時点で、お台場の属する台場1丁目と2丁目を合わせた人口は5648人。2003年1月の人口は台場1丁目が4502人。2丁目は0。当時は2丁目には物件がありませんでした。2006年に高級タワーマンション「ザ・タワーズ台場」ができると、9月には台場2丁目の人口はゼロから606人に増加します。 ザ・タワーズ台場(画像:(C)Google) 同様の傾向は1996年に既にありました。同年3月時点でお台場には住宅・都市整備公団(現・都市再生機構)などの運営する賃貸住宅が10棟1302戸ありました。決して便利なエリアでもないにも拘わらず入居倍率は高いものでした。 都市再生機構(UR)の「シーリアお台場三番街」は平均で26.8倍。最上階の部屋は615倍という状況です。ちなみにこの物件は今でも人気が高く、不動産情報サイトを見ても空き部屋はありません。1LDKの家賃は15万9000円となかなかの高額物件です。 「絶海の孤島」から書店のある文化的エリアに「絶海の孤島」から書店のある文化的エリアに 当時と現在を比較すると、お台場は住むにも便利な街へと変化しています。 1996年頃のお台場は、都心にありながら「絶海の孤島」でした。なにしろ、スーパーマーケットはマルエツだけ。書店もなければ、病院も歯医者以外はありません。もちろんピザの宅配も来ませんでした。この頃にお台場に住んでいた人は、渋谷や新宿に出掛けることを「街に行く」と言っていたくらいです。 しかし、街は次第に発展していきました。スーパーマーケットでいうと、現在はマルエツに加えてオーケーストアと成城石井があります。生活視点で見ると、安いスーパーと高級スーパーの両方がありバランスが取れています。 病院も充実。書店に至っては、くまざわ書店が2店舗出店しています。お台場よりも優位とされる月島・勝どき・晴海エリアに大型書店が存在しないことを考えると、お台場のほうが文化的と言えるでしょう。 オーケー お台場店(画像:(C)Google) このように、一度は諦められた土地になるかと思いきや、それをバネに独特な街となったお台場。単なる観光地とは違うこの街はもっと評価されてしかるべきです。
- 未分類