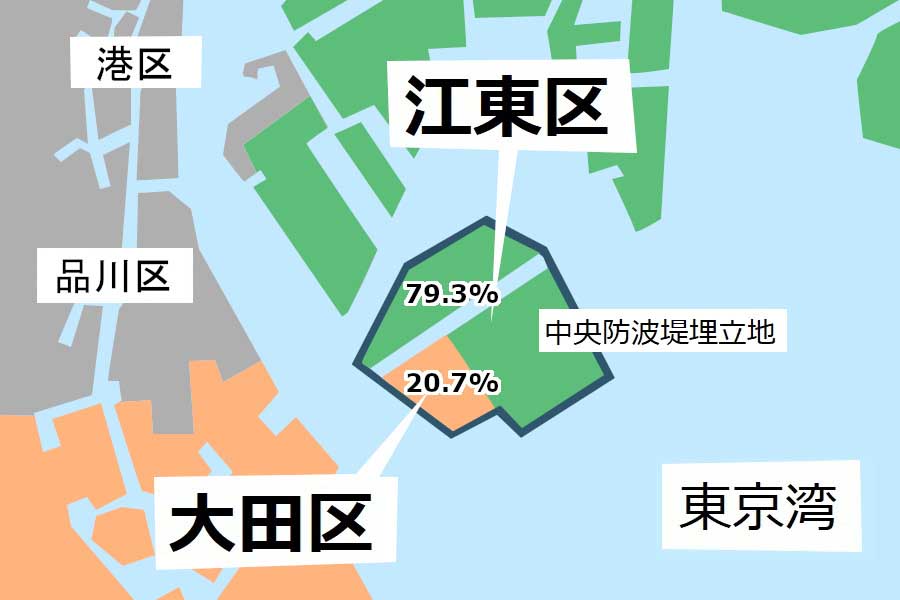かつての「陸の孤島」がトレンドスポットに大変身 1991年オープン「ジュリアナ東京」の衝撃とは
バブル経済が崩壊した1991年、東京港区芝浦に開業した有名ディスコ「ジュリアナ東京」。狂乱の時代の「あだ花」としてだけではなく、同地に思わぬ変化をもたらしていきました。統計データ分析家の本川裕さんが、時代背景とともにその文化を振り返ります。ディスコ・ブームの誕生と発展 生バンドの演奏ではなく、レコードの音楽で踊る「ディスコ」は、パリ、ニューヨークで発祥し、当初はマニアックな存在でしたが、1970年代半ばからは世界的なブームとなりました。 日本でも1960年代後半には、それまでのゴーゴー喫茶とは一線を画す社交場として、作家やモデル、有名人、富裕層を客層としたり、服装チェックを行ったりする店が登場して「ディスコ」を名乗り、時代を先んじた存在になりました。 閉店前最後の週末でにぎわうディスコ「ジュリアナ東京」。1994年08月26日撮影(画像:時事) その後、趣向を凝らしたホールの設計やDJの選曲センス、曲紹介、スクラッチの演出などの音楽文化が若者に受け、何波かのブームの中で、多くのディスコ店が開業し、数々のディスコ・ヒットも生まれました。特に1978(昭和53)年の「サタデー・ナイト・フィーバー」の大ヒットは日本でもディスコを一気に大衆化しました。 有名ディスコは、当初、赤坂や新宿といった旧来型の繁華街に存在しましたが、1980年代後半のバブル期をはさんだ時期に、一方で、麻布・六本木・青山といった新しくオシャレなトレンディー・タウン、他方で、芝浦などウオーターフロントの倉庫街に展開するようになりました。 バブル期の象徴となった「ジュリアナ東京」バブル期の象徴となった「ジュリアナ東京」 コラムニスト・泉麻人の「新・東京23区物語」(2001年)は、港区湾岸部で突如巻き起こったウオーターフロント・ブームについてこう記しています。 「芝浦運河の付近には、40年ほど前までダルマ船の中の三畳ほどの部屋で生活を送る『水上生活者』と呼ばれる家族が千世帯ほど存在していました。そんなダルマ船が浮かんでいた芝浦運河の周辺に、1980年代後半のいわゆるバブル景気の頃、<ウォーターフロント>なるうたい文句の下、バーやディスコ(現・クラブ)がぼつぼつと発生し、六本木に飽きた若者たちのアソビ場として、脚光を浴びるようになります」。 かつて「ジュリアナ東京」のエントランスだった場所。「への字」のデザインは当時のまま(画像:(C)Google) 中でも、1991(平成3)年に芝浦に開業したディスコ「ジュリアナ東京」が一世を風靡(ふうび)しました。 当時の騒がれ方は、湾岸ウオーターフロントの倉庫街に花咲いたロフト文化の中では異色だったといわれますが、最寄り駅田町駅から降りたワンレン・ボディコン・爪長・トサカ前髪といったファッションの女性が多く集まり、大きな話題になりました。 DJの絶叫、女性客の露出の過激化、そして、通称「お立ち台」と呼ばれるステージや荒木師匠こと荒木久美子に代表されるジュリアナ扇子(せんす、通称「ジュリ扇」)を合わせたファッションが「バブル期」を象徴する風俗として有名になりました。 ジュリアナ東京が開店した1991年は、バブル経済が崩壊した年でしたが、バブル時代の余勢はなお根強く、「ひたひたと迫る不況の足音で広がる社会不安にあらがうように、陶酔(とうすい)に浸ったジュリアナの夜」と評されています(東京新聞2013年1月8日) のちに違法派遣、不正請求で問題となった人材派遣業、介護サービスのグッドウィル・グループの折口雅博元会長が当時の日商岩井の社員として、大手倉庫会社のオーナーから有効利用の相談を受け、巨大ディスコとするプロジェクトを計画。綿密な計画の下、立ち挙げ、大成功を収めたという逸話でも有名です(同氏は「ジュリアナ東京」に続いて「ヴェルファーレ」も立ち挙げています)。 ウオーターフロント・芝浦の時代的変遷ウオーターフロント・芝浦の時代的変遷 地元商店街の店主たちが、突如、巻き起こったこうしたブームに大いに面食らった様子が目に浮かぶようです。 創立30周年記念「芝浦商店会のあゆみ」(2000年)の「序(ついで)にかえて:芝浦は今、全国的有名地に」の中では、「ジュリアナ東京」が芝浦地域に「青天の霹靂(へきれき)」のような衝撃を与えたことが次のように記されています。 「一昔前までの芝浦は、知名度が低く、殺風景な埋立地の上にできた、いわゆるダサイ町でした。現在のような生き生きとした街に至るまでには、かなりの時間を要しました。世にいう『陸の孤島・芝浦』というありがたくないレッテルは、一朝一夕にはがすことのできない状況にあったのです。1991年開店のジュリアナ東京は状況を一変させました。オープンと同時に、世の若者の目はジュリアナへホットに向けられ、連日連夜、押すな押すなの盛況。周辺には全国から集まったナンバー車のオンパレードといったすさまじさ。あらゆるマスコミも同店をとりあげたおかげで、「ジュリアナのある芝浦」は、区内の六本木や赤坂といった一等地と肩を並べるほど大々的にクローズアップされました。やがて、ディスコフィーバーも冷めかけた矢先、こんどは芝浦とは目鼻の先に夢の架け橋お台場へとつながるレインボーブリッジが完成。都心の一大観光地へと注目を集め、芝浦は都心から近いウオーターフロントとして見直され、これまたイメージアップにつながったのです」。 当時の興奮を伝えるドキュメントとして、少し長くなりましたが引用しました。 ディスコの盛衰をまとめた年表(画像:本川裕) なお明治末以降、埋め立て開発が進み、ダルマ船が行き交う運河と倉庫の街となる以前の芝浦は、風光明媚(めいび)な海岸に料亭が立ち並び、要人を運ぶ人力車が車列をなす近郊リゾート地であり、それが、小林秀雄らの文士が大学サークル室のように使っていたことでも知られる芝浦花柳界が軒を並べるいわれともなりました。 タワマン立ち並ぶ住宅地への変貌 陣内秀信「東京 (世界の都市の物語) 」(1992年)は、バブル期に注目された芝浦エリアのウオーターフロント・レジャー施設を、明治時代の「芝浦海岸リゾート」の再来と位置づけていますが、芝浦地区をよく知っている者ならではの卓見であると思われます。 かつて「ジュリアナ東京」があった芝浦の周辺(画像:(C)Google) あだ花のような「ジュリアナ東京」だけでなく、倉庫街のロフト文化全体が、その後、時代の流れとともに衰退し、芝浦港南地区は、今では、東京圏における都心回帰の受け皿として、「芝浦アイランド」などタワーマンションの林立する高層住宅地として新しい歴史の歩みを進めています。
- 未分類