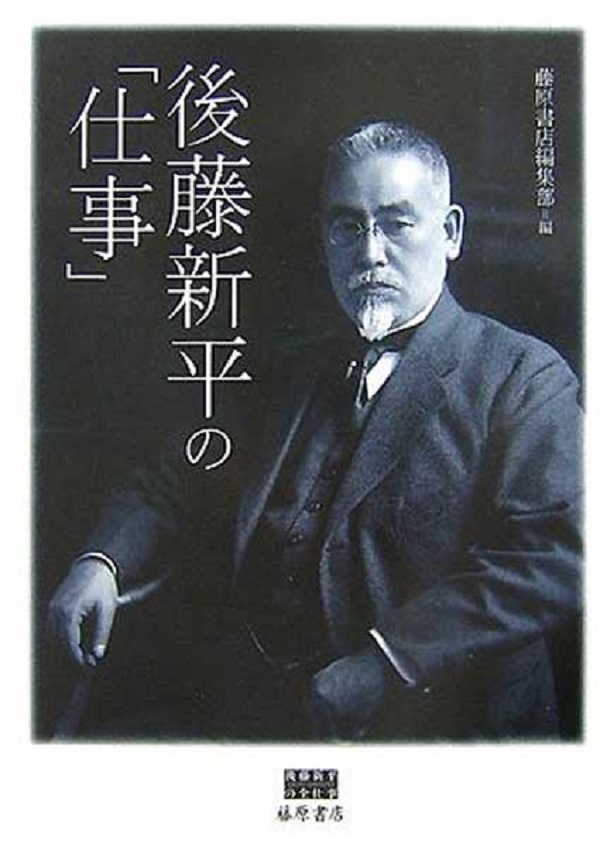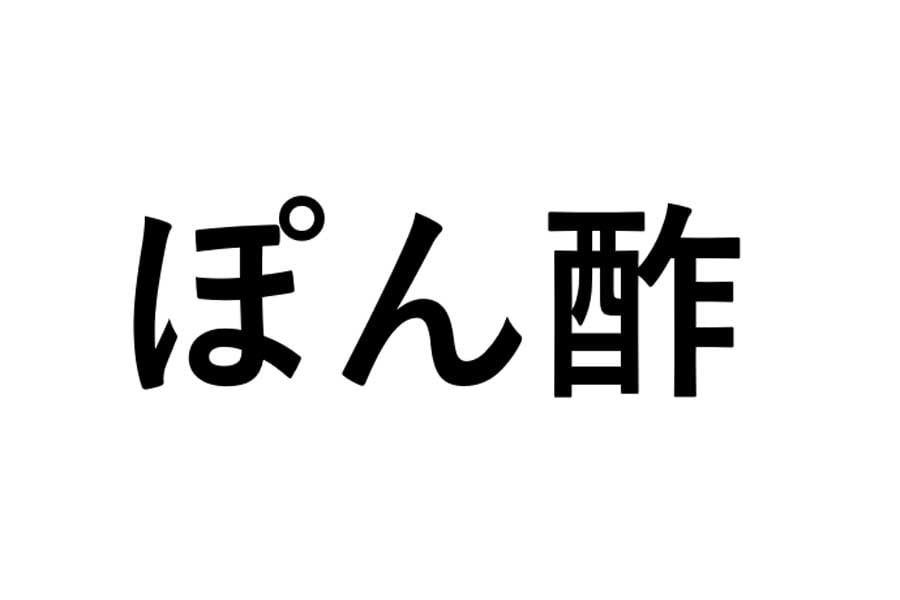東京農工大の馬たちが大ピンチ SNSでの支援呼び掛けに続々と反応が 「善意のリレー」舞台裏を学生に聞いた
「馬たちの快適な暮らしのために、よろしくお願いします!」――。東京農工大学の学生が発信したそんなツイッターの投稿に、ユーザーたちから次々と強力の申し出が寄せられました。善意のリレーが生まれた経緯とてん末を、同大の学生に取材しました。「馬房に敷く『おが』が不足しています」「急募、拡散希望」 「馬たちの快適な暮らしのために、よろしくお願いします!」 2021年9月、そんな投稿がツイッターにアップされました。 発信者は府中市晴見町にある東京農工大学「ミニホースの会」(@miniho_tat)。ミニチュアホースを飼育・調教している同大学の公認サークルです。 ミニホースたちの馬房に敷くためのおかくずが足りなくなり、「馬たちの健康に関わる深刻な問題で、部員一同困っております」と深刻な窮状を訴え、「もし提供してくださる方などいらっしゃいましたら、DM等でのご連絡お待ちしています」と情報提供を呼び掛けました。 すると投稿には、見る見るうちに善意のリプライ(返信)が多数寄せられて……。 ツイッター上で起こった“奇跡の助け合い”について、同会代表の大和久健太さんに経緯とてん末を尋ねました。 2003年創設の同大公認サークル 大和久さんは農学部共同獣医学科の3年生。2003(平成15)年3月に創設された同会で現在、72人の部員を束ねる代表を務めています。 東京農工大ミニホースの会が飼育している、馬のアップルパイ(画像:東京農工大学 ミニホースの会) ミニホースの飼育・調教を通じて(1)命の大切さを学び、(2)社会貢献活動を行い、(3)ミニホースに関する知識や経験を外部へ発信し、これらの活動を通じて、豊かな人間性を育む――というのが同会の掲げる活動目標。 新型コロナウイルスの感染が拡大する以前は、馬について興味を持ってもらうため、地域のお祭りやイベントにミニホースを連れていき、ふれあい体験や乗馬体験、馬車などを積極的に行っていたといいます。 おがくずは馬房の敷材として利用しているもの。1日1回、清掃の際に、フンなどで汚れたおがくずを取り除いて新しいおがくずを追加するのが部員たちの日課です。 馬の飼育におがくずが欠かせない理由馬の飼育におがくずが欠かせない理由「おがくずの主な役割はふたつあって、ひとつめは『馬の蹄(ひづめ)を守る』ことです」(大和久さん) 馬のひづめのイメージ(画像:写真AC)「馬の蹄は湿気にあまり強くないので、馬房など長時間滞在する場所が湿っていると蹄の病気になるリスクが上がります。馬の蹄は『第二の心臓』と言われるほど、血液循環に大きな役割を果たしている大切な部位です。おがくずを敷くことで湿気・水分が吸収されて乾燥した状態が保て、馬の蹄を病気から守ってくれるのです」 「もうひとつは『寝床』としての役割です。おがくずはふかふかなので馬が気持ちよく寝転がることができます。馬が寝転がっても地面からの熱吸収をある程度抑えて体を冷えにくくする効果があるので、寝床としても最適なのです」 馬が馬房で快適に過ごす環境作りに欠かせない、おがくず。普段は近くの材木店などから厚意で譲り受けていましたが、ここに来てピンチが訪れたと言います。 「近年、閉業してしまう材木屋さんが多く、年々おがくずを譲ってくださるところが少なくなってきていました。さらに、季節によってはおがくずがあまり出ない材木屋さんもあり、これもおがくずが不足する理由のひとつとなりました」 祈るような気持ちでツイッターに投稿 おがくずは同大の馬術部と共同で使用しているもの。それぞれの部の馬たちにとって深刻な状況が迫っていました。何としてでもおがくずを確保しなくては――。 9月15日(水)午後、大和久さんや部員たちは祈るような気持ちでツイッターに投稿をしました。「もし提供してくださる方などいらっしゃいましたら、ご連絡お待ちしています」 すると、その日のうちから次々と、提供を名乗り出るリプライが相次いだのです。 「ネットで『おがくず差し上げます』というサイトのページを見つけたので参考にしていただけたら」 「稲わらでは代用できないでしょうか? もし代用可能であれば、大量にお譲りできると思います」 「付き合いのある木工所に聞いてみます。おがくずは毎日のように出るはずです」 「東京葛飾区にある靴木型製作所です。おがくずや、端材などもあります。木材は西洋シデです」…… おがくず不足、解決のめどが立つおがくず不足、解決のめどが立つ「正直、ここまで反響があるとは想像もしませんでした」と、大和久さんはあらためてそのときの驚きを振り返ります。 情報拡散を意味するリツイートは2.6万件、いいね の数は2.4万件に上りました(2021年9月22日18時現在)。 人々の善意を呼んだ、おがくずの提供を求めるツイッターでの呼び掛け(画像:東京農工大学「ミニホースの会」のツイート)「大規模に拡散していただいたおかげで、本当に多くの情報が多く集まりました。それと同時に、ミニホースの会の存在や馬について知っていただける機会にもなって、本当にうれしく、ありがたく思っています」 現在は寄せられた連絡を頼りに、馬術部と協力をして、立地やおがくずの質などの条件が合致しそうな相手と連絡を取り合っている最中とのこと。 現時点ではまだおがくず不足の状態が続いていますが、解決の糸口は見えてきている段階だと言います。 同会が飼育する愛らしい3頭「今回、情報提供や拡散をしてくださった方々に、あらためてお礼を申し上げます。さまざまなアドバイスもいただいたので、今後のおがくずの入手に役立てたいと思います」と大和久さん。 同会が飼育している馬は、現在3頭。 24歳の牝馬シナモンは、体重約124kgで体高99cm。人間で例えると70歳前後のおばあちゃん馬です。 「3頭の中で一番体が大きいです。スタイルがよく脚が長いため、歩く姿はとても美しいです。性格は優しくおとなしい半面、とっても臆病なため、少しのことで驚いてしまいます。ほかの2頭のお母さんでもあります」 シナモンの娘、牝馬のアップルパイは13歳。体重約113kgで、体高は86cm。人間で例えると30代後半のお姉さんです。 「まんまるとした体形がチャームポイントです。警戒心が強く、怒りやすい性格ですが、心を開いてくれるととても人懐っこくなります。(母親の)シナモンと対面させると、お互い気持ちよさそうにグルーミング(毛繕い)をします」 コロナ後は、またイベントに参加もコロナ後は、またイベントに参加も もう1頭は、シナモンの息子でアップルパイの弟にあたる9歳の牡馬カルヴァドス。人間で例えると20代後半です。体重は約92kg、体高は90cmで、3頭の中で一番体重が軽いのが特徴です。 「性格はやんちゃで人と遊んだり、体を動かしたりすることが大好きです。好奇心旺盛で、いろんなことに興味を示します。その半面、元気があり過ぎて部員が手を焼くこともしばしばあります。かわいい“末っ子”です」 3頭について説明する大和久さんの言葉の端々からは、馬に対する深い愛情があふれ出てくるようでした。 府中市晴見町にある東京農工大学(画像:(C)Google)「今回のツイートは、馬に関係する方々はもちろん、今まで馬に関わりのなかった方々にまで拡散してくださいました。このツイートを目にしたことを機に、馬について何か少しでも興味持っていただけたら、本当にうれしいです」 新型コロナが収束したら、また地域のお祭りやイベントで、ミニホースのふれあい体験を行いたいとのこと。善意のリレーを生んだ愛くるしい3頭に会える日を、フォロワーたちも待ち遠しく感じていることでしょう。
- ライフ
- 府中