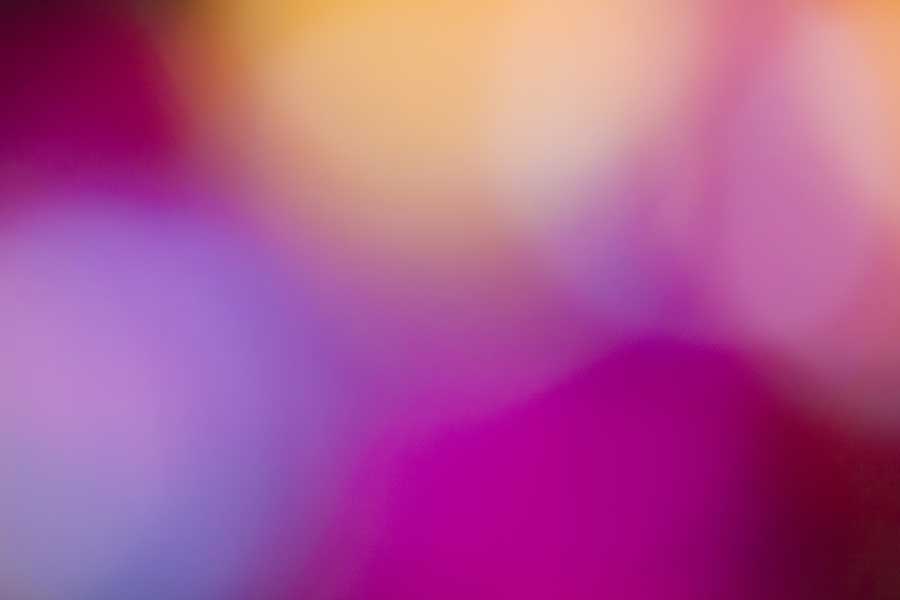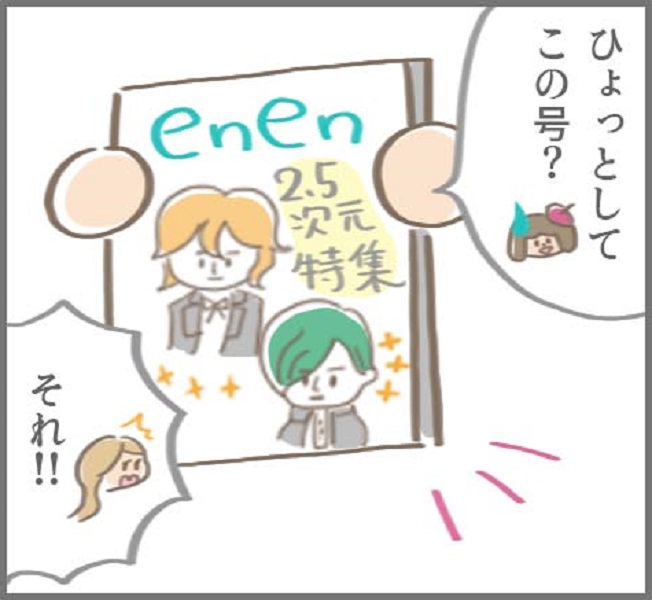猫だけじゃなかった……! 新宿で「巨大3Dカニ」を大発見した投稿者にツイッター民が6.6万いいねの称賛
あっと驚く衝撃の場面、感心させられる発見や豆知識、思わず涙を誘う感動の出来事……。SNS上では毎日、新鮮な話題がいくつも発信されてます。そのなかから「東京」に関連するものを厳選してご紹介します。思いがけない巨大生物が潜んでいた JR新宿駅東口に登場して世間の話題をさらった、大型街頭スクリーンに映し出される3Dの巨大な三毛猫の映像。 そのあまりのインパクトに、ミニチュアサイズの街並みを自宅に再現した飼い猫用「キャットタワー」を作成するクリエーターが現れるなど、さまざまな反響を巻き起こりました。 しかし、新宿に“生息”する巨大3D生物は、猫だけではありませんでした。 猫の街頭スクリーンがある新宿東口の駅前から歩いてわずか6分ほどのところに、負けず劣らず巨大な「3Dカニ」が存在することが判明したのです 東京在住の音楽プログラマー、じーくどらむす/岩本翔(@geekdrums)さんがツイッターに投稿したのは、その巨大なカニを捉えた画像。 新宿で発見された「巨大カニ」の正体とは……?(画像:じーくどらむす/岩本翔さんのツイートより、ULM編集部でトリミング)「新宿のカニちゃん見てきた。ほんとに立体的に見える すごい」 というつぶやきとともに、とても巨大なカニが写った画像をアップしています。 しかしこの巨大カニ、よく見ればすぐ上に「かに道楽 年中無休」という看板が。そう、これは大阪市に本社を構えるおなじみのカニ料理専門レストラン「かに道楽」新宿本店のオブジェなのでした。 しかし言われてみれば、横長で白っぽい長方体の中に収まっているビジュアルは、街頭スクリーンの猫とほとんど瓜ふたつ。 これにはツイッターユーザーも意表を突かれたようで、6.6万もの「いいね」とともに、 「新宿の立体動物ってカニのことだったのか!」 「猫以上に飛び出して見える」 「さすが最新の街頭ビジョン、たまげたなぁ」 など、次々に“ノリツッコミ”のリプライ(返信)が寄せられました。 「カニも映像なの??」混乱する人も……「カニも映像なの??」混乱する人も…… しかし中には「えっ、これ立体じゃないの(映像なの)!?」と本気で混乱する人も出てきたため、じーくどらむす/岩本翔さんが「本当にカニも立体視映像なのかと勘繰る人が出ていて申し訳ない気持ちになっている」と“釈明”するまでに至りました。 ツイッターに投稿され、6.6万いいねが寄せられた画像(画像:じーくどらむす/岩本翔さんのツイート) この日は家族と新宿を通りがかり、話題の巨大猫の街頭スクリーンを見に行こうとしたところ、たまたま近くを見上げた際に「かに道楽」の看板とオブジェを発見。ちょっとした思いつきとして投稿したのだと言います。 「ここまで伸びる(「いいね」が集まる)とは思わなかったです」と、じーくどらむす/岩本翔さんも驚いた様子。 カニを猫と同じく立体視映像と見なしたノリのいいリプライばかりが相次ぎ、誰も“ネタバレ”に言及しなかったため、 「皆さんボケ倒すので新宿に来たことない方を混乱に陥れてないか途中から心配でした」とも話しています。 新宿に誕生した新たな注目スポット、巨大猫の街頭スクリーン。もし現地へ見に行く機会があったら、併せて巨大カニも見上げてみてはいかがでしょうか。
- ライフ
- 新宿駅