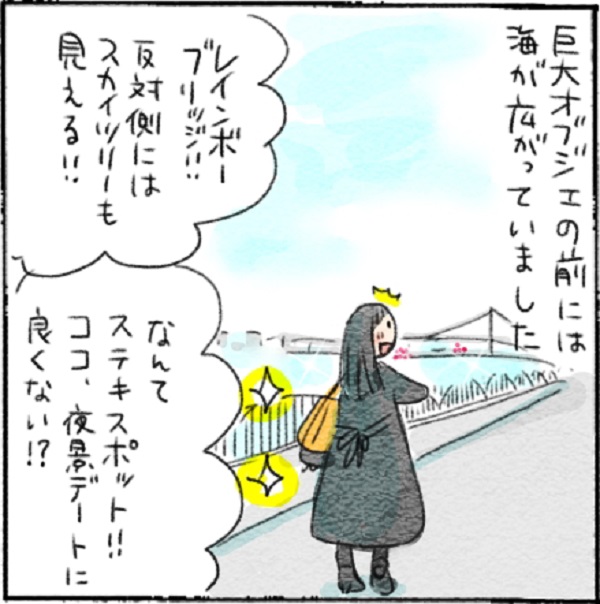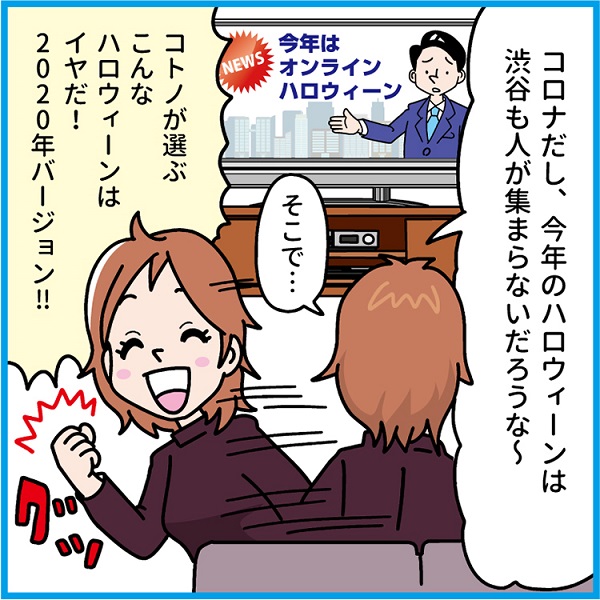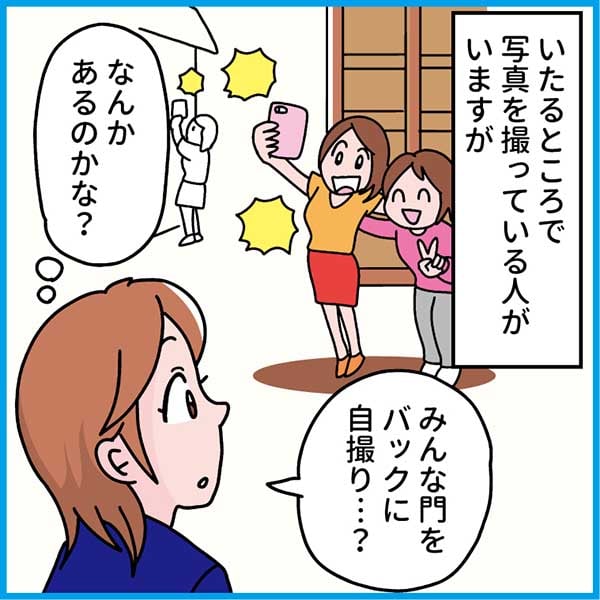商店街の成立と隆盛
過去2回の記事では、商店街の、より正確に言うならば 「生活型」商店街の魅力と、条件に合った選び方などについて言及しました。今回は 「商店街論の基礎講座」 の〆として、商店街の役割や歴史について簡単に触れようと思います。
 筆者の生家があった板橋区の商店街は、江戸時代の下板橋宿(画像:荒井禎雄)
筆者の生家があった板橋区の商店街は、江戸時代の下板橋宿(画像:荒井禎雄)
商店街というシステムがもっとも栄えていたのは、高度経済成長期であると言われています。その後1980年代に衰退が明確となり、商店街に取って代わる買い物場所が次々と誕生、今に至ります。
商店街の起源はさまざまで、門前町であったり、宿場町であったりもしますが、そうした古い街ばかりが商店街となった訳ではありません。
商店街の成り立ちとして意外と多いのが、軍事工場などで働く人々が工場に通うのに便の良い場所に集まり、商店がそうした人々の需要を期待して集まり、商店街となったというケースです。
しかしこうして誕生した街は、戦争が終わって工場が閉鎖されるなど、働き口が無くなれば、利便性が激減し、住民が離れて行ってしまいます。
また、戦後に鉄道駅の広場や神社仏閣の門前など、人の往来のある場所にヤミ市が立ち、それを経て商店街に発展したケースもあります。池袋や秋葉原などはヤミ市から発展した街ですし、アメ横などヤミ市時代の名残りを残し続けています。
このようにして各地に誕生した商店街は、実は意外と新しい存在であり、当時もっとも利便性の高い「買い物システム」だったのです。
ところが、商店街が隆盛を極めていた時期に、ある外敵が出現します。それがスーパーマーケットという「外来種の新システム」でした。
商店街の衰退と次々誕生する外敵
商店街の絶頂期である1950年~70年頃は、イトーヨーカドーやダイエーといった大型スーパーが、駅前の好立地を狙って出店を開始した時期でもあります。
 大型スーパーの入口付近に置かれたショッピングカート(画像:写真AC)
大型スーパーの入口付近に置かれたショッピングカート(画像:写真AC)
この動きに対して、当時まだ力の強かった各地の商店会や商工会は脅威を感じ、国とかけあってある法律を制定させます。それが「大規模小売店舗法(通称・大店法。1974年施行)」です。
この大店法により、スーパーや百貨店は出店の際に審査会による審査(面積、営業時間、休業日数など)を受けねばならなくなり、80年代になると更に「出店抑制地区」が指定されるようになりました。
これにより商店街を構成するパーツである個人商店が守られる事になった……はずなのですが、実際はこの大店法が商店街の、厳密に言うと個人経営の専門店の衰退を決定付けるものとなりました。
個人商店にトドメを刺した最新鋭の業態
大店法によって大資本の大型店が街の中心部に入れなくなり、個人商店及び商店街は法律に庇(かば)って貰える存在となりました。個人商店が「利権化」「既得権益化」されたということになります。
ところが、これによって多くの商店が現状に甘んじてしまい、経営努力や事業の成長力を失い、商店街とは「客にとって魅力のない買い物場所」となってしまったのです。
それが如実に表面化したのが、大型スーパーに次ぐ刺客である「コンビニエンスストア」という、最新鋭の業態の出店攻勢です。
コンビニは街の酒屋と同程度の30坪前後が理想とされており、大店法の規制を受けません。よって、平気で商店街のど真ん中に入り込んで来てしまいます。
私の生家は商店街の古い酒屋だったのですが、大規模商店街の入り口という好立地だった為か、その当時各コンビニ本部からの営業ラッシュが凄く、彼らからの貢ぎ物で生活ができるレベルだったそうです。
コンビニという名の「復讐」
さて、このコンビニは日用品、飲み物、お酒、タバコ、おにぎりやサンドイッチや弁当といった商品に対する需要を個人商店からかっさらい、加えて24時間営業という個人店では絶対に真似できない手法で客を掴みました。これにより、それまでの人の流れが変わるレベルの激変が起きたのです。
 スーパーでは真似できない値付け! 板橋区大山の商店街のお肉屋さん(画像:荒井禎雄)
スーパーでは真似できない値付け! 板橋区大山の商店街のお肉屋さん(画像:荒井禎雄)
上で「酒やタバコ」と書きましたが、これは昔は免許品だった物で、限られた人間しか売買できない商品でした。だからこそ、コンビニの出店ラッシュの時期に、まずは酒類の販売免許を持ち、なおかつ坪数の丁度いい酒屋が口説かれたのです。
法律で庇って貰える状況に甘んじていた個人商店は、このコンビニに太刀打ち出来ず、商売替えやマンション化、はたまた、シャッター店化といった流れが加速してしまいました。
ここで思い出して欲しいのですが、先ほど実名を挙げた、大店法で規制を受けた大資本の企業の名前を憶えておいででしょうか。そう、イトーヨーカドー(セブンイレブン)やダイエー(ローソン)です。ついでに西友(ファミリーマート)やユニー・長崎屋(サークルKサンクス)やジャスコ・イオン(ミニストップ)なども挙げておきましょう。
非常に悪い言い方になりますが、コンビニという業態は大店法に対する「復讐」という一面があったと言えるのではないでしょうか。