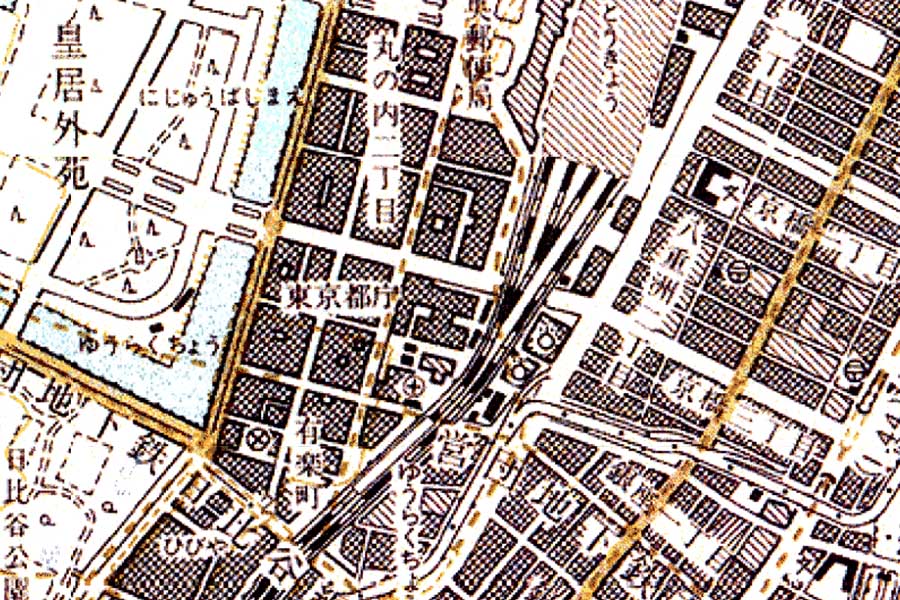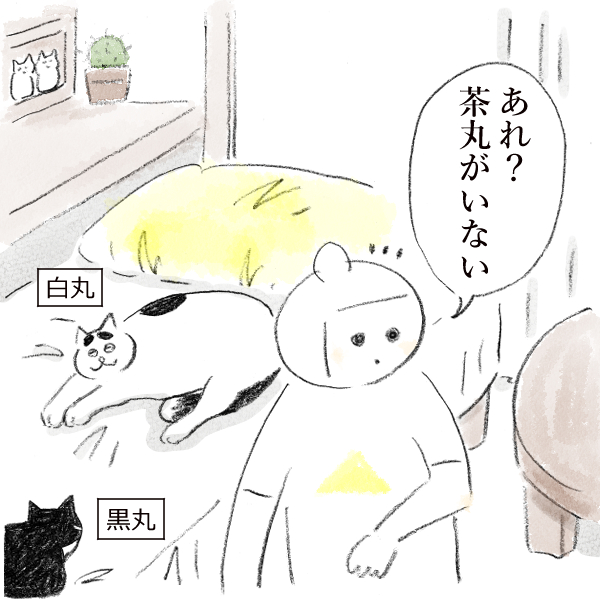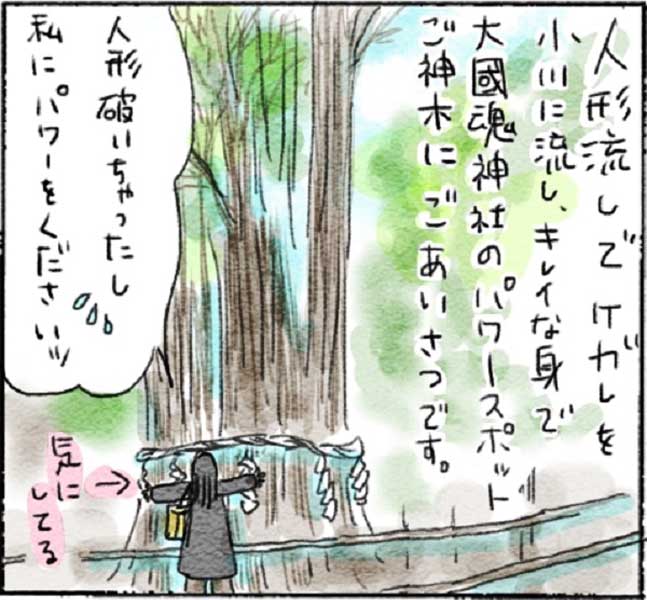徹底解剖「メガドンキ渋谷本店」 毎日がお祭り状態、その戦略とは?
生活密着型の小売店でありながら、各所に遊び心が散りばめられている驚安の殿堂「ドン・キホーテ」。なかでも、訪日外国人の来客が多く、特徴的な店舗「MEGAドン・キホーテ渋谷本店」はどう作られているのでしょうか。店長に話を聞きました。毎日がお祭りのような店内、どう作られている? 世界的観光都市となった渋谷の道玄坂にそびえ立つ「MEGAドン・キホーテ渋谷本店」。1999(平成11)年に誕生した「ドン・キホーテ渋谷店」を移転、拡大するかたちで、2017年にオープンしました。 看板の前などで記念撮影を楽しむ人も多数見受けられる「MEGAドン・キホーテ渋谷本店」(2019年5月30日、高橋亜矢子撮影) 正面入口の左右に置かれるのは、熱帯魚やウツボが遊泳する水槽。店内は、ハチ公を模した銅像が置かれるほか、各所に遊び心がめいっぱい散りばめられており、一言に要約するなら「祭り」のよう。観光を楽しむ訪日外国人の姿も多数見受けられます。 楽しいのは観光客だけではありません。足を踏み入れると、遊園地にいるようなワクワク感がこみ上げてくる人も少なくないのでは。ドンキ系列では珍しく、都心部で生鮮食品を扱う店舗でもあります。 そんな同店。一体どのように作られているのでしょうか。2018年春からMEGAドン・キホーテ渋谷本店の店長を務める長谷部洋平さんに話を聞きました。 まず初めに、ドン・キホーテを語る上で切っても切り離せない言葉が「権限委譲」だと、長谷部さんは話します。 チェーン店に見えるが「同じお店は2つとない」地域密着型チェーン店に見えるが「同じお店は2つとない」地域密着型「チェーン店だと思われることが多い我々ですが、権限は各現場に与えられています。本部はあくまでもサポートという位置付けなんです。つまり、同じお店は2つとありません」 MEGAドン・キホーテ渋谷本店店長の長谷部さん(2019年5月30日、高橋亜矢子撮影) 現場を一番知っているのは現場の人間。だからこそ、店ごとの判断で地域の需要に合わせた品揃えや価格設定を考え、実践しているとのこと。 「元号が令和に変わる際も、僕が『令和だから018じゃないか』と騒ぎ出し、店内に18円や180円の商品を散りばめようと言い始めまして。通常100円以上するお菓子を18円で販売するなど、毎日色々なことをやっていました」 思わず「採算とれるんですか?」と聞いたところ、「販促費を活用しつつ、企業努力をしています」と長谷部さん。「ディスカウント」「コンビニエンス」「アミューズメント」が、ドン・キホーテ全体のコンセプトであり、アミューズメントの精神は、価格にも反映されているといいます。 「”驚きの安さ”もアミューズメントだと考えています。お客様の『えっ!やば!』というコメントをいくつもらえるかに、すごくこだわっているんです。我々、どうお客様に面白いと感じてもらうか、驚いてもらうかが本義なので」 渋谷店独自の取り組みとして特徴的なのは、大きく分けると「店頭でライブイベントを開催」「渋谷オリジナルグッズの販売」「23区内に当日配送が可能(生鮮食品は渋谷区と目黒区のみ)」の3つ。 店頭ライブは、ネクストブレイクを予感させる人に声がけをしているといいます。土日を中心に開催。例えば5月には、ドラマ『絶対正義』の主題歌を担当した「嘘とカメレオン」がライブを開催しています。 「今まで沢山の人を呼んできましたが、うち3組くらいは、僕が街でライブしている人に声をかけて、名刺を渡して、『今度うちでライブやってくれませんか』とお願いした人たちです。とはいえ、我々の本質は小売業なので、一般のお客様に迷惑をかけないよう、1回15~30分を限界値として、スポット的に開催しています」 渋谷だけしか買えないものへのこだわり渋谷だけしか買えないものへのこだわり 続いて渋谷のオリジナルグッズについて話を聞きました。同店の各所には、でかでかと「渋谷」もしくは「shibuya」の文字が入ったTシャツやトレーナー、キャップ、バッグなどが大量に積み上げられています。中には、渋谷のシンボル「ハチ公」のイラスト入りも。 「渋谷最強」と書かれたTシャツは訪日外国人に人気という(2019年5月30日、高橋亜矢子撮影)「こういったグッズを作るのが好きなんです。渋谷だけしか買えないものにこだわりを持っています」(長谷部さん) 試みのスタートは2018年春。同店の店長に就任してまもなく、靴底に「SHIBUYA」と文字の入ったサンダルを企画し、販売したことに始まります。 「売れるかどうか不安はあったのですが、めちゃくちゃ売れたんです。それに便乗というわけではないんですが……以来、色々な渋谷グッズを開発して売っています。海外の方には、背中に漢字で『渋谷最強』と書いてあるTシャツなどがよく売れています」 漢字とアルファベットは、6:4の割合で漢字が人気とのこと。 「海外の人たちは、『渋谷』が大好きなんですよ。文字が入ったものも大好きですし、『渋谷に来た証を残したい』と思っているようです」 そのため、菓子類の「渋谷みやげ」にも力を入れる同店。渋谷区の観光協会とコラボし、ハチ公の使用許可をもらい、たくさんの種類を生み出しており、「非常に好調」といいます。 まずは手を動かす。失敗は「失敗しないこと」 渋谷関連グッズだけではありませんでした。ドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」の形をした「バケツ」も渋谷限定といいます。 「バケツは、元々は店内のモバイルフードショップ『渋谷タピモ』で、ポップコーンをバケツに入れて販売したら、すごく良いんじゃないかと思って作ったものなんです。ですが、ポップコーンなしで買いたいという人が沢山いたので、単品で販売するようになりました」(長谷部さん) 「思いついたらまずは手を動かして、どんどん実践していく感じなのですか?」と尋ねたところ「そうですね。思いつきから始まることがすごく多いんです」と長谷部さん。 「まずはやってみる。失敗は『失敗しないこと』だと思っているんです。失敗してもいいんです。挑戦しないことのほうが、私たちの会社にとっては悪なので、まずは挑戦してみて、ダメだった場合には、反省点を改善してまたやっていけば良いと思っています」 ドンペンが獲れる「UFOキャッチャー」の生みの親ドンペンが獲れる「UFOキャッチャー」の生みの親 長谷部さんは、ドン・キホーテのいくつかの店舗に設置されている、ドンペンが獲れる「UFOキャッチャー」の発起人でもあるといいます。 UFOキャッチャーはMEGAドン・キホーテ渋谷本店にも設置されている(2019年5月30日、高橋亜矢子撮影) 2015年当時、与野店(埼玉県さいたま市)で店長をやっていた頃、「お子様にとって、なにか面白いことができないかと考えたんです」と話します。 「UFOキャッチャーって、すごくワクワクドキドキするじゃないですか」(長谷部さん) 結果、子どもだけでなく、幅広い年齢層や国籍の人に刺さっている様子。取材当日も、同店1階に設置されたUFOキャッチャーの前ではしゃぐ女子高生や、興味深そうに挑戦する訪日外国人の姿がありました。ちなみに「ドンペン」に対し、特に熱狂的なのはタイの方なのだとか。 MEGAドン・キホーテ渋谷本店に赴任後、何度もトライエラーを繰り返したことには、「免税レジ」が挙げられるといいます。 「免税のお会計はすごく大変なんですよ。多言語の方がいらっしゃいますし、厳重に梱包する必要もあり、ひとり当たりの接客時間が、7、8分必要になってしまうんです。 それをいかにノンストレスに出来るか、1年半くらい失敗に失敗を重ねて、何回も何回もやり直しました。全国のさまざまな業態のお店を回って参考にしたり。特注でベルトコンベアーや梱包台を整備したり。 今ではだいぶ改善されて、並ばずに済むようになっています。……予算も使っちゃったんですけどね。顧客最優先主義として、必要投資だと考えています」 1年半というと結構な時間ですが、「しんどいってことは、ないですね」とも。 「我々の理念のなかには『仕事を”ワーク”ではなく”ゲーム”として楽しむ』というのがありまして。免税レジの接客時間の短縮を目指していた時は、改良してみたら、試しに時間を測ってみて、記録が更新できたら皆で喜んだりしながら、ゲーム感覚で楽しく進めていました」 23区への当日配送を行なっている23区への当日配送を行なっている そんな同店ですが、訪日外国人が多いことに加え、もう1つ特徴的なのが、身近な人の生活にも根付いていること。地下1階に降りると、生鮮食品を扱うコーナーが広がります。 生鮮食品を扱うコーナー(2019年5月30日、高橋亜矢子撮影) ほかの売り場同様に、特徴的なPOPが多数並ぶ同フロアでは「黒い値札が『驚安』の商品」。日によって対象が変わります。取材の日は、3玉入りのゆでうどんが49円(税抜)、野菜ジュースが38円で販売されていました。 「渋谷区と目黒区には、生鮮食品の『当日配送』(当日受付20時まで)も行なっています。たとえば朝、出勤前にお店に寄って商品を選んで、帰社後に自宅に届くようにする……ということが可能なんです。 ちなみに生鮮食品以外であれば、23区内への当日配送も出来ます(当日受付18時まで)。配送自体は他店舗でも実施していることがありますが、23区全域が対象なのは当店だけの特徴です(※2019年5月30日時点)。ペットボトルや生活用品などを大量に買った時などに、便利かと思います」(長谷部さん) ドン・キホーテ系列店舗で利用できる電子マネーサービス「majica(マジカ)」アプリの登録者であれば、5000円以上の買い物で、コンテナ1個分(縦36cm、横53cm、高さ32cm、15kg以内/渋谷区、目黒区はコンテナ3個分)無料で配送するそうです。 「我々の温度感がぬるくなるようなことはありません」 取材を終え、ドン・キホーテ各店に足を踏み入れた時に感じる、謎の高揚感の正体が少しわかったように感じた記者。最後に今後について聞いたところ、「我々の得意分野は夏なんですよ!」と頼もしい一言が飛び出しました。 「その後にも、増税や我々が大得意とするハロウィンがあり、毎月イベントのような感じなので、我々の温度感がぬるくなるようなことはありません」 今度行く際にはぜひ、各店舗ごと、各季節ごとの違いも楽しんでみてください。店内を流れる、「ドン・ドン・ドン・ドンキ」の歌詞でおなじみのテーマソングで歌われるように「気分は宝探し」な時間を楽しめるはず。 ※2019年5月30日時点での情報です。商品の取り扱いや価格は変更になる場合があります。 ●MEGAドン・キホーテ渋谷本店 ・住所:東京都渋谷区宇田川町28-6 ・アクセス:各線「渋谷駅」から徒歩4分 ・営業時間:24時間 ・定休日:年中無休
- 未分類