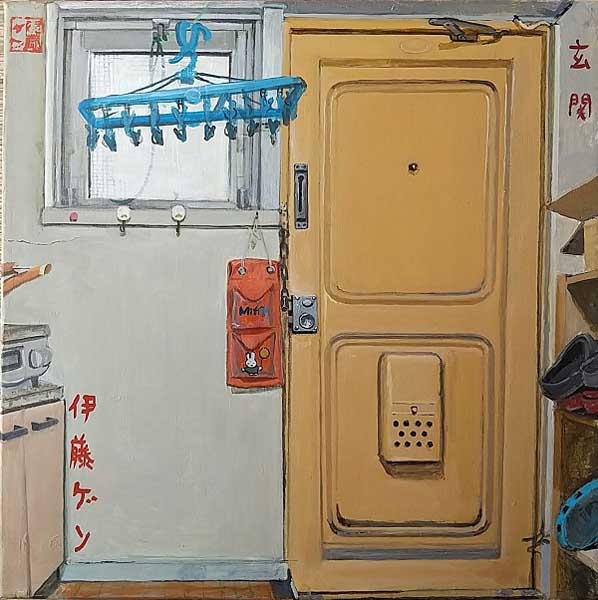コーヒー1杯162円! 日本初のカフェ月額定額制、11月スタートの新サービスとは
4月から始まった日本初のカフェ月額定額制サービスに、新プランが加わりました。日本初のカフェ月額定額制サービス ITベンチャーの「Same Sky(セイム・スカイ)」(渋谷区渋谷)が2018年4月から提供する日本初のカフェ月額定額制サービス「CAFE PASS(カフェ・パス)」が注目を集めています。 「CAFE PASS」の利用イメージ(画像:Same Sky)「CAFE PASS」は同社と提携するカフェのコーヒーなど(アルコールは不可)が毎月規定された杯数まで飲める会員サービスで、都内では代々木上原や神楽坂、三軒茶屋などの計25店(2018年12月11日現在。全国では44店)と提携しています。 新プランは毎月3杯で900円 サービスプランは「CAFE PASS 30CUPS」と「CAFE PASS・LIGHT」のふたつ。「CAFE PASS 30CUPS」は毎月30杯のコーヒーなどが月額4860円で利用できます。1杯あたりの価格は162円。現在の同プラン利用者の7割は30代で、6割は女性だといいます。 11月2日(金)からスタートした「CAFE PASS・LIGHT(ライト)」は毎月3杯で900円。同日にプラン開始をインターネットで発表したところ、その手軽さに注目が集まり「開始2時間弱で、すでに十数人の申し込みがあった」(代表の二方隼人さん)といいます。 サービス当初のターゲットは、頻繁に同じ店に通い詰める「コーヒー好きの人」でしたが、提携店にヒアリングを行ったところ、ときどき店を訪れる人の数が予想以上に多いことが分かり、3杯というプランを新たに設定したといいます。 サービス提携店には接客の質も求めているサービス提携店には接客の質も求めている サービスの登録は現時点でホームページを通じてのみ。登録後はスマートフォンの注文画面を見せるだけで商品を受け取ることができるキャッシュレス方式を採用しています。 サービス登録と利用のプロセス(画像:Same Sky)「CAFE PASS」とコーヒー店の提携条件は個人店、もしくは10店舗以内の法人店であること。コーヒーの質はもちろん、接客も重視しているといいます。さまざまな業界で加速する定額制サービスですが、「CAFE PASS」がコーヒー業界初となったのは、次の理由によるものです。 「コーヒーはお酒のように同じものを何杯も頼まず、基本は1杯のみです。そのため、客単価などの観点から参入する他社がいなかったのです」(二方さん)。 2018年までに会員1000人目指す 同社では年内までに「CAFE PASS・LIGHT」の会員1000人の獲得を見込んでおり、今後は「CAFE PASS 30CUPS」への移行を視野にビジネスを進めていくとしています。 また、コミュニケーションアプリ「LINE」を使った課金プラットフォームもこれから構築していくそうです。
- ライフ