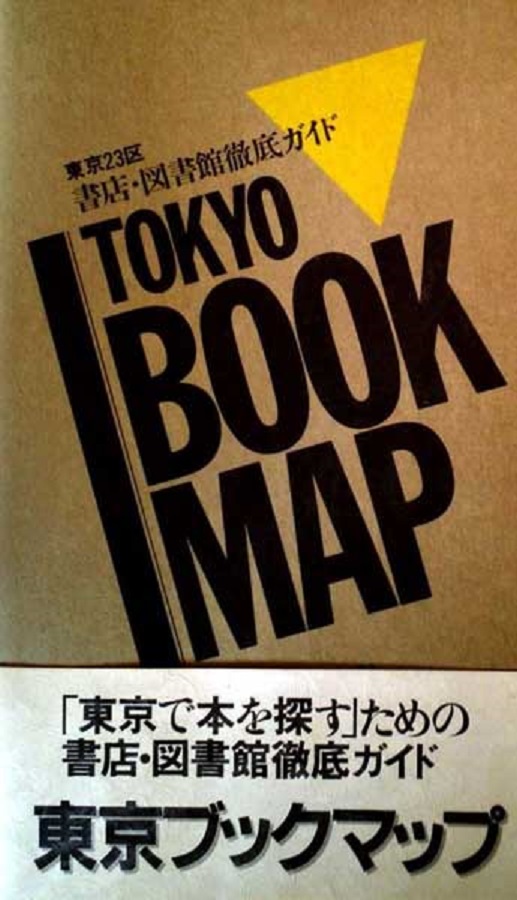おひとりさまブームに逆行? 「バーチャル家族」付きモデルハウス誕生、仕掛人の切実な狙いとは
「モデルファミリー付きモデルハウス体験会」なるイベントが、2019年11月17日(日)に行われました。主催企業いわく「現在は家族を持っていない人に、家族と暮らす幸せを感じてもらう」のが目的だそう。ついに疑似家族サービスまで登場した「令和スタンダード」に度肝を抜かれつつ、現地を取材してきました。赤の他人3人による家族団らんとは果たして…… PR会社から送られてくる膨大な数のイベント情報メールを眺めていたところ、異様な異彩を放つタイトルが目に留まりました。 「家族とのリアルな生活体験ができる 世界初、『モデルファミリー付きモデルハウス』」 ……モデルファミリー付きモデルハウス? 何でも、役者さんが演じる妻と娘(7歳)が出迎えるモデルハウスで、参加者(30代前後の未婚男性を想定)が父親役になりきって、家族とマイホームで過ごすことの喜び・楽しさを味わう「リアルなバーチャル家族体験サービス」なのだそう。 ついに時代は疑似家族を提供するまでに至ったのか。果たしてどんな男性がイベントに申し込んでくるのか、そしてバーチャル妻子とどのような時間を堪能するのか――。これは取材せずにはいられません。 イベント開催日は2019年11月17日(日)、「家族の日」という手の込みようです。現地で目撃した疑似家族3人によるのほのぼの団らんの様子をレポートします。 真新しい注文住宅で団らんするこの3人。とても他人同士には見えないはず(2019年11月17日、遠藤綾乃撮影) 国分寺駅から徒歩10分ほどのところに建つ、端正なたたずまいのモデルハウス(小金井市貫井北町)。応募多数により厳正なる抽選で選ばれた5人の男性たちが、順繰りに現地入りして約20分間の疑似家族体験を行います。ちなみに参加費は無料です。 そのなかのひとり、江戸川区在住27歳の会社員男性は、日曜日にもかかわらず几帳面にスーツ姿で登場。 両親との3人暮らし。未婚。恋人はおらず、目下募集中なのだそう。 「ツイッターでこのイベントの告知を見つけて、家族や家庭という体験を一度はしてみたいと思って応募しました。自分が将来、必ず家庭を持てるという確信はないので……」 ちょっと意味深な参加動機を言い残し、モデルハウスのおしゃれな木製ドアを開けバーチャル妻子の待つ家の中へと足を踏み入れていきました。 貞淑で清楚な妻と、爛漫なひとり娘による「おもてなし」貞淑で清楚な妻と、爛漫なひとり娘による「おもてなし」娘「パパ、おかえり!」 妻「おかえりなさい、あなた。買い出しありがとうね」 おてんば全開な愛くるしい娘と、清楚で品のある美人な妻。絵に描いたような妻子ふたりが玄関で「夫(参加者)」を出迎えました。 男性はふたりに導かれるように家へ上がり、玄関で靴の片づけをすることでシューズクローゼットの広さを、2階の洗面所で手を洗うことで水回りの清潔さを、つまりこの家の作りの良さを次々に見せつけられていきます。 モデルハウスは2階建ての2LDKで土間・書斎スペース付き。延床面積は、1、2階それぞれ45.54平方メートルとややコンパクトなサイズですが、2階の台所ど真ん中にしつらえられたアイランドキッチンに、リビングでくつろぐのにちょうどいいL字型ベンチと、若い夫婦と子どもの楽しい暮らしを彩ってくれそうな設備が満載です。 さらに階段の踊り場には、娘が宿題をしたり夫婦が本を読んだりできる書斎スペースも。収納も豊富で、空間を生かした設計が随所に光ります。 夫(参加者)は、娘の算数の宿題を見てあげて「すごーい! パパ天才!」とほめられたり、妻に「ねえパパ、1杯だけ飲んじゃおっか?」と誘われてビール片手にバルコニーでくつろいでみたり。とにかく家じゅうの機能をフルに利用しながら家族の日常を体験。 踊り場の書斎スペースで、娘の宿題を見てあげる参加者。「パパ天才!」とほめられて、すっかり父親気分である(2019年11月17日、遠藤綾乃撮影)妻「今日は外は寒かったでしょ? その点、この家は気密性が高いから冬も温かく過ごせるのよね」 妻「ダイニングのテーブルを移動させて、パーティー仕様にセットしましょう。使い勝手がいいように建築士さんが考えてくれたデザインなのよ」 妻「このバルコニー、車通りに面しているのにそんなにうるささを感じないわよね。屋根部分が半分吹き抜けになっているおかげで開放感もばっちり」 このように、妻がちょいちょい差し挟んでくるモデルハウスの宣伝用台詞に若干戸惑いを覚えつつも、夫(参加者)は妻子との触れ合いにすっかりデレデレの表情です。メディア関係者やスタッフたちは、3人の団らんを邪魔しないよう別室のモニター越しに彼らの様子をウオッチ。 夫(参加者)「頭いいんだねー、カスミ(娘)は。きっとママに似たんだね」 そうしみじみ語る優しげな笑顔は、もはや7歳の娘を持つ父親そのものだったかもしれません。 未婚率が伸びるなか、住宅販売も「体験型」「コト消費型」へ未婚率が伸びるなか、住宅販売も「体験型」「コト消費型」へ ちなみに、参加者は独身男性ばかりと思いきや、既婚男性もちゃっかりいらっしゃっていて仰天(ぎょうてん)しました。「妻に内緒で疑似家族体験しに来ちゃいました(笑)。子どももいますよ。バレたら怒られちゃうかもしれませんねー」と話すのは東大和市在住の男性会社員(37歳)。むしろこちらがひやひやしてしまいます。 とはいえメディアの取材に顔出しOKをくれる度胸から察するに、きっと日頃から家族仲は良いのでしょう。「いやあ、マイホームを買う予定は今のところすぐにはないですけど、今回の体験はとても楽しかったですよ」と、満足した様子で会場を後にしました。 冒頭に紹介した27歳の未婚男性は、20分間の家族体験を終えるとほんの少しだけ頬を紅潮させて、始まる前よりちょっぴり饒舌に語ってくれました。 「妻役と娘役、おふたりの演技力がすごく高くて、気持ちよく家族になりきれました。……結婚することとか子どもを持つこととか、マイホームを買うことに対しては、僕らの世代はどちらかというと悲観的だと思います。生まれたときからずっと不景気で、景気のいい時代を経験していないからです。家を買ったら30年、子どもを産んだら20年、重い責任が発生しますよね。そんなにも長い時間、仕事に就き続けて十分な収入を得続けられるのか……、そう考えるとやっぱり尻込みはしてしまいますよ」 それからこうも付け加えていました。 「……でも、そうですね。今日の体験はとても貴重でした。自分が一生巡り合わないかもしれないと思っている、とても『きれいな世界』でした」 20分間の体験の後には、記念の「家族写真」を撮影。参加者たちは「妻子」との別れを名残惜しんだ(2019年11月17日、遠藤綾乃撮影) この体験会を行ったのは、東京で注文住宅の建築設計などを担うリガード(国分寺市本多)。モデルハウスももちろん自社のものです。代表取締役の内藤智明さんは、開催に合わせて、 「生涯未婚率が上がり少子化が進む現代社会でわが社は、マイホームを持つことの喜びだけでなく『家族と過ごすことの幸せ』も実感していただきたいと考えます。今回の体験会を通してマイホーム・マイファミリーのある未来を想像していただけたらと思っています」 とのコメントを寄せました。 同社マーケティング事業部部長の高谷一起さんが言葉を継いで、 「未婚者が増え続けるとされる今後、ファミリー用の注文戸建ての市場も厳しくなっていくことは再三指摘されています。だからといって、室内設備のスペックを高めれば消費者の歓心を引けるとは考えません。本当に必要なのは、家族と過ごすかけがえのない時間を体験すること。それは、普通のモデルハウス見学ではまず得られないものだと思います」 つまり住宅販売においても、いわゆる「体験型」とか「コト消費」といった視点が、欠かせない時代になったということのようでした。 今回、世界で初めて開かれた(※リガード調べ)、バーチャル妻子付きモデルハウス体験会。参加した男性たちの感想を聞くと、必ずしも住宅購入につながる様子ではありませんでした。しかし「得難い体験をした」と感じられたことは間違いないようです。 結婚やマイホーム購入に消極的な若者層や、悠々独身生活を謳歌するミドル層。彼らの人生にこの先ふいに違う選択肢が現れたとき、家庭やマイホームを持つことの魅力をわずかでも感じた経験があるのなら、新しいステージへ踏み出す後押しに、あるいはなり得るかもしれません。
- ライフ