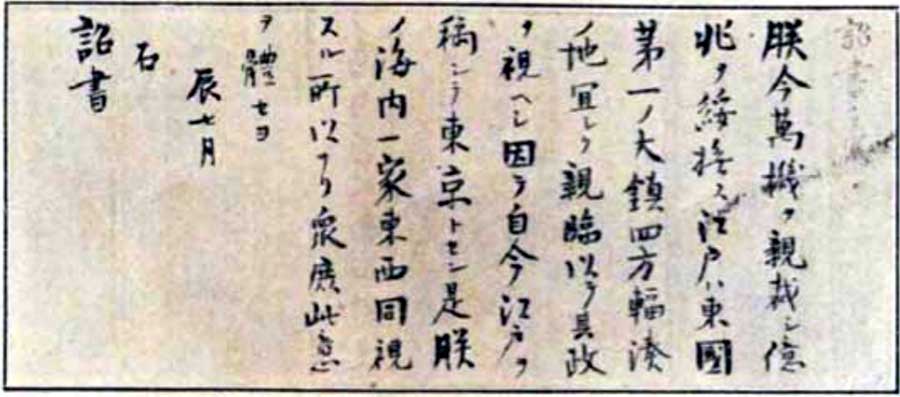高級ブランド街の謎――なぜ東銀座駅はあるのに「西銀座駅」はないのか
商業施設に残る「西銀座」の名前 日比谷線と浅草線の2路線が乗り入れる東銀座駅(中央区銀座4)。その名のとおり、銀座駅の東側にあります。 さて、ここでひとつ疑問が湧いてこないでしょうか。東銀座駅はあるのに、なぜ西銀座駅はないのか――と。 幸いなことに(?)、西銀座の名称が付いた商業施設は存在します。そう、西銀座デパートです。東京高速道路の高架下にある商業施設の名称として広く知られています。一角にある西銀座チャンスセンター(同)は、年末ジャンボ宝くじを買い求める人で毎年行列ができます。 そんな西銀座チャンスセンターの売り場前にある地下鉄入り口(現在は閉鎖中)を下っていくと現れるのは、丸ノ内線銀座駅。 実はこの丸ノ内線銀座駅は、かつて西銀座駅という名前だったのです。ご存知でしたか? そうとなると、俄然気になるのは駅名変更の理由と東・西の由来です。 西銀座駅と「銀座西」 現在の丸ノ内線銀座駅は、1957(昭和32)年12月に開業しました。当時は、現在のように晴海通りの下で銀座線の駅と接続していませんでした。 東銀座駅(画像:写真AC) 銀座線銀座駅は銀座4丁目の交差点の下付近、対して丸ノ内線銀座駅は数寄屋橋付近と少し離れていたことから、当初は別の駅ということで西銀座駅と命名されました。 西銀座駅の命名理由は、銀座駅から見て西に位置しているだけではありません。現在の東京高速道路に沿って「銀座西」という地名が存在していたからです。銀座西の地名は現在の銀座2丁目から銀座5丁目まで南北に長く延びており、1丁目から5丁目まで存在していました。 地名自体の命名理由は1930(昭和5)年に銀座5丁目~8丁目が設置された際、その西側に位置していたことに由来します。 ただ、正式名称は銀座西にも関わらず、呼びやすいという理由で「西銀座」などという呼称で呼ばれることの方が多く、結果として、より広く知られている呼称が採用され、西銀座駅になったとされています。 そんな正式名称の銀座西ですが、住居表示の実施により、1968年に姿を消しました。 西銀座駅の呼称が使われた期間は1957年から1964年までと短く、同年8月に日比谷線が開業して3路線の駅が接続したことから、西銀座駅は銀座駅に改名されました。 東銀座駅と「銀座東」東銀座駅と「銀座東」 一方、東銀座駅の開業は1963年2月。駅名は銀座駅の東にあることに加えて、当時の地名が「銀座東」であり、銀座東には「東銀座」という呼称があったことに由来します。 東銀座という呼称は今でもよく使われますが、一度も正式な地名になったことはありません。東銀座駅ができてから定着していったのです。 東銀座の示す範囲とは ここまで論じてきて、さらに疑問なのは、東銀座はどこからどこまでが範囲なのかということ。南北は、 ・北:昭和通りの新京橋交差点付近 ・南:蓬莱橋交差点から浜離宮付近まで ということに異論はないでしょう。 それでは東西はどうでしょうか。 「昭和通りの東は築地で、銀座ではない」と考える人もいます。歌舞伎座辺りは住所では銀座4丁目ですが、ここは築地というわけです。 銀座東の地名が存在したのは、1951年から1969年までです。 1970年前後の銀座周辺の地図。銀座西、銀座東の地名がある(画像:国土地理院) この地名が決められたのは、銀座を南北に流れていた三十間堀川が埋め立てられることになった際、銀座と地続きになった旧木挽町などの住民が、銀座西に対する形で銀座東を要望したためでした。 現在では木挽町の方が趣のある地名のような気もしますが、当時は銀座という地名になることがステータスだと考えられていたのです。 そして駅も完成し、銀座が東西に広がったことで、中央通りに沿った南北の繁華街以外にも人の流れができるようになり、銀座の街は拡大していきます。 「最先端の街」だった西銀座「最先端の街」だった西銀座 とりわけ発展著しかったのが西銀座です。 西銀座駅が開業する前の1957年5月、有楽町駅を挟んだ千代田区有楽町1丁目に百貨店のそごうが開業。集客効果を狙ったフランク永井の『有楽町で逢いましょう』は、大ヒットソングになります。 さらに翌1958年5月には、同じくフランク永井の歌う『西銀座駅前』がリリースされ、こちらもヒット。7月には日活製作で同名タイトルの映画が公開され、西銀座駅周辺の風景が数多く映し出される、街そのものの宣伝ともいうべき作品になっています。なお、前出の西銀座デパートの開業は、この年の10月です。 こうして西銀座は「最先端の街」として知られるようになりますが、現在はその名を聞くことはあまりありません。その理由は、西銀座駅が銀座駅になったことで、西銀座の周囲が本来の銀座の「延長線」として認識されるようになったからでしょう。 左から旧銀座西エリア、本来の銀座エリア、旧銀座東エリア(画像:(C)Google、弘中新一) こうして見ると、鉄道駅の存在が街のイメージ作りに、実に深く関係していることがわかります。
- 未分類