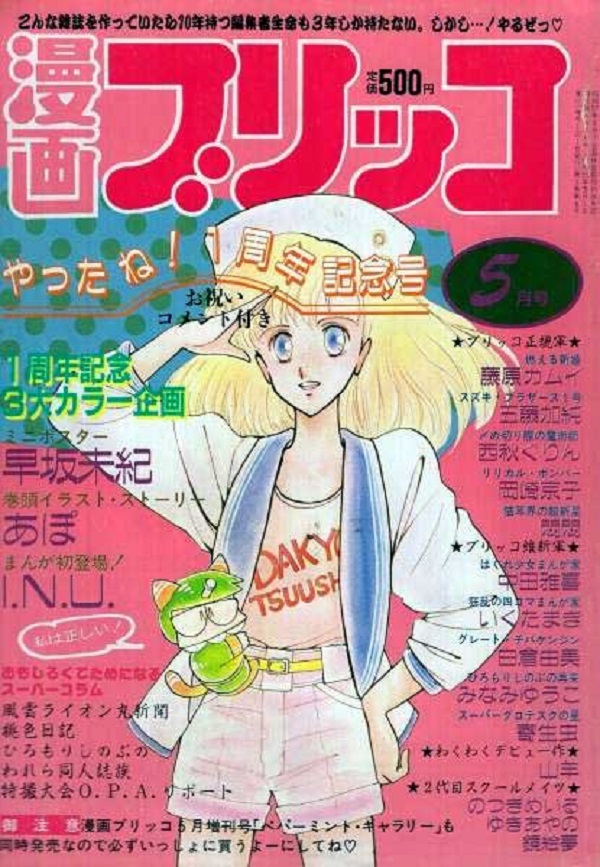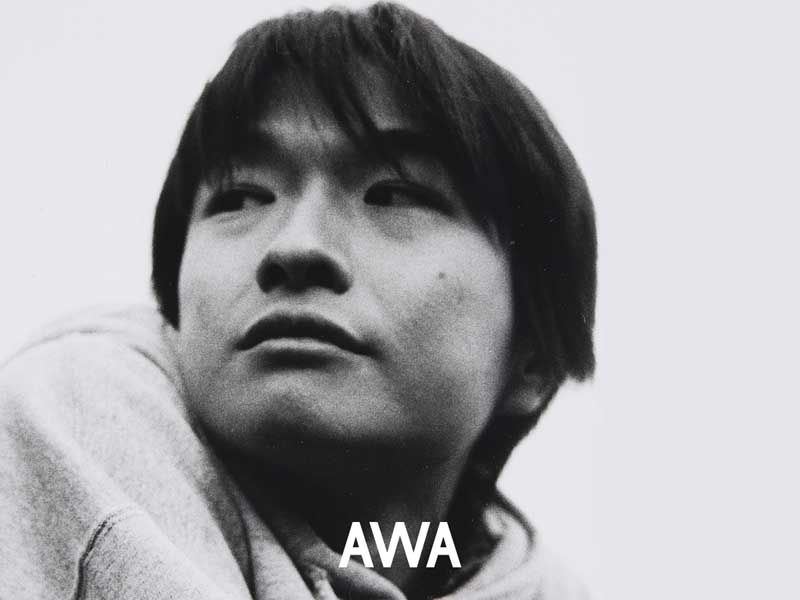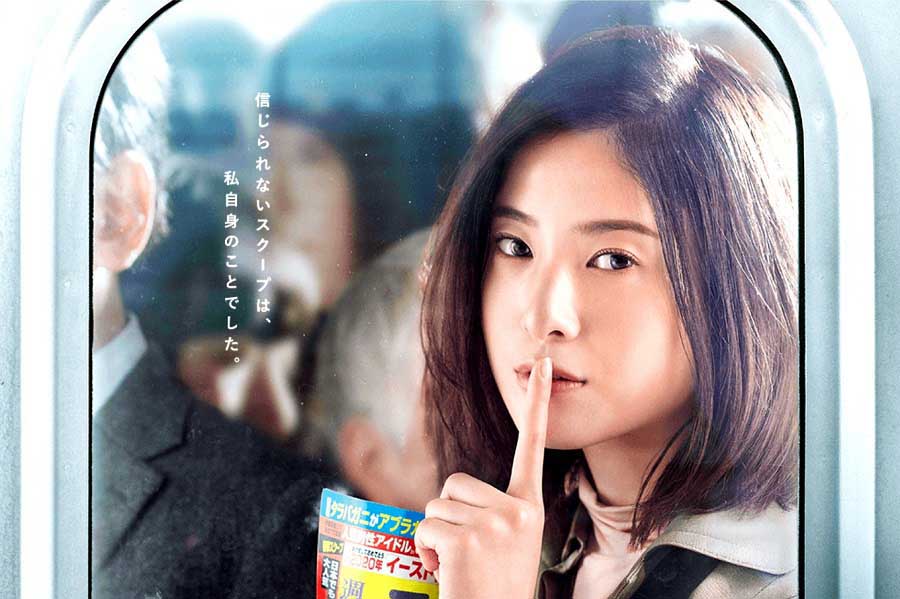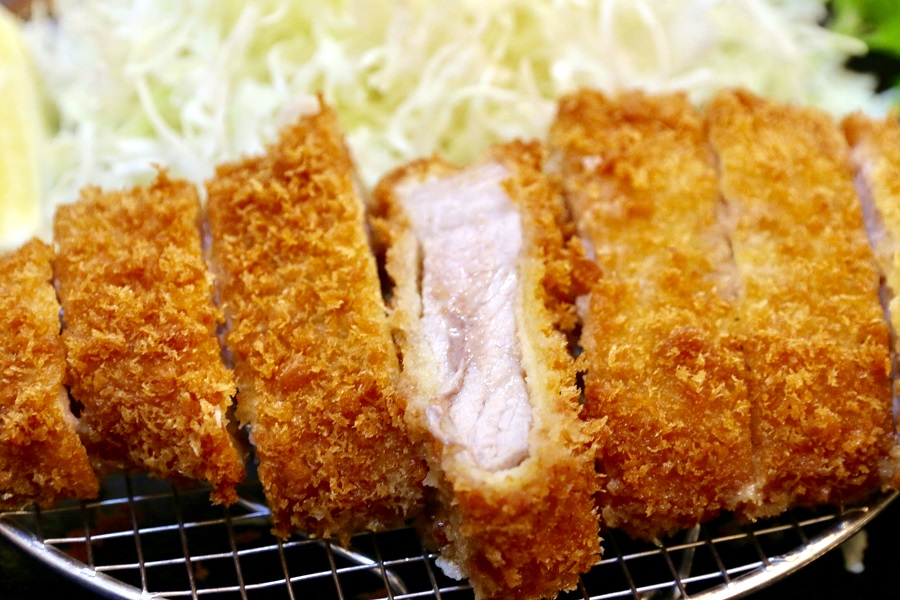コロナ禍で大学サークルの「恋愛カースト」が崩壊 「イケメン = モテる」時代は完全終了か
大学生の恋愛に「地殻変動」 大学生にとって友人や恋人を作るための出会いの場といえば、「サークル」を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。100人規模の大講義では親しい相手を見つけられなくても、サークルなら毎日のように顔を合わせられる仲間内。それゆえ恋愛感情も芽生えやすい環境です。 そんな「サークル」内の恋愛事情にも、新型コロナウイルスは意外な影響を与えていました。 Z世代(1996~2012年に生まれた若者たち)の流行や価値観について調査・分析している私たち「Z総研」が、東京在住の女子大生たちから聞いたお話を紹介します。 モテる男子は、外見や肩書 新型コロナ以前、普段の日常におけるサークル内の「モテる男子」といえば、サークルの代表や副代表などの役職に就いていたり、イケメンだったりノリが良かったりと分かりやすい特徴がある人たちでした。 入会して間もないかわいらしい1年生の女の子を年上の副代表の男子が早くも彼女にしていたり、サークル内に歴代の彼女が何人もいるイケメンがいたり。モテる男子というのは、サークル内である程度決まっていたものです。 大学のサークル内恋愛に、新型コロナがもたらした意外な影響とは?(画像:写真AC) 皆さんは、かつて中学・高校などの学校現場について盛んに使われた「スクールカースト」という言葉をご存じでしょうか。 ひとつのクラスの中には目立つ子、目立たない子がいて、生徒同士が互いに値踏みし合い、集団の中でランク付けし合うこと――。『教室内(スクール)カースト』(光文社新書、2012年)ではそのように解説されています。 価値基準が変化したモテ要素価値基準が変化したモテ要素 大学生ともなると中学・高校のときのような、いわゆるいじめなどの行為は減る傾向にありますが、一方で集団におけるランク付けや「ヒエラルキー」は依然として残っているようです。 そんなに注目されていなかった男子がサークルの代表になったとたんにモテ出したり、サークルの活動には熱心でなくても飲み会ではいつも目立つイケメンが妙に人気があったりというのは、規模の大きいサークルでは特に、しばしば見られる光景ではないでしょうか。 しかし2020年春、新型コロナウイルスの感染が広がり、緊急事態宣言が発令され、大学のサークルもまたリアルな活動の場が失われました。サークルの飲み会はテレビ会議システム「Zoom」で行われるようになり、遊びの場はゲームなどオンラインでのやり取りへと移行。 このことが、サークル内の“力関係”にまで微妙な変化を及ぼしたのです。 一体なぜでしょうか。 今までサークルでモテていたのは、役付きやイケメン、ノリのいい男子。それがコロナの影響で……(画像:写真AC) Zoom飲みで場を取り仕切るのがうまいのは、必ずしも代表とは限りませんし、イケメンがオンラインゲームが得意とも限りません。 オンライン独特のコミュニケーションを取るのがうまい人がだんだん注目され始め、サークル内での立場などはあまり気にされないものへと変化していきました。 ……と言うと、「ただ単にヒエラルキーの基準が、サークル内のポジションからオンラインスキルに変わっただけなんじゃないの?」と指摘されてしまいそうですが、どうもそれだけではないようなのです。 Zoom飲みで画面に映し出されるのは、多くの場合サークルメンバーたち自身の部屋という、最もプライベートな一面。どういう部屋に住んでいるのかを知ったことで意外な親近感が湧いたり、興味を持ったりするようになるそうなのです。 初めて目を向けた相手の内面初めて目を向けた相手の内面 例えば、とても清潔に保たれた室内、リラックスした表情、飼い猫に優しく接するしぐさ、派手ではないけれどこだわりを感じさせる品のいいインテリア。 あ、この人こんな一面があったんだ。そういえばサークルでも、あんまり自己主張はしないけど誰にでも親切にしていたな……。そんな、今まで目を向けることのなかった相手の意外な一面を知ることがとても新鮮で、コロナ以降、もっと相手の中身・人間性を知りたいと思うようになったと、都内のある女子大生は打ち明けてくれました。 Zoomを通して初めて見た男子の部屋。オンラインでのコミュニケーションが、相手の内面に目を向けるきっかけになった(画像:写真AC) 大学生の恋愛におけるこうした「地殻変動」は、別の場面でも見受けられます。 例えば連絡の取り方。 リアルに会えなくなったコロナ以降、連絡手段のメインはLINEになり、連絡の頻度もより重要なものへと変化しました。 コロナ以前までモテていたイケメンは、現実で会えていたときなら、LINEが多少雑でも「イケメンだしいっか」と許されていたそうですが、なかなか会えなくなってしまった現状では、そうもいかないようです。 LINEでの会話のペース、電話の頻度などの価値観が一致しないことで“コロナ破局”してしまったカップルもいるそうで、オンラインでのコミュニケーションというのはコロナ禍でさらに必須のモテ要素へと格上げされたようです。 オンラインだけでつながるからこそ見えてくる、その人の性格や内面、価値観というものがあります。役職や外見に捉われず「その人自身」を見る機会が増えたことで、見た目というのは以前と比べるとそれほど重要ではなくなりました。 厄災でしかない新型コロナウイルスが、若い世代にもたらした意外ともいえる“気づき”です。 さて、そうなると、「カワイイは正義」や「ただしイケメンに限る」などのネットスラングに代表される外見偏重主義や肩書至上主義などは、今後は無くなっていくのでしょうか。 どうやら、そう簡単にはいかないようです。 実際に会ったらギャップが…実際に会ったらギャップが… 女子大生たちにさらに突っ込んで話を聞いてみると、どうもオンラインと現実のギャップというものも生まれているようです。 2020年7月下旬現在、東京を中心に再び新型コロナ感染者数が増えているとはいえ、緊急事態宣言の頃に比べれば実際に会える機会は徐々に増えてきていました。 すると、オンラインでのやり取りでは仲良くなったものの実際に会ってみたらLINEとは雰囲気が違った、とか、LINEではよく話す人だったのに実際には人見知りでなかなか話が弾まなかった、とか、オンラインの画面越しでは分からなかったけど想像していたより身長が低くてギャップを感じた……とか。 自粛が解けた頃、ようやくリアルで会ってみたら「あれ? なんか違う?」と感じることも(画像:写真AC) 実際に会える機会が出てきたことで「あれ? なんか違う?」と感じてしまうことも多々あるのだとか。 画面越しのふたりが長い自粛期間を経てようやく会えたというのに、ちょっと皮肉な結果と言えそうです。 オンラインでは築けないもの 新型コロナウイルスの感染拡大により、誰かと実際に会うことというのは、ハードルが高いものになってしまいました。オンラインでの交流の機会が増え、LINEなどのコミュニケーションツールは以前よりモテに直結する要素に変わったと感じます。 実際に今でもサークル活動を自粛している団体がほとんどだと、都内に住む女子大生は話していました。 しかし、やはり恋愛関係とは実際に会ったときのフィーリングこそが重要になってくるものであり、オンラインでのコミュニケーションには限界があります。 恋愛に限らずどんな人間関係も、あくまで現実の世界でこそ築くものなのです。 大学生たちの恋愛の行方は?大学生たちの恋愛の行方は? これから先、大学生たちの価値観はどのように変化していくのでしょうか。 今度こそコロナが収束し、かつてに近い日常へと戻っていったとき、以前と変わらない恋愛作法へと回帰していくのか、はたまた違った恋愛の仕方に変わっていくのか――? オンラインを通じて「相手の内面」の大切さに目を向けたことは、たとえその後リアルでのギャップを感じたとしても、彼らにとっては非常に重要な気づきとなったと言えそうです。そんな彼らの動向に、これからも注目せざるを得ないでしょう。
- ライフ