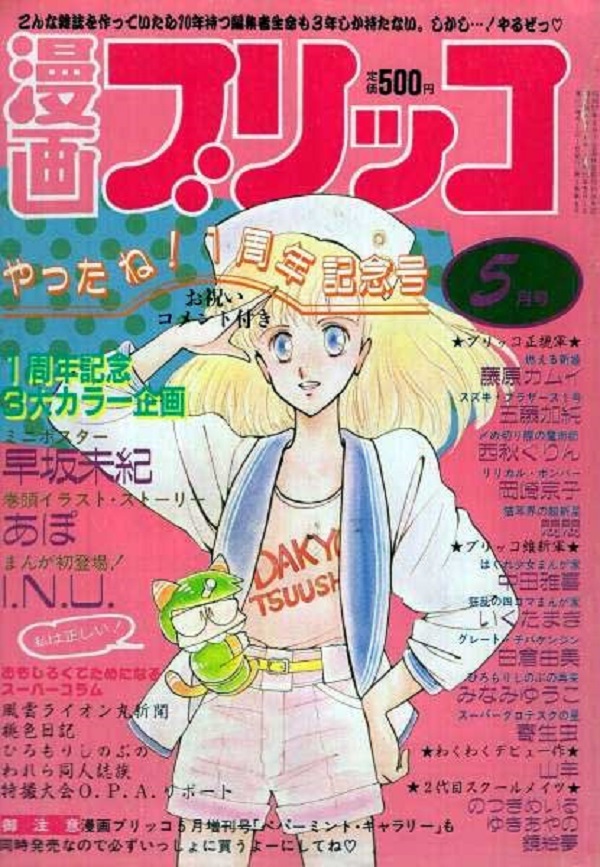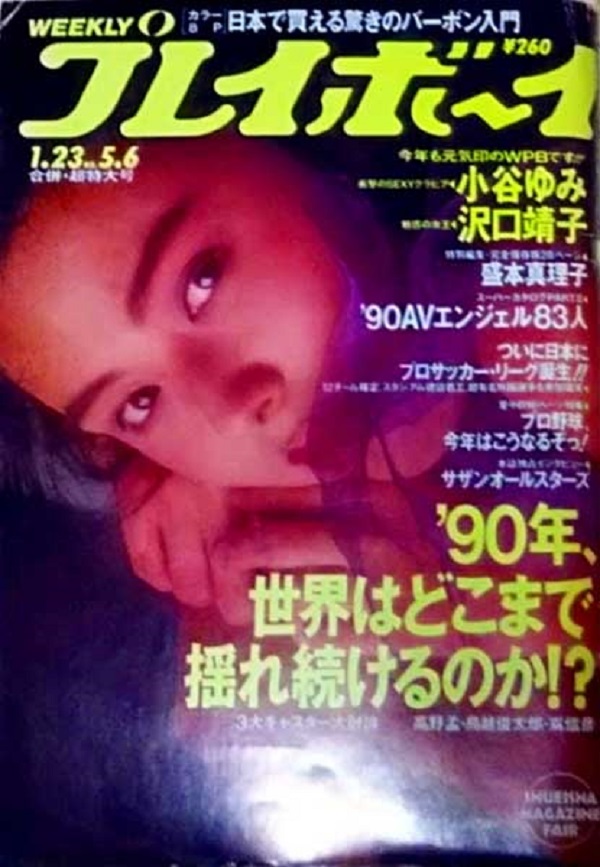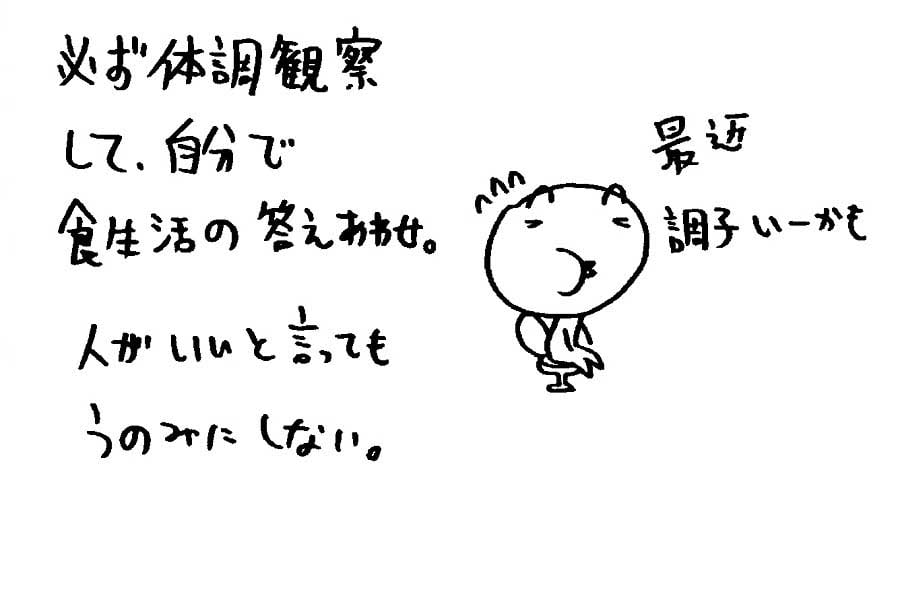サンシャイン水族館が4月に日本最大級の「クラゲ水槽」をわざわざお披露目するワケ
動物園・水族館に迫る困難 東京都は現在、葛西臨海公園内にある葛西臨海水族園(江戸川区臨海町)の改修計画を進めています。 1989(平成元)年に開園された葛西臨海水族園は、クロマグロが群をなして游泳する様子が見られる巨大水槽が目玉になっています。また、建築家・谷口吉生(よしお)さんがデザインしたガラスドーム屋根も葛西臨海水族園の人気に一役買っています。 ハード・ソフトの両面で創意工夫が凝らされた葛西臨海水族園は、これまで約5500万人の来園者を集める人気施設として親しまれてきました。 サンシャイン水族館のクラゲの様子(画像:写真AC) その一方、昨今はレジャーの多様化が進み、動物園・水族館はあらゆる面で難しい時代になってきているともいわれます。 運営の民営化で維持費がネックに 先日、兵庫県神戸市の須磨海浜水族園が民営化を発表。民営化移行に際して、入園料が3倍以上に値上げされるとの報道もなされました。 また、大阪府岬町のみさき公園は遊園地・動物園・水族館などを一体化した複合レジャー施設ですが、経営不振などを理由に運営元の南海電鉄(大阪市)が撤退を表明。引き継ぐ事業者が現れなかったことから、2020年3月末の閉園が決まりました。 動物園・水族館は生き物を扱います。機械のアトラクションが多くを占める遊園地とは異なり、動物・魚などの体調管理には人一倍気を遣わなければなりません。 そうした動物・魚などの体調管理のため、飼育員を削減することは難しく、人件費がかかります。また、早朝・夜間などの閉園中でも、動物・魚のために空調・水質の管理は怠れません。そのため、水道代・電気代などもかかり、施設の維持費なども膨大になります。 須磨海浜水族園のミノカサゴ(画像:写真AC) 特に、逆風にさらされているのが水族館です。動物園とは異なり、水族館の展示は魚がメインになります。 人気のペンギン・アシカ・ラッコ・クジラ・イルカ・シロクマは大きな集客力を持ちますが、マグロやイワシといった魚類は一般的に見た目の違いや生態の違いがわかりづらく、水族館のメインターゲットでもある“子ども”には響きにくいコンテンツでもあったのです。 マンボウやウーパールーパー展示で人気にマンボウやウーパールーパー展示で人気に しかし、近年は“大人”を対象にした水族館も増えつつあります。 1978(昭和53)年にオープンしたサンシャイン水族館(豊島区東池袋。オープン当初は、サンシャイン国際水族館)は、デートスポットなどを取り上げる情報誌でも頻繁に扱われまる存在でした。 池袋駅から徒歩10分ほどの距離という立地も手伝って、若者を中心にサンシャイン水族館は人気を獲得してきました。 サンシャイン水族館の場所(画像:(C)Google) その一方、サンシャイン水族館はビルの中にあるために大型水槽を設置することが難しいという泣きどころがありました。 そのため、巨大な魚を展示するのではなく、マンボウやウーパールーパーといった展示する生き物を工夫。珍しい生物は話題を集めることにもなり、それが集客にもつながりました。 逆境を跳ね返すサンシャイン水族館 そんな工夫を重ねたサンシャイン水族館は、2020年4月にクラゲの巨大水槽を新たに設置する計画を発表しました。 「海月空感」の4月オープンを告げるサンシャイン水族館のウェブサイト(画像:サンシャインエンタプライズ) これまでにもサンシャイン水族館はクラゲのトンネルといったクラゲを十二分に楽しめる展示をしていました。新設されるクラゲ水槽はクラゲの魅力をさらに引き出すもので、幅が約14mと巨大で、国内最大級をうたっています。 スケールの大きなクラゲ水槽は、来館者に迫力を感じさせることは間違いありません。水槽の中をたゆたうクラゲの姿は幻想的で、ストレスの多い現代社会において、新たな人気スポットとして期待されています。クラゲの生態は、いまだ謎の部分も多く、それゆえに神秘的でもあります。そうした謎に満ちた部分も、クラゲに魅了される人が多い理由のひとつです。 一大旋風を起こすクラゲ一大旋風を起こすクラゲ サンシャイン水族館にはクラゲ水槽があるにも関わらず、新たにクラゲ水槽を新増設するのは、なぜでしょうか? 実は、水族館業界ではクラゲが一大旋風を起こしているのです。 クラゲは魚ではなく、プランクトンの一種とされています。クラゲは脳を持たず、ゆえに自分で考えて行動することはありません。クラゲは海の中を泳いでいるように見えますが、実はクラゲは水流に身を任せているだけです。泳いでいるわけではありません。また、エサを食べることも生殖も、自分の意思によるものではなく、条件反射によるものと考えられています。クラゲは、特に「何もしない」「何もしていない」生き物なのです。 そんな、ただ浮遊するだけのクラゲを水族館業界のアイドルに押し上げたのが、山形県鶴岡市の加茂水族館と言われています。加茂水族館は長らく経営難が続いていましたが、クラゲの展示で息を吹き返しました。 クラゲブームを起こした山形県鶴岡市の加茂水族館(画像:写真AC) そして、いまや鶴岡のみならず山形県を代表する観光スポットになり、全国から多くの観光客を呼び寄せています。 2020年はクラゲブームが起こる? 加茂水族館のクラゲ人気は、とどまることを知りません。加茂水族館から火がついたクラゲ人気は、日本各地の水族館にも飛び火していきました。神奈川県藤沢市の新江ノ島水族館や愛知県名古屋市の名古屋港水族館でも“クラゲ”をウリにした巨大水槽を設置。クラゲは集客の目玉になっているのです。 これまで、クラゲは面白みに欠けるとされてきました。しかし、時代の変化からじわじわと人気を上昇させてきました。特に人気になっているのは、ミズクラゲです。数多くのクラゲの中でも、ミズクラゲはもっともポピュラーなクラゲとして知られますが、その形状や色、海を漂う様子は美しく、多くの人たちを魅了しています。 行列のイメージ(画像:写真AC) 4月にお目見えするサンシャイン水族館のクラゲ水槽も人気になることでしょう。2020年、クラゲブームが巻き起こるかもしれません。
- ライフ