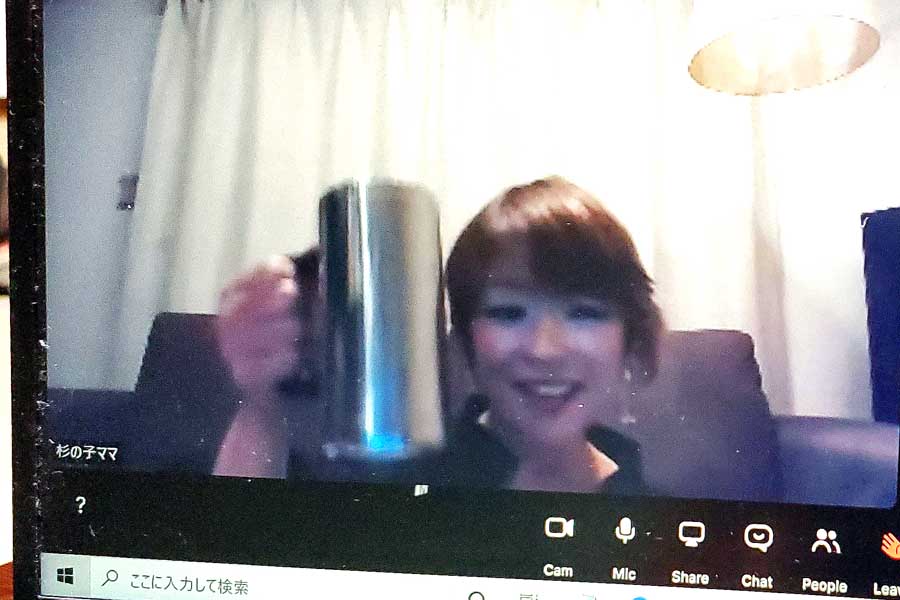絶対ドアを開けないで――東京への帰国者が体験 「隔離ホテル」厳戒の15泊ルポ
海外からの水際対策 日本国内で新型コロナウイルスの変異株が発生していた可能性という報道(『朝日新聞デジタル』2021年3月5日付)が、衝撃をもって受け止められましたが、みなさんが主に懸念しているのは海外から流入した変異株の市中感染でしょう。 3月12日(金)現在、政府が変異株流行国に指定しているのは、イギリス、南アフリカ共和国、アイルランド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギーです。 これら17か国からの日本人帰国者と再入国外国人は、水際対策として、「検疫所が確保する宿泊施設」に3泊する措置が取られています。陰性証明を持っていなければ6泊になります。また変異株流行国・地域以外からであっても陰性証明がなければ3泊となります。 東京・成田空港へ帰国 2020夏に仕事で渡英、年末に帰国の予定でいた筆者はイギリス変異株の問題により現地での滞在を延長し、ようやく帰国したのが2021年1月末のこと。ビザの期限が切れるので、この時期にどうしても帰国をしなければなりませんでしたが、少しでも後になった方が政府の受け入れ態勢が整うのではないかと考えたからでした。 「絶対にドアを開けないで」「自分の部屋から出ないで下さい」などと書かれた張り紙が貼られたホテルのドア(画像:鳴海汐) 成田の空港に到着し、道なりに進んでいくと突如椅子が並べられたコーナーが現れました。順番に問診コーナーに向かい、変異株流行国・地域からの人々が振り分けられます。その後はスタッフの誘導でグループ行動となり、唾液を用いた検査を行いました。 想像と違う穏やかな雰囲気想像と違う穏やかな雰囲気 実は、あからさまに避けられるような対応や緊迫した雰囲気を覚悟していたのですが、現場はとにかく穏やかな雰囲気です。 ところで、対象国以外からの入国であっても14日以内に対象国に立ち寄っていれば、その人も政府隔離ホテルに入るルールになっています。 それを知らないでやってきた人が、「(高級ホテルにしか泊まったことがないので)ビジネスホテルなんかに泊まりたくない。それならこの後のフライトで帰る」と大騒ぎしていたのが印象的でしたが、スタッフが丁寧に対応していたことにも、接客が雑なことが多いイギリス帰りのせいか強い感銘を受けました。 バスに乗りホテルへ 飛行機を降りてから、ホテルへ向かうバスに乗るまでは2時間半ほど。検査結果は陰性でしたが、バスの中はビニール張りで物々しい雰囲気です。筆者のほかに6人ほど乗っていましたが、誰もひと言も口をききません。 到着したホテルのロビーにはブースが設置されて、イベント会場のような雰囲気でした。ほほ笑みさえ湛えたスタッフから個別に滞在についての説明を受け、夕食のお弁当を受け取り、希望した禁煙ルームに向かいます。エレベーターに乗る際は、「どこにも触らないように」と指示を受け、フロアに到着すると、そこで待っていたスタッフがすでにドアを開けていて、部屋に誘導してくれました。 あとで同時期に帰国した友人の家族とは違うビジネスホテルだったのを確認しましたので、少なくともこのとき、ふたつ以上のホテルが使われていたようです。 ドアの内側には、「自分の部屋から出ないで下さい」という貼り紙があり、改めて文字として見ると衝撃的でした。なお、コインランドリーを使いたいときだけスタッフの付き添いで部屋の外に出ることができます。 お弁当にはサラダ、お茶、フルーツジュース、カップのみそ汁がついて、栄養バランスを考えていると思われる内容でした。冷たいお弁当でしたがそれなりにおいしく、まずは陰性だったという事実とともに、よく噛み締めました。宿泊が無料なこともありがたく思いながらいただきました。 日に6度のアナウンスの苦しみ日に6度のアナウンスの苦しみ イギリスと日本は、冬時間では9時間の時差があります。現地出国のしばらく前から不眠症が始まっていたのですが、もしも自分が変異株ウイルスを持ち込んだらと考えると疲れているのにほとんど眠れず、朝を迎えました。 この施設では、その日に退所予定の人の検査と回収がまず行われ、その後全体に朝食が配布されます。また朝は体温を測り、健康状態をチャットで報告する時間でもあります。 朝食配布のスタッフとの接触がないよう、配布開始のタイミングでアナウンスが入り、絶対に廊下に出ないよう呼びかけられます。その後配布完了のアナウンスが入るまで、しばらく時間がかかりました。 食事ごとにそれぞれ2回アナウンスが入るので、日中に寝付くことができても連続して眠ることは難しい状況です。 お弁当は、朝はホテルのもの、昼と夜は機内食の工場がつくっていると思われるものです。ときに年配の人が好みそうな純和風メニューが続きます。味付けがかなり濃いのに焼き魚は味付けがほとんどなく、これは味覚障害なのかと、食事は戦々恐々とする場面でもありました。 初日はおいしいと思ったお弁当も、冷たいせいか、味が濃いせいか、はたまた運動ができないせいか、眠れないせいか、日に日に食べられなくなっていきました。温かいものを食べるべきだとカップのみそ汁を飲むと、お弁当をだいぶ残してしまうという悪循環が発生。顔がむくみ続け、鏡を見ては落ち込んでいました。 ありがたいサービス 食事については人によって好みがあるからか、ありがたいサービスが設けられていました。家族の差し入れ、出前などが可能です。お酒が健康状態を把握するために禁止になっていて、そのためかスタッフによる中身のチェックが入ります。 筆者が利用したのは、スタッフが代行でコンビニに行ってくれるサービスです。本部に電話すると、スタッフが部屋番号を記入したジップロックをドアにマグネットで貼り付けます。そこに現金を入れると、入金を確認したスタッフが買いに行ってくれるというもの。その後電話連絡を受けたら、ドアの外に置かれた椅子の上にある商品とおつりをピックアップします。 つまりスタッフと接触がない仕組みなのですが、お金を置いたときにふと見上げたら、離れた階段からこちらの様子をうかがっている学生バイトらしきスタッフと目が合ったので、頭を下げて感謝の気持ちを表しました。当初はヨーグルトや甘いものなど、頼むのはワガママかとちょっと悩みましたが、問題なく対応してもらえました。 宿泊所を「退所」宿泊所を「退所」 3泊した翌朝は、7時台に検査キットが配布されます。ノックの合図でドアを開けたら、防護服を着た女性が3人いました。そのうちのひとりにあらかじめ唾液を入れておいた容器を手渡しました。なんだか重要機密物質を渡すような緊張感がありました。看護師さんの朝から爽やかな笑顔が眩しく、検査時間が朝早いことを不満に思った自分を恥じたのでした。 唾液を提出するための検査キット(画像:鳴海汐) 落ち着かない時間を過ごし、13時半頃に電話で陰性と伝えられました。陽性の場合は滞在が延長することを考えて部屋はそのままにしていたので、家族に連絡を入れたあと、15時の出発に向けて急いでパッキングしました。 ロビーでは、感染対策アプリ「COCOA」と厚労省のLINEがインストールされているかの確認などがありました。またここでは検疫官が待機していたので、ずっと疑問に感じていた、なぜ「3泊なのか」という質問をしました。コロナのウイルスは接触してから感染が確認できるまで72時間が目安で、完全にではないけれど大体の人がそれまでにウイルスが確認できるようになっている、というのが理由とのこと。 筆者は、ロンドンから帰国のフライト(乗り継ぎ便)の1便目が満席だったのが不安で不安で仕方がなかったので、検査の結果はイギリスや機内からウイルスを持ち込まなかったことをほぼ意味すると聞き、かなり気持ちが楽になったのでした。 バスにはスタッフが荷物を運ぶのを手伝ってくれるなど、サービスレベルの高さに申し訳なく感じるほどでした。 ホテルに来たときのバスと違い、ビニールが張られていない、きれいなバスでした。退所時はロンドンでの検査も含めると3回連続陰性なので、扱いが違うのかと想像しました。 「お先です」 別れ際の挨拶「お先です」 別れ際の挨拶 バスは成田空港、羽田空港に向かいます。羽田空港のことは分かりませんが、成田空港からは市内のホテルへ向かうバスが1時間に1本出ていて、それを利用して自己隔離のホテルに向かうことができます。 その専用バスが利用できるバス乗り場を一緒に探したおじさんが、自身のホテルに到着したとき「お先です」と挨拶してくれました。お互い相当なプレッシャーを感じながら帰国した者同士。前述の友人の家族も「本当に大変な思いをして帰国した」と言っていたそうです。 海外からの帰国者が批判されることもありますが、軽い気持ちで帰ってきている人の方が少ないのではないかと筆者は考えています。 自己隔離ホテル12泊 日本入国後は、入国日の翌日を1日目として、まるまる14日間の隔離が要請されています。実家には戻れないので、自身で手配したホテルに12泊滞在しました。かなりの厳戒態勢を感じさせられた政府隔離ホテルよりはリラックスできましたが、陽性になるかもしれない恐怖と食事確保の苦労があり、そこを出た途端に不眠症が治った事実がその緊張を表していると思います。 ところで、検疫所のバスを降りてから自己隔離のホテルに到着して驚いたのが、併設のレストランに人がいっぱいだったことでした。 家族や友人同士、もしくは同僚らしき人々が席に着き、ほんわかした雰囲気なのです。日本では飲食店が時短営業などになっていて、必ずしも閉まっていないことを知っていましたが、それまで特殊な環境にいたこと、さらにその前はロックダウンでレストランが長らく閉まっているロンドンにいたので、全く別の世界にやって来たような気分になったのでした。
- ライフ