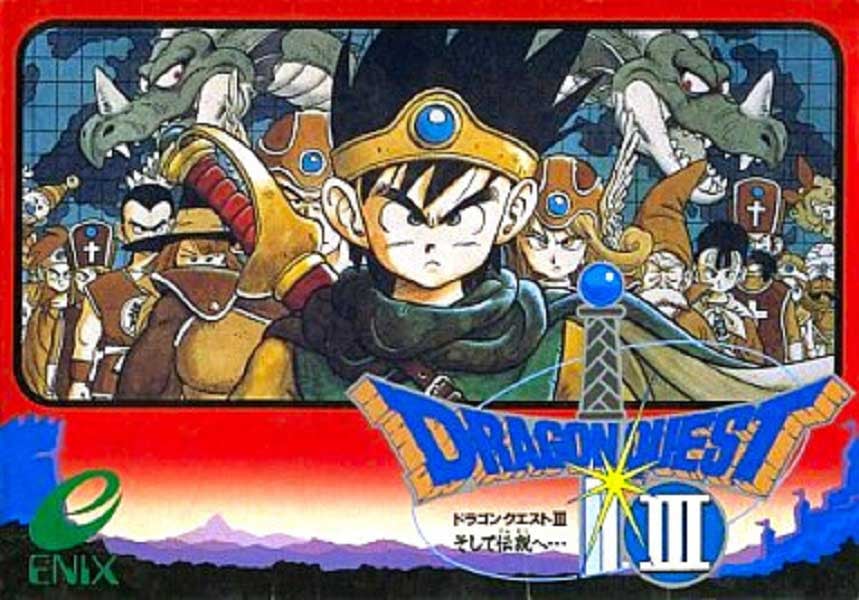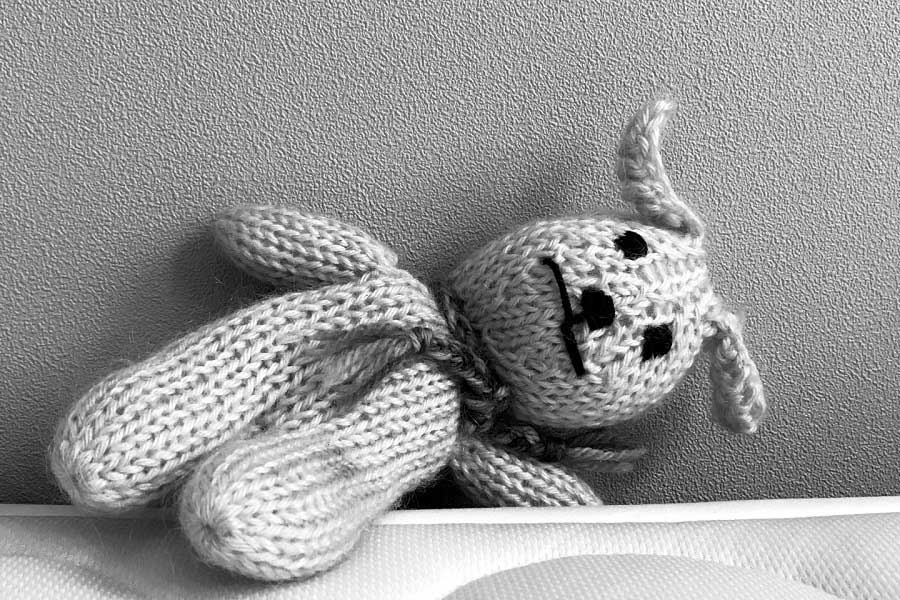大掃除シーズン到来! ガラスクリーナー特需のライバルはSNS、ユニーク製品も
大掃除に欠かせないガラスクリーナー。いったいどのような製品があるのでしょうか。実施はやはり12月28日~30日に集中 2018年も残りわずか。今年もあっという間の1年でしたね。そんな1年を締めくくるイベントといえば大掃除です。 ダスキン(大阪市)がこのたび発表した「2018年末大掃除 実施意向調査」によると、年末に大掃除をする人は74.1%に上るといいます。 大掃除の実施予定に関するグラフ(画像:ダスキン) 肝心の実施日は12月28日(金)から30日(日)までの期間にもっとも集中しており、皆さんただでさえ忙しい年末の中、バタバタしながら大掃除に取り組んでいることが分かります。 2018年の大掃除の実施予定日に関するグラフ(画像:マクロミル) 大掃除に必須なものといえば、掃除用具や洗濯用品。インターネットを使った市場調査大手のインテージ(千代田区神田練塀町)が2017年12月に発表した調査よると、12月のガラスクリーナー(スプレー/液体タイプのガラス用洗剤)の販売額は、1月から11月の平均と比べて、なんと645%に上るとのこと。その数値からも、いかに大掃除シーズンに消費が集中しているかが分かります。 12月に販売額が伸びる掃除関連製品のグラフ(画像:インテージ) ガラスクリーナー自体の市場は「各メーカーから新製品が出ず、新しい消費者を取り込めていないことや、SNSの発達で洗剤以外の掃除方法が知られるようになった」(インテージ)ため、年々縮小傾向(2014年度比82%)にあります。しかし、12月に集中という構図は今後も変わらないといいます。 スクイージー併用も効果的 そんななか、洗剤メーカー大手の花王(中央区日本橋茅場町)がコンシューマ向けに唯一展開する「ガラスマジックリン」(400ml)は、前身の「液体ガラスマイペット」時代から、約40年間に販売されているロングセラーです。洗剤液を垂れにくくするなどして、「市場ほど(販売額を)落とさず、シェアはアップしている」(同社製品広報部)とのこと。 「ガラスマジックリン」(400ml)の製品イメージ(画像:花王) また同社は、スクイージー(余分な水気を取り去るゴムローラー)を使ったガラス窓の掃除をホームページ上で提案するなどして、シェアの拡大を図っています。 「大きな面積を占める窓のくすみがなくなってピカピカになると、部屋全体が明るくキレイな印象になります。年末時期だけでなく、夏時期のお掃除もおすすめしています」(同)。 ロフトで人気のユニーク製品4選ロフトで人気のユニーク製品4選 生活雑貨店大手のロフト(千代田区九段北)も年末に向け、ガラスクリーナーの販売に力を入れています。同社で人気のユニーク製品を4つ紹介してもらいました。 「技・職人魂 ガラス職人」はプロの清掃会社が現場で開発した、スプレータイプのガラス用洗剤です。窓ガラスに直接スプレーして乾いたタオルで拭きとるだけで、拭きムラやギラツキを残しません。 「技・職人魂 ガラス職人」(500ml)の製品イメージ(画像:ロフト)「静電気防止機能でぞうきんの繊維やほこりの付着も防ぎます。窓ガラスや鏡以外にも、テレビ画面やパソコン画面、メガネ、ステンレスなど、拭き跡を残したくない箇所の掃除におすすめです」(ロフト広報・渉外部) 雨ざらしでしつこい水あか汚れがついた窓掃除に合った製品です。天然成分100%で中性洗剤のため、肌にも優しく臭いもありません。汚れを落とすだけでなく、表面を滑らかに仕上げることで、水滴が付きにくくなり美しさが長続きします。 「水アカ・油膜除去クリーナー すっごい水あか取り」の製品イメージ(画像:ロフト)「掃除した箇所を水で洗浄後、付属の専用スポンジ、もしくは研磨剤の付いていない柔らかい布などにこの製品を適量含ませて、こすり洗いしてください」(同) 住宅用万能クリーナーです。主な洗浄成分は手肌に優しいアミノ酸系洗浄成分。ゴム手袋を使わずに、素手で本格的な掃除ができます。 「ウタマロクリーナー」の製品イメージ(画像:ロフト)「しつこい油汚れや水あか、湯あか、手あかをしっかり落とします。キッチン廻りや風呂、トイレ、水拭きできる家具、床、壁紙など、家じゅうの掃除に使えます。生分解性(微生物によって分解される性質)で、環境にも優しい洗剤です。昔からあるウタマロシリーズは定番製品として、世代を問わず人気です」(同) 洗剤が不要。水につけてこするだけで、クレンザーでもなかなか落とせない頑固な水あかを落とせます。 「鏡・ガラス用 ウロコ状水アカ 汚れ落とし」の製品イメージ(画像:ロフト)「保水性や柔軟性に優れたPVA(ポリビニルアルコール)スポンジと、高硬度ダイヤモンド粒子の組み合わせにより、キズが目立ちにくく高い研磨力を発揮します」(同) この1年を総括する大掃除。せっかくやるなら、製品選びも楽しみたいものですね。
- ライフ