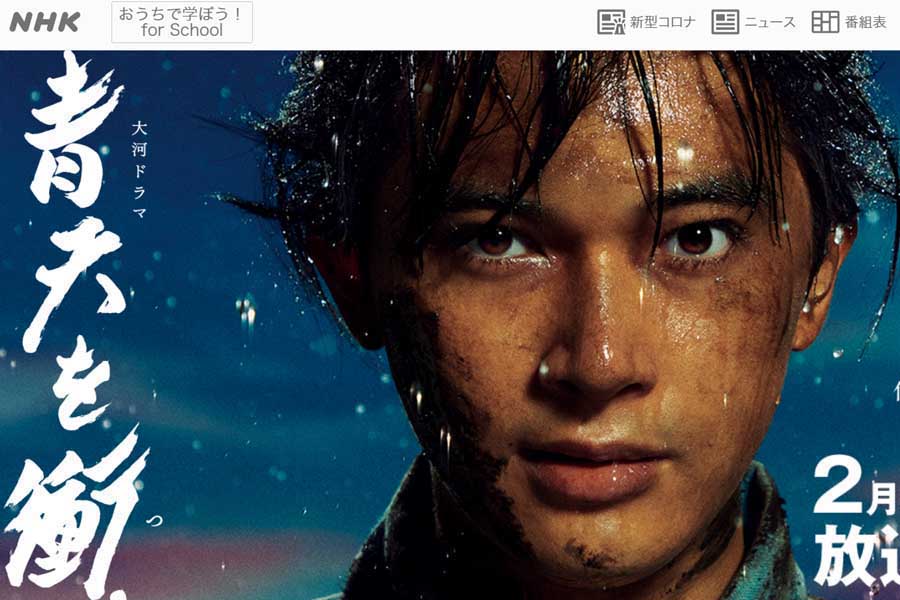今秋もチノボトムスが大本命? パンツとスカート、着回し法をご紹介します♪
人気の「チノボトムス」について、ファッションライターの野々宮怜さんがチノパンツとチノスカートの秋の着回し法を紹介します。ワークテイストで「足のライン隠し」も 春と秋は気温が似ている分、同じ服を着まわすという人も多いのではないでしょうか。この秋新たに購入する服も、2020年の春着回せるようなアイテムがいいですよね。 そのようなときにおすすめしたいアイテムが「チノボトムス」。2018年から人気急上昇中ですが、2019年も引き続き注目したいアイテムです。 ワークテイストなイメージがあるチノボトムスは、キレイめにも、カジュアルにも、スポーティーにも着れる優れ物。「足のラインを隠したい」という方にもおすすめです。 ということで、チノパンツとチノスカートの秋の着回し法をご紹介します。 春秋気回せる「ベージュ」&「カーキ」のチノパンツ チノボトムスといえば、「チノパン」です。春秋共通でチョイスしたいのは、ラインがキレイなベージュのチノパン。どちらかというと春向けのベージュチノパンですが、秋でもトップス次第で上手に着こなせます。キレイめを狙うなら、「ベージュ」がおすすめ。 センターパーツの入った「細身のチノパン」は、キレイだけでなくさまざまなアイテムと合わせることができます。初秋には、チェックやレオパード柄といったクセのあるトップスも、スッキリと見せてくれます。 秋本番には、くすみピンクや甘めの黒ブラウスとベージュチノパンとの組み合わせも、シックに見せてくれます。ピンクもくすんだ色味だと秋向けでしょう。 晩秋にはボリュームのある黒ニットと合わせると、大人っぽい印象を与えます。ボリュームニット以外をコンパクトにまとめると、メリハリがついてより女性らしく見えるでしょう。靴やバッグでアクセントのある色をチョイスすると、オシャレ度もアップします。 トップスはインしてコンパクトに カジュアルに着こなしたいなら、「チノワイドパンツ」も引き続き人気です。足のラインを出すのに抵抗のある方にも、おすすめです。トップスはインしてコンパクトにまとめると、スッキリした印象になります。 Dickies×08sircus×CITYSHOP トリプルコラボレーション・チノパンツ。Dickies定番のTCツイル生地をソフトにし、08sircusの型に仕上げている(画像:ベイクルーズ) 秋には「カーキ」色のチノパンもおすすめ。カーキも細身のチノパンだとキレイにみえます。カジュアルにしたいならゆるめでもよいでしょう。 トップスの色を選びがちなカーキですが、「黒、グレー、深みのあるベージュ、濃いパープル、ワインレッド」など、秋色にピッタリ合います。 カーキだとボーイッシュな印象がありますが、トップスに甘めのデザインブラウスを持ってきたり、Vネックニット、レース仕様のトップスをもってくると「女性らしさ」を出せます。 春にはカーキに白や薄めのベージュを合わせると、涼しさを演出できます。意外ですがブルーデニムを合わせても、大人カジュアルに仕上がりますよ。カーキのチノパンに白のインナー、デニムのアウターという組み合わせも合うでしょう。 チノスカートはオンにもオフにも活躍チノスカートはオンにもオフにも活躍 チノスカートはグンと秋らしくしてくれるので、晩夏や初秋からとりいれたいアイテム。ベージュのチノスカートは、大人っぽくも、カジュアルにも、スポーティーにも着ることができます。下半身のラインも隠してくれるので、お尻~足が気になる方も取り入れたい1着です。 ふんわりと立体的に広がるデザインで、裏地にはドット柄が配されたチノタックスカート(画像:ジュン) チノスカートには、さまざまなデザインがあります。 腰の高い位置~足首まである「ボリューミーなロングチノスカート」は、夏に着たノースリーブトップスやTシャツを、チノスカートにインして着ると、これからの季節でも秋らしさを感じさせるコーディネートとなります。足首をきちんと見せてコンパクト感をだしてくださいね。 ボリューミーなチノスカートは、柄トップスとも相性が良いです。トップスはインすると、すっきりまとまって見えますよ。デニムやロゴTと合わせると、スポーティーな印象に早変わり。チノスカートなので女性らしさも忘れません。さらに差し色に赤をもってくると良いでしょう。 オンにもオフにも着用したいなら、Iラインでひざ下丈の「タイトなチノスカート」がおすすめ。薄めの生地だと、さらにキレイに見えます。トップスにゆるニットやもこもこニットを合わせて女性らしさを出したり、黒トップスをインしてきちんと感を演出しましょう。 ベージュのチノスカートには、「黒や暗いグレー、ブラウン、カーキ、デニム」といった秋色も、チェックやボーダーといった柄も合います。もちろん春色の白やピンク、薄いグレーも合うので、重宝するでしょう。 この秋はチノパンツとチノスカートで、キレイめからカジュアルまで着こなしてくださいね。
- ライフ