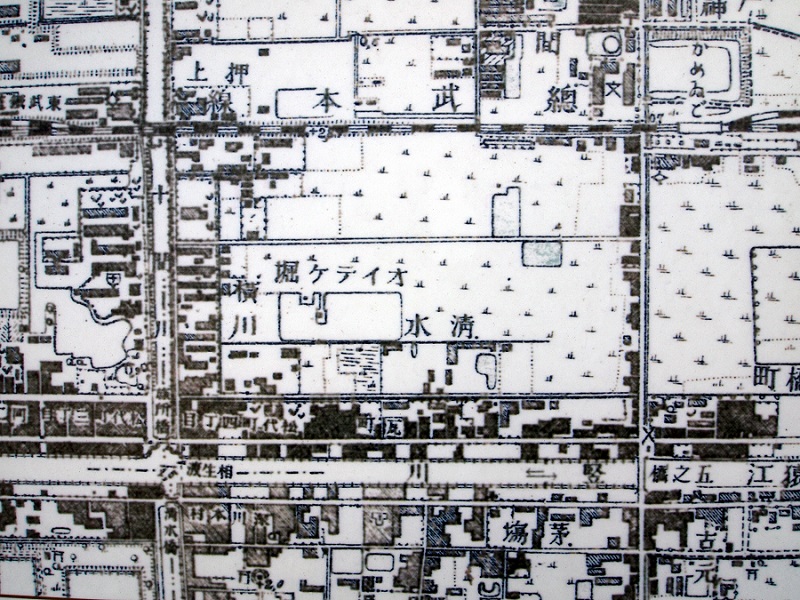浅草? いいえ「浅草橋」です 飛鳥~平安時代の香り漂う知られざる魅力に迫る
浅草橋から浅草まで歩いてみよう JR総武線を「浅草橋」駅で降りて改札を出ようとすると、その直前に「浅草は東口を降りて地下鉄をご利用ください」と書かれた掲示板が、いやが応でも目につくようになってます。 JR浅草橋駅を出ようとするとこんな案内が(画像:荻窪圭) きっと「浅草橋」という駅名を見て「駅名からして、ここなら浅草まですぐだろう」と思って降りる人に「いやいや、浅草橋から浅草までは地下鉄で2駅分の距離がありますから、ここで乗り換えてくださいね」と警告を出しているのでしょう。 スマホの路線検索アプリは駅から駅への経路を調べるアプリですから、似てるけど駅名を間違えても気付きづらいですよね。いちいち地図もチェックする人は少数派でしょうし。 さて、浅草橋駅。駅名の元になった神田川にかかる「浅草橋」は浅草へつながる橋、というくらいの意味。日本橋を出発した日光街道は浅草橋を渡り、浅草を経由して日光や奥州へ向かっていたのです。 であれば、地下鉄に乗り換えたりせず、浅草橋駅から江戸時代の人と同じ道筋で浅草に向かってみようと思うのが人情というもの……かどうかは知らないけど、これがなかなか登場する歴史の古さに驚くレベルなのです。行ってみましょう。 平安時代の伝承を持つ神社がずらり平安時代の伝承を持つ神社がずらり 浅草橋駅を出ると目の前は国道6号にして江戸通り。この江戸通りが江戸時代の日光街道(旧日光街道)です。浅草橋駅は浅草橋の北にありますから、浅草橋駅東口を出たら、浅草橋を背に北に向かって歩きます。 そしていきなりですが、最初の狭い路地を左に入ると奥に鳥居が。銀杏(いちょう)岡八幡神社(台東区浅草橋1)。まずここが古いのです。なんと創建は平安時代。 平安時代創建という銀杏岡八幡神社(画像:荻窪圭) 平安時代後期、源頼義と義家の親子は奥州へ向かう途中この辺りに立ち寄ったのだそうです。今の江戸通りは平安時代から奥州へつながる街道だったほど古い街道で、この辺りは少し小高い丘で隅田川を一望できる絶景の場所だったそうです。今でも江戸通りから少し東へ向かうと隅田川が流れてます。昔は川沿いの街道だったことでしょう。 そのとき川を流れてきた銀杏の枝を拾い、丘の上に挿して戦勝を祈願。無事奥州を平定した帰途、再び立ち寄ったら銀杏の枝が大きく茂っていたので八幡宮(はちまんぐう)を勧請(かんじょう)したのがはじまり(八幡は源氏の氏神)――。平安時代の東京にもこんな伝承があったのです。 浅草寺より古い神社も 銀杏岡八幡神社を出て、江戸通りに戻り、大昔の奥州街道を北上しましょう。 次に出会うのが須賀神社(浅草橋2)。須賀神社は素戔嗚尊(スサノオノミコト)を祭る神社です。これはもっと古いのです。伝承によると推古天皇9(601)年と言いますから、聖徳太子の頃ですね。疫病が流行した際、牛頭(ごず)天王(素戔嗚尊)の祠(ほこら)を建てたのが初めといいます。 ちなみ浅草の浅草寺が推古天皇36年創建ですから、その27年前とは驚きです。 須賀神社裏手の道にひっそりと残る「閻魔堂跡」の碑(画像:荻窪圭) 江戸時代はこの隣に長延寺というお寺もありました。名残はないかと探したら、1本裏手の道に「閻魔(えんま)堂跡」碑を発見。江戸時代、長延寺は運慶作の閻魔大王を納めた閻魔堂で有名だったそうです。 伝承にツッコむのはやぼ?伝承にツッコむのはやぼ? さらに北上しましょう。すると「須賀橋交番前」という交差点にたどり着きます。江戸時代、ここに橋があったのですね。須賀橋、あるいは鳥越橋と呼ばれてました。鳥越川という小さな川が流れ、隅田川に注ぎ込んでいたのです。 次の交差点が「蔵前一丁目」。ここを左折して少し歩くと、道路の北側に鳥越川の語源となった「鳥越神社」があります。 鳥越神社の鳥居の前にある白鳥橋。大昔は白鳥大明神と呼ばれていた(画像:荻窪圭) ここの創建はなんと651(白雉2)年。大化の改新の時代に日本武尊(ヤマトタケルノミコト)がかつてここに滞在したことをしのんで創建したと言います。伝承ではありますがそこまでさかのぼるとは驚きです。 その後、ここを源頼義と義家が奥州へ向かう途中にここに差しかかった際、川に遮られてしまったが、「名も知らぬ鳥が超えるのを見て浅瀬を知り隅田川を渡った」ことから鳥越大明神と名付けた、といいます。銀杏岡八幡神社の次にこちらへ来たのでしょうか。 鳥がわざわざ浅瀬を越えるか? とか奥州街道のルート的にここで隅田川は渡るのはちょっと変じゃない? ツッコミどころはあるのですが、伝承にツッコむのはやぼってことで、鳥越川を渡ったときの話が長い年月で盛られたのかもしれません。 大昔は境内のあたりがもうちょっと高くなっていたが、江戸時代、隅田川沿いに米蔵を作る際、土を削られて平らになったそうです。 再び江戸通りに戻って浅草を目指しましょう。 人間になりたい白い犬の像がある神社人間になりたい白い犬の像がある神社 しばらく歩くと、また古い神社があります。1本裏の道にある蔵前神社(台東区蔵前)。 元々は日光街道沿いにあった大きな八幡宮でしたが、今は街道沿いにビルが並び、神社は1本裏になってしまいました。ここは江戸時代の1694(元禄7)年に五代将軍・徳川綱吉公が京都の石清水(いわしみず)八幡宮を勧請したものです。この神社の見どころは「元犬」。 蔵前神社にある「元犬」の像。落語好きならクスリとするに違いない(画像:荻窪圭) 有名な古典落語に「元犬」というのがありまして、人間になりたい白い犬が蔵前の八幡さまに祈っていると人間の姿になった、という話。その蔵前の八幡さまが今の蔵前神社ということで、犬の像があるのです。そのほか、江戸時代の勧進大相撲発祥の地ということでも有名です。 さらに北上すると、今度は駒形諏訪神社(台東区駒形)。詳細は不明ですが、境内の掲示によりますと、平安時代後期とも(源頼義と義家一行がこの辺りを通ったという時代)、鎌倉時代ともいわれてます。 そろそろ浅草が近くなってきました。次の注目は江戸時代から続く、1801(享和元)年創建の「駒形どぜう 本店」(同)が見えます。今でもどじょう鍋を食べさせてくれます。かなり美味でした。 駒形堂まで来たらもう浅草 そして駒形橋西詰交差点。ほぼ浅草ですね。この角にある駒形堂(台東区雷門)は浅草寺の入り口。大昔はここに浅草寺の総門があったといいます。 浅草寺への入り口でもあった駒形堂。浅草寺はここからはじまったといっても過言ではない(画像:荻窪圭) 浅草寺は推古天皇36年、檜前(ひのくまの)浜成と竹成の兄弟が宮戸川(今の隅田川)で漁をしている最中に網に観世音菩薩(ぼさつ)像がひっかかり、それを祭ったのが始まりですが、そのときの船着き場が駒形堂のあたりだったそうです。 ここまでくれば、あとは浅草寺の雷門まで参道が続きます。 浅草の観音様といえば江戸時代からにぎわっていた場所、というイメージかもしれませんが、浅草橋から歩いてみると、江戸時代どころか平安時代や飛鳥時代にさかのぼる神社が並んでおり、実に古くから隅田川沿いににぎわっていたことが実感できます。 浅草橋から歩くと浅草寺に着くまでにおなかいっぱいになるかもしれませんが、それはそれでまたよし。浅草橋から浅草寺への隅田川沿いの街道は大昔から人が行き来していたのだなあと思いつつ浅草を詣でるとより味わい深いかと思います。 秋は散歩に向いたシーズン。ぜひ挑戦を。
- 未分類