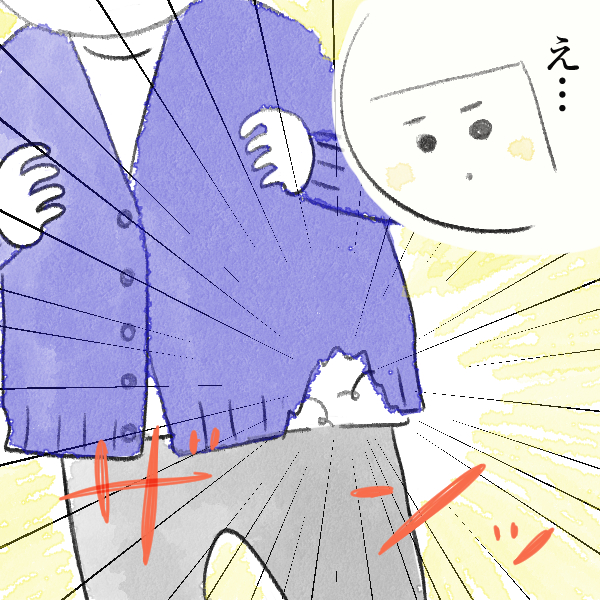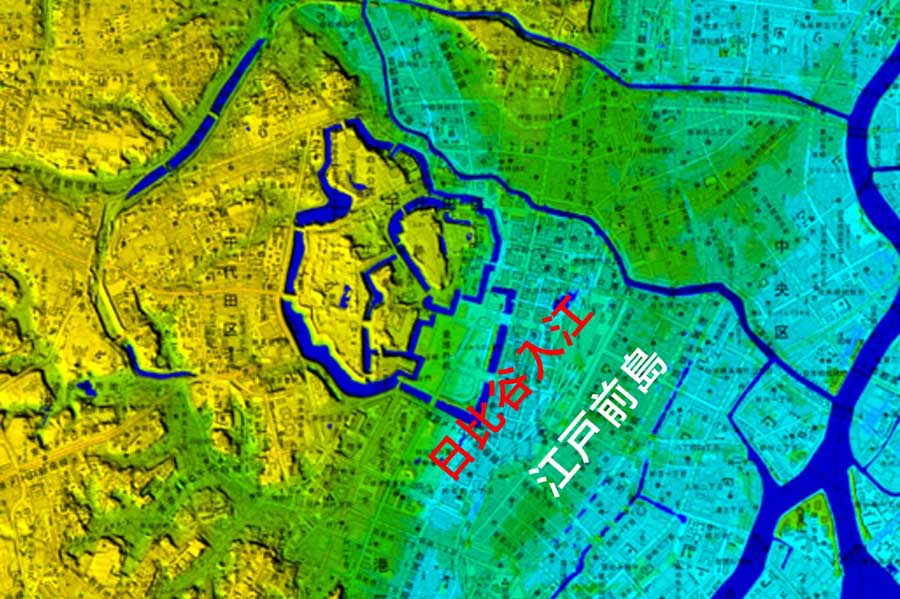鉄道事故の9割が、踏切関連
2019年9月5日(木)、京浜急行電鉄(京急)の神奈川新町駅~仲木戸駅間にある踏切で、電車とトラックが衝突するという痛ましい事故が起こりました。同事故により、京急本線は運休。首都圏の大動脈を担っている幹線だけに、各所に大きな影響が出ています。
 2005年に踏切事故が起きた竹ノ塚の踏切(画像:小川裕夫)
2005年に踏切事故が起きた竹ノ塚の踏切(画像:小川裕夫)
今回の事故が起きた踏切は長時間にわたり踏切が遮断される、いわゆる「開かずの踏切」で起きました。詳細な事故原因はこれから究明されることになりますが、今回の事故で踏切の廃止と立体交差化が加速することは間違いありません。
踏切は道路と線路が交差する地点です。そのため、鉄道事故の9割近くが踏切および踏切付近で発生するといわれています。事故を未然に防ぐ目的で、地方自治体と鉄道会社が協力し、踏切の除去を積極的に進めています。
線路の立体交差は、以前より取り組まれていましたが。その重要性が強く認識されるようになったのは、2005(平成17)年に起きた東武伊勢崎線竹ノ塚駅(足立区)の踏切事故がきっかけでした。竹ノ塚駅の南北両端には踏切があり、ふたつの踏切は開かずの踏切として地元住民の間では有名でした。
竹ノ塚の踏切には、もうひとつ特徴がありました。
それが踏切保安員と呼ばれる、踏切を監視・操作する職員が配置されていたことです。踏切保安員は今では珍しい存在になっていますが、かつては踏切警手とも呼ばれ、あちこちに配置されていました。地元住民にとって、もっとも身近な鉄道職員でもあり、慕われる存在でもありました。
安全を確保することや鉄道の定時運行を守ることが、踏切警手の最大の使命です。いわば、踏切を横断する歩行者や自動車、電車を利用している乗客の命を預かる大事な任務を担っています。しかし、そうした重責はなかなか理解されません。
2005年の竹ノ塚事故では、踏切待ちに業を煮やした通行人が踏切警手を「早く開けろ」と恫喝。恐怖のあまり踏切警手は踏切を開けてしまい、歩行者ふたりが死亡する事故になったのです。
開かずの踏切問題、廃止は「各論で反対」多し
竹ノ塚の踏切事故がきっかけとなり、同駅の踏切警手は廃止。代わりに、警備員が配置されました。踏切警手が手動で踏切の開閉を操作することもできますが、警手が配置されている踏切でも基本は自動制御です。いわば、警手は人の目による安全確認・監視という役割が濃く、踏切警手を廃止したことは、かえって危険性が高まったともいえます。
事故から間もなく15年が経過します。まだ竹ノ塚は立体交差工事が完了していません。それほど立体交差化には時間がかかるのです。
 連続立体交差化のために、線路沿いには事業用地が点在(画像:小川裕夫)
連続立体交差化のために、線路沿いには事業用地が点在(画像:小川裕夫)
新宿駅の近くにある小田急電鉄の新宿1号踏切は、かつて踏切警手が配置されていました。現在、踏切警手はいなくなりましたが、新宿1号踏切が開かずの踏切である実態は変わっていません。
開かずの踏切である新宿1号踏切の前後には、常に長蛇の車列ができます。新宿1号踏切に限らず、開かずの踏切は渋滞の原因になります。そのため、鉄道会社だけの問題ではなく、地元自治体が解消に積極的に乗り出しているのです。
ただ、敷地的な問題もあって、新宿1号踏切は立体交差化される気配はありません。
開かずの踏切をなくす立体交差化工事は、交通量の多いところから優先的に始められています。それでも東京23区内にはたくさんの踏切が残り、その大半は開かずの踏切です。
開かずの踏切をなくすことは、世間から同意を得られやすい政策です。しかし、総論は賛成でも、各論になると反対があり、その調整に難航しているのが実情です。
京王電鉄の笹塚駅(渋谷区)~仙川駅(調布市)間には、多くの踏切が残っています。すでに同区間の連続立体交差事業は始まっており、線路沿いを歩けば、そこかしこに連続立体交差のための事業用地を見ることができます。
土地の買収から始まる踏切の連続立体交差ですが、一工区あたりに費やす歳月は短くて10年。通常は20年ほどかかります。
地下化「水脈を枯らしていまう」という声も
京王線の連続立体交差事業は、京王線の線路を高架化する方針で進められています。しかし、沿線住民すべてが高架化を望んでいるわけではないのです。先述したように高架化に取り掛かるためには、沿線の家々に立ち退いてもらわなければなりません。立体交差という公共目的があるとはいえ、長らく住んでいた自邸を引き払ってくれる人は少数なのです。
 立体交差事業が進む京王線の沿線では、地下化を訴えるポスターやステッカーなども(画像:小川裕夫)
立体交差事業が進む京王線の沿線では、地下化を訴えるポスターやステッカーなども(画像:小川裕夫)
また、高架化ではなく地下化にしてほしいというリクエストもあります。高架化すると騒音・振動・日照・景観などの問題が出てきます。一方、地下化は高架化に比べて工費が高くなるうえ、維持費も増大します。工費を負担する地方自治体や運行する鉄道会社は、そうした面からも地下化を嫌がります。
2018年に代々木上原駅(渋谷区)~登戸駅(川崎市)間の複々線化を完成させた小田急は、30年近くにわたって同区間の複々線化と同時に立体交差化を進めていました。同区間の連続立体交差事業は高架線で建設されましたが、騒音・振動によって日常生活が脅かされると住民から訴訟を起こされています。そのため、訴訟後に着工した区間は地下線で建設されています。
逆に、水脈を枯らすといったケースが想定されるので、地下化を嫌がる地域もあります。京王線の立体交差化でも、高架化に向けて地域住民と行政・鉄道会社による話し合いが持たれていますが、解決の糸口は見えていません。
立体交差事業は「総論賛成」ながら「各論反対」に陥りやすく、一筋縄で事業は進みません。複雑な要因をひとつひとつ解決しなければならないため、開かずの踏切の解消工事には20~30年という長い歳月が必要になるのです。