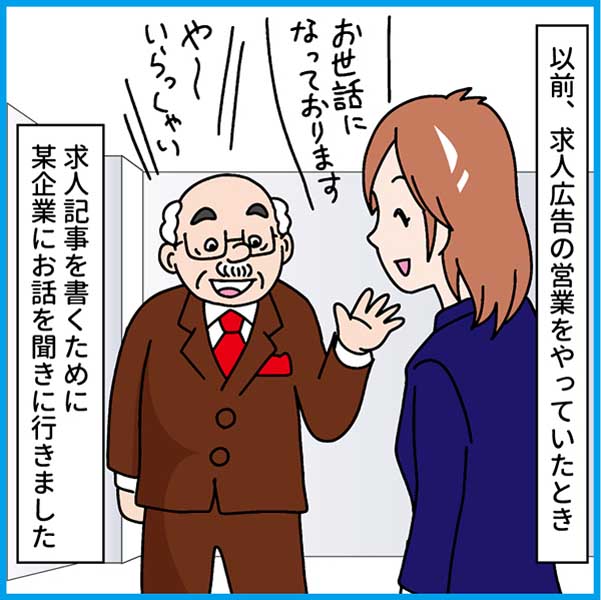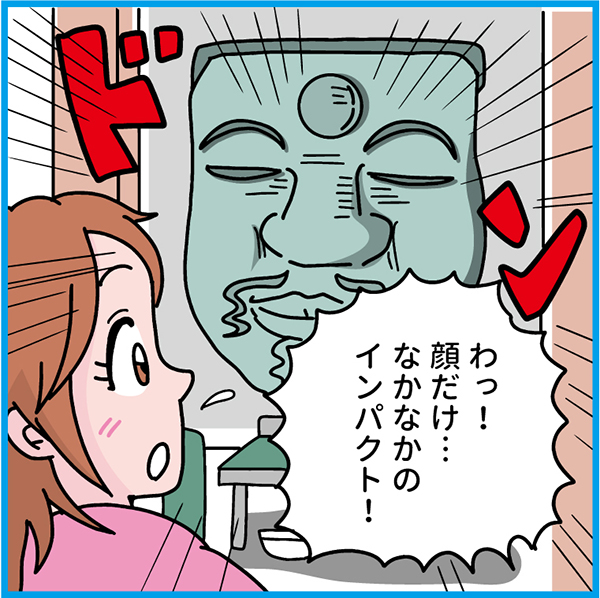豊洲市場、抽選入場の見学デッキからマグロのせりはどう見える? 市場見学徹底ガイド
豊洲市場では2019年1月15日からまだ一般に開放していない見学デッキからマグロのせりを間近に一望できるようになります。築地よりずっと広くなった豊洲市場のマグロの卸売場。どんな風に見えるのでしょうか。「広くて迷う」との声も多い市場内の案内とともに紹介します。一般の人は現在立ち入り禁止の見学デッキからせりを見てみた 開場より2か月が経過した豊洲市場。築地市場の面積が約23.1ヘクタールだったのに対して、豊洲市場は約40.1ヘクタール(東京ドーム約8個分)と2倍近い面積で、「広くて移動が大変」「迷子になった」との声を、買出人を含む市場関係者からも見学に訪れた人たちからも聞きます。 豊洲市場でのマグロのせりの様子(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) 豊洲市場は見学ギャラリーや飲食店を設けていますが、あくまで飲食のプロ向けに生鮮食料品を供給する卸売場で、観光施設ではありません。そのためか市場内に見学者への案内が少なく、事前に下調べをして尋ねることをおすすめします。まずは豊洲市場の今を整理します。 ・2018年に移転したのは築地市場内の事業者のみ。寿司屋や物販店舗も築地市場内にあった店だけが豊洲に移転。場外市場の店は、今も築地で営業しています。 ・市場関係者以外の一般見学者は卸売場にも仲卸売場にも立ち入ることはできません。 ・マグロのせりが見られるのは開市日の午前5時半から午前6時半くらいまで(入荷量による)。朝5時から建物内に入ることができますが、一般駐車場は近くになく、ゆりかもめの豊洲駅発の始発に乗っても市場前駅到着は5時18分です。 ・マグロのせりは水産卸売棟に設けられた見学ギャラリーからガラス越しに見られますが、より間近に見られる「見学デッキ」は2018年12月現在、一般開放していません。2019年1月15日(火)から事前申し込みの抽選により、人数限定で入れるようになります。 ・飲食店は 1か所に集まっているのではなく、3つの棟に分散されています。 上記4番目に挙げた、抽選で入れる見学デッキに筆者は取材目的で立ち入りが許可され、せりを見ました。どんな風に見えるのか、豊洲市場の案内とともに紹介します。 まず、見学デッキへの行き方を案内します。 市場駅の改札を出たところ。マグロのせりが見られる水産卸売場棟は突き当たりを左へ、飲食店が一番多く入る水産仲卸売場棟は右へ(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) 豊洲市場で見学者が訪れることのできる建物は、水産卸売場棟、管理施設棟、青果棟、水産仲卸売場棟の4つです。水産卸売場棟への市場前駅からの行き方は、改札を出てまっすぐ行くと突き当たりに案内板があり、左手に進みます。 見学者が訪れることができる場所は水産卸売場棟、管理施設棟、青果棟、水産仲卸売場棟。黄色のラインが見学者通路(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) 進んで行くと、途中で通路がふた股に別れますが、左は青果棟へ行く通路なのでまずはまっすぐ歩いて行きましょう。その行き止まりの左手に管理施設棟の入口があります。管理施設棟は、水産卸売場棟と渡り廊下でつながっています。 管理施設棟内に入ると、そこは銀行や飲食店などが入っている3階です。 管理施設棟3Fの飲食店が集まるエリア。見学ギャラリーへはここを通って行く(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) 飲食店については、後述します。せりが終わってしまわないよう、ここでお寿司の誘惑に負けずに通り過ぎ、「水産卸売場棟見学ギャラリー」の案内に沿って見学通路を進んで行きましょう。そして、長い渡り廊下を進むと水産卸売場棟入口に到着。エントランスホールを通り過ぎるとせりの見学ギャラリーがあります。ガラス越しに1階の卸売場を見下ろします。 水産卸売場棟3Fのガラス越しにせりの見える見学ギャラリー(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) 見学デッキへのアクセスは、見学ギャラリーの一番奥にあり、入口前に警備員さんが立っています。許可を得た人だけがそこの階段を降り、見学デッキに入ることが可能です。 見学デッキに入って間近に見たマグロせりの様子は圧巻見学デッキに入って間近に見たマグロせりの様子は圧巻 国内外から多彩な魚介類の集まる豊洲市場ですが、築地時代の取扱量トップは冷凍メバチマグロ。その量たるや約2万1692トンに及んだとのことです(2015年 東京都中央卸売市場年報 水産物編 調べ)。卸売場に突き出すように設けられた見学デッキに入ると、並べられたおびただしい数の冷凍マグロが間近に目に飛び込んできました。見学デッキは売場より少し高い中2階のような場所にあるため、広大な面積のせり場が一望でき、まさに圧巻。マグロの巨大さも見学ギャラリーから見るより、よく分かります。 見学デッキから間近に見る水産卸売場の様子。上部が空いているので、せりの声も聞こえる(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影)かなりの数の冷凍マグロが並ぶ様子は圧巻(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) この日、生マグロは入荷量が少なめでした。日にもよるそうですが、筆者が訪れた5時40分過ぎには、生マグロのせりはほぼ終わりかけ。それでも生マグロの方が冷凍マグロよりやはり迫力があり、目が釘づけになりました。 売場に横たわる迫力ある生マグロ(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) 大物生鮮(生マグロ)のせり場は見学ギャラリーの真下なので、量が少ない日は見学デッキからしか見えないようです。 大物生鮮のせり場の雑感(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) 見学デッキはガラスの上部が空いているので、せりの声がよく聞こえてきて、臨場感も楽しめます(何を言ってるか筆者にはさっぱりわかりませんでしたが)。冷凍マグロのせりは6時半頃まで行われていました。 仲卸業者は念入りに品定めし、せりに臨む(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) せり落とされたマグロは仲卸売場へと運ばれて行き、6時半を過ぎるとさっきまでの賑わいが嘘のように閑散としてきてやがて終了。1時間弱の見学でしたが、世界最大級と言われる水産市場の活気とスケールを体感できる貴重な経験となりました。 せり落としたマグロをターレで運ぶ(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) マグロのせりが概ね終わる頃、今度は青果棟で青果物のせりが始まります。 青果棟へは来た道を逆行して、管理施設棟の外へ出ます。ゆりかもめの駅の方へ歩いて行く途中にある通路を右へ曲がって進むと青果棟です。 青果棟も2階に仲卸売場が見える見学ギャラリーと卸売場でのせりが見られる見学デッキがあり、こちらは誰でも見学デッキに入れます。 青果棟の仲卸売場を見下ろす見学ギャラリー。壁に1〜12までの番号が書いてあり、月を表す。月の下に旬の青果物の名前も書かれ、壁の色と合わせている(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) 青果棟2階の見学ギャラリーを急ぎ通り抜け、見学デッキに到着したのは6時50分。ちょうどせりが行われていました。こちらの卸売場も無数の段ボールが積まれていて、まさに「日本の台所」といった感じ。 見学デッキから見る青果卸売場。朝はせりの様子も見られる(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) 青果物の仲卸業者や売買参加者は5時くらいから品物の下見に市場にやってきて、品定めと値決めをしてせりに備えるそうです。せりは6時半頃から開始。青果物のせりには、固定されたせり台に人々が集まって来てせりを行う「固定せり」と、せり人が品物の山から山へ移動して次々とせり落とされる「移動ぜり」があり、双方が見られました。 せりが終わると、仲卸業者の人たちの店に買出人がやってきます。築地と違って水産仲卸売場と青果仲卸売場がかなり離れているので、両方をひとりで購入する買出人から「移動が大変」との声を聞きました。 お寿司が食べられるのはどこの棟? 土曜は朝から行列 お寿司が食べられるのはどこの棟? 土曜は朝から行列 青果棟には飲食店が3店舗入っていますが、見学ギャラリーとフロアが異なり1階にあるため、知らないと気がつかないかもしれません。 豊洲市場には、お寿司を目的に来る人も多いと思います。飲食店は、管理施設棟、青果棟、水産仲卸棟の3か所に別れています。数が多いのは、水産仲卸売場棟、管理施設棟、青果棟の順です。水産仲卸売場棟は、他のふたつの棟とは道路を挟んだ反対側にあり、少し離れています。 青果棟の飲食店は、寿司屋が1店、天ぷら屋が1店、蕎麦屋が1店です。 青果棟1階の飲食店施設(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) 筆者が訪れた11月下旬の平日朝8時半は、この3店の前にはさすがにまだ列はできていませんでした。朝5時半から開いている人気店の大和寿司は、以前より店の面積が広くなりました。土曜は朝から並んでいるそうです。3店舗とも土曜の昼は待ち列ができていました。 前述の管理施設棟3階には飲食店が13店舗あります。平日の朝8時半はどこも列はできていませんでしたが、土曜の昼に行ったときは、ほとんどの店前に列ができて賑わっていました。 水産仲卸売場棟の3階には、飲食店が22店舗入っています。人気店の寿司大や海鮮丼の大江戸は、平日の朝8時半ですでに店前に列ができていました。ここは店舗数が一番多いこともあり、土曜に訪れた際の混雑ぶりはかなりのものでした。 最も多くの店舗が入る水産仲卸売場棟の飲食店街(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) 築地の時代からそうですが、日曜は休市日のため、土曜に人が集中します。豊洲市場の飲食店の狙い目は平日の早朝といえますが、多くの人にとって利用しづらい時間なのが辛いところ。 ちなみに、出店場所はどのようにして決まったのかを大和寿司の板前さんに聞いたところ、「くじ引きで決まった」との答えでした。 水産仲卸売場棟の「屋上緑化広場」は絶景、物販店舗も集まる水産仲卸売場棟の「屋上緑化広場」は絶景、物販店舗も集まる 水産物の仲卸業者が卸売場でせり落とした魚介類を魚屋や寿司屋などの買出人に売る場が水産仲卸売場棟です。仲卸売場に関係者以外は立ち入ることはできませんが、同棟には見学ギャラリー、物販店舗、屋上緑化広場、前述の飲食店と、見学者の楽しめる場所が4か所あります。 ゆりかもめの市場前駅を出て突き当たりを右方向に進むと、水産仲卸売場棟です。管理施設棟から行く場合、出てすぐ斜め前に道路を横断する高架通路があり、そこを渡って左手の建物の方へ歩いて行きます。 水産仲卸売場棟。見学ギャラリーのほかに、飲食店や物販店舗なども入る(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) 水産仲卸売場棟見学ギャラリーへ向かう通路の途上左手に、屋上緑化広場へ行くエレベーターがあります。5Fの屋上プロムナードまで行き、そこから階段かスロープを上って到着。 豊洲市場の屋上はところどころ植え込みによって緑化されており、広大な面積が緑で埋め尽くされている屋上緑化広場は、ヒートアイランド対策ともなっているそうです。東京湾にレインボーブリッジ、摩天楼、天気によっては富士山も見える絶景が広がっています。食後の散歩に最適なほか、デートに足を伸ばすのにもおすすめです。現状、建物は17時で閉まってしまうので、夜景を見られるのは冬のみです。 なお、屋上緑化広場での食事は禁止されています。 屋上緑化広場からの眺め。この日は富士山も望めた(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影)屋上緑化広場からの眺め(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) 屋上緑化広場から再び3階に戻り、飲食店関連施設の入口前を通り過ぎ、突き当たりに見学ギャラリー入口があります。見学通路にターレが置いてあり、乗って写真を撮ることができます。 飲食店関連施設の入口は、水産仲卸売場の見学ギャラリー入口へ向かう途中にある(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影)見学者ギャラリーにはターレが置いてあり、写真スポットになっている(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) 水産仲卸売場で取引される魚介類は約480種類。見学ギャラリーからは水産仲卸売場が屋根と屋根の隙間から見えます。複数の魚種を取り扱う店もありますが、大半が1種類の魚に特化して販売しているそうです。買出人は目利きの仲卸業者と良い関係を築いて、いい仕入れをすることに努めるという、魚河岸の時代から続く絆の世界が未だ存在します。 この棟の4階に物販店舗「魚がし横丁」があります。築地市場内にあった物販店舗が移転したほか、新たに9店舗が加わりました。包丁や長靴などプロ用の品もあれば、漬物店や海苔店、青果店、玉子焼き店といった一般来場者が利用できるものも販売されており、合わせて70店舗近く入っています。 70近くの物販店舗が入っている魚がし横丁(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影)物販店舗の雑感(2018年11月30日、宮崎佳代子撮影) 市場関係者や一般来場者が利用できる休憩所もあり、ドリンク類の自販機があります。物販店舗の多くは、朝早くから店を開けているため、昼過ぎには閉めてしまうところがほとんどです。どの棟の飲食店も、店によっては早く(14時〜15時)に閉店してしまうので、豊洲市場には午前中に行くのがおすすめです。 豊洲市場の管理棟3階にPRコーナーがあり、そこで豊洲市場の情報を得ることができます。全てを迷わずに回ってもかなり歩くので、事前に情報を得ておいた方がいいでしょう。 水産卸売棟の見学デッキの入場については、公式HPに詳細がアップされています。 ● 豊洲市場 ・住所:東京都江東区豊洲6丁目6番1号 ・アクセス:ゆりかもめ「市場前駅」から徒歩約3分 ・開場時間:5:00〜17:00 ※飲食、物販店舗の営業時間は店舗によって異なる。 ・定休日:日祝日、休開市日 ・PRコーナー運営時間:月〜金曜(休市日を除く)8:30〜14:30、土曜 8:30〜11:30 ※2018年12月29日(土)〜2019年1月4日(金)は休み ・水産卸売場棟見学者デッキの申し込み:応募方法等の詳細は公式HP内の「豊洲市場の見学について」に掲載されています。見学は無料です。 ※掲載の情報は全て2018年12月時点のものです。
- 未分類