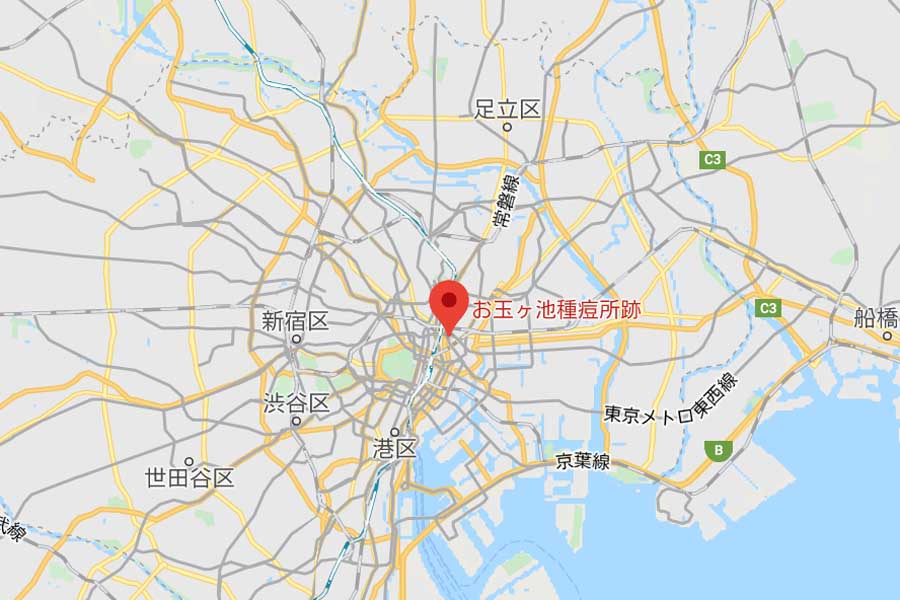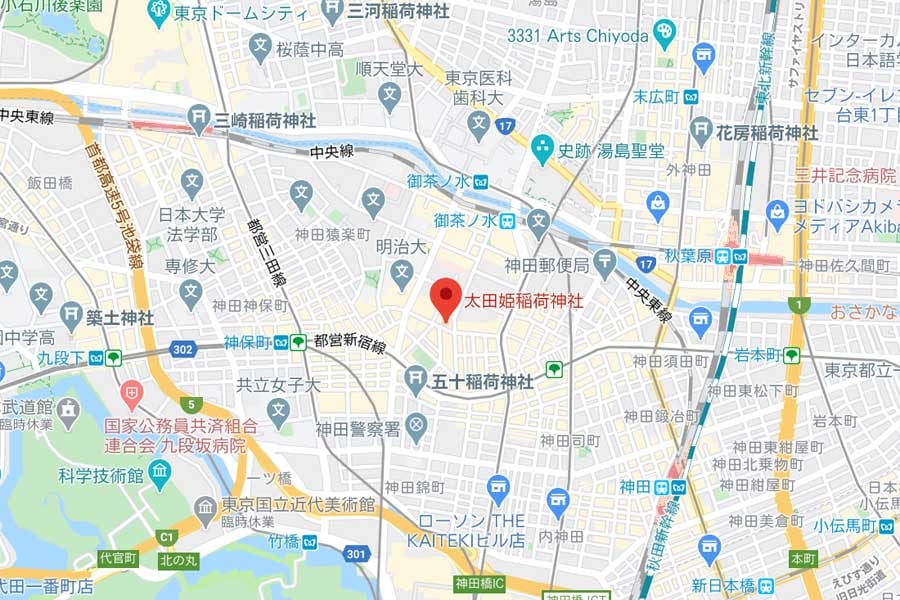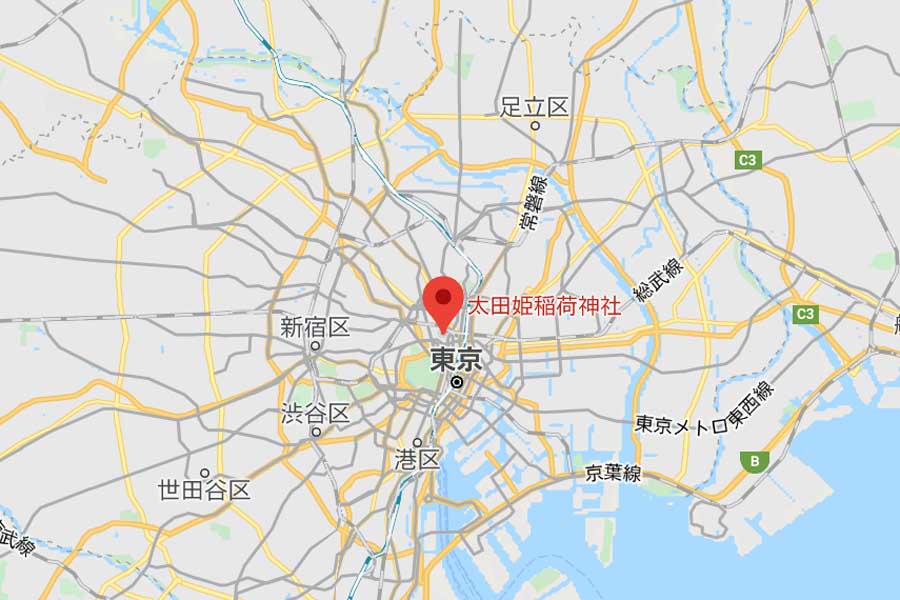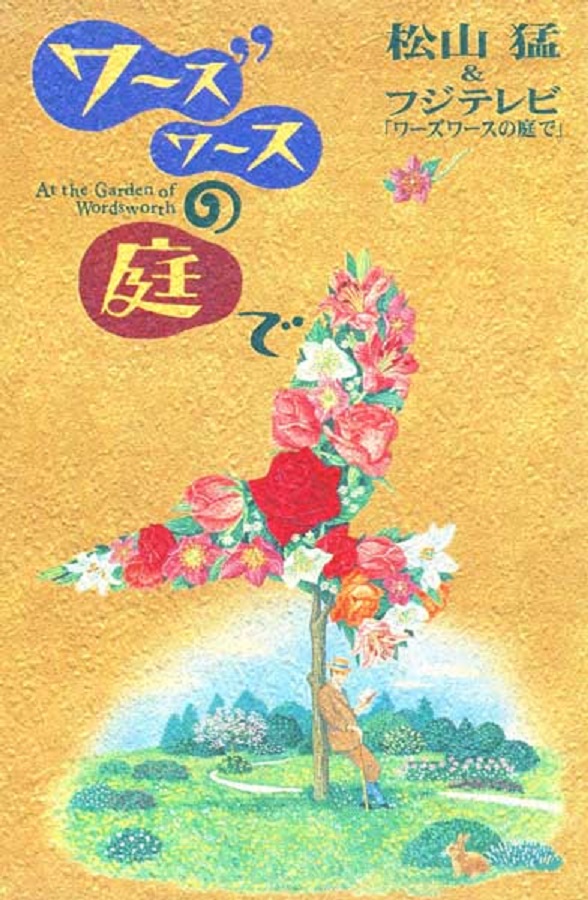東京とマスメディアが作り上げてきた「恋愛文化」はいったいどこへ行く? 令和の今こそ考える
古今東西、恋愛話は鉄板です。そんな恋愛と都市の関係性について、日本女子大学人間社会学部准教授の田中大介さんが考察します。恋愛というゆらぎのゲーム 一般的に恋愛は「する」ものであり、「語る」のは野暮とされています。しかし、 愛とは? 恋とは? 恋愛と結婚は違う? 友達と恋人の境界線は? などの「語り」を生み出しがちです。 筆者(田中大介。日本女子大学准教授)には、これらの理由を答える能力はありません。ただ、こういう考えがしぶといのは、恋愛の「定義」があいまい、もしくは共有されてないからではないでしょうか。 東京の恋愛のイメージ(画像:写真AC) 人間はこれまで、恋愛のマッチングにさまざまな「手続き」や「装置」を介在させ、それを文化的・社会的な儀式や儀礼としてきました。古くは歌垣や懸想文(けそうぶみ。恋文)に始まり、かつてのお見合いもそうした伝統的な手続きのひとつでした。 そうした手続きを逸脱した人は、社会から「不潔」「不粋」「ケダモノ」などのレッテルを張られます。不法行為になることさえもあります。 また恋愛がややこしいのは、「理屈じゃない」「こういう愛もある」などといった、「ルールではないルール」が語られるからです。 いずれにしても恋愛は皆が納得できるような定義が難しく、「どういう関係が恋人なのか」もはっきりしていません。結婚なら「入籍した」、同級生なら「学籍がある」、社員なら「契約している」という制度的な裏付けとは異なるのです。 恋愛したからといって、どこかに届けを出すことはありません。恋人・恋人ではないという境界線もあいまいです。また、「友だち」や「友情」というカテゴリーも輪をかけてあいまいですから、恋愛には「告白」という儀式めいた手続きが重要なのです。 恋愛が興味深いのは相手にやきもきしたり、相手を試したりして気持ちが高まるところです。恋愛は双方の関係の「境界」を人為的につくったり、ずらしたりするゲームといえるでしょう。 では、具体的にどのようになったら恋人で、恋愛をしているといえるのでしょうか。そのことを公的に学べる学校や教科書はありません。ですから、どうやって出会い、どうやって関係を深めるかというマッチングの手続きを学び、気持ちを高め合うシナリオや舞台、装置が必要になるのです。 消費文化をけん引したバブル世代消費文化をけん引したバブル世代 1980年代後半のバブル期には、東京やその近郊を舞台にした「トレンディドラマ」と呼ばれる恋愛物語が盛んに放送されました。都市情報誌やファッション誌はそのような物語をなぞるデートコースやマニュアルを特集し、都市は当時、恋愛の格好の舞台でした。 バブル期のイメージ(画像:写真AC) この時期に発刊された「Hanako」や1990年代に流行した「東京ウォーカー」は、東京や首都圏の最新スポットやイベント、旬の食べ物や流行のエンターテインメントを繰り返し紹介しています。 特に東京ウォーカーに使われていた写真は、その多くが若い男女のペアモデルで、デートの手引きとして紹介されていたことがわかります。たくさんの人が恋愛物語にあこがれ、親密さを深めるために都市情報誌を読み、街へ出かけ、お金を使う――。20世紀後半以降、恋愛を起爆剤とした消費文化が、マスメディアを介して都市を活性化させていたのです。 国立社会保障・人口問題研究所(千代田区内幸町)の「出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)」を読むと、「異性の交際相手」のいない未婚者の割合で、バブル期に20歳前半を過ごした世代がもっとも低いことがわかります。つまりその世代は、30代にかけて活発に異性と交際し、都市的な消費文化をけん引していました。 なお、18~34歳の時期に婚約者と恋人のいる割合が男性で25%、女性で35%を超えていたのは、1992(平成4)年から2005(平成17)年までの間だけです。平成前期の日本社会は、かなりあけすけな「恋愛の時代」だったといえます。 恋するメディアと都市恋するメディアと都市 21世紀に入ってから、どのように変化したのでしょうか。マスメディアが作る恋愛物語は今でも恋愛のシナリオを提供していますが、その一方でインターネット上には大量の恋愛マニュアルが散見されます。今やデートコースを調べるのも、インターネット情報を参考にする時代です。 では、恋人に「なる」ための舞台はどうでしょうか。20世紀後半はナンパが今よりもポピュラーで、都市の街路や消費・娯楽施設が出会いの舞台となっていました。また「ダイヤルQ2」や「テレクラ」という電話メディアも、アンダーグラウンドに使われていました。 マッチングアプリ利用のイメージ(画像:写真AC) それらと比較して、現在のインターネットやスマートフォンを利用した出会い系サービスは規模が大きく、また効率的に見えます。そのような出会いが、かつてのいかがわしさを残しつつも、もう少し出会いをカジュアルなものにしています。 利用しているアプリやSNS、またそこでの発言や活動、写真、マナー、タイミング、プロフィールなどが相手を惹きつけ、遠ざける自己呈示(ていじ)の要素になります。いつでもどこでもつながれる関係だからこそ、その距離感やタイミングには念入りなマナーが必要です。情報の選択や加工が容易にできるがゆえの印象操作にも、いろいろと気を遣います。 ひるがえって、「スマートフォン時代の都市」という舞台はどうでしょうか。いつでもどこでも記録・加工・発信できるスマートフォンは、日常のささいな出来事をイベント化する装置といえます。「盛る」装置といってもいいでしょう。 また、恋愛を盛り上げる非日常的なイベントやスポットも必要です。都市部にはSNS映えし、恋愛をさらに高揚させるイベントやスポットが多くあります。企業や自治体もそれをビジネス・チャンスととらえているのが現状です。2000年代以降に増えた「イルミネーション」などのイベントや、2010年代に活発化した「街コン」などはそのわかりやすい実例といえるでしょう。 次は、異性の友人の減少や恋愛文化のゆくえについて解説します。
- ライフ